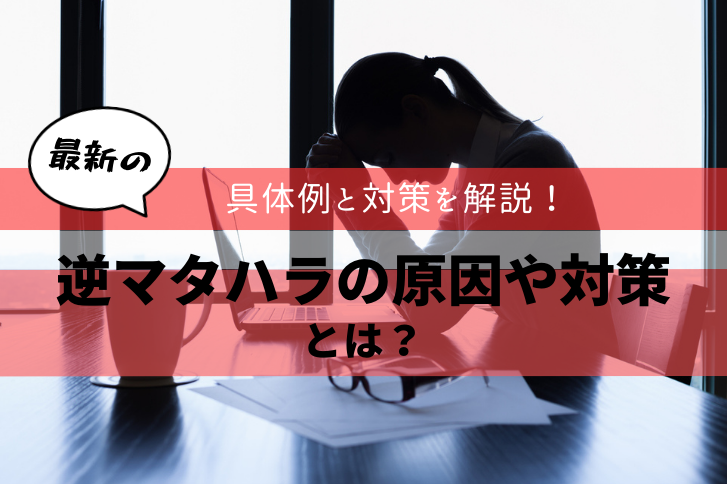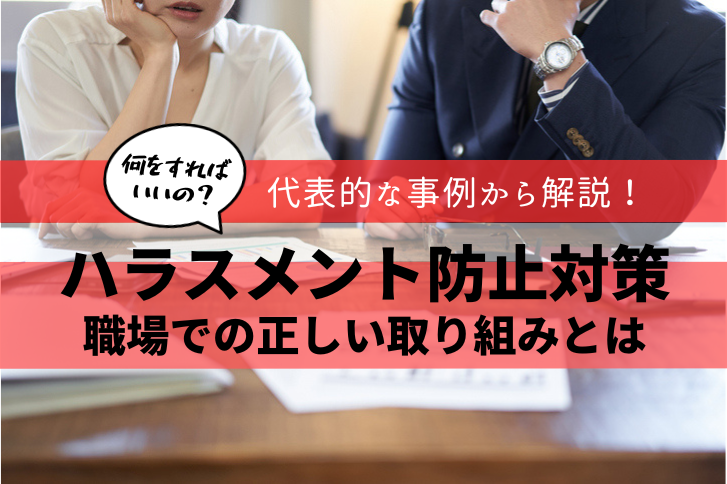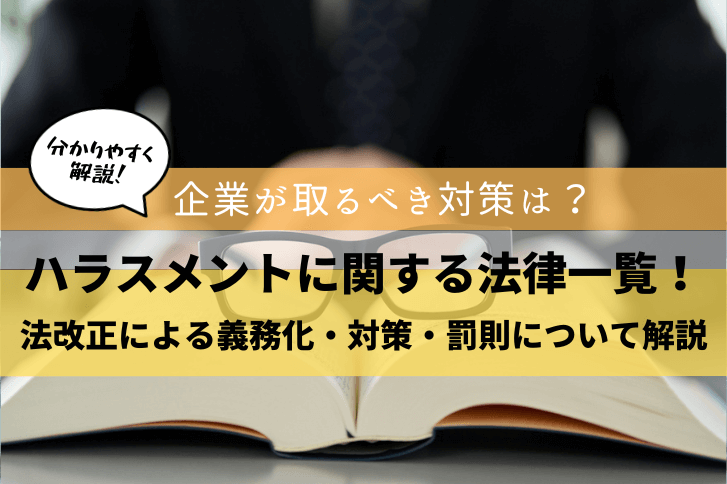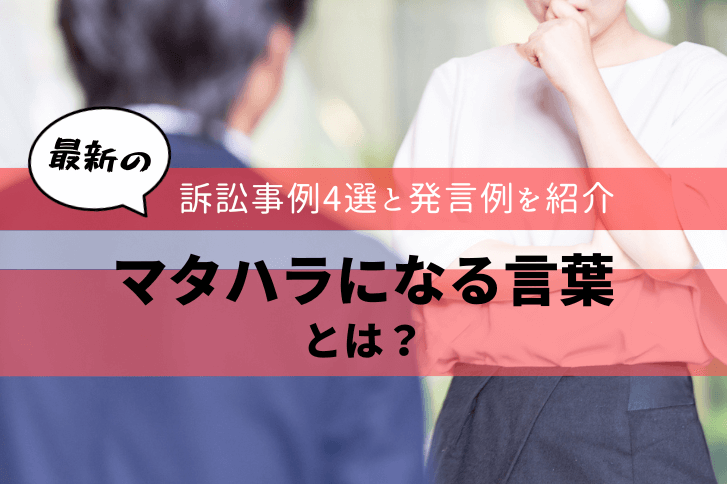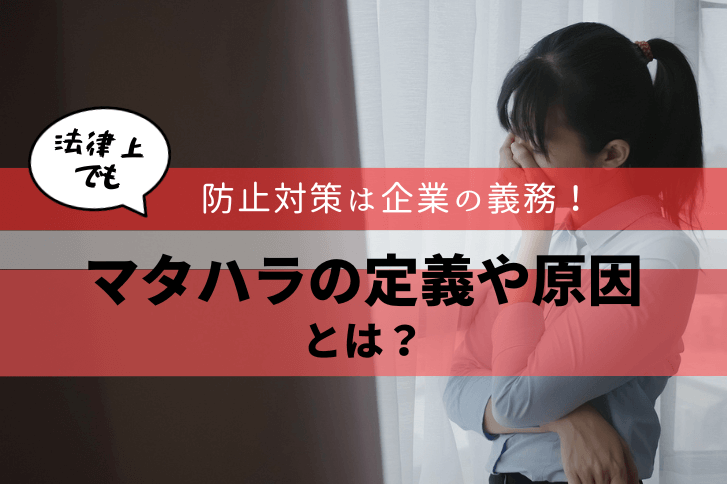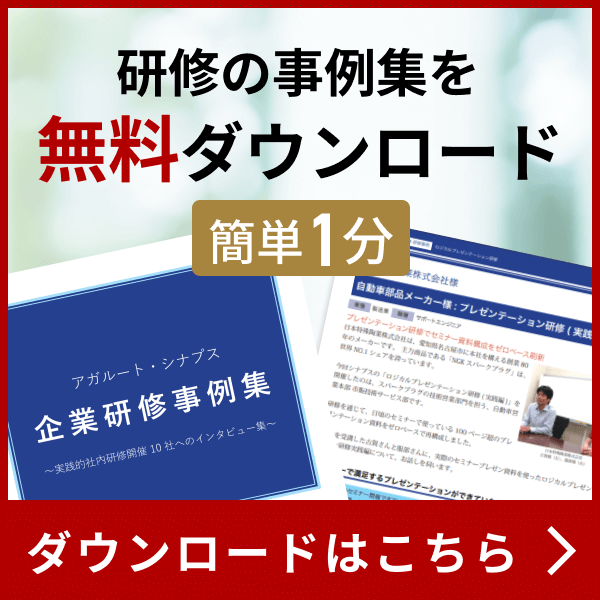「男女雇用機会均等法って、難しくてよくわからない」
「セクハラが起きたら、どうしたらいいんだろう」
男女雇用機会均等法が改正され、ハラスメントに対して企業が取り組むべきことが増えました。
自分の会社は、きちんと対応できているのかと心配になる人事労務担当者の方もいるのではないでしょうか。
このコラムでは、男女雇用機会均等法と2020年の改正、罰則についてわかりやすく解説します。
最後まで読むと、今すぐ会社で取り組むべきことがわかります。
「ハラスメント研修」会社探しにお困りではありませんか?
このような課題をお持ちでしたら
是非一度アガルートにご相談下さい
目次
男女雇用機会均等法とは
男女雇用機会均等法は、職場での性別による差別を禁止する法律です。
労働者の募集や採用、人員配置や教育訓練、福利厚生などさまざまな場面で、男女ともに平等に扱うことを求めています。また、セクシャルハラスメント防止のため、事業主に対して雇用の管理義務を設けています。
男女間の格差をなくし、労働者が働きやすく自分の能力を発揮できる環境を作ることを目指し、時代とともに何度も法改正されており、企業も対応が求められているのです。
男女雇用機会均等法|制定・改正の目的と2020年6月施行のポイント
男女雇用機会均等法は1986年(昭和60年)に初めて施行され、以降時代に合わせて改正を繰り返してきました。
しかしその目的は一貫して「男女間の雇用面での男女平等と待遇を確保するため」です。
最近では2020年6月に3つの条例が追加され、企業に求められることが増えています。
下記より詳しく解説していきます。
いつ制定された?セクシャルハラスメントが認められたその背景と目的
男女雇用機会均等法は、1986年(昭和60年)に施行されました。
制定の背景としては、多くの女性が働くようになったことが挙げられます。しかし、女性を単純・補助的な業務に限定するなど、男性とは異なる取扱いを行う企業がみられ、「女性は家庭を守る」という性別役割分担意識が社会に根強く残っていました。
男女間の雇用面での男女平等と待遇を確保するため、男女雇用機会均等法は制定されたのです。
1989年(平成元年)に日本で初めてセクハラの民事裁判が起こされ、社会に広く「セクシャルハラスメント」という概念が浸透します。
1997年(平成7年)には、事業主はセクハラ防止のため、配慮する義務がある(配慮義務)という規定が新設されました。
2020年6月に3つの条例が追加!ポイントをわかりやすく解説
男女雇用機会均等法はこれまで何度か改正されており、制定された当時は男女間の差別的な取り扱いの禁止は「努力義務」でした。
1997年(平成9年)の改正で女性であることを理由とする差別的扱いの禁止が定められ、2006年(平成18年)には、男性に対する差別的扱いが禁止されています。
2020年(令和2年)6月の改正では、3つの条例が追加されています。
不利益取扱いの禁止(均等法11条2項)
事業主は、労働者が職場でのセクハラを相談したことや、相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、「解雇やその他不利益な取扱いをしてはならない」こととされました。
他の事業主への協力義務(均等法11条3項)
自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行った場合、事業主が他の事業主から事実確認等の協力を求められた際には、応じるように努めなければならないという「協力義務」を定めています。
セクハラ防止の啓発活動とセクハラに必要な注意を払うべき努力義務(均等法11条の2)
事業主は、労働者が他の労働者(取引先や求職者も含む)に対して注意を払うよう、必要な配慮をすべきであると「努力義務」として規定されました。
事業主は、自分だけではなく労働者に対しても、研修を実施するなどしてセクハラへの関心と理解を深めるように対処することが求められています。
男女雇用機会均等法違反した際の罰則!違反企業はどうなる?
厚生労働大臣は、企業に対して違反の事実確認のため、報告を求めます。法違反がある場合には助言、指導、勧告が行われ、事業主は必要な措置を講じなければなりません。
厚生労働大臣の報告の求めに応じなかったり、虚偽の報告を行った事業主には、過料(20万円以下)が科されます。
勧告に従わない場合は、企業名公表の対象となります。過料は前科になりませんが、企業名公表の社会的信用へのダメージは大変大きくなるでしょう。
男女雇用機会均等法に対し企業が取るべき対応とは
下記より男女雇用機会均等法に対し企業が取るべき対応と、もしハラスメントが起きてしまった場合の対応策について解説していきます。
セクシャルハラスメントを防止するための対策は5つあります。
- セクハラに関する事業主の方針の明確化と周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備
- 男女雇用機会均等推進者の選任
- セクハラにかかる事故後の迅速な事実調査と加害者・被害者への適切な措置、再発防止措置
- 申告者・調査協力者等のプライバシー保護と不利益取扱禁止
順番に解説します。
セクハラに関する事業主の方針の明確化と周知・啓発
事業主は、セクハラは許されない行為であり、発覚した場合は厳正に対処していく方針を明確に示し、就業規則等に記載するなど社内ルールを文書化して、労働者に知らせます。
セクハラの内容や発生原因などに関する研修や講習を行い、セクハラへの正しい理解を深めることも重要です。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備
相談窓口を設置し、労働者がセクハラで困ったときには相談できることを周知します。
苦情も聴取し、セクハラかどうか曖昧なケースにも対応することで、未然に防ぐ効果も期待できます。相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるように体制を整えておきましょう。
男女雇用機会均等推進者の選任
男女雇用機会均等推進者は、企業や団体において男女の均等な雇用を促進するために活動する役割を担う方のことで、厚生労働省からも積極的に選任に努めることとされています。
具体的には、人事制度や採用・昇進制度の見直しや改善提言、女性の職場進出支援やワークライフバランスの整備、男女の給与格差の是正、性的ハラスメントやセクシャルハラスメントの防止など、多岐にわたる業務を行います。推進者が日頃から様々な情報を収集することで、様々な取り組みが円滑に進むようになるのです。
男女雇用機会均等推進者は、企業のCSR活動や労働法令遵守など、社会的責任を果たす上でも重要な役割を担っています。
また、今後ますます進展するダイバーシティ&インクルージョンを牽引していくことが求められています。
セクハラにかかる事故後の迅速な事実調査と加害者・被害者への適切な措置、再発防止措置
セクハラが発生した場合、相談窓口担当者は事実関係を迅速かつ正確に確認します。
被害者の心情や関係者のプライバシーに十分配慮し、双方の話を公平に聴きましょう。セクハラがあったと確認できた場合は、必要に応じて加害者への制裁を含めた措置をとり、再発防止に向けて対策を立てます。セクハラが確認できなかった場合も、再発防止のための措置を取ることが大切です。
申告者・調査協力者等のプライバシー保護と不利益取扱禁止
相談窓口でセクハラの相談をしたり、相談への対応として調査協力をしたなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをされないと就業規則等で定め、労働者に周知します。
相談者のプライバシーは守られ、安心できる相談場所であることも合わせて知らせましょう。
セクシャルハラスメントが起きてしまった時の対応
セクハラが起きたら、以下のような対応を心がけ、事実確認をします。
- プライバシーを尊重し、誰かに見られたり、聞かれないように配慮する
- 被害者に対して否定的な言葉をかけない
- 断定的な言い方は避ける
- 今後どうしたいのか、被害者の希望を聞く
- 被害者が同意しない場合、社内での情報共有は避ける
被害者に寄り添うことが大切です。
企業がハラスメントの情報をアップデートし続けることが重要!
男女雇用機会均等法は、時代の流れや雇用環境の変化に対応し、度々改正されてきました。
コロナ渦を経て、今後も職場の環境や働き方は大きく変わることが予想されます。これからも法改正の度に、企業は対応し続けなければなりません。
変化し続ける雇用環境や法改正への対応には、アガルートのハラスメント研修がおすすめです。アガルートのハラスメント研修では、下記の対応が可能です。
- 事前にヒアリングを行い、貴社独自の研修プログラムを制作
- 貴社の事業課題や参加メンバーの特性に合わせて重要パートの充実が可能
貴社の実情に合わせたプログラムで、効率的なハラスメント研修の実施を検討されてみてはいかがでしょうか。
「ハラスメント研修」会社探しにお困りではありませんか?
このような課題をお持ちでしたら
是非一度アガルートにご相談下さい

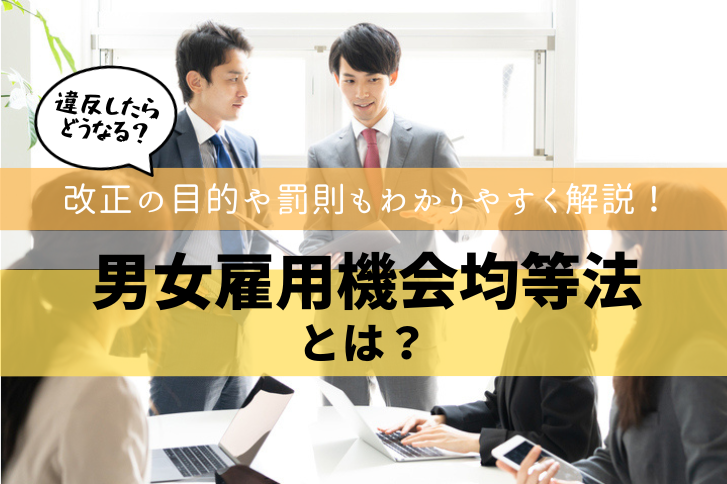
-1.jpg)