税理士になるには?資格取得の流れや、高卒や主婦から目指す方法も解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

税理士は、3つの独占業務を有する国家資格。
税理士を目指している方は、以下のような疑問をお持ちではないでしょうか。
「高卒や主婦でも税理士になれる?」
「税理士になるためには何年かかるのか知りたい」
本コラムでは、税理士になるための方法について解説します。
税理士資格を取得するための一般的な流れや、受験資格がない方が税理士になるための方法なども紹介しているため、ぜひ参考になさってください。
税理士試験の合格を
目指している方へ
- 税理士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
税理士試験講座がおすすめ!
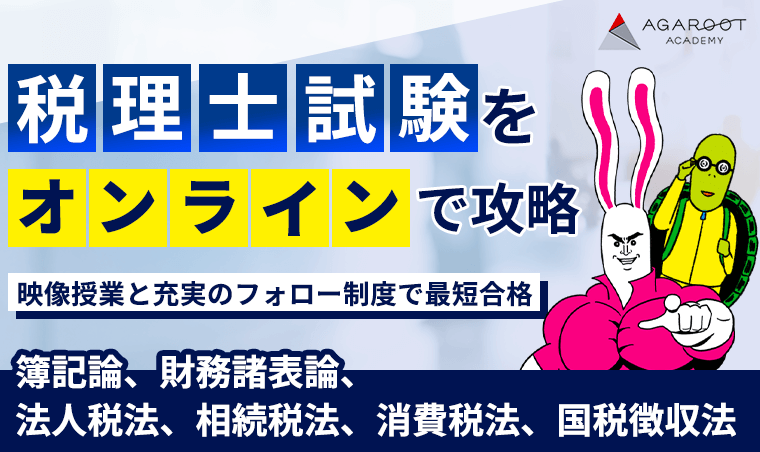
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
受講生専用SNS「学び舎」で受験生同士の交流が可能
▶税理士試験講座を見る
目次 [非表示]
税理士になるには
税理士になるための一般的な方法は、税理士試験に合格後、「租税または会計に関する事務」の実務経験を2年以上積むことです。
実務経験を満たしたうえで、日本税理士会連合会への登録が完了すれば、税理士資格を取得できます。
ただし、税理士試験には受験資格が設けられているため、税理士試験を受ける際は、自分が受験資格を満たしているかどうかを確認する必要があります。
また、税理士試験免除者および弁護士または公認会計士の資格をお持ちの方は、税理士試験を受けずに税理士として登録することが可能です。
税理士資格取得の方法・流れ
税理士資格を取得するための一般的な流れは、以下の通りです。
- 税理士試験の受験資格を満たす
- 税理士試験に合格する
- 2年以上の実務経験を積む
- 税理士登録を行う
それぞれ詳しく解説していきます。
1. 税理士試験の受験資格を満たす
税理士資格を取得するための最初のステップは、税理士試験の受験資格を満たすことです。
受験資格は科目の分野によって異なり、会計学に属する科目には受験資格が設けられてません。
一方で、税法に属する科目には、学識・職歴・資格による受験資格が設けられています。
税法に属する科目の受験資格は、以下の通りです。
学識による受験資格
- 大学又は短大の卒業者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
- 大学3年次以上で、社会科学に属する科目を1科目以上含む62単位以上を取得した者
- 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
- 司法試験合格者
- 公認会計士試験の短答式試験に合格した者(平成18年度以降の合格者に限られます。)
資格による受験資格
- 日商簿記検定1級合格者
- 全経簿記検定上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限られます。)
職歴による受験資格
税理士の資格取得 – 日本税理士会連合会
- 法人又は事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
- 銀行・信託会社・保険会社等において、資金の貸付・運用に関する事務に2年以上従事した者
- 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
上記の受験資格のいずれかひとつを満たしていれば、税法科目を受験できます。
なお、受験の際は、受験資格を満たしていることを証明するための提出書類が必要です。
必要な提出書類は受験資格の内容によって異なるため、国税庁のホームページを確認のうえ、必要な手続きを行いましょう。
また、これらの受験資格に該当していなくても、海外の大学を卒業された方や、記帳指導事務などに従事された方は、国税審議会の個別認定によって受験が認められる場合があります。
税理士試験の受験資格について詳しく知りたい方は、以下のコラムも参考になさってください。
2. 税理士試験に合格する
税理士試験は11科目に分かれており、それぞれ必須科目・選択必須科目・選択科目に分類されます。
税理士資格を取得するためには、以下の合計5科目の試験に合格する必要があります。
- 会計学に属する科目(簿記論および財務諸表論)2科目
- 税法に属する科目のうち、所得税法または法人税法のいずれか1科目以上
- 税法に属する科目のうち、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税のいずれか1~2科目
会計学に属する科目である簿記論および財務諸表論は、いずれも必須科目です。
税法に属する科目は9科目あり、そのうち所得税法と法人税法は選択必須科目です。
残りの7科目、すなわち相続税法・消費税法又は酒税法・国税徴収法・住民税又は事業税・固定資産税は選択科目であり、これらの中から1~2科目を選んで受験します。
| 分野 | 科目 | 選択/必須 |
|---|---|---|
| 会計学 | ・簿記論 ・財務諸表論 | 必須 |
| 税法 | ・所得税法 ・法人税法 | 1科目以上の選択必須 |
| ・相続税法 ・消費税法 又は 酒税法 ・国税徴収法 ・住民税 又は 事業税 ・固定資産税 | 1~2科目を選択 |
税理士試験は科目合格制を採用しており、一度合格した科目は生涯有効です。
そのため、一度にすべての科目に合格する必要はなく、自分のペースで5科目の合格を目指せます。
また、各科目の合格基準は満点の60%ですが、実質的には相対評価で決まると言われています。
税理士試験の科目や出題範囲について詳しく知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。
3. 2年以上の実務経験を積む
税理士試験の合格者が税理士資格を取得するためには、租税に関する事務、または会計に関する事務における通算2年以上の実務経験が必要です。
「租税に関する事務」とは、税務官公署や会社などにおける、税務に関する事務のことです。
また、「会計に関する事務」とは、賃借対照表や損益計算書を用いた会計に関する事務のうち、機械的な業務を除いたものを指します。
ただし、業務の内容が実務経験に該当するかどうかは、登録申請書および必要書類を提出後、税理士会の調査によって個別に判断されます。
なお、実務経験を積むタイミングは定められていないため、あらかじめ実務経験を積んでから税理士試験を受験したり、実務経験を詰みながら税理士試験に挑戦したりすることも可能です。
4. 税理士登録を行う
税理士資格を得るためには、日本税理士会連合会の税理士名簿への登録が必要です。
税理士試験に合格し、実務経験を満たせば、税理士として登録できます。
税理士試験に合格していても、税理士名簿への登録が完了するまでは税理士を名乗れないため、注意しましょう。
登録の流れや必要書類については、日本税理士連合会のホームページをご確認ください。
税理士になるには何年かかる?
税理士になるには、平均10年程かかるといわれています。
税理士になるためには、税理士試験の合格と、2年以上の実務経験が必要です。
税理士試験に合格するまでかかる時間は早くて3~5年、平均では約10年といわれています。
そのため、税理士試験の合格後に実務経験を積む場合は、最大で12年程かかると考えていいでしょう。
税理士試験は各科目の難易度が高いため、1年で5科目の試験に合格することは困難です。
また、税理士試験は年に1回しか行われないため、不合格となった場合は、翌年まで再受験できません。
できるだけ短期間で税理士になるためには、無理のない学習計画を立て、通信講座や予備校の活用も検討しましょう。
高卒から税理士になるには
税理士試験の受験資格を満たせば、高卒から税理士を目指せます。
高卒の方は、大学・短期大学・専門学校などで必要科目を履修するか、日商簿記検定1級などの資格を取得すれば、税理士試験の受験資格を得られます。
また、税理士事務所や会計事務所で2年以上の補助業務に従事すれば、職歴による受験資格を得ることが可能です。
税理士試験には複数の受験資格が設けられているため、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。
また、高卒の方の税理士試験合格率は、決して低くありません。
令和5年度(第73回)税理士試験結果表によると、2023年における税理士試験の全体合格率は21.7%でした。
対して、高校・旧中卒の受験生の合格率は23.8%であり、受験者数は少ないものの、合格率は受験生全体の平均を上回っていることがわかります。
高卒の方におすすめの方法
高卒の方が大学や専門学校に通わずに税理士を目指す場合は、資格または職歴による受験資格を満たす方法がおすすめです。
資格による要件は、日商簿記1級または全経簿記検定上級の取得です。
また、会計士補または会計士補となる資格を有している場合も、資格による要件を満たせます。
これらの資格はいずれも難易度が高いため、通信講座や予備校を活用し、スムーズな合格を目指しましょう。
また、職歴による要件を満たすためには、税理士事務所や会計事務所で2年以上の補助業務に携わる必要があります。
働きながら税理士を目指したい方は、職歴による要件を満たす方法が適しているでしょう。
主婦が税理士になるには
主婦の方が税理士を目指す場合は、まず自分が税理士試験の受験資格を満たしているかどうかを確認しましょう。
大学・短期大学・専門学校などですでに必要科目を履修している方は、学識による受験資格を得られます。
また、日商簿記検定1級や全経簿記検定上級などの資格を有していれば、資格による受験資格が認められます。
加えて、これまでに税理士事務所や会計事務所で2年以上の補助業務の経験がある方は、職歴による受験資格に該当する可能性があるでしょう。
自分が受験資格を満たしているかどうかを確認のうえ、効率的に税理士資格を取得できる方法を判断しましょう。
主婦の方におすすめの方法
受験資格がない主婦の方が税理士を目指す場合は、通信大学で必要科目を履修し、学識による要件を満たすか、資格または職歴による要件を満たす方法がおすすめです。
職歴による要件を満たすためには、税理士事務所や会計事務所で通算2年以上の補助業務に従事する必要があります。
また、資格による要件を満たすためには、日商簿記1級または全経簿記検定上級の資格を取得しなければなりません。
しかし、簿記に関する知識がない方は、資格による要件を満たすために一定の時間がかかると考えられます。
税理士試験の勉強時間を確保するためにも、通信講座や予備校を活用し、早期合格を目指すことが望ましいでしょう。
税理士になるには?まとめ
本コラムでは、税理士になるための方法について解説しました。
税理士になるための一般的な方法は、税理士試験の受験資格を満たしたうえで税理士試験に合格し、実務経験を積むことです。
これらのステップを経て、税理士としての登録を行えば、税理士資格を取得できます。
税理士試験には複数の受験資格が設けられているため、いずれかの要件を満たせば、学歴や年齢を問わず税理士を目指すことが可能です。
また、一度合格した科目は生涯有効であるため、生活と試験勉強を両立させている主婦の方や、働きながら長い時間をかけて税理士を目指す社会人の受験生も多く見受けられます。
受験資格を確認し、自分にとって最も効率的な方法を見つけましょう。
一方で、税理士試験は難易度が高い試験であるため、独学での挑戦はあまりおすすめできません。
特に、資格による受験資格を満たそうと考えている方は、税理士試験を受験する前に簿記の学習に取り組まなければならないため、学習期間を多めに確保しておく必要があるでしょう。
まとまった勉強時間を確保することが難しい社会人の方や、生活の中のスキマ時間を有効活用したい主婦の方には、通信講座や予備校の活用がおすすめ。
オンラインで学べる通信講座なら、自分のペースで効率良く学習できます。
また、フォロー制度が充実した講座を選べば、最後までモチベーションを維持しやすくなります。
本コラムを参考に、自分に合った方法で税理士を目指しましょう。
税理士試験の合格を
目指している方へ
- 税理士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
税理士試験講座がおすすめ!
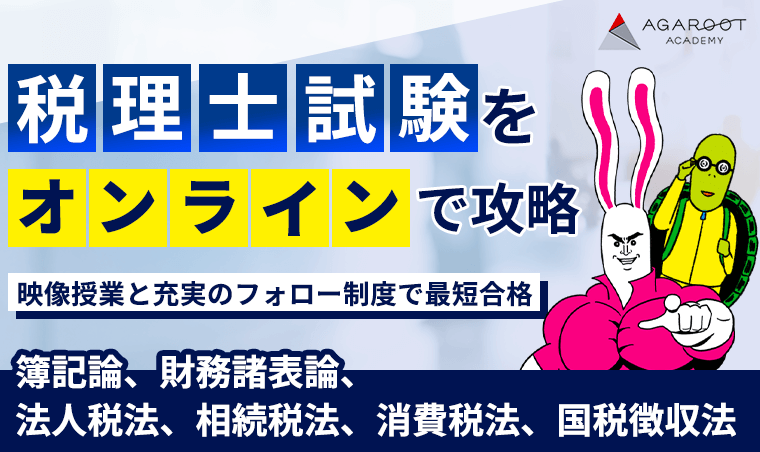
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
受講生専用SNS「学び舎」で受験生同士の交流が可能
▶税理士試験講座を見る






