税理士とは?どんな仕事内容?業務の流れや資格取得についてわかりやすく解説!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

国家資格である税理士資格を取得すると、社会的需要が高い税理士として活躍できます。
最近では、税理士の活躍の幅が広がっており、キャリアアップのために税理士資格を取る方も増えています。
しかし、税理士とは実際どんな仕事なのか、資格はどうすれば取れるのかを知らないままでは、どこから勉強を始めればいいのかわからない方も多いでしょう。
本コラムでは、税理士の仕事内容や資格の取得方法について詳しく解説します。
税理士のキャリアプランについても触れるため、税理士試験に挑戦したい方はぜひ参考にしてください。
税理士試験の合格を
目指している方へ
- 税理士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
税理士試験講座がおすすめ!
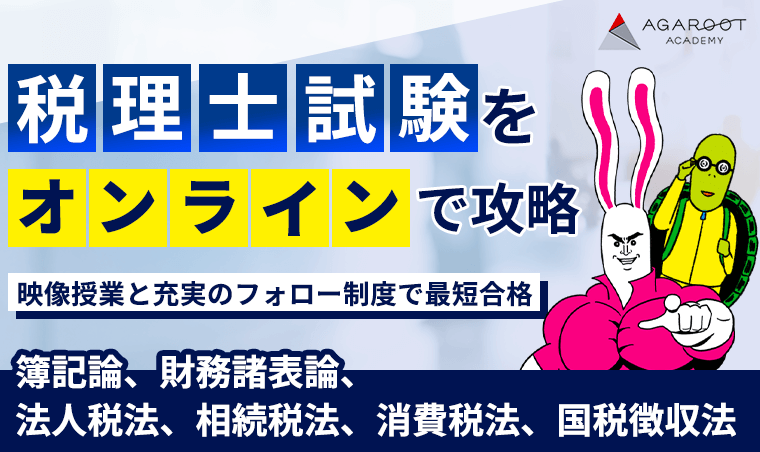
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
受講生専用SNS「学び舎」で受験生同士の交流が可能
▶税理士試験講座を見る
目次 [非表示]
税理士とは?どんな仕事?
税理士とは国から認められた、税務に関する専門家です。
税理士は税務の専門家として納税者の相談相手になり、納税者の代わりに税の計算や申告書の作成などを行うのが主な仕事です。
税理士の使命について、税理士法第1条では
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
税理士法 | e-Gov法令検索
と規定されています。
税理士の仕事内容
国家資格の税理士には独占業務があります。近年税理士の仕事内容は多様化しており、独占業務以外の仕事にも従事しています。
税理士の主な仕事内容は、以下のとおりです。
- 独占業務:税務代理、税務書類の作成、税務相談
- 独占業務以外:記帳代行、会計業務、会計参与、補佐人、申告支援、行政・司法の支援、コンサルティング・アドバイザリー業務
独占業務の仕事内容
税理士には、以下の3つの独占業務が認められています。
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
税務代理
税務代理とは、クライアントの代理で税に関するさまざまな手続きを行うことです。
具体的には、個人や経営者などの代理で確定申告や青色申告の承認申請などを行います。
また、税務調査の立ち会いや税務署の更正や決定に不服がある場合の申立て、審査請求などの代理業務も可能です。
税法はかなり複雑なため、一般の方はスムーズに税務手続きができません。
税理士が代理することによって、多くの方の適正で正確な納税が実現できています。
税務書類の作成
税理士はクライアントに代わって、税の各種申告手続きなどに必要な書類を作成することが認められています。
主な税務書類は以下のとおりです。
- 確定申告書
- 相続税申告書
- 青色申告承認申請書
- そのほか税務署などに提出する書類
税務書類を代理で作成することは税理士の独占業務のため、有資格者以外が行うことは違法行為になります。
なお、税理士事務所などで無資格のスタッフが税理士の指示のもとで書類を作成することは、責任者が税理士になるため違法ではありません。
税務相談
税務相談とは、クライアントが税金に関することで困った時やわからない時、知りたい時に話を聞いて、適切なアドバイスを行う業務です。
以下が、主な相談内容の例です。
- 確定申告や帳簿の付け方
- 節税や決算について
- 役員報酬について
- 資金繰りや融資について
- 経営計画や事業計画について
- 社会保険や生命保険について
- 経理業務の進め方や経理部門の統制システムについて
税理士は税の手続きに関すること以外に、企業の経営方針や経理部門に関する相談を受ける場合があります。
独占業務以外の仕事内容
税理士が担当する業務は独占業務以外にも多くあり、さまざまな場面で活躍しています。
税理士が対応できる業務は、以下のとおりです。
- 記帳代行
- 会計参与
- 補佐人
- 行政・司法の支援
- コンサルティング・アドバイザリー業務 など
記帳代行
記帳代行とは、クライアントの企業の経理や税務に関する記帳業務を代理で行う業務です。データ入力業務も含みます。
会計帳簿の記帳、財務書類の作成、給与計算など、クライアントのお金に関する幅広い業務を代行します。
会計参与
会計参与とは、会社役員という立場になってクライアント企業の取締役などと共同して計算関係書類の作成を行うことです。
会計参与は株式会社の設置機関のひとつであり、株式会社の定款規定により設けられています。
税理士は、会計参与の有資格者として会社法で明記されており、各企業の計算関係書類の正確さに対する信頼度を高めるのに貢献しています。
補佐人
補佐人とは、税務訴訟で納税者が正当な権利、利益を主張できるように、訴訟代理人の弁護士とともに裁判所への出頭・陳述ができる人のことです。
税務訴訟では法律の専門家である弁護士と納税者だけでは、税の知識面において不十分な可能性があります。
税の専門的な知識不足によって納税者が不利益にならないよう、補佐人の税理士による援助が可能です。
行政・司法の支援
税理士の専門的な知識や経験は、行政や司法の場でも活かされています。
以下は、税理士が活躍している例です。
- 国税不服審判所での国税審判官
- 地方共同団体の監査委員
- 家庭裁判所での民事・家事調停員
- 法テラス(日本司法支援センター)の相談員
- 成年後見支援センター(各地域の税理士会)による成年後見人
- 登録政治資金監査人
そのほか、一般の方向けの無料税務相談などに参加する申告支援や租税教育の講師業務などが挙げられます。
税理士の業務の流れ
税理士の業務は、クライアントが個人の場合、法人の場合で流れが異なります。
仕事内容についても異なる部分があるため、それぞれのケースを確認して業務の流れを把握しましょう。
クライアントが個人の場合
個人のクライアントは、個人事業主やフリーランス、自営業者、不動産のオーナーなどの事業所得がある方が主な対象です。
仕事内容の中心は、確定申告と確定申告に付随する業務になります。
確定申告とは1年間の経費と収入を計算し、税務署に申告する作業です。
確定申告によって1年間の納税額も決定します。
以下、クライアントが個人の場合の業務の流れです。
| 時期 | 業務内容 |
|---|---|
| 12月 | 年末調整 |
| 1月 | 厳選納付、給与支払報告、償却資産税申告 |
| 2〜3月 | 確定申告(所得税、消費税) |
ただし、表は消費税の中間申告がない場合の流れになります。
中間申告とは、直前の消費税の納税額が一定以上の事業者が行う申告です。
確定消費税の金額によっては、消費税の中間申告を行わなければなりません。
また、確定申告のほかに遺産相続税や登録免許税、不動産取得税の申告業務などが必要に応じて発生します。
クライアントが法人の場合
クライアントが法人の場合、仕事のスケジュールは各企業の決算期によって決まります。
日本では多くの企業が12月もしくは3月を決算月に設定しており、年末調整を行う12月から決算後の確定申告が終了までの期間、税理士は忙しくなるケースが多いです。
また、クライアントが法人の場合、月末などの締日に試算表作成から決算内容をとりまとめる業務を毎月行い、決算期に備える流れが一般的です。
なお、納税額によっては消費税に加えて法人税の中間申告が必要になります。
以下、3月決算を想定した法人の場合の1年の流れ(消費税・法人税の中間申告なし)です。
| 時期 | 業務内容 |
|---|---|
| 12月 | 年末調整 |
| 1月 | 源泉納付、給与支払報告、償却資産税申告 |
| 3月 | 決算 |
| 4月~5月 | 財務書類の作成、確定申告(法人税、法人事業税、消費税など) |
クライアントが法人の場合、例年にない大きな利益が発生すると納税額が急増し、資金繰りが困難になるリスクがあります。
税理士は予期しないことが起きても経営が悪化しないよう、クライアントの経営状況や財務内容を考慮して納税とビジネスが両立できるアドバイスを行っています。
税理士資格を取得するには?
税理士になるには、税理士試験に合格して資格を取らなければなりません。
税理士は人気の資格ですが、税理士試験は難易度の高い試験といわれています。
合格に近づくためにも、試験について理解しておきましょう。
税理士試験の概要
税理士試験の概要を、以下の4つに分けて解説します。
- 試験時期
- 受験資格
- 試験科目
- 合格基準
試験時期
税理士試験は年に1回、例年8月上旬に実施されます。
2024(令和6)年度(第74回)の試験実施スケジュールは、以下のとおりです。
- 試験実施官報公告:2024年4月5日
- 受験申込受付:2024年4月22日~5月10日
- 試験実施:2024年8月6日~8月8日
- 合格発表:2024年11月29日
試験は全国12〜16か所にある、各国税局・国営事務所の所在地などで行われます。
以下は、例年の試験スケジュールです。
- 試験実施官報公告:4月初旬
- 受験申込受付:5月上旬~5月中旬
- 試験実施:8月上旬〜中旬過ぎの3日間
- 合格発表:11月下旬〜12月中旬
例年のスケジュールに比べて、2024(令和6)年度の試験は受験申込受付期間が前倒しになっています。
受験資格
税理士試験の科目は、会計学に属する科目と税法に関する科目に分かれます。
会計学に属する科目については受験資格がないため、誰でも受験することが可能です。
一方で、税法に属する科目は、受験資格が定められています。
以下の要件のうち、いずれかひとつを満たせば受験することが可能です。
学識による受験資格
- 大学・短大卒かつ1科目以上の社会科学に属する科目を履修した者
- 大学3年次以上かつ社会科学に属する科目を1科目以上を含む62単位以上を取得した者
- 一定の専修学校の専門課程修了者かつ1科目以上の社会科学に属する科目を履修した者
- 司法試験合格者
- 公認会計士試験の短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る)
資格による受験資格
- 日商簿記検定1級合格者
- 全経簿記検定上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る)
職歴にする受験資格
- 法人または事業を行う個人の会計に関する事務を2年以上従事した者
- 銀行・信託会社・保険会社などにおいて、資金の貸付・運用に関する事務を2年以上従事した者
- 税理士・弁護士・公認会計士などの業務の補助事務を2年以上従事した者
上記の要件を満たさなくても、あらかじめ国税審議会の個別認定を受けることで受験が認められる場合があります。
試験科目
試験の合格には、会計学に属する科目の2科目と税法に属する科目の3科目、合計5科目の合格が必要です。
会計学に属する科目は簿記論・財務諸表論の2科目で、いずれも必須科目です。
税法に属する科目では、所得税法・法人税法・相続税法・消費税法・酒税法・国税徴収法・住民税・事業税・固定資産税の9科目があります。
上記9科目から、選択必須科目である所得税法と法人税のいずれか1科目以上を含む、3科目を選択します。
| 分野 | 科目 | 選択/必須 |
|---|---|---|
| 会計学 | 簿記論 財務諸表論 | 必須 |
| 税法 | 所得税法 法人税法 | 1科目以上の選択必須 |
| 相続税法 消費税法 又は 酒税法 国税徴収法 住民税 又は 事業税 固定資産税 | 1〜2科目を選択 |
税理士試験では科目合格制を採用しているため、一度に5科目に合格する必要はありません。
また、1回の試験で5科目受ける必要はなく、1科目ずつ受験することも認められています。
さらに合格した科目は生涯有効です。時間がかかっても勉強すれば確実に合格できる試験といえるでしょう。
合格基準
会計学に属する科目2科目、税法に属する科目3科目の合計5科目に合格すると、税理士試験合格となります。
各科目の合格点は、満点の60点以上とされています。ただし、例年の合格率推移から、相対評価による合否判定ではないかといわれています。
その他、税理士試験について詳しくは以下コラムで解説しています。ぜひ参考にしてください。
税理士のキャリアプランは?
税理士の働き方はひとつではありません。税理士資格をもつと、ライフスタイルや目指す年収などを基準に、さまざまな働き方が選べます。
税理士の主なキャリアプランは、以下のとおりです。
- 開業税理士
- 社員税理士
- 所属税理士
- 一般企業の経理部門などで勤務
それぞれ詳しく解説していきます。
開業税理士
開業税理士とは、自分で税理士事務所などを設立して所長税理士として働く人を指します。
つまり、独立開業をした税理士は開業税理士ということです。
税理士の独立開業は、数人のスタッフを雇って小規模の税理士事務所(会計事務所)を経営する場合や、ほかの税理士と共同で税理士法人を設立して大規模な事務所を目指すなど、さまざまなパターンがあります。
開業税理士になると経営が安定するまで苦労することもありますが、軌道に乗れば高収入も夢ではありません。
また、自分の思いどおりの働き方ができ、定年制などにとらわれないメリットもあります。
社員税理士
社員税理士とは税理士法人に所属している税理士を指し、税理士法人の共同経営者として業務を行う人です。
社員という名がついていますが、税理士法人に所属している正社員という意味ではありません。
社員税理士はすべての業務を執行できる権利・義務を有しており、一般企業内の役員に近い立場です。
そのため、財務業務以外に法人の経営や事業計画にかかわる仕事も行います。
責任が重い立場であり、そのぶん年収も高い傾向です。
社員税理士には、以下のようなパターンで就くことが可能です。
- 所属する税理士法人で昇格する
- 既存の税理士法人に社員税理士として入る
- 何人かの税理士と共同で税理士法人を設立して社員税理士になる
3つ目の例は開業税理士と共通している部分がありますが、会計事務所と税理士法人は組織形態や規模が異なります。
独立した法人での役員になった場合、社員税理士と呼ばれるポジションになります。
所属税理士
所属税理士とは、税理士もしくは税理士法人などの補助業務を行う税理士のことです。
税理士事務所(会計事務所)や税理士法人に所属し、補助業務を行うのがメインになります。
所属税理士はクライアントからの直接受任も可能ですが、ほとんどの仕事は事務所の所長税理士や税理士法人のパートナーなどから指示されます。
所属税理士は、一般企業でいうと役職のない一般社員に近いポジションであり、年収は開業税理士や社員税理士よりも低い傾向です。
しかし、補助業務が中心の所属税理士は自分から顧客を獲得する必要はなく、振られた業務を遂行するだけです。
そのため、営業力に自信がない方や家事や育児と両立したい方でも、資格を活かして無理なく働けるでしょう。
一般企業に勤める
税理士資格を取得すると、一般企業の経理部門や税務部門などで資格の知識を活かしながら働くことも可能です。
一般的には企業の税務や会計業務は、税理士法人や会計事務所などと顧問契約を結んで依頼するケースが多いです。
しかし、中には社内で完結できるよう、社員として税理士資格保有者を直接雇用する企業があります。
仕事内容は企業によって幅はありますが、ほかの税理士が行う業務と同じ内容を行うことが可能です。
また、税務業務だけでなく、経営戦略のコンサルティングなどを任されることも多くなっています。
具体的には新規事業の立ち上げやM&A、事業再編など、企業のあらゆる大事な場面で税理士の知識が活かされています。
税理士の仕事についてよくある疑問
この章では、税理士の仕事についてよくある疑問についてお答えします。
公認会計士との違いとは?
税理士と公認会計士は専門分野が異なるため、仕事内容や独占業務が違います。
税理士は税務に関する専門知識を持ち、主に個人や法人を対象に税金の申告などの税務業務の代行やサポートが可能です。
一方で公認会計士は、企業の財務に関する専門知識を持ち、財務書類の作成や会計処理の監査や指導を行います。
以下、独占業務とそれ以外の主な業務の比較です。
| 独占業務 | 独占業務以外の業務 | |
|---|---|---|
| 税理士 | 税務代理 税務書類の作成 税務相談 | 記帳代行 会計参与 補佐人 行政・司法の支援 コンサルティング・アドバイザリー業務 |
| 公認会計士 | 監査業務 (法定監査、法定以外の監査、国際的な監査) | 経理業務 財務業務 税務業務(税理士登録をした場合のみ) コンサルティング・アドバイザリー業務 |
独占業務以外の業務については、自分の状況や所属する事務所や企業によって内容が異なります。
また、税理士と公認会計士は専門とする仕事内容が異なるため、顧客や就業先も違ってきます。
税理士の主な顧客は、個人や中小規模の法人です。
就業先は税理士法人や税理士事務所(会計事務所)、企業内の税務部門などです。
一方で公認会計士の顧客は、財務諸表の作成が義務づけられる大手の企業や上場企業がメインになります。
就業先は監査法人や公認会計士事務所、税理士法人、企業内の監査部門などです。
税理士と公認会計士の違いについては、以下コラムでも詳しく解説しています。
仕事内容がきついといわれる理由は?
税理士の仕事内容は、以下の理由できついといわれています。
- ミスをしてはいけない
- 試験合格後も勉強し続けなければならない
- 繁忙期の仕事量が多すぎる
ミスをしてはいけない
税理士の仕事はミスをしてはいけない業務です。
クライアントに代わって正確に納税処理を行わなければならないため、数字を正確に扱って税額を算出する必要があります。
「計算を間違えた」、「数値を誤って見ていた」などのミスを税理士がすると、納税する額も異なってしまうでしょう。
納税額が違った、納めるべき金額を納めてなかったという事態が起きれば、故意ではなくても追加料金の支払いや延滞料などをクライアントが払うことになります。
ミスできないプレッシャーや責任の重さから、税理士はきつい仕事だというネガティブなイメージがついたと考えられます。
試験合格後も勉強し続けなければならない
税理士は税に関する専門家として、常に情報をアップデートしなければなりません。
そのため、税理士試験に合格したあとも税に関する勉強をし続ける必要があります。
また、税制や確定申告の方法などは、時代に合わせて変化します。
クライアントの代理業務や経営面において適切なアドバイスを行うためには、税に関するあらゆる知識を身につけていく必要があるでしょう。
税理士の仕事を続ける限り勉強しなければならないため、人によってはきついと感じるかもしれません。
繁忙期の仕事量が多すぎる
税理士はクライアントの確定申告や決算を行う時期が繁忙期のピークです。
クライアントによって差はありますが、繁忙期の仕事量は閑散期と比べると大幅に増えます。
個人と3月に決算期としている法人の両方が顧客にいる場合、2〜3月に両者の繁忙期が重なり、一気に忙しくなるでしょう。
また、納税や関係書類の提出には期間が設定されているため、スケジュールをずらすこともできません。
繁忙期だけに注目してしまうと、税理士は仕事量が多くてきついという印象になるかもしれません。
将来仕事がなくなるって本当?
税理士の仕事は将来AIに取って代わられてしまうのではないか、といわれていますが、それは考えにくいといえるでしょう。
確かに、技術の発達により記帳などの業務が自動化されています。
最近では、国税庁のホームページでチャットボットに国税に関する相談をすることも可能です。
しかし、税理士の仕事は税務処理だけではなく、クライアントの相談に乗り、経営と納税のバランスを取るためのコンサルティング業務なども行います。
顧客との綿密なコミュニケーションや代理業務の最終的なチェックや判断はAIでは難しいため、将来も人間が担っていくと予想されています。
ただし、業務の効率化を図るためにAIを利用して業務を進めていくことは、今後大いにあり得るでしょう。
AIをうまく利用できる税理士になれるよう、知識を付けておくのをおすすめします。
税理士とは?どんな仕事内容?まとめ
税理士は税務に関する専門家としてクライアントの相談相手となり、納税者の税に関する業務を代理で行うのが主な仕事です。
また、国家資格の税理士は、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つが独占業務です。
独占業務の他には、記帳代行や会計業務、コンサルティング業務などを行っており、税の知識を活かしてさまざまな業務ができます。
また、税理士のクライアントは個人と法人がメインです。
クライアントによって業務の流れが異なり、個人の場合は例年2〜3月に行われる確定申告、法人では各企業が定める決算期に合わせて仕事を進めます。
税理士として働きたい場合は、税理士試験に合格しなければなりません。
試験合格には会計学に属する科目と税法に関する科目の合計5科目の合格が必要です。
難易度が高い試験ですが、合格して税理士資格を取得できれば、税理士として自分の希望に合わせた働き方が叶います。
自身で独立して開業税理士になり、高い年収を得るということも夢ではありません。
「これから試験勉強を始めたい」という方は、効率的に学べる予備校や通信講座などを利用するのがおすすめです。
時間を有効に使いながら、最短ルートで人気の税理士資格合格を目指しましょう。
税理士試験の合格を
目指している方へ
- 税理士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
税理士試験講座がおすすめ!
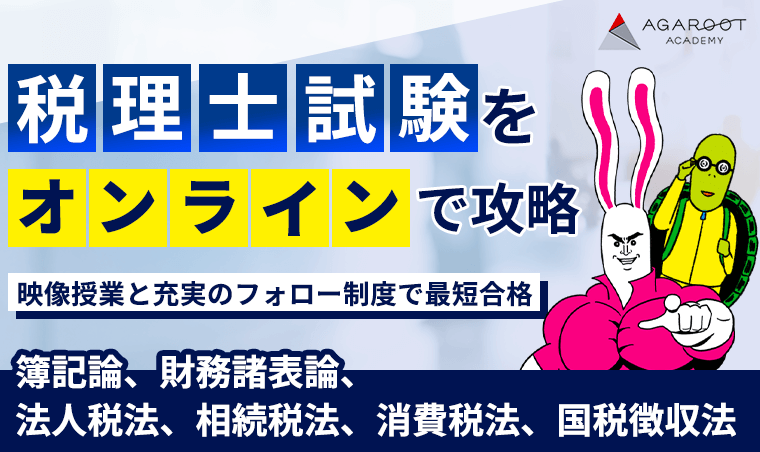
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
受講生専用SNS「学び舎」で受験生同士の交流が可能
▶税理士試験講座を見る




