宅建試験の合格率や難易度は?偏差値で例えると?難しい?など解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
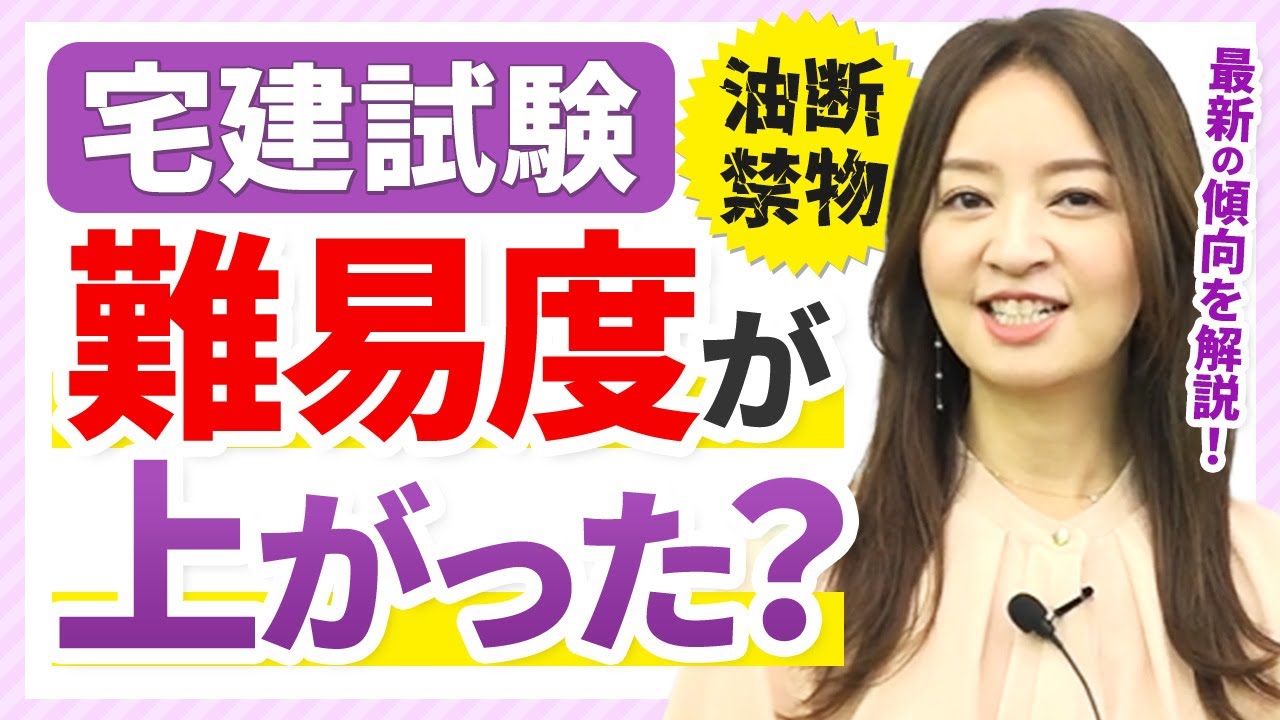
宅建試験の難易度や合格率はどの程度なのでしょうか?また、偏差値で例えるとどういった値となるでしょうか?
この記事では、宅建試験の難易度や合格率の推移、偏差値で例えた場合の値などについて解説していきます。
宅建試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 宅建試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの宅建試験講座を
無料体験してみませんか?


約8.5時間分の講義が20日間見放題!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
宅建試験に合格するためのテクニック動画!
直近の試験の解説動画+全問解説テキスト!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
宅建試験の難易度・合格率について
宅建の合格率は例年13%〜19%。宅建の難易度は必ずしも高くないと考えられます。社労士などと比べると合格率は高めであり、国家資格の中では比較的合格しやすいと言えるでしょう。
なお、『令和6年度宅地建物取引士資格試験結果の概要』によると令和6年(2024年)度の宅建試験の合格率は18.6%(受験者数241,436人 、合格者数44,992人)、合格点は37点という結果となりました。
また、令和5年(2023年)度の宅建試験の合格率は17.2%、合格点は36点でした。
宅建の合格率・合格点の推移 過去10年分
過去10年の宅建試験は、合格点が例年13~19%、合格点が31~38点/50点で推移しています。
詳細なデータは以下の通りです。
| 年度 | 合格率 | 合格点 | 合格点 (5点免除) |
受験者数 | 合格者数 |
| 2024年度 (令和6年度) |
18.6% | 37点 | 32点 | 241,436人 | 44,992人 |
| 2023年度 (令和5年度) |
17.2% | 36点 | 31点 | 233,276人 | 40,025人 |
| 2022年度 (令和4年度) |
17.0% | 36点 | 31点 | 226,048人 | 38,525人 |
| 2021年度 (令和3年度12月実施) |
15.6% | 34点 | – | 24,965人 | 3,892人 |
| 2021年度 (令和3年度10月実施) |
17.9% | 34点 | 29点 | 209,749人 | 37,579人 |
| 2020年度 (令和2年度12月実施) |
13.1% | 36点 | 31点 | 35,261人 | 4,610人 |
| 2020年度 (令和2年度10月実施) |
17.6% | 38点 | 33点 | 168,989人 | 29,728人 |
| 2019年度 (令和元年度) |
17.0% | 35点 | 30点 | 220,797人 | 37,481人 |
| 2018年度 (平成30年度) |
15.6% | 37点 | 32点 | 213,993人 | 33,360人 |
| 2017年度 (平成29年度) |
15.6% | 35点 | 30点 | 209,354人 | 32,644人 |
| 2016年 (平成28年度) |
15.4% | 35点 | 30点 | 198,463人 | 30,589人 |
| 2015年 (平成27年度) |
15.4% | 31点 | 26点 | 194,926人 | 20,028人 |
例年の受験生は20万人以上であり、そのうち合格者は3万~4万人程度と多くの方が不合格となっています。
しっかり勉強して備える必要がある試験といえるでしょう。
宅建試験の難易度を大学の偏差値で例えると?

宅建試験の偏差値は55〜56で、難易度としては測量士や管理業務主任者試験などと同じくらいと言えるでしょう。
また、宅建試験の合格に必要な勉強時間は300〜400時間ほど。
資格試験の難易度と大学入試の難しさは比べられるものではないという前提がありますが、あくまでひとつの目安としてイメージが湧きやすいように参考にしていただければと思います。
資格の難易度と大学入試の難易度を、以下の表にまとめました。
| 大学 | 偏差値 | 試験 |
| 東京大学・京都大学 | 68~ | 司法試験・予備試験 |
| 慶應大学・早稲田大学・ 上智大学 |
65~67 | 不動産鑑定士・司法書士・ 弁理士 |
| 明治大学・立教大学・ 中央大学・法政大学・ 青山学院大学 |
60~64 | 土地家屋調査士・中小企業診断士・社労士・ 行政書士・技術士二次試験・通関士・ マンション管理士・ケアマネジャー |
| 日本大学・東洋大学・ 駒澤大学・専修大学 |
55~56 | 技術士一次試験・宅建・測量士・ 管理業務主任者・社会福祉士・ インテリアコーディネーター |
※上記の表は、資格試験の合格に必要な勉強時間をもとに作成しています。宅建の難易度をわかりやすく知っていただくためのイメージとして参考にしていただけましたら幸いです。
宅建試験の難易度を大学入試に例えてみると、あくまでイメージにはなりますが早稲田大学や慶応大学、青山学院大学の入試よりは、難易度が高くないと考えられます。
大学に例えるならば、日本大学、東洋大学、駒澤大学などの大学入試と同等の難易度と考えられます。
宅建試験も簡単すぎるということはなく、しっかり対策する必要があると言えるでしょう。
また、宅建試験とよく比較される他の不動産資格には、マンション管理士や管理業務主任者といった資格があります。
マンション管理士試験の難易度を大学に例えると中央大学や明治大学、法政大学と同じ位の難しさであり、マンション管理士の方が宅建よりも難易度は高いといえます。
宅建と管理業務主任者の難易度は、近いところにあるといえるでしょう。
宅建と難易度を比べられることの多い行政書士と比較すると、宅建よりも行政書士の方がやや難しいと考えられます。
宅建の難易度ランキング(合格率・勉強時間)

宅建をその他国家資格と比較してランキング化したところ、合格率では行政書士より少し高く管理業務主任者より少し低い、勉強時間では管理業務主任者と同程度でマンション管理士よりは少し少ないといった結果になりました。
以下でそれぞれについて詳細に見ていきます。
まず、「合格率」の点で、宅建試験とよく比較される国家資格と直近の合格率を並べてみると以下のようになりました。
| 資格名 | 合格率*1 | 受験者数*1 |
| 宅建士 | 15~19% | 約20万人*2 |
| 司法書士 | 3~4% | 約1万人 |
| 社労士 | 6~7% | 約4万人 |
| マンション管理士 | 8~9% | 約1万人 |
| 行政書士 | 11~15% | 約5万人 |
| 管理業務主任者 | 20~30% | 約1.5万人 |
| 簿記2級(統一試験) | 11~30% | 約1万人 |
宅建試験の合格率は、管理業務主任者に次いで高いことが分かります。
合格率の観点では、宅建試験は比較に挙げた法律系の資格より合格率が高く、不動産関係資格の中では管理業務主任者に次いで合格率が高いため、取得しやすい資格といえるでしょう。
そのため、宅建士試験は他の資格への登竜門と位置付けられることもあります。
その登竜門的な位置づけが、宅建試験の合格率が13~19%と低い理由にもつながっています。
また、簿記2級は合格率17%~30%と幅がありますが、宅建士と比べると難易度は低いといえます。
次に勉強時間で難易度を比較してみましょう。
一般に、宅建士試験の合格に必要な勉強時間は300~400時間といわれています。
他の資格ではどのくらいの勉強時間を必要としているのか、以下の表でまとめてみました。
| 宅建士 | 300~400時間 |
| 管理業務主任者 | 300時間 |
| マンション管理士 | 500時間 |
| 行政書士 | 600~1000時間 |
| 社労士 | 1000時間 |
| 司法書士 | 3000時間 |
| 簿記2級 | 200時間 |
これをみると、司法書士は3,000時間以上もの多くの時間を勉強時間を費やす必要があり、年単位での勉強をしなければならないことが分かります。
また、行政書士も1,000時間と長い勉強時間が必要です。
一方、宅建士の勉強時間は管理業務主任者と同様、300~400時間の勉強で合格水準に到達します。
他の国家資格より短い勉強時間で合格できるということが分かります。
司法書士試験やマンション管理士試験などと宅建士試験では、民法や区分所有法といった科目が共通します。
そのため他の国家資格の勉強をするときにも、宅建試験で学習した部分は必ずしも改めて学習する必要はなく学習量の圧縮ができます。
更に、マンション管理士や管理業務主任者などと職域が近く、宅建士としてマンションの売買で関わったうえこれらの資格に基づいて引き続き管理業務に関与できるでしょう。
このような点から、宅建士とのダブルライセンスを目指すことも可能です。
もっとも、宅建士試験は簡単という意味ではなく、あくまで「他の資格と比較」すると「難しくない」ということに注意が必要です。
毎年20万人以上が受験し合格率が13~19%で推移していることからわかる通り、17万人以上もの多くの人が不合格になり涙をのんでいます。
宅建試験に合格することはすごいと言えるレベルです。
また、勉強時間300~400時間とはいえ、この水準まで勉強せずに受験し、何年も不合格になる受験生もいます。
確実に合格したい場合には講座の利用も一つの手。
講座を受講すれば効率的に学習することが可能であり、試験へのモチベーションを維持しながら、より確実に合格しやすいといえるでしょう。
今まで法律や資格試験の勉強をしたことが無い人にとって特におすすめと考えられます。
なぜなら、これらの人は勉強を進めていくうちに疑問が多く出るため調べる時間が沢山必要なうえ、集中して勉強する機会が少なかったのでモチベーションが上がらず、挫折しやすいから。
また、勉強を始める時期に関しましては、必要な勉強時間から逆算すると、勉強を開始する時期としては約半年前から行っている方が多くいるため、余裕をもって勉強に励んでいただくのが良いでしょう。
宅建の合格率が低い理由は?予備校を活用した方が良い?など解説
宅建試験は合格率が低いから合格は無理と諦めていませんか?
多くの受験者が、宅建試験に挑む前に合格を諦めてしまいがちです。
しかし、宅建試験の合格率が低い理由は、難易度の高さ以外にも多くあります。
ここでは、宅建試験の合格率が低い理由と、予備校活用のメリットを解説します。
宅建の合格率は低い?まずは公式データをチェック!
宅建士試験の合格率が「低い」との声が多いなか、真偽の程はどうなのでしょうか。
噂だけでなく、公式のデータに基づいて現状を把握することが重要です。
以下では、宅建士試験を運営している一般財団法人不動産適正取引推進機構が公表しているデータに基づいて、合格率の実際を探っていきましょう。
| 試験年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2024年度 (令和6年度) | 18.6% |
| 2023年度 (令和5年度) | 17.2% |
| 2022年度 (令和4年度) | 17.0% |
| 2021年度 (令和3年度12月実施) | 15.6% |
| 2021年度 (令和3年度10月実施) | 17.9% |
| 2020年度 (令和2年12月実施) | 13.1% |
| 2020年度 (令和2年10月実施) | 17.6% |
| 2019年度 (令和元年実施) | 17.0% |
データを見ると、宅建試験の合格率は過去数年間で13%から19%の間で推移していることが分かります。
この合格率を「高い」と取るか「低い」と取るかは受け手の主観に左右されます。
しかし、毎年20%は切っている=5人に4人以上は不合格となる試験であるため、「低い」と捉える声があるのも無理はないでしょう。
次の章では、これらの数字がなぜ低いと感じられるのか、その背景にある主な要因を詳しく解説します。
公表されている合格率のデータは一つの指標に過ぎませんが、受験者が試験に臨む際の心構えや、どのような準備が必要かを考える上での参考になるでしょう。
実際の合格率を知ることで、受験勉強に対するモチベーション維持や、より効果的な学習法の策定に役立てることが可能です。
宅建の合格率が低いと考えられる3つの理由
「宅建の合格率は低い」という声が多く聞かれますが、それにはいくつかの理由が考えられます。
この章では、その背後にある主要な3つの理由を詳細に分析していきます。
具体的には
- 受験制限がないこと
- 合格者数を調整している可能性
- 不動産関連資格としての受験のしやすさ
が挙げられます。以下でそれぞれについて詳しく見ていきます。
受験制限がないため
資格試験における受験制限は、受験者の質を確保し、その結果、合格率にも影響を及ぼす重要なファクターです。
多くの資格試験、特に専門性が高いものでは、受験資格が厳格に定められています。
各種試験において、受験できる人に一定の制限をかけている理由としては、社会で必要とされる人数に対して、受験者が多いことが挙げられます。
誰もが合格できても、その後、供給が多すぎればその職業で食べていけなくなる人が出てしまいます。そのため、専門性の高い多くの国家資格は、受験資格を厳格に定めているのです。
具体的な例としては、司法試験があります。
この試験は、法律の専門家(弁護士や検事など)を目指す者にとっての関門であり、受験するためには予備試験の合格などの特定の経歴・学歴が要求されます。
受験資格が設定されているため、受験者は高い知識レベルや深い理解を持つ者が多く、結果的に合格率も20~40%と、他の一般的な資格試験と比較して高い水準に保たれています。
一方、宅建試験はその受験資格に特に制限がないため、受験する意思さえあれば原則誰もが受験することができます。
業界知識がほとんどない初学者から、キャリアチェンジを考えている人、あるいは「試しに」という軽い気持ちで受験する人など、多種多様な背景を持つ受験者がいるでしょう。
真剣に取り組んでいる受験者も多いですが、同時に目的やモチベーションがそれほど強くない受験者も少なくありません。
こうした状況は、全体の受験者層の質が不均一であることを意味し、受験者全員が試験の難易度に適切に対応できるわけではないことを示しています。
これが宅建試験の合格率が他の専門的資格試験と比較して低い要因の一つとされています。
合格者数を調整している(可能性がある)ため
宅建試験の運営においては、その合格基準が一定ではなく、毎年の受験者のパフォーマンスや市場のニーズ、業界の状況に応じて変動する可能性が指摘されています。
具体的には、宅建試験において、合格点は固定されているわけではなく、その年の受験者の平均点、難易度、及び試験のバランスから動的に算出されるとされています。
この方式は、他の多くの専門試験でも採用されている標準化されたテスト手法の一つで、試験の公平性と一貫性を保つためのものです。
しかし、合格点を毎年変化させるという方法には一定の合格者数を維持するという副次的な効果がある可能性が指摘されています。
実際、過去数年にわたるデータを見ると、宅建試験の合格者数は毎年約3万人前後という数字に一定の傾向が見られます。
この傾向は、不動産市場の規模や業界内での認定資格者の需要に応じて、合格者数が調整されている可能性を示唆しているのです。
「調整」には、業界の健全性を維持するという理由があるとされています。
資格を持つ者が市場に氾濫すると、サービスの質が低下したり、不動産業界における賃金や就職機会にネガティブな影響を及ぼす恐れがあります。
そのため、業界自体が持続可能な成長を遂げ、質の高いサービスを提供できるよう、資格取得者の数を適切にコントロールする必要があるのです。
合格率は市場の状況やその年の受験者の質によって左右されるため、一定の割合を保つというよりは、総合的な状況に基づいて調整されると考えられています。
したがって、受験者数が増加しても、合格者数は一定である傾向があり、それが自動的に合格率を低く抑える結果を生んでいるのです。
不動産関係の資格の中でも「とりあえず選ばれやすい」ため
不動産業界において、宅建士資格はその知名度と権威から不動産系国家資格の一つに数えられることがあります。
宅建士資格以外には、マンション管理士や管理業務主任者などが含まれます。
不動産系の国家資格は、不動産業界におけるプロフェッショナルの証であり、特に宅建士は不動産取引全般に関する幅広い知識を要求される資格であることが特徴です。
宅建士資格の魅力は、資格の取得が業界内での地位向上、キャリアアップ、さらには顧客からの信頼獲得に繋がる点にあります。
また、不動産という領域は日常生活に密接に関わっており、多くの人が一度はそのサービスを利用することから、資格の認知度も自然と高まっています。
その結果、不動産関連の資格を目指す多くの人が、他の選択肢を十分に検討することなく、あるいは業界についての深い理解や実務経験を有していない状態で「まずは宅建から」と考えるケースが少なくありません。
しかし、こうした「とりあえず」の精神は、宅建士試験の受験者層に多様性をもたらす一方で、必ずしも宅建試験の難易度や業界の要求する専門性を十分に理解した上で挑戦しているわけではないため、合格率に影響を与える重要な要因となっています。
資格取得を目指す者が増えれば増えるほど、その中で実際に合格できるのは一握りという現実が、合格率の低さに拍車をかけているのです。
さらに、宅建士試験には広範な法律知識や業界特有の実務経験が求められるため、試験対策として必要な学習量は他の国家資格と比較しても少なくありません。
特に法律関連の問題では、細部にわたる理解と正確な知識が必要とされます。そのため、「とりあえず」の心構えで臨んだ受験者が直面する難易度は、予想以上であることが多いのです。
こうした背景を踏まえると、宅建士試験の合格率が他の資格試験に比べて低い理由は明らかです。
受験者自身が試験の本質とその要求する能力を正しく理解し、適切な準備と真剣な取り組みが不可欠という事実が、この資格が業界内外から高い評価を受けている理由の一つでもあります。
特に独学だと合格率が低くなる可能性も
宅建試験の合格率が低い要因をこれまで見てきましたが、特に独学での挑戦はさらに厳しいとされています。
実際、アガルートアカデミーのアンケートによれば、独学受験者の合格率は約10%にとどまっています*。
*全国向け無作為抽出調査ではないため、あくまで参考数値です。
独学では試験に必要な広範で複雑な知識を網羅することの難しさを示唆しています。
対照的に、アガルートアカデミーの利用者の合格率は令和6年度において66.26%の合格率を示し、専門的な指導が受験成功に大きく寄与することを反映しています。
2024年度(令和6年度)における宅建試験の全受験者の合格率が18.6%であるのに対して、アガルートアカデミーを利用した方の合格率は66.26%と圧倒的に高いことが特徴です。
加えて、独学受験者の合格率は10%程度となっていることから、宅建試験に独学で合格することの難しさが際立っています。
こうしたデータから、宅建試験の難易度は高く、特に独学での学習では不十分な場合が多いことが伺えます。
したがって、資格取得を目指す際には、適切な学習方法とサポート体制の選択が重要となるでしょう。
宅建の合格率を高めるためのポイント

- 登録講習(5点免除のために受講する講習)を利用する
- 受験指導校(予備校・資格スクール)を利用する
- なるべく早めに開始する
①登録講習(5点免除のために受講する講習)を利用する
現在不動産業にお勤めの方等「登録講習」を利用することができる環境にある方は、この講習を受講するのも一つの手。
5点免除の適用を受けると、必要得点率の観点では難易度は下がります。
また5点免除ということで、問題を5つ(問46から50までの5問)解く必要がなくなるので、勉強する範囲が少し減ります。
②受験指導校(予備校・資格スクール)を利用する
資格試験の勉強をするにあたって、受験指導校を利用するというのも一つの手。
プロの講師が要点を絞った指導をしてくれるため、宅建試験を独学で学習するよりも効率よく合格を目指すことが可能です。
なお、中でもアガルートアカデミーの宅建試験講座はオンライン講座であり、時間や場所を選ばずに勉強可能です。
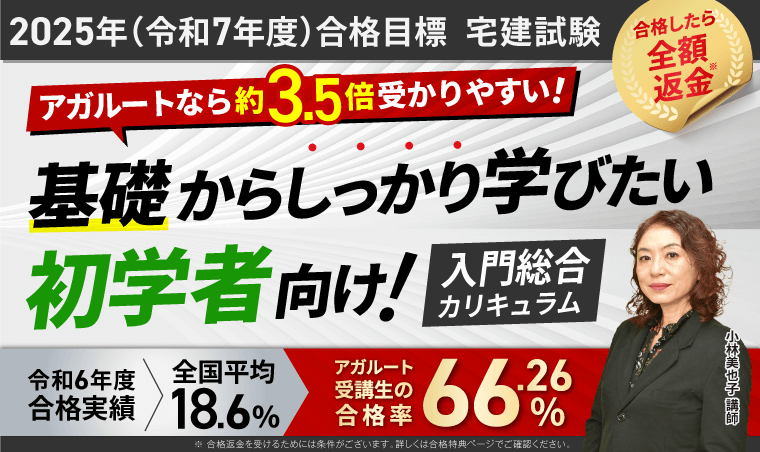
③なるべく早めに開始する
宅建試験の合格を決意したなら、早速勉強を始めると良いでしょう。
一般論として、試験勉強は早く始めた方が合格可能性が上がると考えられます。
なるべく早い時期に勉強を始めることで、例えばなかなか勉強がうまくいかないときの軌道修正を図るタイミングを多く設けることができたり、期間を長くする分だけ1日・1週間の勉強時間を少なくすることもできます。
まとめ

今回は、宅建の難易度を解説しました。
最後にこのコラムをまとめます。
- 宅建試験は例年、合格点が例年20%弱、合格点が30点前後
- 宅建は大学入試に例えると、日本大学・東洋大学等と同じくらいの難易度といえる
- 宅建の合格率は受験制限がないことなどを理由として低いと言われる
- 合格を目指す場合予備校利用など賢い選択を
宅建の難易度についてイメージが湧けば幸いです。
より確実に合格を目指すのであれば、通信講座の活用もおすすめです。
アガルートアカデミーの宅建試験講座は資料請求で講座の一部を無料体験できます。
ぜひ講座を無料で体験してみてはいかがでしょうか?
宅建試験の合格を
目指している方へ
- 宅建試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの宅建試験講座を
無料体験してみませんか?


約8.5時間分の講義が20日間見放題!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
宅建試験に合格するためのテクニック動画!
直近の試験の解説動画+全問解説テキスト!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
豊富な合格実績!
令和6年度のアガルート受講生の合格率66.26%!全国平均の3.56倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!



