宅建テキスト・参考書・教科書おすすめ!独学の勉強で重宝する10選など!2025年最新
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

宅建試験の勉強を始めるぞ!と決意し、「まずは教科書を買わなくっちゃなぁ~」というわけで書店へ行って「宅建」のコーナーを見てみたら……「え、こんなにあるの?」と戸惑ったのではないでしょうか。
今回この記事を執筆するのにあたり私も宅建試験のテキストを書店へ見に行ってきたのですが、私が受験していた頃よりも種類が増えていました(汗)。
「この中から独りで選ぶのか……どうやって?」
率直にそんな風に思いました。
宅建試験の勉強を始めるのにあたり必須のアイテムである「教科書(テキスト)」をどうやって選べばよいのか。
独学に向いたおすすめのテキストには、一体どんなものがあるのか。
今回の記事ではそういった点を紹介したいと思います。
私なりのおすすめポイントをピックアップしながら紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。
宅建試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 宅建試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの宅建試験講座を
無料体験してみませんか?
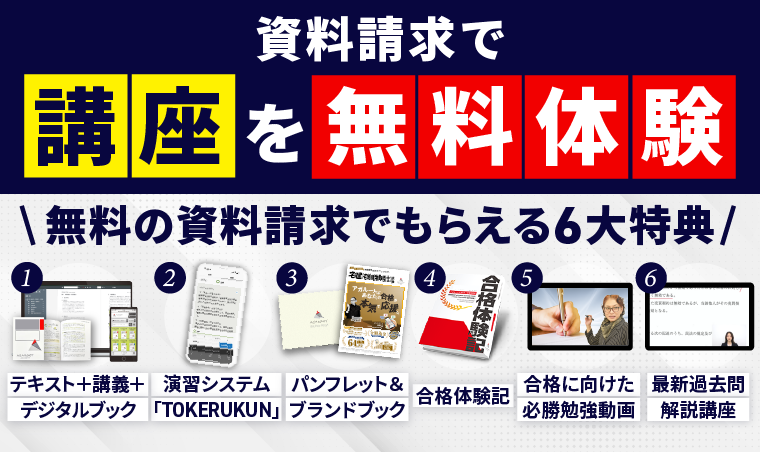
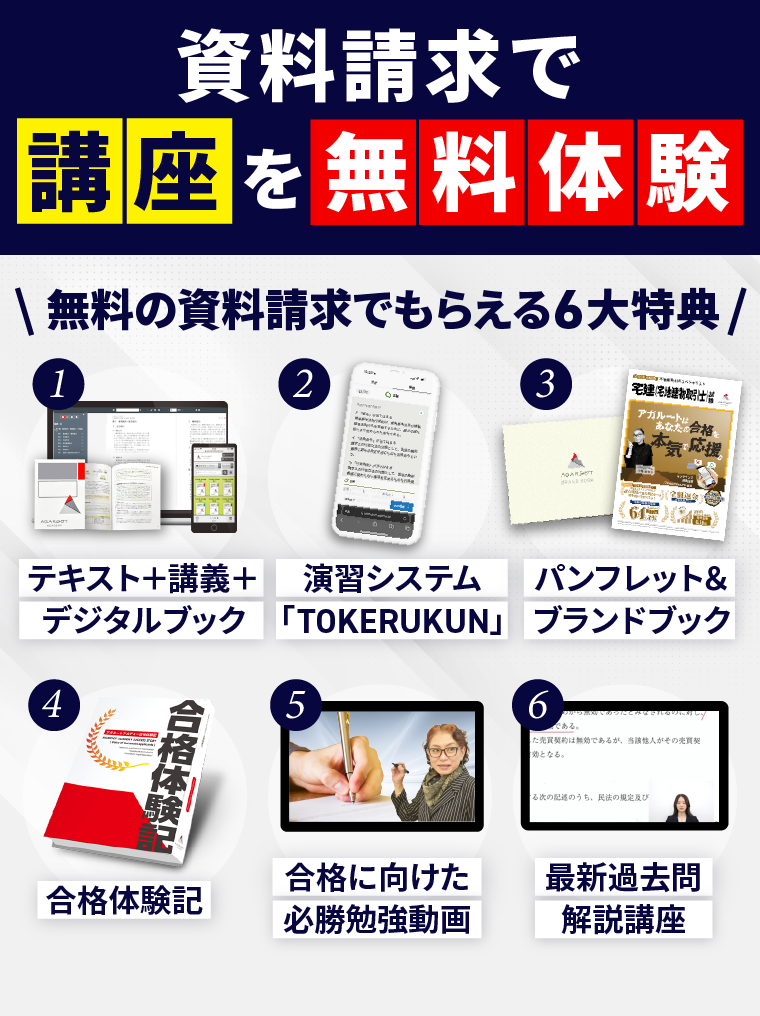
約8.5時間分の講義が20日間見放題!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
宅建試験に合格するためのテクニック動画!
直近の試験の解説動画+全問解説テキスト!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
- 1 宅建試験の独学におすすめのテキスト10選
- ①この1冊で合格!水野健の宅建士神テキスト(2025年度版)(KADOKAWA)
- ②どこでも!学ぶ宅建士基本テキスト(2025年度版)(建築資料研究社)
- ③パーフェクト宅建士基本書(2025年版)(住宅新報出版)
- ④さくさくわかる!やさしい宅建士のテキスト(2025年度版)(TAC出版)
- ⑤スッキリわかる宅建士 中村式戦略テキスト(2025年度版)(TAC出版)
- ⑥みんなが欲しかった!宅建士の教科書(2025年度版)(TAC出版)
- ⑦わかって合格る宅建士基本テキスト(TAC出版)
- ⑧宅建士合格のトリセツ基本テキスト(2025年版)(東京リーガルマインド)
- ⑨出る順宅建士合格テキスト(2025年版)(東京リーガルマインド)
- ⑩どこでも宅建士とらの巻(東京リーガルマインド)
- 2 目的別宅建テキストおすすめについて
- 3 マンガで学習!宅建の勉強ができるおすすめマンガ3選
- 4 宅建の勉強にオススメの電子書籍(Kindle)4選
- 5 宅建の独学に六法は必要か?
- 6 宅建試験の独学におけるテキストの選び方
- 7 まとめ
1 宅建試験の独学におすすめのテキスト10選
まずは、書店やインターネットショッピングで購入可能な宅建試験のテキストのうち、おすすめのテキストを10冊(10種類)紹介していきます。
近くに大きな書店があるという方は、この記事を見ながらテキストを選んでみてくださいね。
※ 掲載順は「出版社名」「書籍名」のかな順です。
①この1冊で合格!水野健の宅建士神テキスト(2025年度版)(KADOKAWA)

共通テスト向けの「面白いほど」シリーズや英単語帳の「鉄壁」で有名なKADOKAWAから出版されている宅建試験向けのテキストです。
学習参考書の製作実績のある出版社さんが手がけたものということもあり、全体的にデザインがよく、情報の1つ1つがまとまっているといった印象です。
宅建試験を受験される方には法律初学者の方が多いことへの配慮なのか、イラストが多く、学習者のイメージ・想像を助ける構成になっています。
それでいて、イラストに対応した説明文もしっかりと記載されており、試験に向けた勉強を進めていくなかでスキのない作りとなっています。
私個人としては、特に「第3章 法令上の制限」のところの「6 土地区画整理法」の箇所が、土地区画整理事業というイメージが非常に難しい分野への理解を促す仕組みが随所にこめられているという印象を持ちました。
②どこでも!学ぶ宅建士基本テキスト(2025年度版)(建築資料研究社)

宅建講座などの講座を開講されている日建学院さんが、宅建試験の受験生向けに出版しているテキストです。
字が大きくてレイアウトがいいなという第一印象。
説明文が適度にかみ砕かれており、初めて法律の勉強をしようという方も、この1冊で無理なく宅建試験の勉強を始められるでしょう。
各ページに余白が適度に設けられており、例えば過去問集を解くなかでテキストに追加したいメモをたくさん書き込むことも可能です。
こういった使い勝手の良さは、学習期間が長くなっても、テキストが私たちの“相棒”として最後まで活躍してくれるのにあたり重要な要素です。
また、このテキストは、民法などを学習する「権利関係」の学習順がオーソドックスなものとなっています。
宅建試験向けのテキストは、学習順が他の試験とは違ったものになることが多いのですが、このテキストの場合そのようなことがないというわけです。
ほかの資格試験の受験生の方が、宅建試験にチャレンジされる際にこのテキストを選んでいただくと、違和感なくスムーズに宅建試験の勉強に移行できるでしょう。
③パーフェクト宅建士基本書(2025年版)(住宅新報出版)

一言で言えば、「ザ・王道」。非常に「硬派な」テキストといってよいでしょう。
宅建試験の業界において大変有名な住宅新報社さんが毎年出版しているテキストで、老舗の王道テキストは、とても信頼性の高いものとなっています。
文章による説明をメインとした構成となっており、理解重視・情報量重視の方にはぴったりの“骨太な”テキストです。
1つ1つの項目をしっかりと理解していただこうという著者陣のこだわりを随所に感じるような作りとなっており、ほかの資格試験の受験生の方たちにはとても相性の良い1冊と言えます。
また、説明文のさまざまな箇所では、説明の根拠となっている法律の条文番号が掲載されています。
法学部の学生さんが、日頃の講義で用いている六法(法令集)を使いながら勉強することも可能で、学部で受講している講義の復習の助けにもなってくれることでしょう。
④さくさくわかる!やさしい宅建士のテキスト(2025年度版)(TAC出版)

とてもページ数の少ないテキストです。
1つ1つの説明がとてもシンプルであり、試験で問われるポイントを大胆に絞ったうえで解説を行うスタイルのものとなっています。
「まとめノート」を使うような要点を絞って短期間で一気に仕上げるスタイルの勉強が自分に合っているという方には、良いものなんじゃないかと思います。
徹底的に情報を絞り込んでいることから、各項目の説明は決して詳しいほうではありません。
その意味で、試験対策ということで割り切った勉強ができる方向けと、使う方を選ぶテキストと言ってよいかもしれませんね。
⑤スッキリわかる宅建士 中村式戦略テキスト(2025年度版)(TAC出版)

キツネやタヌキなどのキャラクターがたくさん出てくる表紙・内容ということもあり、書店で手に取った際の印象は「う~ん……」といったものでしたが、買って実際に使ってみると、字が大きく読みやすいものとなっています。
それでいて、余白も適度にあり、吹き出しコメントの形式で挿入されている補足説明がメインの説明箇所の読解の邪魔にならず、とても気の利いたテキストです。
私個人としては、特に「パートⅡ」の「法令上の制限」が全体的によくまとまっているなという印象を持ちました。
勉強すべき情報をセレクトしたうえで、図やイラストの力を借りながら理解してもらおうという著者の努力が垣間見えました。
「法令上の制限」に苦手意識のある受験経験者の方は、初めにこのテキストの力を借りてみるのもいいかもしれません。
⑥みんなが欲しかった!宅建士の教科書(2025年度版)(TAC出版)

宅建試験向けのテキストのなかでは異色の1冊です。
このテキストは、「教科書」というよりも「絵本」「イラスト集」というイメージのほうが近いかもしれません。
非常に直感的な作りとなっていて、理解重視というよりも印象重視のテキストと言ってよいでしょう。
なので、書店で実際に手に取り、ほかのテキストと比較した際の印象がとてもいい。
「これはまぁ売れますわな」という感想です。
構成はフルカラーで、プレゼンテーションの際に使うスライドにカラーペンで書き込んだような内容となっています。
テキストの使用者が書き込むような内容を予め書き込んでおきました!といった具合です。
イラストをたくさん用いたことや、説明を簡素にしたことの代償として、全体的に情報は決して多くはありません。
説明文も必ずしも理解を重視したものとは言えませんから、受験経験者の方にはあまり向いてないかなと思います。
初学者の方が、「はじめの一歩」を踏み出すための1冊と言えるでしょう。
⑦わかって合格る宅建士基本テキスト(TAC出版)

「わかって」と書籍名に入っているとおり、理解重視のテキスト。
『パーフェクト宅建士 基本書』と同じように、説明のなかには条文番号が掲載されており、法学部の学生さんやほかの資格試験受験生の方が宅建試験の勉強をするのにあたり相性が良いテキストと言えるでしょう。
それでいて、字が大きく適度にカラー化されており、初学者の方への配慮も忘れていない。
出題実績も邪魔にならない範囲で挿入されており、独学でもメリハリの効いた勉強が可能なように配慮もされている。
試験勉強に必要な情報が過不足なく触れられており、表紙の「最強」に恥じぬ構成となっています(「最強」の冠を堂々と出すだけの自信の根拠がよく分かりました)。
⑧宅建士合格のトリセツ基本テキスト(2025年版)(東京リーガルマインド)

各種資格試験の講座を開講しているLECさんで宅建試験の講座を担当されている友次先生のテキスト。
字が大きくイラストが豊富に盛り込まれています。
それでいて、説明文も、理解に必要な要素をしっかりと押さえつつシンプルなものとなっており、法律の説明・文章に慣れていない方でもスムーズに勉強を進めていくことが可能となっています。
これから宅建試験の勉強を始める初学者の方への配慮がふんだんに盛り込まれた“渾身の1冊”と言ってよいでしょう。
また、余白もしっかりと設けられています。
これは、このテキストと連動している「無料講義動画 全編45回」を視聴する際や、このテキストの姉妹本となる『分野別過去問題集』や『一問一答式過去問題集』で学習した際のメモ書き用のスペースとして用いることが可能です。
こういった配慮は、合格を勝ち取るための“相棒”とテキストになってもらう上で重要で、とてもスキのない作りになっています。
⑨出る順宅建士合格テキスト(2025年版)(東京リーガルマインド)

圧倒的な情報量。この一言で、このテキストの特徴を言い表すことができます。
「出る順」が、他のテキストを寄せ付けない圧倒的な長所は、その情報量の多さです。
これまで紹介したテキストが「教科書」だとしたら、「出る順」はまさに「辞書」と呼んでよいでしょう。
それほどに、ほかと比べて量の差があります(書店へ行かれた際には、ぜひ実物をご覧になってみてください)。
とにかく量が多いこともあり、初学者の方が「はじめの一歩」として手にとるのは危険すぎます。
また、他資格試験の受験生の方も、宅建試験は初めてなのですから、やはり手を出すべきではありません。
完全に「受験経験者向け」のテキストです。
この圧倒的な量を乗りこなし、このテキストで勉強していけば、試験本番には圧倒的な自信を持って臨めることでしょう。
⑩どこでも宅建士とらの巻(東京リーガルマインド)

試験で問われる可能性の高い箇所に限定し、メリハリの効いた学習で短期合格を目指す方向けのテキストです。
要点を絞った説明で構成されており、テンポよく読み進めていくことが可能です。
分野別過去問題集の『ウォーク問」と連動しており、このテキストに掲載されている情報にプラスアルファしたい場合には『ウォーク問』を利用して過去問の情報を追加することができます。
以上が、今回紹介する10冊(10種類)のテキストです。
なお、宅建試験のテキストには、これら以外にも以下のテキストがあります。
- いちばんわかりやすい!宅建士合格テキスト(’25年版)(成美堂出版)
- 動画で学べる宅建士テキスト(2025年版)(翔泳社)
- ユーキャンの宅建士きほんの教科書(2025年版)(自由国民社)
- 史上最強のテキスト(2025年版)(ナツメ社)
- らくらく宅建塾基本テキスト(2025年版)(宅建学院)
2 目的別宅建テキストおすすめについて
さて、ここまででさまざまなテキストを紹介させていただきました。
ここからは、これまで紹介したテキストを、目的物・タイプ別におすすめしていきたいと思います。
宅建試験の学習を始めるにあたり、参考にしていただければ幸いです。
(1) 図解・イラストを豊富に扱った学習をしたい方向け
まずは、「図解・イラストを豊富に扱った学習をしたい」という方におすすめのテキストから紹介していきましょう。
図解・イラスト重視の方におすすめのテキストは、以下の3冊です。
- みんなが欲しかった!宅建士の教科書(2025年度版)(TAC出版)
- スッキリわかる宅建士 中村式戦略テキスト(2025年度版)(TAC出版)
- 宅建士合格のトリセツ基本テキスト(2025年版)(東京リーガルマインド)
これらの3冊はイラストが豊富で、各項目の説明をイラストによるイメージ付けとセットで学んでいくことが可能です。
既に利用しているテキストがあるけど、どうしてもイメージしづらい箇所があるといった悩みがある方は、これらのテキストを「参考書(副読本)」として利用し、理解の助けにしていただくのも良いです。
(2) 理解を重視した正統派スタイルで学習をしたい方向け
次に、「理解重視・1つ1つの項目を正確に理解し記憶する」といった、いわば“正統派スタイル”の学習が好みだという方におすすめのテキストを紹介しましょう。
理解重視の正統派スタイルの方におすすめのテキストは、以下の3冊です。
これらの3冊は、図表やイラストを中心とした説明ではなく、文章を中心とした説明によって理解してもらおうというコンセプトのものです。
まさに正統派と呼べるテキストとなっており、これらをきちんと使いこなしていただくことで、受験生の皆さんを宅建試験の合格までしっかりとナビゲートしてくれることでしょう。
(3) 情報量を重視した学習をしたい方向け
次は、情報量を重視した方向けのテキストです。
以下の2冊が該当しますが、これらは情報量が多いことから、使いこなすのが結構難しいものとなっています。
情報量を重視した勉強というのは、どちらかと言えば、受験経験者向けのやり方になりますから、選ぶ際はご注意ください。
これら2冊は、宅建試験の書籍のなかでもその情報量の多さがトップクラスのものです。
情報量を追及する方は、これら2冊から選んでいただければよいです。
(4) 短期間の学習で一気に合格を目指したい方向け
最後に、受験申込みをした後から開始する等、短期の学習期間で合格を目指そうという方向けのものです。
短期間で合格レベルまで持っていくには、情報の取捨選択は避けられません。
テキストを購入する段階で、適切に取捨選択が行われたものを選んでおく必要があります。
宅建試験のテキストでは、これら2冊が短期間で合格を目指そうという方向けのものとなっています。
宅建試験で出題される可能性のある各論点を、コンパクトにテンポよく読み進めることが可能となっています。
3 マンガで学習!宅建の勉強ができるおすすめマンガ3選
これまで紹介したようなテキスト以外に、宅建試験の勉強用の書籍のなかには、マンガを使って試験で問われる項目を学んでいこうというコンセプトの書籍もあります。
いわば「マンガで学ぼう!」といった具合です。
そんなコンセプトの書籍のなかでおすすめするとなると、以下の3冊が該当します。
これらの3冊は、宅建試験で問われる項目をうまくマンガの世界に落とし込んでいるため、スムーズに理解できるでしょう。
いきなりテキストを買って勉強スタート!というのは不安だなぁ……という方は、こういったマンガの力を借りて、まずは各項目のイメージ作りからスタートしてみるのも手ですね。
番外編
最近、『正直不動産(ビッグコミックス)』を題材にした書籍が発売されました。
これは、『正直不動産』のなかで出てくる宅建試験に関わる話題をピックアップし、解説を加えるといったものです。
上記の「マンガで学ぼう!」というコンセプトからは少し離れていますが、コンセプトが近いものと思われるため、今回番外編としてピックアップしてみました。
『正直不動産』を読んだことのある方やドラマをご覧になったことのある方は、利用を検討してみるとよいかもしれませんね。
4 宅建の勉強にオススメの電子書籍(Kindle)4選
宅建試験の勉強には、紙の書籍(テキスト)ではなくKindleなどの電子書籍を利用したいという方もいらっしゃるでしょう。
今回紹介したテキストのなかには、電子書籍でも販売されているものがあります。
ここでは、電子書籍のなかでもメジャーなものであるAmazonのKindleで取り扱われているものを紹介しておきます。
- みんなが欲しかった!宅建士の教科書(2025年度版)(TAC出版)
- スッキリわかる宅建士 中村式戦略テキスト(2025年度版)(TAC出版)
- 宅建士合格のトリセツ基本テキスト(2025年版)(東京リーガルマインド)
- 出る順宅建士合格テキスト(2025年版)(東京リーガルマインド)
「(1) 図解・イラストを豊富に扱った学習をしたい方向け」で紹介した3冊は、図解・イラストをメインにした構成となっていることから、電子書籍として利用するのに向いていると思います。
「(3) 情報量を重視した学習をしたい方向け」で紹介した「出る順」は、情報量が多いこともあり、「電子書籍を用いた勉強」に慣れている方向けと言えるでしょう。
5 宅建の独学に六法は必要か?
さて、宅建試験の教材を紹介していると、「宅建試験の勉強に、六法は必要ですか?」といったご相談をいただくことがあります。
結論から言うと、六法は必要ありません。
というのも、宅建試験で勉強する法律は、「権利関係」という科目で出てくる法律であれば一般的な六法にも載っているのですが、「法令上の制限」「税その他」という科目で出てくるものに関してはほぼ掲載されていません。
得点源である「宅建業法(宅地建物取引業法)」ですら、かなり大きなもの(『判例六法プロフェッショナル(有斐閣)』級の大きさのもの)でないとまず掲載されていません。
宅建試験の勉強のなかで六法を用いるのは、相当ハードルが高いという話なんです。
先述のとおり、法学部の学生さんや他資格試験の受験生の方のような他の事情で六法を持ってますという方であれば、宅建試験の勉強に用いるのもよいかもしれません。
ですが、宅建試験の勉強のために六法をご用意いただく必要は全くありません。
6 宅建試験の独学におけるテキストの選び方
それでは最後に、独学で宅建試験の勉強を始めるにあたってテキストをどうやって選んでいけばよいのか、テキストの選び方についてお話をしたいと思います。
① 「テキスト」だけでなく「問題集」も一緒に見る・購入すること
今回紹介したテキストには、姉妹本として「問題集」が存在しています。
「分野別過去問題集」だったり「一問一答集」だったりしますが、テキストと問題集がセットで考えられているわけです。
このことは、例えば紹介したテキストのうち『宅建士合格のトリセツ基本テキスト』だと、各項目の冒頭に『合格のトリセツ』シリーズの一問一答過去問題集や分野別過去問題集の対応箇所が記載されていることからも分かります。
テキストを読んだだけでは、必ずしも問題が解けるようになるわけではありません。
そのため、「問題を解く」ことによりどれほどできるのかを試す必要があります。
テキストだけを選んで使っていたので、慌てて問題集を買って解いてみたら、「なんだか解説がわかりづらい・使いづらいな」とか「テキストのどこを見たらいいのか全然書いてない」とかいうように、問題集が全然合ってないなんてこと割とよくあります。
ですから、テキストを購入される際は、問題集も一緒に選んでおきましょう。
② 初学者向け・受験経験者向けを意識すること
テキストの紹介文のなかでも言及しましたが、「宅建試験向けテキスト」と名乗っているもののなかでも、初学者向けのものと受験経験者向けのものが存在しています。
初学者向けのものは、図解やイラストが豊富で、説明文が詳しいというよりも直感重視・インパクト重視という側面が強く、深い理解や情報を求める受験経験者にはあまり向いていません。
受験経験者向けのものは、深く正確な理解や多くの情報が求められることを考慮し、詳しい説明文や取り扱う情報量の多さで勝負する傾向があり、法律の世界の考え方や文章に不慣れな初学者には不向きといえます。
ご自身が果たして「初学者」なのか「受験経験者」なのか。
それによって選ぶべきテキストはずいぶんと変わってきます。
「売れているから」「みんなが使っているから」とかいったような購入の理由を他人に求めるのは、テキストの選び方としては相当危ないやり方ですのでなるべく止めましょう。
③ 勉強スタイルに合っているかを意識すること
例えば、電子書籍は、場所を取りませんし、スマートフォンがあればすぐに取り出すことができ、とても便利なものです。
しかし、宅建試験の勉強の場合、勉強のために電子書籍を利用する以上、スマートフォンはある程度大きな画面のものが求められてきます(小さな画面でも表示は可能ですが、表示領域が小さいので、とてもじゃありませんが勉強には向いていません)。
大きな画面のものは持っていないという方は、パソコンで表示して勉強することになると思いますが、それだと今度は勉強する機会が「パソコンの前にいるときだけ」になってしまい圧倒的に効率が悪いです。
以上のように、電子書籍自体は便利なものなわけですが、だからといって「あなたの勉強環境(勉強スタイル)」にあったものかといえば、それはまた別の話だというわけです。
ご自身の勉強スタイルに合ったテキストを選ぶことは、比較的長い期間勉強を続けていくうえでも重要なポイントであると言えるでしょう。
7 まとめ
宅建試験の勉強におすすめのテキストの紹介でした。
この記事をご覧になっている方は、今年の宅建試験に合格しよう!と決意し、勉強を始めるのにあたって「まずは情報収集だ!」ということで色々と調べてらっしゃる方だと思います。
きっと「宅建試験の教科書って、こんなにあるのか……どれにしたらいいんだろう?」とお悩みだったんじゃないかと思うのですが、この記事はそんなあなたにお役に立ったでしょうか?
今回紹介するのにあたり、どういった方に向いたテキストなのか、このテキストのおすすめのポイント・優れた箇所はどんなところか等テキストを購入するのにあたり気になるであろう話題を中心に解説させていただきました。
この記事の内容を参考にしていただいて、早速テキストを手に取ってみてください。
あなたの合格を期待しています、頑張りましょう!
宅建試験の合格を
目指している方へ
- 宅建試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの宅建試験講座を
無料体験してみませんか?
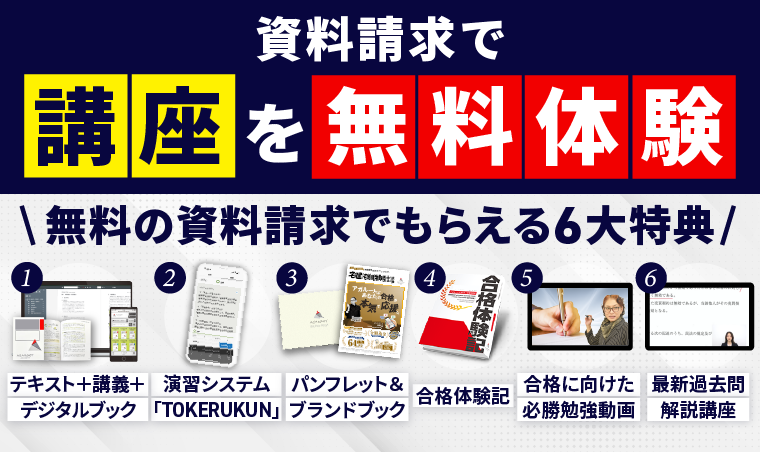
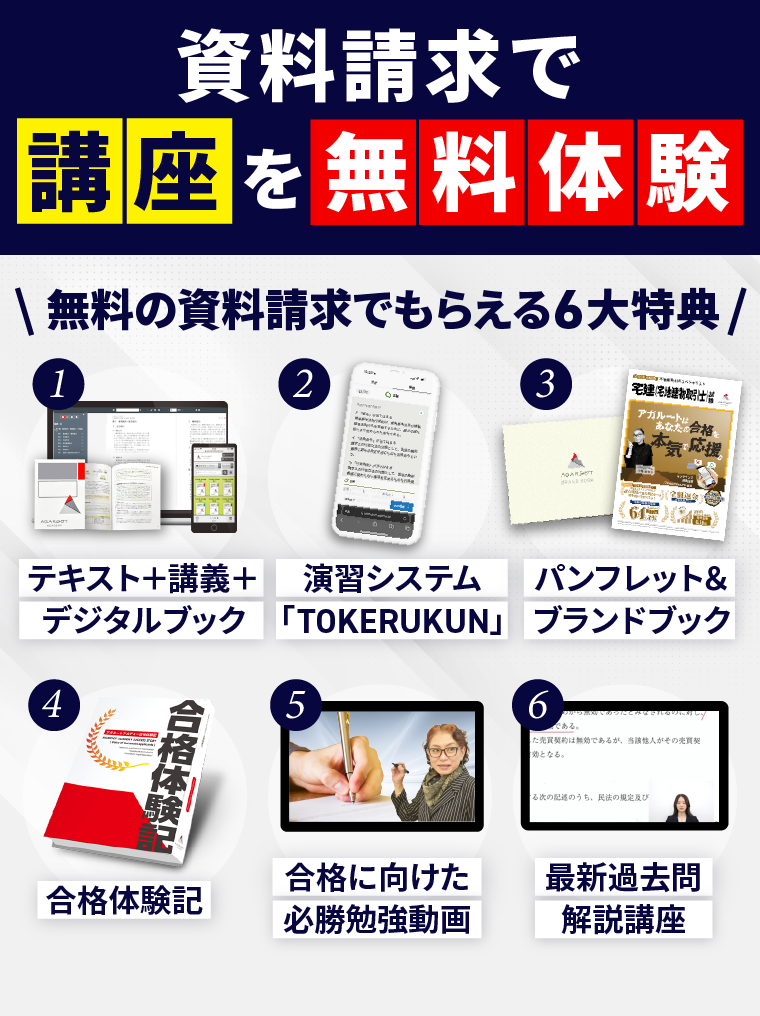
約8.5時間分の講義が20日間見放題!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
宅建試験に合格するためのテクニック動画!
直近の試験の解説動画+全問解説テキスト!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
豊富な合格実績!
令和6年度のアガルート受講生の合格率66.26%!全国平均の3.56倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!




