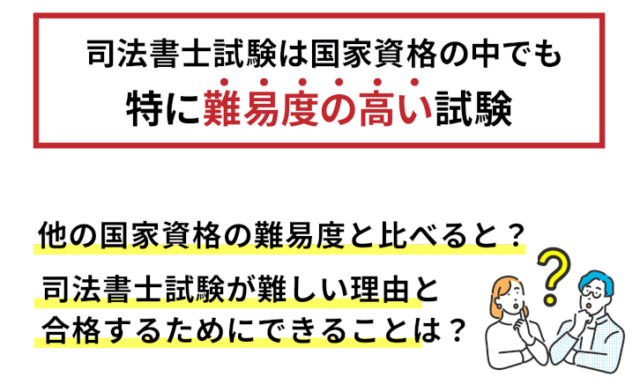【2024年度・令和6年度】司法書士試験の日程は?試験概要とスケジュールを解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

受験生にとって、司法書士試験のスケジュールについては事前にきちんと把握しておくことが大切です。
試験の日程に合わせた学習計画を立てることで、効率的に学習が進められます。
また、手続きに不備があり受験できないような事態は絶対に避けなければなりません。
ここでは、司法書士試験の日程や注意点などについて解説します。
司法書士試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 司法書士試験の情報収集が大変
アガルートの司法書士試験講座を無料体験を
してみませんか?
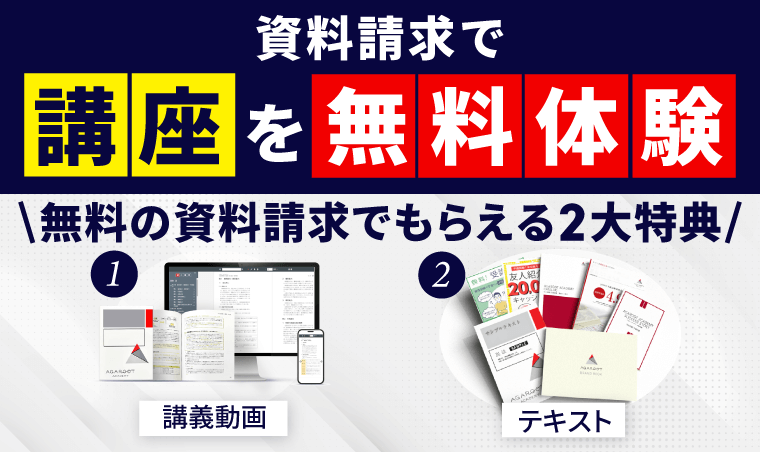
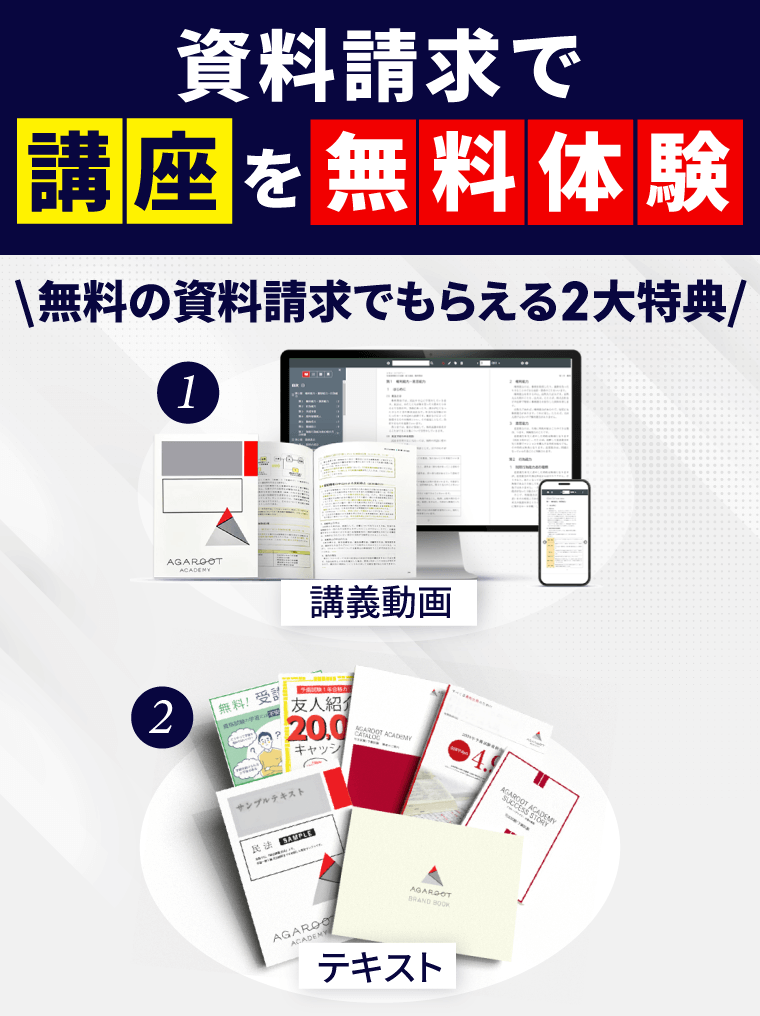
約13.5時間分の民法総則の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法書士試験対策のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る目次
2024年度 司法書士試験はいつ?予想日と全体の流れ
2024年度(令和6年度)の司法書士試験 筆記試験は、2024年7月7日(日)の予定です。
司法書士試験の筆記試験は例年7月の第1日曜日に実施されています。
司法書士試験のスケジュールの全体の流れを、2024年度(令和6年度)を例にご紹介します。
(1)2024年4月3日(水)~ 受験案内、願書の配布
(例年4月初めから5月中旬まで)
(2)2024年5月7日(火)~5月17日(金) 出願期間(受験申請受付期間)
(例年4月末または5月初めから5月中旬までの10日間程度)
(3)2024年7月7日(日) 筆記試験
(例年7月の第1日曜日)
(4)2024年8月13日(火) 正解と基準点の発表
(例年8月上旬から中旬)
(5)2024年10月3日(木) 筆記試験の合格発表
(例年9月下旬から10月上旬)
(6)2024年10月15日(火) 口述試験
(例年10月中旬から下旬)
(7)2024年11月5日(火) 最終合格発表
(例年10月下旬から11月中旬)
試験の実施について、例年4月初めに官報(国が発行する新聞のようなもの)に掲載され、同時に受験案内が配布されます。
そのため、具体的な試験のスケジュールがわかるのは、4月初めになります。
まずは法務省のホームページを確認するとよいでしょう。
なお、2020年度(令和2年度)は、新型コロナウイルスの影響により試験の日程が延期となりました。
今後についても、法務省のホームページで最新の情報をチェックして、変更等がないか注意を払う必要があります。
司法書士試験概要
試験のスケジュールとともに、司法書士試験の概要を確認しておきましょう。
| 受験資格 | なし。誰でも受験できる。 | ||
| 試験会場 | 東京・横浜・さいたま・千葉・静岡・大阪・京都・神戸・名古屋・広島・福岡・那覇・仙台・札幌・高松の15か所(2023年度) | ||
| 試験方式 | 筆記試験と口述試験 | ||
| 筆記試験の試験科目 | 午前 | 憲法、民法、刑法、商法・会社法の4科目(択一式) | |
| 午後 | 択一式 | 民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、供託法、不動産登記法、商業登記法の7科目 | |
| 記述式 | 不動産登記法、商業登記法の2科目 | ||
| 合格基準 | 筆記試験後に総合得点・午前の部択一式・午後の部択一式・記述式それぞれの基準点が公示され、その全てを超える成績上位の者が合格となる | ||
受験資格について
司法書士試験の受験資格は特にありません。
年齢、性別、学歴、国籍などを問わず受験することができます。
受験回数の制限もないため、たとえば10回以上受験することもできます。
試験会場について
司法書士試験の受験会場は、例年、全国で15カ所程度です。
47都道府県すべてに受験会場があるわけではなく、他県での受験となる場合があるため注意が必要です。
なお、試験会場は住所とは関係なく自由に選ぶことができます。
2023年の受験会場は15カ所で、東京・横浜・さいたま・千葉・静岡・大阪・京都・神戸・名古屋・広島・福岡・那覇・仙台・札幌・高松です。
関連記事

司法書士試験の会場は?選ぶことはできる?
試験の内容と科目
司法書士試験は、筆記試験と口述試験があり、どちらも合格する必要があります。
ただし、口述試験については不合格になることはほぼないと言われており、実質的には筆記試験によって合否が決まります。例年、筆記試験が7月、筆記試験の合格者に対する口述試験が10月に実施されます。
筆記試験の試験科目
(試験時間割:午前の部9:30~11:30 午後の部13:00~16:00)
| 午前(択一式) | 午後(択一式) | 午後(記述式) |
| ①憲法(3問・9点) ②民法(20問・60点) ③刑法(3問・9点) ④商法・会社法(9問・27点) |
①民事訴訟法(5問・15点) ②民事執行法(1問・3点) ③民事保全法(1問・3点) ④司法書士法(1問・3点) ⑤供託法(3問・9点) ⑥不動産登記法(16問・48点) ⑦商業登記法(8問・24点) |
①不動産登記法(1問・70点) ②商業登記法(1問・70点) |
| 105点 | 105点 | 140点 |
| 合計350点 | ||
記述式の配点は「2問で70点満点」でしたが、令和6年度より「2問で140点満点」に変更されます。
参考:法務省:【重要】司法書士試験筆記試験記述式問題の配点の変更について
出題数が多い主要科目は、民法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法の4科目です。
午前科目は、憲法、民法、刑法、商法・会社法の4科目で、すべて択一式問題です。
午後科目は、択一式問題と記述式問題があります。
択一式問題は、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、供託法、不動産登記法、商業登記法の7科目です。
午後の記述式問題は、不動産登記法、商業登記法の2科目で、実際に登記申請書を記述する形式です。
配点は、午前科目は各3点で計105点、午後科目は択一式問題が各3点で計105点、記述式問題は各70点で計140点、午前午後の総合計点は350点です。
司法書士試験のスケジュール詳細
それでは司法書士試験のスケジュールと、それぞれの詳細ややるべきことを解説します。
(1)受験案内、願書の配布
令和6年度は4月3日(水)~
例年4月初め頃に受験案内書・願書(受験申込書)の配布が始まります。
この書類の配布を受ける方法には、①法務局に出向いて受け取る、②法務局に郵送で請求、③予備校で受け取る、の3つがあります。
自分にとって都合の良い方法を選びましょう。
法務局は全国どこの支局でも配布しているため、近くに法務局があるのであれば出向いて直接受け取るのが早くて確実です。
受験申込みは自己責任です。受験案内には、すみずみまできちんと目を通して、誤解や手違いがないように気を付けましょう。
(2)出願
令和5年度の出願期間は5月7日(火)~5月17日(金)
願書の提出先は、自分の選んだ受験地の筆記試験を実施する法務局の総務課となります。
受験地は、住所地以外でも自由に選ぶことができます(全国で15カ所)。
願書の提出は、窓口に持参する方法または郵送の方法があります。
受験には8,000円の手数料がかかりますが、この手数料を現金で払うことはできず、収入印紙で納付する必要があります。
収入印紙は郵便局や法務局で販売されています。
(3)筆記試験
令和6年度は7月7日(日)
先述したように、筆記試験は、午前の部と午後の部に分かれて実施されます。
試験科目はすべて法令科目で合計11科目です。
2024年度の司法書士試験筆記試験は、2024年7月7日(日)に実施されると考えられます。
司法書士試験の試験時間は午前の部は9時30分から11時30分までの2時間、午後の部の試験時間は13時から16時までの3時間です。着席時間は午前の部は9時00分、午後の部は12時30分となっています。
(4)正解と基準点の発表
令和6年度は8月13日(火)
司法書士試験では、午前の択一式問題、午後の択一式問題、記述式問題のそれぞれにいわゆる足切り点(基準点)が設定されています。
どれか1つでも基準点に達しなければ、その時点で不合格となります。
8月中旬に択一式問題についての正解と基準点が法務省のホームページで発表されます。
令和5年度の多肢択一式問題の基準点は、8月14日(月)に発表されました。
法務省:令和5年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の基準点等について
この時点で、自己採点することによりある程度合否の見通しが立つ受験生も多いでしょう。
(5)筆記試験の合格発表
令和6年度は10月3日(木)
筆記試験の合格発表は、合格者の受験番号を、受験地の法務局で掲示する方法と法務省のホームページに掲載する方法で行われます。
どちらも午後4時に発表されます。
また、筆記試験合格者には口述試験の受験票が法務局から送付されます。
(6)口述試験
令和6年度は10月15日(火)
記試験合格者に対し、例年10月に口述試験が行われます。
口述試験の受験地は、全国8カ所の法務局から指定されます。
口述試験の試験科目は、不動産登記法、商業登記法、司法書士法です。
受験しさえすれば不合格になることはない試験と言われていますが、やはり試験であることに変わりはありません。
質問にしっかりと回答することができるように準備をしておきましょう。
(7)最終合格発表
令和6年度は10月3日(木)
最終合格者の発表は、合格者の受験番号を、筆記試験の受験地の法務局で掲示する方法と法務省のホームページに掲載する方法で行われます。
最終合格者の発表も、 午後4時です。
また、後日の官報に合格者の受験番号と氏名が掲載され、記念に官報を購入する合格者もいます。
合格後は、数種類の研修を受ける必要があります。
研修終了後に就職活動を始める人もいれば、研修中から就職活動をしたり、働きながら研修を受ける人もいます。
関連コラム:司法書士試験の合格発表はいつ?発表方法とその後やるべきこと
試験日程・申し込みの注意点
試験日程や受験申し込みの際の注意点を3つ紹介します。
1.願書の提出期間が短い
司法書士試験の願書の提出期間は10日間程度で、土日は受付をしていないため実質的に1週間程度しかありません。
そのため、うっかり提出するのを忘れてしまい、気づいたら受付期間が過ぎていたという事態になりかねません。
受験案内を受け取ったら、カレンダーに印を付けるなどして、願書の提出期間を過ぎてしまうことがないように気を付けましょう。
2.写真は本人と分かるものを
受験票に貼る写真は、試験官が見て一目で本人と分かるものにしましょう。
本人かどうかわからないと、受験が認められない危険があります。
メガネをかけて受験する場合にはメガネを着用した写真、裸眼やコンタクトで受験する場合はメガネを着用していない写真としなければなりません。
試験官から別人を疑われるような昔の写真や加工した写真なども絶対に避けましょう。
3.収入印紙は事前に購入しておく
受験手数料の収入印紙8,000円は、早目に購入しておく方が安心です。
願書提出の時に買おうと思っていても、収入印紙を取り扱っている場所は思いのほか少ないため、必ず購入できるとは限りません。
収入印紙を取り扱っているコンビニなどもありますが、8,000円分の収入印紙が常時あるとは限らないので注意が必要です。
まとめ
司法書士試験の合格率は例年4~5%程度で、とても合格率の低い試験です。ただし、全員が準備万端の状態で受験しているわけではなく、まだ受験勉強中でお試し受験する人なども含まれるため、実質的な合格率はもう少し高いと言えるでしょう。
合格までに必要となる勉強時間の目安は、3000時間と言われています。試験科目数が11科目と多いことなどから、1日4時間勉強するとしても2年以上必要な計算となります。
午前科目、午後の択一科目、午後の記述式問題のそれぞれで基準点(足切り点)があり、それをクリアしたうえで、総合得点でも例年7割程度の得点を取らなければ合格できません。
合格率を考えると、とても難しい試験に思えますが、実際には様々な学歴、経歴の人が合格しています。秀才でなくても、コツコツと真面目に勉強に取り組むことができる人であれば、十分合格を目指せる試験だと言えます。
司法書士試験の受験生は、スケジュールを頭に入れておき、不備がないように受験の申し込みを行うことが欠かせません。
万一申し込みに不備があれば、その年の受験をすることができず、それまでの努力が水の泡になってしまいます。
早めの準備を行い、万全な態勢で試験に臨めるようにしましょう。
司法書士試験の合格を
目指している方へ
- 司法書士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法書士試験講座を
無料体験してみませんか?

令和5年度のアガルート受講生の合格率15.4%!全国平均の2.96倍!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
全額返金など合格特典付き!
6月30日までの申込で10%OFF!
▶司法書士試験講座を見る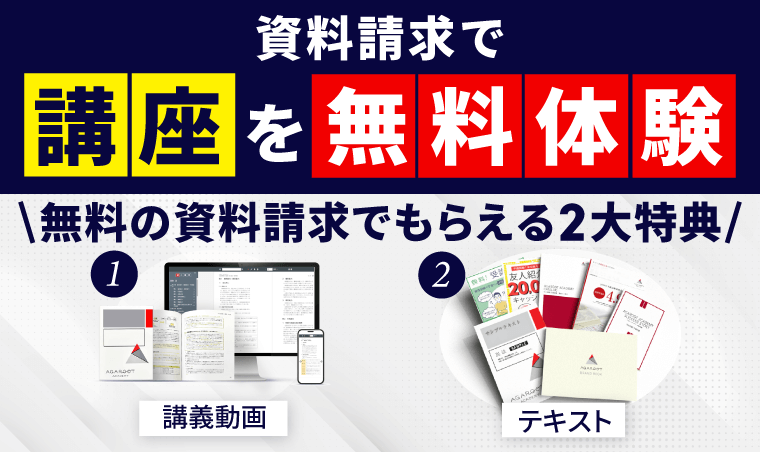
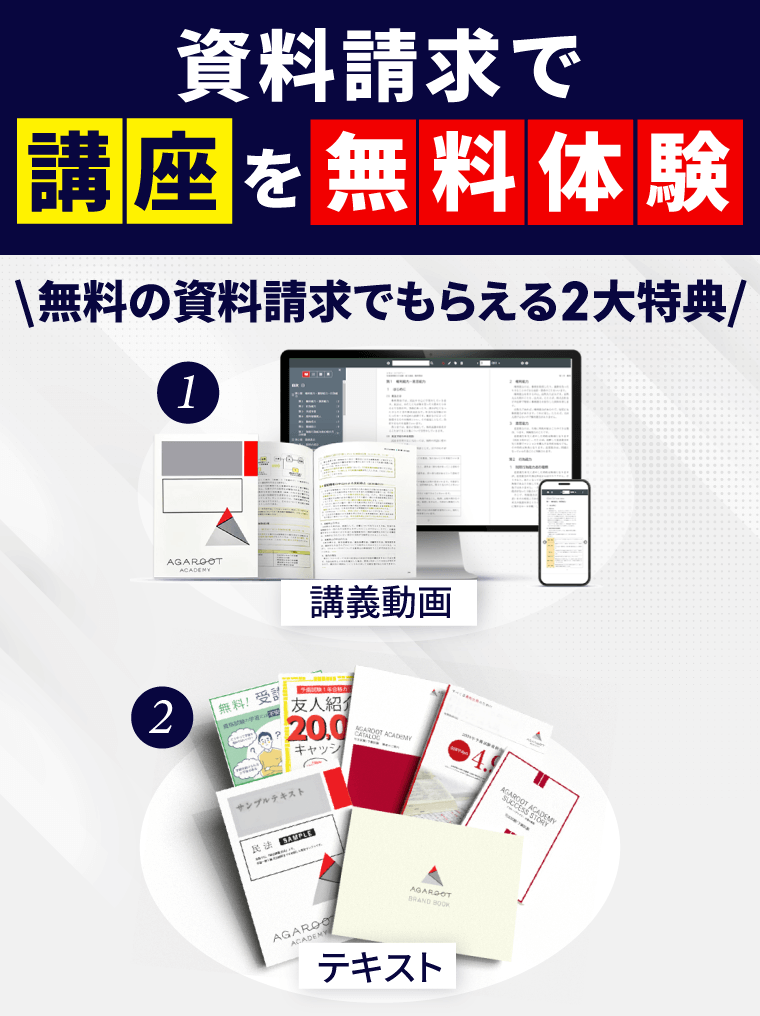
約13.5時間分の民法総則の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法書士試験対策のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
この記事の監修者 竹田 篤史講師
竹田篤史講師
社会保険労務士事務所、司法書士法人勤務後、大手資格予備校にて受講相談、教材制作、講師を担当。
短期合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため、株式会社アガルートへ入社。
これまで、ほぼ独学で行政書士試験、司法書士試験に合格し、社会保険労務士試験には一発で合格。
自らの受験経験で培った短期合格のノウハウを余すところなく提供する。
竹田篤史講師の紹介はこちら