社会保険労務士がセカンドキャリアにおすすめの理由と社労士を目指したきっかけ
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

セカンドキャリアとは、人生における第2の職業のことです。
近年は、ひとつの職業を全うするよりも、資格などを取得して第2の職業に転職する方も少なくありません。
中でもおすすめの資格は、社会保険労務士(以下、社労士)です。
セカンドキャリアを検討している中で、社労士の資格にたどり着いた人もいるでしょう。
本コラムでは、社労士がセカンドキャリアにおすすめの理由を解説します。
合格者の体験談なども紹介するため、興味がある方はぜひ今後の参考にしてください。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?

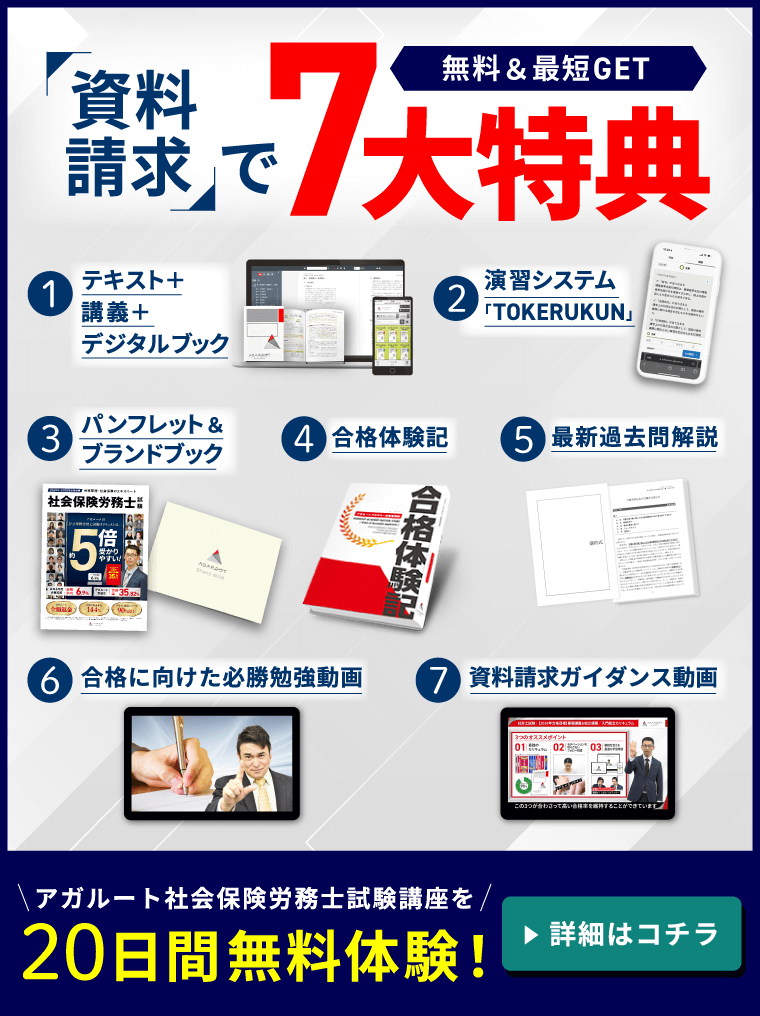
約7.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!
1分で簡単お申込み
▶資料請求して特典を受け取る目次
社会保険労務士がセカンドキャリアにおすすめの理由5選
セカンドキャリアに社労士がおすすめな理由は、以下の5つが挙げられます。
- 受験資格に年齢制限がない
- 実務経験がなくても目指せる
- 需要があり転職に有利
- 独立開業も可能
- 定年退職がない
受験資格に年齢制限がない
社労士試験には年齢制限がないため、ほかの受験資格を満たせばどんな年齢の方でも受験が可能です。
受験資格には3つの条件が定められており、いずれかひとつを満たせば受験できます。
3つの条件は、以下のとおりです。
- 学歴による受験資格
- 実務経験による受験資格
- 厚生労働大臣が認めた国家試験合格による受験資格
実務経験、国家試験合格に関する条件クリアは厳しい方もいるでしょう。
しかし、学歴による受験資格であれば、大学・短大・専門学校などを卒業している方は条件を満たすことができます。
つまり社労士は年齢関係なく取得が目指せるため、セカンドキャリアとしての資格に向いています。
※参考:受験資格について | 社会保険労務士試験オフィシャルサイト
実務経験がなくても目指せる
社労士試験は実務経験がなくても受験が可能なため、しっかり試験対策をすれば合格できる試験です。
受験資格の中に実務経験に関する要件はありますが、そのほかの学歴・試験合格のどちらかの要件を満たせば問題なく受験できます。
また、社労士関連の仕事は、全くの未経験でも資格保有者であれば働けるケースが多いです。
需要があり転職に有利
社会保険労務士は人事・労務の専門家です。
社労士資格をもつ人材は社労士事務所はもちろん、一般企業などでも需要が高いため、転職が有利になるでしょう。
社労士が行う主な業務には1号・2号・3号業務があり、中でも1号と2号業務は独占業務です。
以下、社労士の主な業務内容です。
- 1号業務:社会保険関連書類の作成、申請書などの手続き代行、事務代理業務、紛争解決手続き代理業務
- 2号業務:帳簿書類などの作成
- 3号業務:労務管理や社会保険に関する相談または指導
独占業務がある資格は収入や地位が安定しやすいため、セカンドキャリアとして取得すると大きなメリットが期待できます。
独立開業も可能
社労士資格は独立開業が可能なため、セカンドキャリアで取得を目指す方も多いです。
社労士は独占業務があり、顧問契約をすれば安定した収入が得やすいでしょう。
中には年収1,000万円以上を稼ぐ社労士もおり、独立開業するケースは珍しくありません。
また、独立開業すれば働き方の自由度が一気に広がるメリットもあるでしょう。
担当する案件の量や勤務時間の調整がしやすく、無理なく自分のペースで働けます。
ライフステージに合わせて、収入重視で仕事量を増やす、体調を鑑みて仕事量を減らすなどが可能なため、セカンドキャリアにもおすすめです。
定年退職がない
国家資格である社労士には、定年退職制度がありません。
自分が働きたいと思えば、65歳以上になっても自由に働くことが可能です。
セカンドキャリアとしてパートやアルバイトに応募する方もいますが、年齢を重ねれば重ねるほど採用されにくい傾向があります。
また、体力が必要な仕事を選んだ場合、体調を崩してしまうと仕事が続けられなくなることもあるでしょう。
対して社労士は、資格を取得してしまえば地位が安定し、転職だけでなく独立開業という選択肢が増えます。
年齢による制限がなくなるため、セカンドキャリアを成功させることができるでしょう。
社労士がシニア・ミドルシニア世代にも人気な理由
社労士がシニア・ミドルシニア世代にも人気な理由は、以下の4つが考えられます。
- 社労士の平均年齢が高め
- 社会人経験を活かせる
- 社会への貢献度が高い
- シニア世代でも応募できる求人がある
社労士の平均年齢が高め
「社会保険労務士白書」によると、登録している社労士の平均年齢は56.27歳です。
全体的に年齢層が高いため、シニア・ミドルシニア世代の方でも無理なく活躍できる業務内容だと考えられます。
また、最年少が22歳に対して、最年長は102歳です。
年齢を重ねても問題なく仕事ができるため、意欲があればシルバー世代になっても働くことができるでしょう。
なお、社労士の登録が一番多い年齢層は、40〜60代。
多くのシニア・ミドルシニア世代が現役で活躍しており、セカンドキャリアでも新規参入しやすい環境だといえるでしょう。
社会人経験を活かせる
社労士の業務では社会人経験が活かせるため、長い人生を過ごしてきたシニア・ミドルシニア世代が活躍できる職業です。
社労士は人事・労務に関する専門家として、企業などのクライアントと深くかかわりながら仕事をします。
これまでの社会人人生で培ってきたコミュニケーション能力や経験が役に立つことが多く、人柄により信頼性がアップすることもあります。
また、社労士は事業における労務管理や社会保険に関する相談に応じる機会が多いです。
専門家として指導する場合、若い世代よりも人生経験豊富な世代のほうが実際の経験に基づいた説得力のあるアドバイスができるでしょう。
社会への貢献度が高い
社労士はクライアントの働く環境をより良くするサポートを行うため、社会貢献度が高い職業です。
年齢を重ねても無理なく続けられる仕事でありながら大きなやりがいを得られるため、人の役に立ちたいシニア・ミドルシニア世代に人気があります。
むしろシニア・ミドルシニア世代がこれまで経験して得た経験や知識を還元できる仕事であり、人生経験豊富な社労士に対する需要が高い傾向もあります。
自分のやってきたことがダイレクトに役に立ち、感謝される機会が多い点から、セカンドキャリアとして選ばれやすいと考えられるでしょう。
シニア世代でも応募できる求人がある
社労士の求人には、シニア世代でも歓迎しているケースが多いです。
有資格者であれば年齢関係なく応募できる求人もあるため、セカンドキャリアとして社労士を選ぶ方が増えています。
特に社労士事務所に事務員として勤務していた方や、労務関係の業務経験がある方は、シニア世代でも採用されやすい傾向があるでしょう。
【体験談】セカンドキャリアとして社労士を目指したきっかけ
セカンドキャリアとして社労士資格取得を目指す方の理由やきっかけはそれぞれです。
本章では、セカンドキャリアに社労士を選択し、目標を叶えた方々の体験談を紹介します。
「今後のキャリアについて考えたい」「第2の人生をどう生きるか」など、セカンドキャリアに迷っている方は今後の参考にぜひご覧ください。
ミドルシニアとしてのセカンドキャリアを考えて
40代〜60代になると、今後のキャリアや自分の人生と向き合う機会が訪れるでしょう。
これからの生き方、働き方を考えた時、セカンドキャリアとして社労士を選ぶ人が多くなっています。
ここでは、ミドルシニア世代になって社労士を目指した合格者の方の体験談を2人紹介します。
社労士の試験を受けようと思ったきっかけは、49歳の時に当時会社では役職定年制という制度があり、同僚がリストラされてしまい、その同僚からハローワークに行っても資格が無いと、希望するような仕事の求人は無いという現実を聞かされたのがきっかけでした。
※引用:合格者の声|同僚のリストラをきっかけに受験を決意!
公務員として、約20年勤務していますが、自動車運転免許以外は何ら資格を有していませんでした。そして、仮に現在の職を辞した場合、自分には何もないことに気づき、何か資格を取得したいと思うようになりました。
※引用:合格者の声|年金科目を集中的に勉強し6ヶ月間の学習で一発合格!
現在の仕事が、労働関係法令を取り扱うものであるので、仕事にも役立つと思い、社労士試験を受験することとしました。
出産・子育て後のセカンドキャリアを考えて
社労士は、業務内容や専門とする分野により、女性でも働きやすいといわれている職業です。
また、独立開業すれば勤務時間や仕事量を調節することが可能なため、出産や子育てをきっかけに社労士の資格取得を目指す女性の方も増加中です。
社労士は独占業務をもつ国家資格のため、出産や子育てでブランクがある方も取得すれば再就職しやすいメリットがあります。
専業主婦の方が資格を取得し、現在は社労士として高収入を得ているケースも珍しくありません。
ここでは、出産や子育てをきっかけに社労士を目指し、合格した方々の体験談を3名紹介します。
結婚、退職、転職、出産を経験し、2年ほど子育てに専念する日々を過ごしてきました。その間、将来への自分のキャリアに漠然と不安を抱えておりました。以前から自分に武器になる資格を持ちたいと思っていたこと、会計事務所の総務で働いていた経験があり社労士の仕事内容を身近に感じていたこと、義父が社労士として実際に開業しており、様々話を聞く中でイメージが膨んだことがきっかけで、取るなら比較的時間のある今しかないと思い、受験することを決めました。
※引用:合格者の声|寝るときに目を瞑っていても竹田講師のお顔が浮かんでくるほど長い期間講義を視聴していました
子どもが生まれたことがきっかけとなり、転職を決意しました。前職の労働環境では子どもに向き合う時間がなかなか取れず、別の道をと考えていた時に社会保険労務士という職業を知りました。労働環境を改善するサポートができる職業という点に強く惹かれ、社労士試験の合格を目指しました。
※引用:合格者の声|合格できた1番の理由は「テキスト」だと言い切れます
妊娠を機に社労士試験を目指しました。悪阻や切迫早産で仕事が続けられない状態だったので退職し、子育てが一段落した時に再就職できる様にと考えて社労士試験を選びました。それまでに第一種衛生管理者の資格を取得しており、勉強したことが活かせるのではないかと思ったことも理由の一つです。社労士は勤務することも独立開業もできる資格なので自分に合う働き方を選べるという点でも魅力を感じました。
※引用:合格者の声|「あと1点分」の背中を押してくれたのがアガルートの講座
コロナがきっかけ
2020年から日本で猛威を振るい、社会的に大きな影響を及ぼしたコロナ。
業界や職種によっては仕事を失うケースもあり、多くの人々が自分の働き方や生き方について見つめ直す機会となりました。
自分にとって働きやすい環境を得るために、「資格を取って独立開業をしたい」「将来のために国家資格を取っておきたい」と目標を立てた方も多かったでしょう。
ここでは、コロナをきっかけに社労士資格取得を目指し、合格した方々の体験談を2名紹介します。
飲食店で勤めており昔からサービス業イコール劣悪な労働環境であるというのが当たり前だったため労務環境について何も疑問に思うことなく日々を過ごしておりました。コロナによる緊急事態宣言での休業や時短営業を経験し、働き方や自身の将来について考えるきっかけとなりました。
今までなかったまとまった自由な時間を有効活用しようと考え、せっかくなら難関資格にチャレンジしてみようと思いました。その中でも、元々労基法や年金などには興味があり、世のため人のためになるような教養をつけたいと思い社労士試験にチャレンジしてみようと決断いたしました。
※引用:合格者の声|過去問はひたすら解きまくりました
40歳になって、仕事や将来について考えることが増えました。そのタイミングで新型コロナウイルスが流行し、経済不安や危機感が増し、退職した後も仕事ができるにはどうすればいいか考えるようになりました。
そんな時、社会保険労務士はとてもやりがいのある仕事だという話を妻の父から聞き、社会保険労務士資格に興味を持ちました。
※引用:合格者の声|模擬試験・答練の結果から合格するための軌道修正をした
病気がきっかけ
労務や社会保険に関する専門家である社労士は、自分や身近な人が病気になると深くかかわる機会が増えます。
また、社会保険制度を自分で調べるうちに興味をもち、「社労士の仕事をしてみたい」と考える方も少なくありません。
ここでは、病気をきっかけに社労士資格取得を目指し、見事合格した方々の体験談を2名紹介します。
会社員をしていましたが、持病と過労が重なり病状が悪化したために退職を余儀なくされました。長期の療養生活を送っている中で、職場で社会保険労務士には会社でお世話になり、自身でも職業安定所や年金事務所で手続きを行った事がありました。また自分自身が利用できる年金・健康保険等の制度があるかどうかについて興味を持ったことがきっかけで目指すことになりました。
※引用:合格者の声|療養中、学習時間の管理に気をつけながらコンスタントに学習し合格!
社労士試験を目指したのは、子どもがまだ幼い頃に病気にかかり、社会福祉や社会保険など保険制度ついてもっと知りたいと思ったのがきっかけです。
また、個人事業主として独立開業でき自宅でも働けるという点も魅力に感じました。
※引用:合格者の声|今回こそは絶対に合格する!仕事と家庭、受験勉強を両立し資格を取得
社会保険労務士になる流れ
社労士は、社会保険労務士試験に合格したあと、全国社会保険労務士連合会の社労士名簿に登録すると就業を開始できます。
ただし、名簿の登録には条件があり、実務経験2年以上もしくは事務指定講習を修了した者でなければ登録することができません。
1. 社労士試験に合格する
社労士になるためには、まず例年8月の第4日曜日に実施される社労士試験に合格する必要があります。
試験内容は、計8科目から出題される選択式試験(8問・計40点)と、計7科目から出題される択一式試験(70問・70点)の2つです。
合格基準点は、選択式試験・択一式試験それぞれの総得点と、それぞれの科目ごとで判定されます。
総得点が高得点でも、各科目のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となるため注意が必要です。
2. 合格したら社労士名簿に登録する
社労士試験に合格したら、全国社会保険労務士連合会の社労士名簿に登録しましょう。
2年以上の実務経験が認められる場合は、合格後すぐに登録申請が可能です。
合格の時点で実務経験がない場合は、全国社会保険労務士連合会が実施する事務指定講習を受講する必要があります。
事務指定講習とは、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定にもとづき、2年以上の実務経験に代わる資格要件を満たすために実施する講習です。
講習を修了すれば実務経験の要件に満たす経験を有する者と認められるため、社労士名簿に登録することができます。
まとめ
本コラムでは、社労士がセカンドキャリアにおすすめの理由を解説しました。
最後に、コラムの要点である社労士がおすすめな理由を再度紹介します。
- 受験資格に年齢制限がない
- 実務経験がなくても目指せる
- 需要があり転職に有利
- 独立開業も可能
- 定年退職がない
社労士は活躍している年齢層が高い傾向がある職業のため、セカンドキャリアでも新規参入しやすいです。
そのため、シニア世代でも応募できる求人が多く、社会人経験を活かして社会貢献ができる点で人気が高くなっています。
また、社労士試験の受験資格に年齢要件はないため、シニア・ミドルシニア世代でもチャレンジしやすいです。
安定したセカンドキャリアを築きたい方は、ぜひ社労士を目指してみましょう。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 社会保険労務士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?

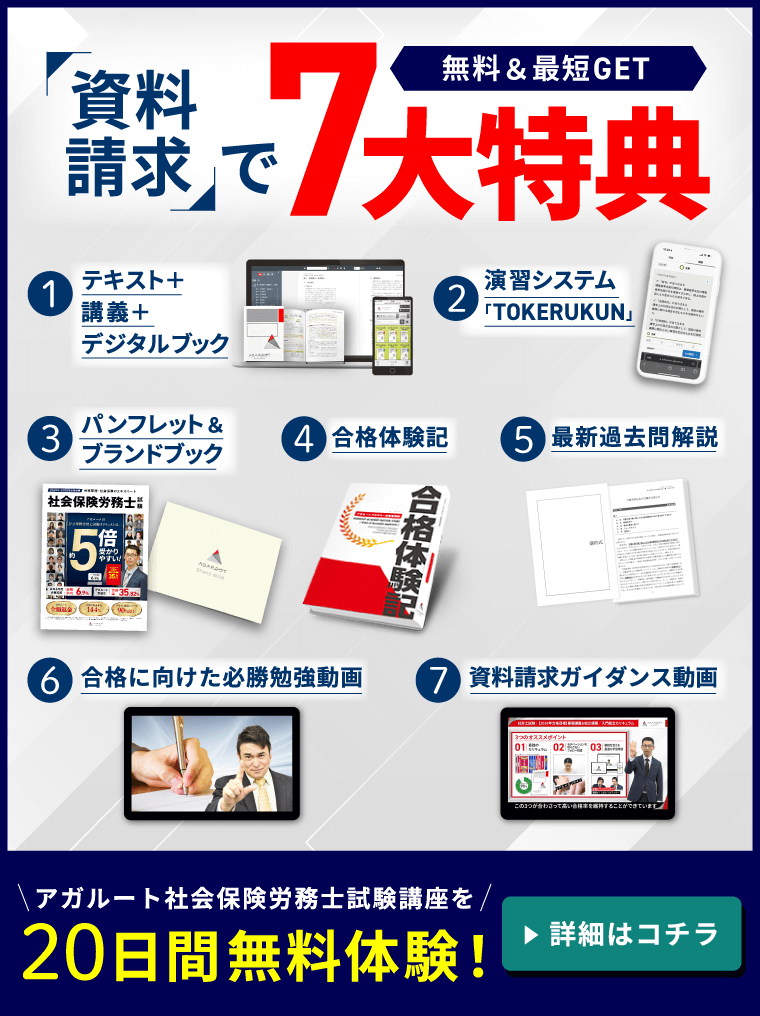
約7.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る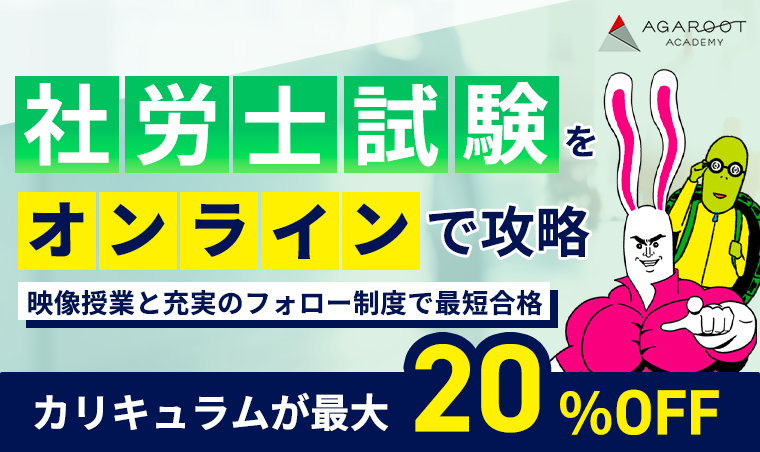
令和6年度のアガルート受講生の合格率35.82%!全国平均の5.19倍
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!
会員20万人突破記念!
全商品5%OFF!



