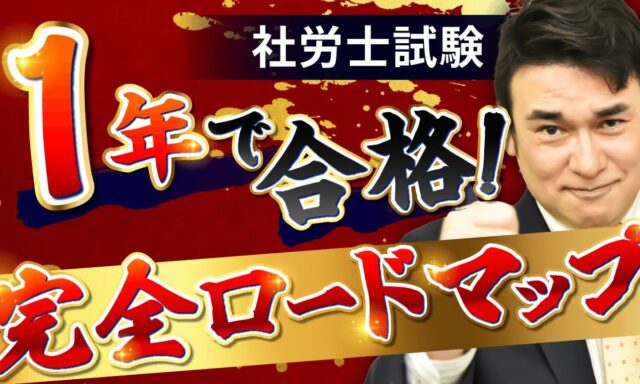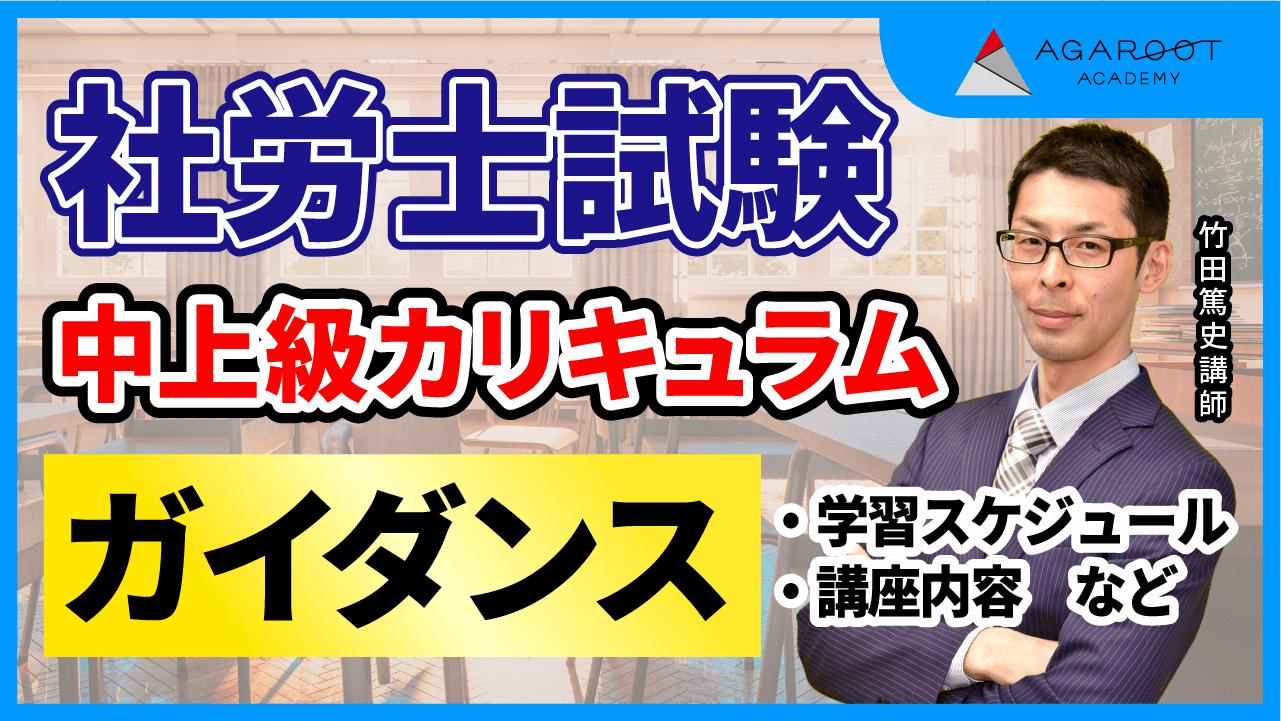社労士とは?仕事内容・年収・試験内容を解説!将来性や需要はある?
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
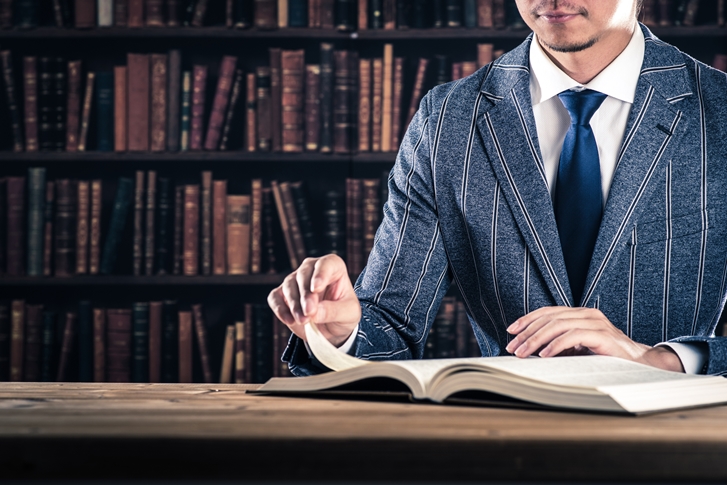
社労士とは一体どのような仕事をするのでしょうか?
社労士の正式名称は社会保険労務士といいますが、具体的にどのような仕事をしているのか、今後社労士を目指そうという方にとって気になることだと思います。
そこで、社労士の仕事内容、社労士に求められるスキルや能力、社労士の年収、将来性や需要について分かりやすく解説していきます。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?


約6.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
1分で簡単お申込み
▶資料請求して特典を受け取る目次
社会保険労務士(社労士)とは?わかりやすく解説
社会保険労務士とは、人事労務管理分野の唯一の国家資格者です。
主に職場や企業の経営・業務を効率化するため、人事や労務に関する悩み・問題の改善などの支援をしています。
また、社労士は人材に関する専門家のため、職場や企業の「入社時の保険に関する問題」や「年金問題」、「給与計算代行」なども対応しているため業務は多岐にわたります。
また、人材だけではなく厚生労働省管轄の助成金申請の代行も社労士の業務の一つです。
企業の労務コンプライアンスを整え、働きやすい職場づくりの取り組みを推進し、企業の助成金活用をサポートするのも社労士の大事な役割の一つ。
働き方改革が叫ばれる中、企業の労働生産性向上の取り組みのサポートや育児や介護と仕事の両立支援などを行う社会保険労務士の需要は高まっています。
社労士の主な仕事内容は?独占業務って何?

社会保険労務士の仕事内容とは、労働法や社会保険に関する専門知識を活かし、企業や個人に対して労務管理や社会保険に関するアドバイスや支援を行うことです。
具体的な仕事内容は以下のようなものが挙げられます。
- 労働法コンサルティング: 労働法に関するアドバイスや労働条件の改善提案を行います。労働契約や労働時間、賃金、退職制度など、労働関係に関する法的な問題や規制についてアドバイスを行います。
- 労務管理支援: 企業が労働法や労働基準法に適合するように労務管理体制を整えるお手伝いをします。労働規則の策定や就業規則の作成、労働時間管理や労働条件の改善など、労働環境の整備を支援します。
- 社会保険手続き: 企業や個人のために社会保険に関する手続きを行います。社会保険の加入手続きや保険料の計算、給与明細書の作成、社会保険給付の申請など、社会保険制度に関する業務を担当します。
- 労働紛争の解決: 労働紛争の仲裁や解決に関わります。労使間のトラブルや労働条件に関する紛争の解決に向けて、交渉や調停を行います。
- 助成金・補助金の申請支援: 助成金や補助金に関する情報提供や申請書類の作成支援を行います。労働条件改善や雇用の促進など、企業が利用できる支援制度を活用するためのサポートをします。
社会保険労務士の仕事内容「独占業務」とは?
社会保険労務士の主な仕事内容は、大きく1,2号業務と3号業務に分けられます。
1,2号業務は社会保険の手続きや就業規則の作成など社会保険労務士の独占業務となります。
また、3号業務は労務管理のコンサルティング業務などで残業時間削減のコンサルなども3号業務に該当します。
社会保険労務士の1号業務、2号業務、3号業務をそれぞれ分かりやすく解説します。
【1号業務】行政機関に提出する労務管理書類の作成を代行
簡単に言えば、労務管理に関する書類を作成することです。
例えば労働保険の加入申請の代行。
企業は1人でも労働者を雇用する場合、労働保険に加入しなければいけません。
そして、加入にあたって、労働基準監督署などに労働保険の保険関係設立届を提出し、保険料を納付する必要があります。
このような書類や保険料の計算を社労士が代行して行います。
社労士が代行することで、企業は事業に集中して取り組むことができ、労務管理に煩わされることがなく合理的に事業を遂行することが可能となります。
この仕事は社会保険労務士法2条1号に規定されているので、「1号業務」と言われることが多いです。
【2号業務】労務管理に関する帳簿を作成
こちらは、①と同じく書類の作成ですが、帳簿の作成をします。
ここでいう帳簿とは「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の3つの帳簿を言い、これらを「法定三帳簿」といいます。
例えば、賃金台帳では全ての労働者の氏名、性別、基本給及び手当などを労働者ごとに記載しなければならず、また最後に記載された日から3年間は保管しなければなりません。
労働法に詳しい社労士がこの帳簿を作成することで、精度の高い帳簿を作成することができます。
この仕事は社会保険労務士法2条2号に規定されているので、「2号業務」と言われることが多いです。
また、①②は社労士の独占業務。
独占業務がある資格では、誰でも仕事をすることができないため新規参入が難しいという特徴があり、資格を取得する人にとって安定的に仕事が入るというメリットがあります。
社労士は労務管理のスペシャリストとして、労務管理の書類や帳簿の作成といった独占業務が認められており、安定的に仕事ができる資格といえるでしょう。
【3号業務】労務管理や社会保険に関する相談や指導をすること
簡単に言えば労務・社会保険のコンサルティングです。
例えば同一労働同一賃金への対応の相談。
働き方改革に伴って、会社の給与形態や会社の制度を見直すことが必要になるため、社労士は制度に沿った給与形態や制度のアドバイスを行います。
労働法に詳しい社労士がアドバイスをすることで、労働に関する紛争を未然に防ぐことができます。
この仕事は社会保険労務士法2条3号に規定されているので、「3号業務」と言われることが多いです。
③の仕事は独占業務ではないので、社労士の資格を持っていなくともコンサルティングをすることは可能です。
しかし、社労士は労務管理のエキスパートとしての地位があるため、相談者の安心感や信頼を得ることができるでしょう。
このようなコンサルティング業務においても社労士の資格が役に立ちます。
社労士の年収

資格を持って会社に勤める場合(勤務社労士)
社労士事務所や企業等に勤務する社労士の年収は、令和5年度賃金構造基本統計調査によると約947.6万円となっています。
サラリーマンの平均年収が458万円となっているので、サラリーマンより多く年収を得ているといえるでしょう。
独立開業する場合
独立開業する場合の年収は、同じ調査によると約724万円となっています。
会社に勤める場合より平均年収は低いといえそうですが、独立開業の場合1,000万円を超える年収の人の割合も多いです。
大阪大学『社労士科研報告書第2部』によると13.5%の人が年収1,000万円以上となっており、中には3,000万円以上の年収を得ている人がいます。
独立開業の場合、努力により高い年収を得ることが可能となっています。
社労士の資格は意味ない・役に立たない・食えないって本当?
皆さんは、「社労士を取得しても意味がない」そんな話を聞いたことはないでしょうか。
何故、そのような話が出るのでしょう。
それは、社労士の独占業務の内容にあります。
社労士は、士業資格の一つであり、その取得者にのみ認められた独占業務があります。
「1号の手続き代行」と「2号の帳簿作成」です。
これらは社労士の独占業務となるため、一見すると社労士資格を有していない方は出来ない業務のように見受けられます。
しかし、これらの業務はあくまでも代行をすることが独占となっています。
企業が社労士に委託せずに自社で対応する場合、独占業務の対象となりません。
また、3号の相談業務については、独占業務となっていないため、いわゆる人事コンサルタント等の方々も競合する可能性があります。
これらの理由から、わざわざ社労士資格を取得しなくても、企業内であれば1号業務、2号業務はでき、知識・経験があれば3号業務はできるとして、社労士を取得しても意味がないなどと言われます。
それ以外にも、社労士資格を有している=業務ができるとは言えないため、その人自身の社会人基礎力やその他の知識・経験が必要になるという視点から、「社労士資格を取得しただけで食べることは出来ない」と主張する方も見受けられます。
ただ、この意見については、決して社労士だけが言われるものではなく、どの資格にも言えることであるため、あまり気にする必要はないでしょう。
社労士の仕事の将来性や需要はどうなる?
社労士資格を有していなくても業務を行うことは出来ると前述しましたが、本当に社労士の取得は不要なのでしょうか。
これについては、今後も社労士の需要はあり、将来的にはより高まるという見方があります。
確かに、AIの発達により、申請代行や給与計算代行といった業務は影響を受けるかもしれません。
しかし、それ以上に、3号業務に対しての需要が高まる可能性があると考えられています。
例えば、昨今、新型コロナウイルスが蔓延し、各社は急遽テレワークへの対応等を求められることになりました。
この時に各社が苦慮したのは、テレワークでの労務管理です。
どのようにして適切な労務管理を行うのか、
あるいは新しい働き方に合わせてどのように社内制度をチューニングするのか、、、
様々なことを検討しなくてはならなくなりました。
事実、テレワークで感じた課題について企業からアンケートを行ったところ、労働時間の管理等、社労士が支援できる項目に対して、企業が課題を感じていることが見て取れます。
テレワークで感じた課題
- 34.2%:労働時間の申告が適正かどうかの確認が難しい
- 31.8%:勤怠管理が難しい
- 27.5%:在籍・勤務状況の確認が難しい
- 14.7%:労働災害の認定基準が分かりづらい
- 6.1%:労働時間の適正な申告が徹底されていない
また、それ以外にも近年、様々な検討が企業に求められています。
ダイバーシティやSDGs、男性の育児休業の促進や女性管理職の登用、定年延長等、、、
会社の在り方さえ変わらざるを得ない世の中となってきています。
このような状況下で、どのように会社を運営し、社員を守るかを考えるとなると、社内の監督者だけでは追いきれないのではないでしょうか。
様々な労働環境の変化に対して、いち早く情報を察知し、法律的な視点も持ち合わせた社労士は、多くの活躍の場を開拓することが出来るはずです。
よって、既存業務の需要があるかについては判断が難しいところではありますが、様々な国内の環境変化を鑑みると、社労士には十分に需要・将来性があると考えられるでしょう。
社労士の仕事に求められるスキルや能力
数字に強く、地道な作業でも乗り越えられる
例えば賃金台帳の作成では、労働者ごとに基本給や手当の合計や控除額などを電卓を用いて計算する必要があります。
そのため社労士は、数字と向き合いながら地道な作業をすることも多くあります。
数字につよく、地道な作業でもやり遂げる能力が必要となるでしょう。
コミュニケーション能力が高い
社労士の仕事は書類仕事だけではなく、労務管理のコンサルティングを行うこともあります。
コンサルティングでは、相手の意見をきいて説得的で的確なアドバイスを行うことや、難しい法律用語を嚙み砕いて説明することが求められます。
このようにアドバイスを行うためには高いコミュニケーション能力が欠かせません。
正義感が強い
社労士は、時には労働法を遵守するよう経営者に指導することもあります。
労務管理のエキスパートとして的確な指導を行うこともあるので、正義感の強さも挙げられます。
社労士になるには
社労士になるには3つのステップが必要になります。
- 社会保険労務士試験に合格
- 実務経験を2年以上積む、または事務指定講習を修了
- 全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録
難関はなんといっても社会保険労務士試験に合格することです。
晴れて試験に合格することができたら、全国社会保険労務士会連合会に備える社労士名簿に登録を受ける必要があります。
登録するには2年以上の実務経験を積むこと、もしくは全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習の修了が条件です。
社会保険労務士試験の試験概要
社労士試験は超がつくほどの難関として知られています。
合格を勝ち取るためにも、社労士の試験概要や勉強法について、しっかり把握しておくようにしましょう。
| 受験資格 | 下記いずれかに該当している方 ・大学や短大等を卒業した方 ・3年以上の実務経験 がある方 ・行政書士資格や税理士資格を有している方 |
| 試験日 | 例年8月の第4日曜日 |
| 申し込み期間 | 例年4月中旬~5月31日 |
| 申し込み方法 | インターネット or 郵送 |
| 受験手数料 | 15,000円(非課税) |
| 受験地 | 試験地一覧(2024年) 北海道、宮崎県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県 |
| 試験の方法 | マークシート式(択一式 70問/選択式 8問) |
| 合格発表 | 例年10月の第1水曜日 |
社会保険労務士試験の試験内容
社労士の試験内容は「択一式試験」「選択式試験」の2つに分かれ、以下の全10科目から出題されます。
| 試験科目 | 択一式 計7科目(配点) | 選択式 計8科目(配点) |
| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | |
| 健康保険法 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 厚生年金保険法 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 国民年金法 | 10問(10点) | 1問(5点) |
| 合計 | 70問(70点) | 8問(40点) |
社労士試験の合格率・難易度
社労士試験の合格率は約5~7%ほどという超難関試験となっています。
直近である令和5年度の第55回社会保険労務士試験は、受験者数42,741人に対し合格者は2,720人、合格率は6.4%という結果でした。
わかりやすく大学入試の例で例えると、MARCHを受験するのと同じくらいの難易度と考えられ、偏差値でいうと60~64あたり。
合格するための勉強時間は800~1000時間必要と言われています。
社労士試験の勉強方法は?
社労士試験の勉強方法として大切なポイントは『苦手科目を作らない』『適切な順序で効率的に学習を進めていく』『理解しながら暗記していく』の3つです。
1つずつ解説していきましょう。
苦手科目を作らない
社労士はすべての科目で得点がとれなければ合格できない仕組みになっています。
得意科目ばかり勉強するのではなく、すべての科目を漏れなく学習することが大事です。
適切な順序で効率的に学習を進めていく
試験科目の中にはつながりの強いものや、基礎・応用関係にあるものがあります。
労働の分野では基本となる「労働基準法」と「労働安全衛生法」、社会保険の分野では「健康保険法」から学習していくのがおすすめです。
理解しながら暗記していく
社労士試験は暗記の比重が大きいですが、すべてを暗記するには範囲が広すぎますし応用問題への対応も難しいです。
基本となる考え方をしっかり理解しながら暗記することで、一つ一つの知識がつながり学習が楽しくなります。
独学で合格することは可能?
初心者が独学で合格するのはまず難しいでしょう。
社労士試験を独学で合格する人は確かにいます。
ただ独学合格者は実務経験があったり、法律の知識が長けている方が多く、受験生の中で見るとほんの一握りです。
社労士は試験範囲が膨大かつ、毎年必ず法改正があります。
自分で情報を集め、出題される箇所を見極めるのは至難の業。
また社労士試験のための勉強時間は800~1000時間程度と、長期的に勉強を続けなければならないため、モチベーションの維持がとても難しいです。
まとめ
以上で社労士の仕事についての解説をしてきました。
・社労士の仕事は労務管理に関する書類の作成とコンサルティング
・具体的な仕事内容は、労務管理書類の作成の代行、労務管理に関する帳簿の作成、労務管理や社会保険に関する相談・指導など
・社労士の年収は、会社などに勤務する場合で約895万円、独立する場合で約724万円
・働き方改革などで社労士の需要が高まってきており、今後も法改正などが考えられるため社労士には将来性がある
・社労士に必要な能力やスキルは、数字に強く地道な作業ができること、コミュニケーション能力が高いこと、正義感が強いこと
・社労士になるには社会保険労務士試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録する必要がある
・社労士の試験は合格率約5~7%ほどという超難関試験なので、試験概要と勉強法をしっかり把握することが大事
社労士は独占業務もあり、安定的に仕事をすることができる資格です。
ぜひ取得を目指してはいかがでしょうか。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 社会保険労務士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?
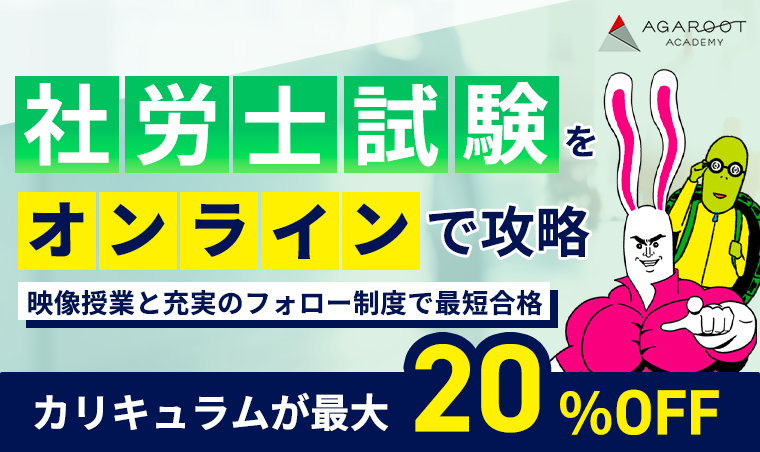
令和5年度のアガルート受講生の合格率28.57%!全国平均の4.46倍
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!


約6.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る
この記事の監修者 池田 光兵講師
広告代理店で、自らデザインやコピーも考えるマルチな営業を経験後、大手人材紹介会社で長年キャリアアドバイザーを経験、転職サポートを行う。
面接対策のノウハウや数々の自作資料は現在でも使用されている。
その後、研修講師や社外セミナーの講師などを数多く経験。
相手が何に困って何を聞きたがっているのかをすばやく察知し、ユニークに分かりやすく講義をすることが得意。
社会保険労務士試験は、ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の挑戦で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。
合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社。
自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。
池田講師の紹介はこちら