社労士は独立すべき?開業社労士の準備・費用や未経験でもなんとかなるのか解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

労務管理に関するエキスパートの資格である社労士。
「独立するのは難しいのか」「未経験でも開業して成功できるのか」
社労士の資格を目指している方にとって気になるところではないでしょうか。
そこで、社労士の独立によるメリットやデメリット、独立までに準備すること、独立開業に必要な費用、未経験でもいきなり開業できるのかといった点について解説していきます。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?

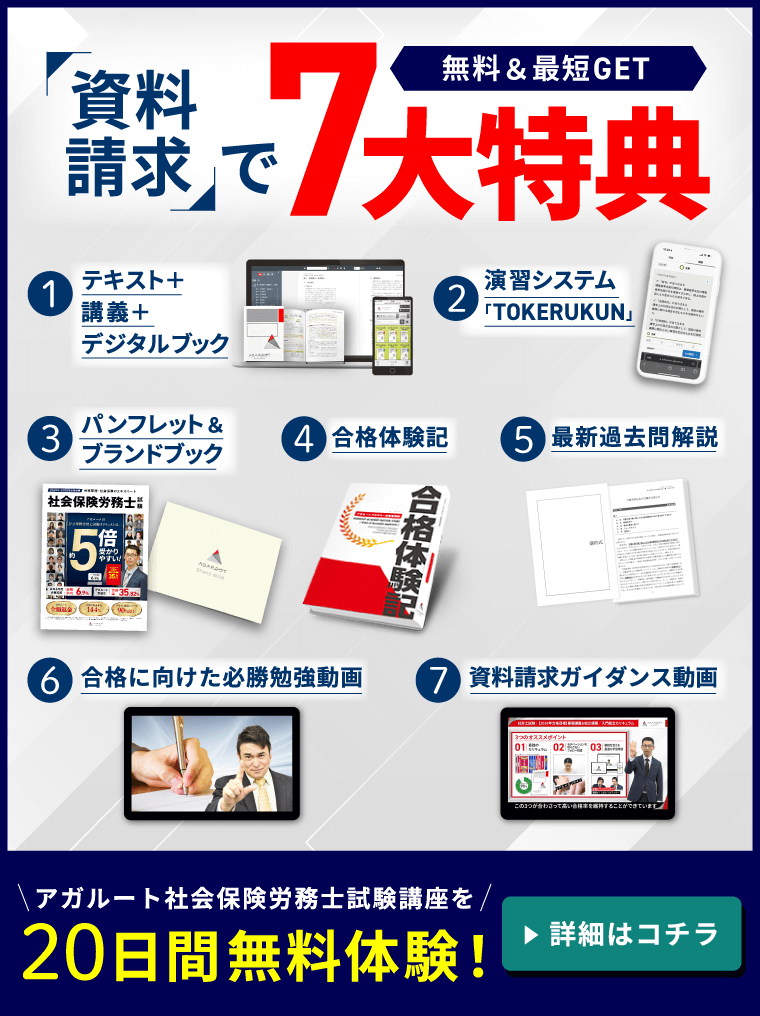
約7.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!
1分で簡単お申込み
▶資料請求して特典を受け取る目次
勤務社労士と開業社労士の違い
勤務社労士と開業社労士の違いは、「勤務先以外の仕事を引き受けられるかどうか」と「働き方や収入の仕組み」です。
勤務社労士は、企業や事務所に雇用されて働く社労士で、独立してほかの顧客と契約して業務を行うことはできません。
一方、開業社労士は自ら事務所を構え、複数の企業と契約を結び、自由に業務を請け負うことができます。
それぞれについて解説していきましょう。
勤務社労士の働き方
勤務社労士は、企業や社労士法人、社労士事務所などの組織に所属し、その一員として社労士業務を担当します。
労務管理や社会保険手続きなどの専門業務に従事しますが、報酬は月給制であり、成果にかかわらず一定額。
収入が安定している点が大きな特徴です。
また、営業活動は基本的に営業部門が担うことが多いため、社労士自身が営業にかかわる機会は少なく、業務に集中しやすいというメリットがあります。
ただし、勤務先以外で個別に契約して業務を行うことは原則できません。
開業社労士の働き方
開業社労士は、独立して事務所を立ち上げたり、フリーランスとして活動したりする社労士です。
複数の企業と顧問契約を結び、就業規則の作成や助成金申請、労務相談など幅広い業務を提供します。
営業活動や顧客開拓も自ら行う必要があるため、仕事を獲得できなければ収入が得られないというリスクが伴いますが、その反面、努力次第で高収入を目指すことも可能です。
また、働く時間や案件の選び方に自由があり、自分のペースで仕事を進めやすいという魅力もあります。
勤務社労士と開業社労士の年収の違い
| 働き方 | 平均年収 |
| 開業社労士 | 約724万円 |
| 勤務社労士 | 約895万円 |
上記データのとおり、社労士の年収は開業か勤務かで大きく異なります。
企業や事務所に所属し安定した給与が得られる勤務社労士の平均年収は約895万円。
経験や勤続年数によって収入が増える可能性が高く、安定した働き方といえるでしょう。
一方、開業社労士の平均年収は約724万円ですが、個人の営業力や実績によって収入の幅が大きくなります。
独立後、顧客を獲得できなければ収入がゼロの人もいる一方で、成功すれば数千万稼ぐことも可能です。
自由度は高いものの、経営手腕が求められるでしょう。
社労士は独立開業するべき?メリットとデメリット
社労士が独立開業した際、どんなメリットとデメリットがあるのか見ていきましょう。
自分のペースで仕事ができるが営業努力が必要
開業をすれば、誰にも命令されず自分の裁量の下で仕事を行うこととなるため、自分に合ったペースで仕事を行うことが可能です。
社労士であれば自宅で開業することもできるので、子供のいる方でも社労士は働きやすいです。
仕事と生活の両立を目指すワークライフバランスを実現しやすいのもメリットの1つと言えます。
ただし社労士の仕事は、事務所に座って待っているだけでは舞い込みません。
紹介、営業、Web集客(ホームページやSNS)、社労士マッチングサービスなどの営業努力が不可欠です。
いくら社労士資格があるとは言え、開業したら営業努力を欠かさないようにする必要があるでしょう。
良くも悪くも努力が収入に直結する
自分の頑張り次第で収入は増えますが、何もしなければ収入は増えないというが独立した開業社労士の現実です。
『2024年度社労士実態調査』によると、開業社労士の年間売上(収入)金額の平均は1657.9万円、中央値は550.0万円となっています。
年間売上(収入)金額が1,000万円以上の開業社労士は33.8%存在していて、努力次第では高収入を得ることも可能です。
ただ年間売上(収入)金額が「収入なし」が6.3%、500万未満の割合が36.5%という割合も事実としてあります。
顧客と親密になりやすい
勤務する場合に比べ、開業すれば顧客とより身近に接することが多くなる傾向にあります。
その分、顧客から感謝される機会も増え、仕事にやりがいを感じやすくなるでしょう。
ただし親密になるにつれ無茶な要求をしてくるクライアントと対峙することもあります。
そんな時も開業社労士は個人事業主のため、すべて自分でどう対処するかを考え行動しなければなりません。
開業社労士として独立するまでに準備すること
ここでは、開業社労士として独立するまでに必要な準備を段階ごとに解説します。
1. 社労士試験に合格する
まず、社労士になるためには国家試験「社会保険労務士試験(以下、社労士試験)」に合格することが必須です。
社労士試験を受験するには、「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣が認めた国家試験の合格」のいずれかの条件を満たさなくてはなりません。
これらのうち、ひとつでも該当すれば受験資格を得られます。
また、試験の申込み時には、受験資格があることを証明する「受験資格証明書」の提出が必要です。
2. 実務経験がない場合は事務指定講習を受講する
社労士試験に合格したあとも、すぐに開業はできません。
実務経験が2年未満の場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する「事務指定講習」の受講が必要になります。
講習は、通信指導(4か月)とeラーニング講習または面接指導課程(4日間)で構成されており、両方の受講が必須。
受講料は77,000円(税)です。
「労働基準法及び労働安全衛生法」や「雇用保険法」など、人事や労務に関する法律知識を学習します。
実務経験のない人にとって、社労士業務の基本を身につける大切な機会です。
3. 社労士名簿へ開業登録を行う
講習を終えたら、全国社会保険労務士会連合会の社労士名簿に登録を行います。
自身が所属する都道府県の社労士会を通じて、登録の申請を行い、書類審査が通れば証票が交付されます。
提出書類は、以下の8点です。
- 社会保険労務士登録申請書
- 個人番号カードの両面の写し、もしくは個人番号が記載されている書類1種類+身元確認のできる書類1種類
- 社会保険労務士試験合格証書の写し
- 従事期間証明書(様式第8号)または事務指定講習修了証の写し
- 住民票の写し(提出の日前3ヶ月以内かつ市区町村から交付されたマイナンバーの記載のないもの)
- 写真票
- 「戸籍抄本」「個人事項証明書」「改製原戸籍」「住民票の写し」のいずれか1つ
- 通称併記願(※必要な場合のみ)
また、登録にあたって登録免許税と手数料を合わせて60,000円がかかります。
加えて、社労士会への入会金・年会費も別途必要です。
4. 開業準備と手続きをする
資格登録が完了したら、開業に向けた実務的な準備に入りましょう。
まずは、事業計画を立てることが重要です。
どのような顧客層をターゲットにするか、どの業務を主軸にするかなど、業務内容と営業方針を具体化します。
競合分析や地域性の確認も、営業活動を進めるうえで欠かせません。
次に、事務所開設に向けたオフィス探し、備品の準備も必要になります。
ただし、コストを抑えたい場合や小規模でスタートしたい場合は、自宅を事務所として開業することも可能です。
その場合、自宅の一部を業務スペースとして確保したうえで、必要な設備をそろえます。
開業準備が整ったら、国税庁のホームページから「個人事業の開業届出」をダウンロードし、税務署に提出しましょう。
5. 集客をする
開業後のもっとも大きな課題が「集客」です。
独立したからといって、すぐに顧客が集まるとは限りません。
継続的に仕事を得ていくためには、自ら営業活動を行っていく必要があります。
集客には以下のような方法が効果的です。
- 交流会に参加等して人脈を作る
- ホームページを作る
- SNSやブログを開設する
- セミナーを開催する等
自分の専門分野や強みを明確に打ち出し、情報発信を継続していくことがポイント。
少しずつ信頼を築き、顧客を獲得していくことができるでしょう。
社労士は独立開業する際に必要な費用はいくら?
独立開業に必要な費用として、100万円前後は見込んでおいた方が無難です。
最低限必要となるのが登録料。
社労士登録時に、登録免許税30,000円と登録手数料30,000円が必要となります。
これらに加え、全国にある各地の社労士会に入会費と年会費を払います。
(例)東京都社労士会:入会金50,000円、年会費96,000円
つまり、東京都で開業するなら、登録料だけで合計206,000円が必要となるわけです。
※詳しくは社労士の登録料はいくら?合格後の登録方法や更新について解説をご覧下さい
登録料だけでなく、活動費や広告費に数十万円は確保しておかなくてはなりません。
事務所も借りるとなればさらに多額に費用が必要です。
やはり100万円程度の費用は見込んでおいた方が良いでしょう。
未経験でもいきなり社労士として独立開業できる?
未経験であっても社労士としていきなり独立開業することは可能です。
社労士として資格を活かして仕事をするためには、以下の2つを満たす必要があります。
- 社労士試験に合格していること
- 2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験又は事務指定講習の履修
つまり、実務経験がなくとも、社労士試験に合格して事務指定講習を履修すれば独立開業を行うことが可能なのです。
しかし、勤務経験を経ずにいきなり独立すると、ノウハウ不足から新規顧客の開拓に苦労する可能性は高いでしょう。
また、実務の面においても「健康保険・厚生年金保険等の加入・給付の手続き」や「雇用保険・労災保険の加入・給付の手続き」といった開業社労士の中心業務は実務経験がないと難しく、未経験での開業は簡単ではありません。
未経験での開業に不安を抱いているなら、社労士事務所などに勤めて実務経験を積んだ後に独立開業をした方が成功しやすいでしょう。
社労士の開業セミナーやイベント等も数多く実施されているので、一度参加してみるのもおすすめです。
まとめ|開業は簡単ではないが社労士には選択肢が多い
以上、社労士の独立開業について解説していきました。
現在多くの社労士が開業しており、未経験でも開業はできますが、軌道に乗せるのは簡単ではありません。
しかし、実際に成功している方も数多くいます。
社労士として独立開業するのに、年齢制限等は一切ありません。
育休を取得した主婦の方のセカンドキャリアとして、定年後の第二の人生として独立して開業社労士を選択する人も多いです。
労務管理のエキスパートであり、独立開業から勤務まで幅広い選択肢を持つ社労士は魅力的な資格だと言えるでしょう。
この機会に、資格取得を目指してみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 社会保険労務士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?

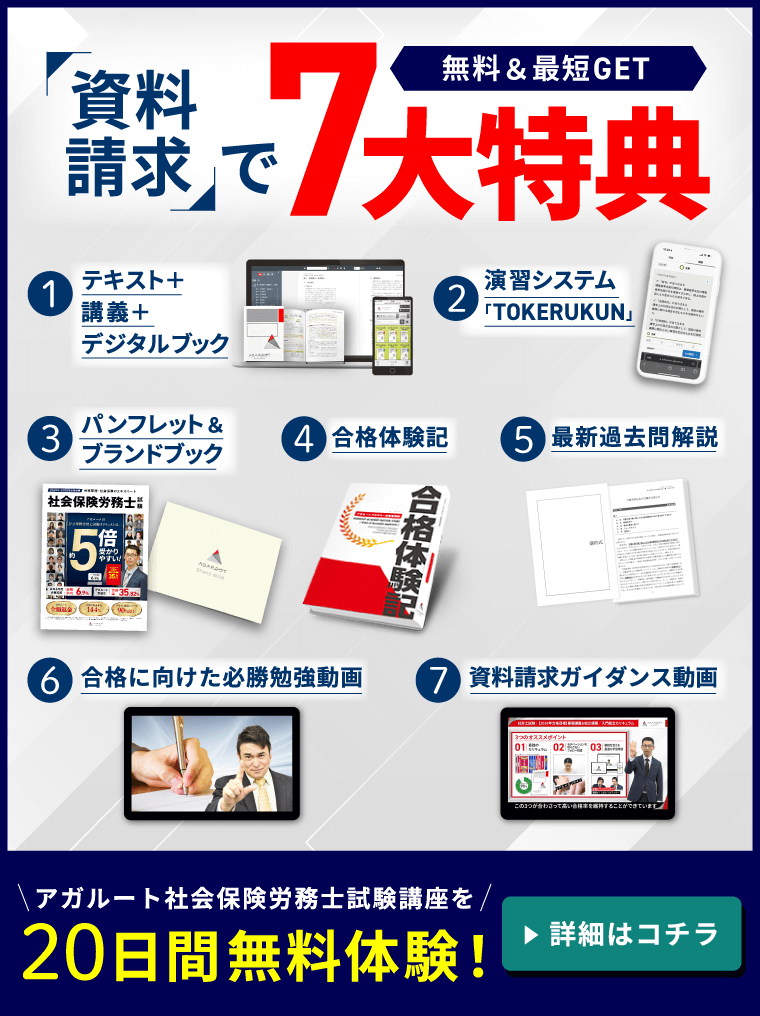
約7.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る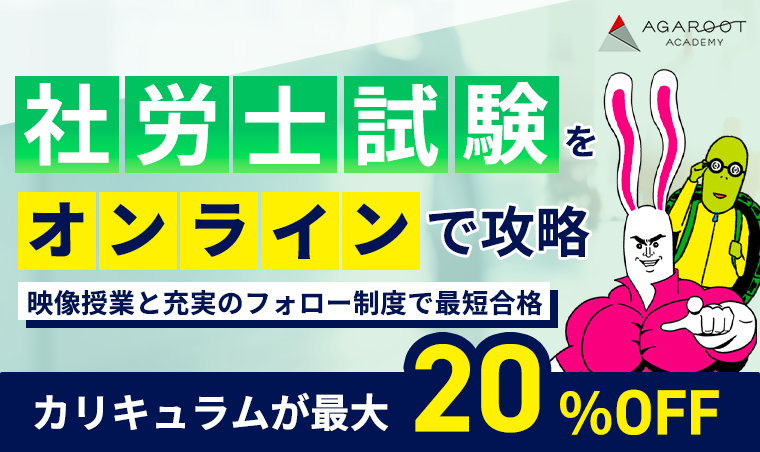
令和6年度のアガルート受講生の合格率35.82%!全国平均の5.19倍
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!
▶社会保険労務士試験講座を見る



