高卒でも社労士の受験資格を得られる!最短取得は実務経験と国家資格合格どっち?
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

社会保険労務士(以下、社労士)は、専門性が高い国家資格。
社労士試験は高卒でも受験できますが、実務経験などの受験資格を満たす必要があります。
高卒から社労士を目指そうと考えている方は、最短で社労士になるための方法が気になりますよね。
本コラムでは、高卒で社労士を目指すための方法について解説します。
社労士の受験資格やおすすめのダブルライセンスなども紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?

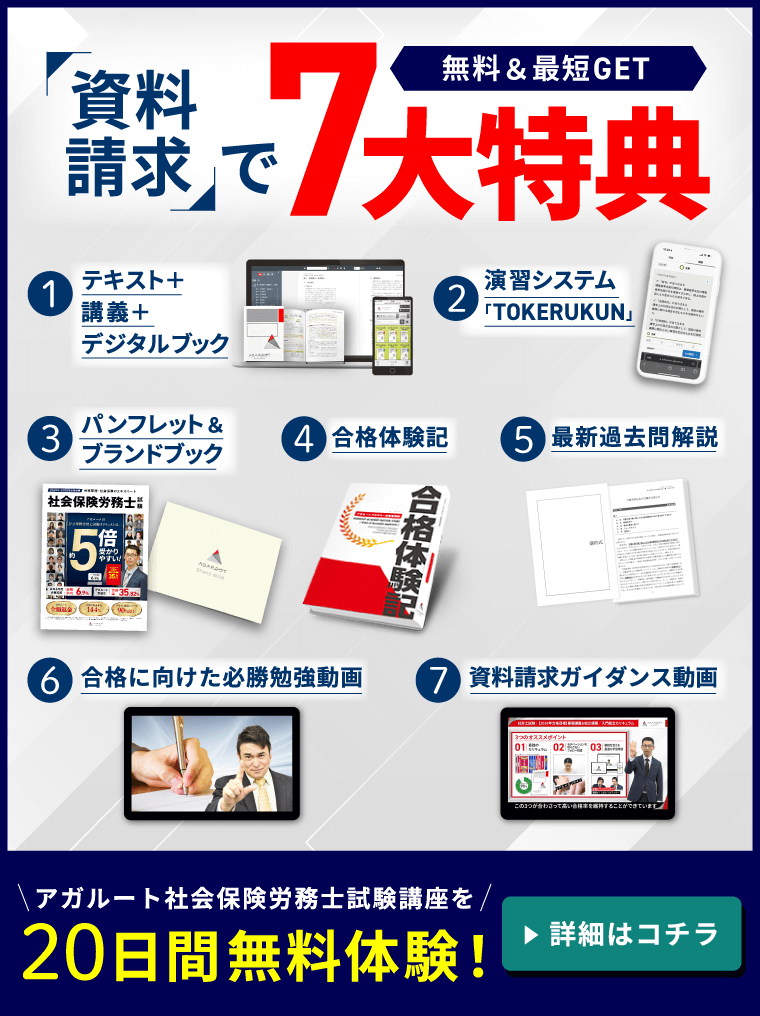
約7.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!
1分で簡単お申込み
▶資料請求して特典を受け取る目次
社労士試験の受験要件はこの3つ!
社労士試験には受験資格があり、受験するためには「学歴」「実務経験」「国家試験合格」の3つのうち、いずれかひとつの要件を満たす必要があります。
3つの受験資格の詳細は、以下の通り。
- 学歴
- 実務経験
- 国家試験合格
学歴
以下のいずれかを卒業していれば、社労士試験を受験するための学歴要件を満たせます。
- 大学
- 短大
- 専門学校
- 厚生労働大臣が認めた学校
- 専門職大学
- 専門職短大
- 5年制の高等専門学校
ただし、4年制大学の場合は、62単位以上を取得していれば受験資格を得られます。
大学を中退した場合や在学中の場合も、単位数を満たしていれば問題ありません。
「厚生労働大臣が認めた学校」の一例は、保健師学校や看護師学校、助産師学校などです。
さらに、各種教員の養成機関や医療関係の専門学校なども含まれます。
実務経験
3年以上の実務経験があれば、実務経験による社労士試験の受験資格を得られます。
要件として認められる実務の例は、以下の通り。
- 社会保険労務士や弁護士の補助業務
- 社会保険庁での行政事務
- 労働組合の役員業務
- 会社またはそのほかの法人の役員としての労務
- 事業を営む個人として労働社会保険諸法令に関する事務
- 健康保険組合や労働保険事務組合などでの関連業務
- 公務員の行政事務
- 全国健康保険協会または日本年金機構の関係法令事務
実務経験による受験資格を得るためには、「実務要件証明書」の提出が必要です。
事前に記載内容や記載方法を確認しておきましょう。
なお、実務経験が要件を満たしているかの判断が難しい場合は、全国社会保険労務士連合会による確認が行われます。
国家試験合格
以下のいずれかの試験に合格した場合は、国家試験合格による社労士試験の受験要件を満たせます。
- 行政書士試験
- 司法試験予備試験等
- 社労士試験以外のうち、厚生労働大臣が認めた国家試験
社労士試験以外の国家試験には、司法書士試験や土地家屋調査士試験、司法試験などが該当します。
また、資格試験だけでなく、労働基準監督官や入国警備官などの国家公務員の採用試験も対象です。
厚生労働大臣が認めた国家試験について詳しく知りたい方は、厚生労働大臣が認めた国家試験をご覧ください。
高卒が最短で社労士になるにはどうする?
結論から述べると、高卒から最短で社労士になるための方法は、行政書士試験に合格することです。
実務経験または学歴によって社労士試験の受験資格を満たす場合、最低でも2年以上かかります。
そのため、2年未満で行政書士試験に合格できれば、最短で社労士試験を受けられるでしょう。
受験資格の要件を簡単にまとめた表は、以下の通り。
| 受験要件 | 内容 | 所要期間 |
| 学歴 | 短大を卒業する | 2年以上 |
| 実務経験 | 実務経験を3年積む | 3年以上 |
| 試験合格 | 行政書士試験に合格する | 最短数ヶ月(努力次第) |
以下では、各要件について、受験資格を満たすまでの所要期間が短い順に解説します。
- 行政書士試験に合格する
- 短大を卒業する
- 実務経験を3年積む
行政書士試験に合格する
高卒から最短で社労士になりたい場合は、行政書士試験の合格を目指しましょう。
行政書士試験は、例年11月の第2日曜日に実施される国家試験。
合格に必要な勉強時間の目安は500〜1,000時間、例年の合格率は約10%であり、難易度は高いといえるでしょう。
行政書士試験は決して簡単な試験ではありませんが、努力次第で短期合格を目指せます。
毎日5時間ずつ学習に取り組めば、約半年で必要な勉強時間を満たせるでしょう。
また、通信講座や予備校を活用して勉強時間を短縮すれば、数か月で合格することも不可能ではありません。
行政書士試験の概要は、以下の通りです。
行政書士試験の概要
| 試験日時 | 例年11月 第2日曜日 13時~16時(3時間) |
| 受験資格 | なし。 年齢、性別、学歴、国籍等関係なく誰でも受験可能。 |
| 試験科目 | ●行政書士の業務に関し必要な法令等 ・民法 ・行政法 ・憲法 ・基礎法学 ・商法 ・会社法 ●行政書士の業務に関し必要な基礎知識 ・一般知識 ・行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 ・情報通信 ・個人情報保護 ・文章理解 |
| 合格基準 | ①法令科目で122点以上得点すること ②基礎知識で24点以上得点すること ③合計で180点(全体の6割)以上得点すること (絶対評価) |
| 難易度 | 合格率10%前後 |
| 受験手数料 | 10,400円 |
行政書士試験では、主に法律に関する知識が問われます。
法律の知識は社労士試験にも役立つため、試験勉強の面でもメリットがあるでしょう。
短大を卒業する
高卒から社労士になるためには、短大を卒業して学歴要件を満たす方法もあります。
学歴による社労士試験の受験資格は複数ありますが、短大なら最短2年で要件を満たせます。
学費を抑えたい方や、仕事や育児と通学を両立したい方には、通信制の短大がおすすめ。
通信制短大は、全日制の短大よりも学費が安い傾向があります。
また、通信制短大の授業は土日に行われることが多いため、働きながら卒業を目指せるでしょう。
実務経験を3年積む
資格試験合格や短大卒業が難しい場合は、3年以上の実務経験を積みましょう。
実務経験による受験資格を満たすメリットは、実務に関する知識を学べること。
また、給与を受け取りながら資格の勉強に取り組めるため、試験勉強中の生活に不安がある方にもおすすめです。
ただし、未経験から入社して、すぐ要件に該当する実務に携われるとは限りません。
そのため、実際には3年以上かかる可能性があるでしょう。
社労士と行政書士のダブルライセンスのメリット
行政書士は社労士と業務上の相性が良く、ダブルライセンスにおすすめの資格です。
高卒の方が行政書士を取得すれば、社労士の受験資格を満たす以外にもさまざまなメリットが期待できるでしょう。
社労士と行政書士のダブルライセンスを取得する主なメリットは、以下の3つ。
- 仕事の幅が広がる
- アピールポイントになる
- 働き方の選択肢が増える
仕事の幅が広がる
社労士と行政書士のダブルライセンスを取得する最大のメリットは、仕事の幅が広がることです。
社労士と行政書士は、それぞれ担当領域が異なります。
行政書士は、主に許認可申請や申請書類の作成に関する専門家。
また、社会保険労務士は、社会保険や労務管理、各種助成金の申請手続きなどに携わります。
どちらか片方の資格だけを取得した場合、クライアントはそれぞれの業務を行政書士と社労士に依頼しなければなりません。
しかし、ダブルライセンスを取得すれば、これらの業務をすべて一人で行えます。
クライアントからの依頼をワンストップで請け負えるため、双方にメリットがあるでしょう。
アピールポイントになる
ダブルライセンスの取得は、大きなアピールポイントになります。
社労士と行政書士は、いずれか片方でも独立開業を目指せる資格です。
両方の資格をもっていることをアピールすれば、同業者との差別化を図れるでしょう。
また、ダブルライセンスは転職や就職に役立つというメリットもあります。
企業に対してダブルライセンスをアピールすれば、難関資格を取得するための努力や向上心、勤勉さなどを評価される可能性が高いでしょう。
働き方の選択肢が増える
社労士と行政書士のダブルライセンスを取得すれば、働き方の選択肢が広がります。
行政書士は、どちらかといえば独立開業に向いている資格です。
そのため、すぐに独立しない場合は、資格を活かせる場面が少ないと感じるかもしれません。
しかし、社会保険労務士は企業から重宝されやすく、就職や転職にも役立つ資格です。
独立開業はもちろん、企業での人事・労務部門や社労士事務所での勤務など、さまざまな選択肢を得られるでしょう。
高卒で社労士になるなら資格取得がおすすめ!
高卒から社労士を目指す場合、国家試験の合格によって受験資格を満たす方法が最短ルートです。
受験資格として認められる国家試験は多くあるため、自分が受けたいものを選べます。
一方で、受験資格として認められる国家試験は、いずれも難易度が高い傾向がある点に注意が必要です。
どの試験を受けるべきか迷っている方には、行政書士試験がおすすめ。
行政書士試験の勉強によって法律系の知識を身に付ければ、社労士試験の学習がスムーズに進みます。
また、行政書士は社労士と相性が良い資格であるため、ダブルライセンスによるメリットも期待できるでしょう。
高卒で社労士を目指している方は、まず行政書士試験から挑戦してみてはいかがでしょうか。
まとめ
本コラムでは、高卒で社労士を目指すための方法について解説しました。
高卒で社労士になるためには、まず社労士試験の受験資格を得る必要があります。
学歴や実務経験、国家試験合格などの受験資格があるため、自分に合ったものを選びましょう。
高卒から最短で社労士になるための主な方法は、以下の3つ。
- 行政書士の資格を取得する
- 短大を卒業する
- 実務経験を3年積む
行政書士試験は難易度が高いため、十分な試験対策が必要です。
最短で社労士になりたい方には、アガルートアカデミーの資格試験講座がおすすめ。
興味をお持ちの方は、無料の受講相談や資料請求をご活用ください。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 社会保険労務士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?

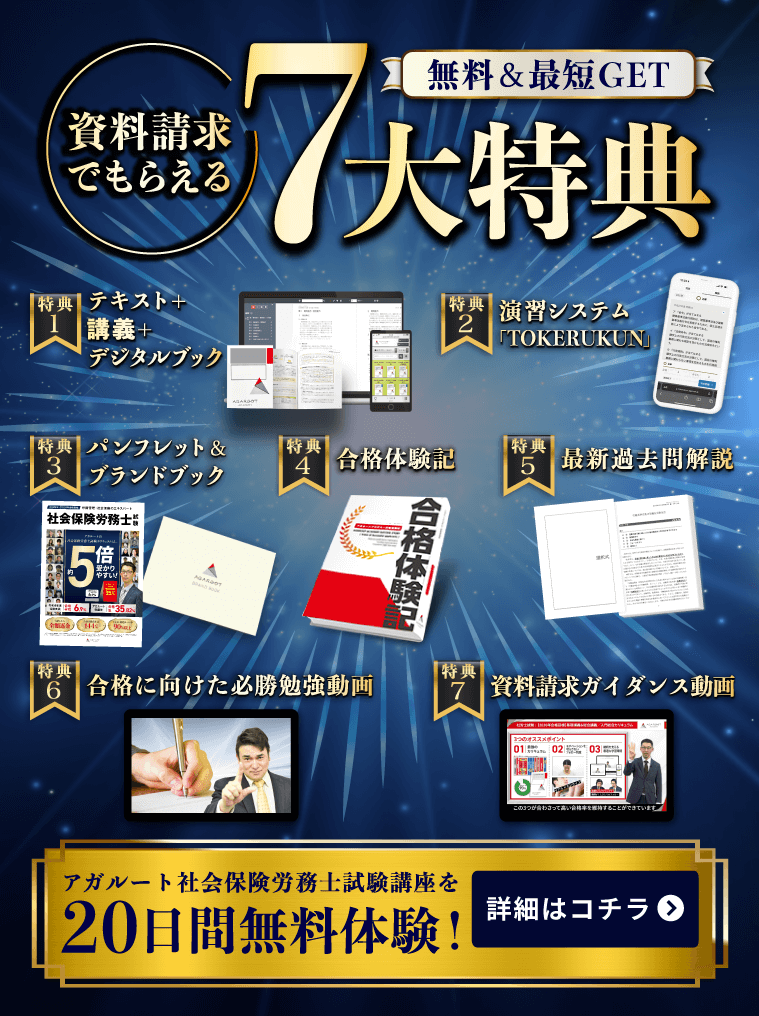
約7.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る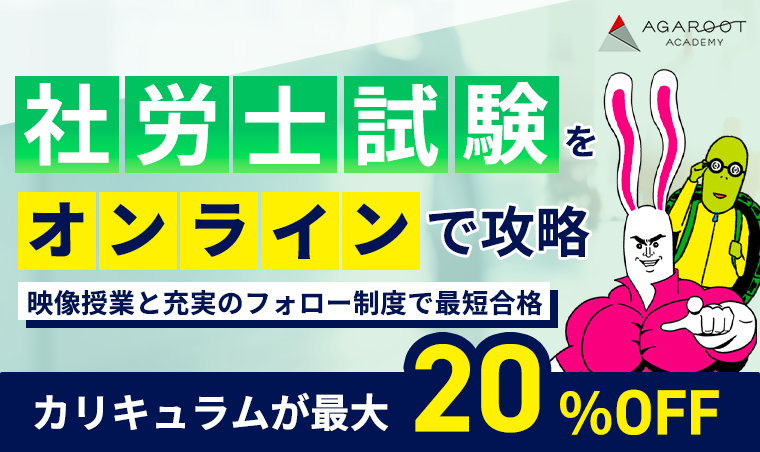
令和6年度のアガルート受講生の合格率35.82%!全国平均の5.19倍
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!
7月23日までの申込で10%OFF!
▶社会保険労務士試験講座を見る※2025年合格目標



