登録日本語教員とは?なるには?資格取得ルートと試験概要を解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
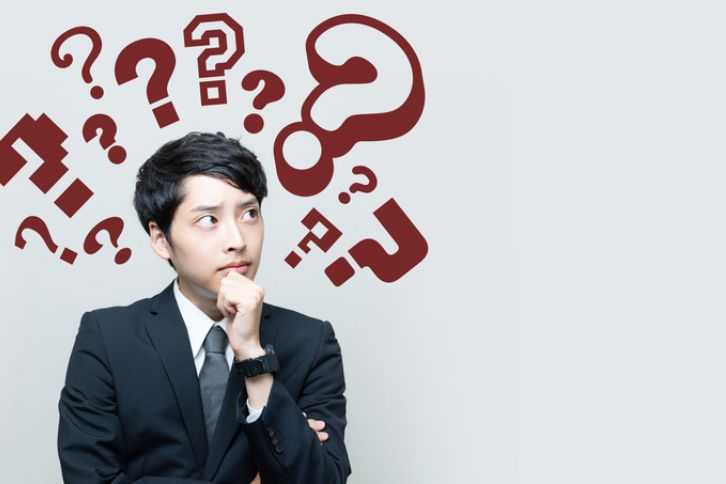
「登録日本語教員ってどんな資格?」
「登録日本語教員資格を取得するにはどうすれば良い?」
「現職の日本語教員も登録日本語教員の資格を取得した方がいいの?」
外国人に日本語を教えている教員の方やこれから外国人に日本語を教える教員を目指している方は、上記のような疑問を持っている方が多いのではないでしょうか。
今後は、登録日本語教員資格をもっていないと、認定日本語教育機関において日本語を教えることができなくなります。
したがって、今から正しく登録日本語教員制度や資格取得までのプロセスを理解しておくことが重要です。
そこで本コラムでは、登録日本語教員とはどのような資格かを解説します。
現職の日本語教員の方にも参考になるように、資格取得までの原則的なルートと一定期間のみ利用できる経過措置ルートも説明するので、ぜひ参考にしてください。
日本語教育能力検定試験・
日本語教員試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの日本語教育能力検定試験・
日本語教員試験講座を
無料体験してみませんか?

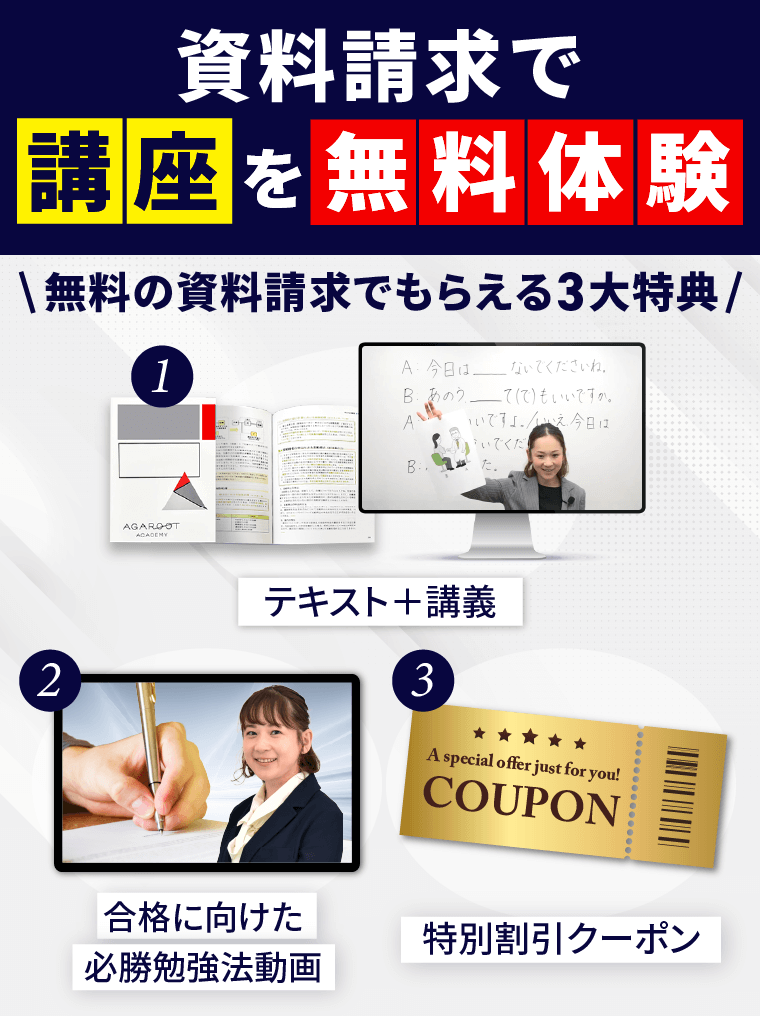
約3.5時間分の世界と日本、 異文化接触、言語教育法・実習講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!日本語教育能力検定試験・日本語教員試験対策のフルカラーテキスト
プロ講師が解説!合格に向けた必勝勉強法動画
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
登録日本語教員とは
登録日本語教員とは、日本語教育の質の向上と教師の専門性を担保する目的で創設された新しい国家資格です。
外国人に日本語を教える日本語教師の専門性を確立し、教育の質を保証するために導入されました。
制度の導入は「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」に基づき、2023年5月26日に制定され2024年4月1日から実施されています。
登録日本語教員になるには、
- 基礎試験(日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能について判定する試験)
- 応用試験(応用に関する知識及び技能について判定する試験)
を含む日本語教員試験に合格し、認定日本語教育機関において実践研修(日本語教育を行うために必要な技術を習得する研修)を修了しなければなりません。
実践研修は、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関で行われます。
登録日本語教員は国家資格なため、資格取得のためには一定の努力が必要となりますが、日本語教師としての資質が公的に認められ、教育機関や学習者からの信頼が得られやすくなります。
登録日本語教員の資格取得のメリットとしては、認定日本語教育機関での就労機会が増えることが挙げられます。
認定日本語教育機関とは、日本語教育課程を適正かつ確実に実施できる機関として、文部科学大臣から認定を受けた日本語教育機関のことです。
日本語教育を適正かつ確実に実施することが求められるため、認定日本語教育機関で日本語教師として働くうえで、日本語教員は登録日本語教員の資格を必ず取得していなければなりません。
登録日本語教員になるには?資格取得ルート

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93982901_17.pdf
2025年現在、登録日本語教員になるには大きく2つのルートが用意されています。
「養成機関ルート」「試験ルート」と呼ばれるルートです。
2つのルートは、登録日本語教員になりたい方の個々の経験や状況に応じて選択できるように設計されています。
養成機関ルートは、特定の養成機関で教育を受けることで、基礎試験が免除され、応用試験を受け、実践研修を受けることで登録日本語教員になれるルートです。
一方、試験ルートでは、基礎試験・応用試験を突破し、実践研修を受けることで登録日本語教員になれるルートとなります。
養成機関ルートの対象者と資格取得の流れ
養成機関ルートは、特に日本語教育の専門知識と技術を系統的に学びたいと考えている方に適したルートです。
養成機関ルートを選択する候補者は、文部科学省に認定された「登録日本語教員養成機関において座学プログラムを受講します。
養成機関における課程を修了した方については、基礎試験が免除され、応用試験を受けることになります。
その後、養育機関における課程で登録実践研修機関で行われる実践研修を受けていない場合は、実践研修を受けなければなりません。
試験ルートの対象者と資格取得の流れ
一方、試験ルートは、特定の養成機関を経ずに直接試験に挑戦したいと考えている方のために用意されているルートです。
試験ルートを選んだ場合、基礎試験と応用試験の両方に合格しなければなりません。
その後、文部科学省に登録された実践研修機関での実習も修了する必要があります。
登録日本語教員試験の概要
登録日本語教員試験の概要は以下のとおりです。
| 基礎試験 | 応用試験 | ||
| 聴解 | 読解 | ||
| 試験時間 | 120分 | 50分 | 100分 |
| 出題数 | 100問 | 50問 | 60問 |
| 出題形式 | 選択式 | ||
| 配点 | 1問1点(計100点) | 1問1点(計110点) | |
| 合格基準 (参考基準) |
必須の教育内容で定められた5区分において、各区分で6割の得点があり、かつ総合得点で8割の得点があること | 総合得点で6割の得点があること | |
| 受験料 | 通常:18,900円 基礎試験免除:17,300円 基礎試験・応用試験免除:5,900円 |
||
なお、以下で説明する試験日以外の情報は確定したものではありません。
登録日本語教員試験の試験日
次回の登録日本語教員試験は、令和7年11月2日に実施されます。
登録日本語教員試験の開催地
登録日本語教員試験の開催地は、以下となります。
| エリア | 会場 | 住所 |
| 北海道 | TKP 札幌カンファレンスセンター | 北海道札幌市北区7条西2-9 |
| 東北 | TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 | 宮城県仙台市青葉区花京院 1-2-15 |
| 関東 | 駒澤大学(駒沢キャンパス) | 東京都世田谷区駒沢 1-23-1 |
| TOC 五反田 | 東京都品川区西五反田 7-22-17 | |
| TKP ガーデンシティ PREMIUM 品川高輪口 | 東京都港区高輪 4-10-18 | |
| TKP 新橋カンファレンスセンター | 東京都千代田区内幸町 1-3-1 | |
| 中部 | 名城大学(天白キャンパス) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目 501 番地 |
| 近畿 | 大阪公立大学(中百舌鳥キャンパス) | 大阪府堺市中区学園町 1 番 1 号 |
| 中四国 | TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前 | 広島県広島市南区大須賀町 13-9 |
| 九州 | 九州大学(伊都キャンパス) | 福岡県福岡市西区元岡 744 |
| 沖縄 | 沖縄コンベンションセンター | 沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1 |
第1回日本語教員試験については、紙ベースの試験として実施されました。
ただし今後、受験機会の拡大等を目的として、日本語教員試験のCBT(Computer Based Test)化も検討されています。
登録日本語教員試験の受験料
登録日本語教員試験の受験料は通常18,900円です。
基礎試験免除の場合は17,300円となり、基礎試験及び応用試験も免除の場合は5,900円となります。
登録日本語教員試験の科目・出題内容
登録日本語教員試験のうち、基礎試験では日本語教育を行うために必要となる基礎的な知識及び技能を区分ごとに出題することになっています。
登録日本語教員試験のうち、基礎試験における5つの区分とその出題割合は以下の表のとおりです。
| 全体目標 | 一般目標 | 必須の教育内容 | 基礎試験 おおむねの 出題割合(※) |
| 1.社会・文化・地域 | ①世界と日本 | <1>世界と日本の社会と文化 | 約1~2割 |
| ②異文化接触 | <2>日本の在留外国人施策 <3>多文化共生(地域社会における共生) |
||
| ③日本語教育の歴史と現状 | <4>日本語教育史 <5>言語政策 <6>日本語の試験 <7>世界と日本の日本語教育事情 |
||
| 2.言語と社会 | ④言語と社会の関係 | <8>社会言語学 <9>言語政策と「ことば」 |
約1割 |
| ⑤言語使用と社会 | <10>コミュニケーションストラテジー <11>待遇・敬意表現 <12>言語・非言語行動 |
||
| ⑥異文化コミュニケーションと社会 | <13>多文化・多言語主義 | ||
| 3.言語と心理 | ⑦言語理解の過程 | <14>談話理解 <15>言語学習 |
約1割 |
| ⑧言語習得・発達 | <16>習得過程(第一言語・第二言語) <17>学習ストラテジー |
||
| ⑨異文化理解と心理 | <18>異文化受容・適応 <19>日本語の学習・教育の情意的側面 |
||
| 4.言語と教育 | ⑩言語教育法・実習 | <20>日本語教師の資質・能力 <21>日本語教育プログラムの理解と実践 <22>教室・言語環境の設定 <23>コースデザイン <24>教授法 <25>教材分析・作成・開発 <26>評価法 <27>授業計画 <29>中間言語分析 <30>授業分析・自己点検能力 <31>目的・対象別日本語教育法 |
約3~4割 |
| ⑪異文化間教育とコミ ュニケーション教育 | <32>異文化間教育 <33>異文化コミュニケーション <34>コミュニケーション教育 |
||
| ⑫言語教育と情報 | <35>日本語教育とICT <36>著作権 |
||
| 5.言語 | ⑬言語の構造一般 | <37>一般言語学 <38>対照言語学 |
約3割 |
| ⑭日本語の構造 | <39>日本語教育のための日本語分析 <40>日本語教育のための音韻・音声体系 <41>日本語教育のための文字と表記 <42>日本語教育のための形態・語彙体系 <43>日本語教育のための文法体系 <44>日本語教育のための意味体系 <45>日本語教育のための語用論的規範 |
||
| ⑮コミュニケーション能力 | <46>受容・理解能力 <47>言語運用能力 <48>社会文化能力 <49>対人関係能力 <50>異文化調整能力 |
他方で、応用試験は、基礎的な知識及び技能を活用した問題解決能力が測定される試験です。
問題解決能力とは、教育実践において発揮されるものと捉えられており、応用試験は、教育実践と関連させて出題されることになっています。
そのため、上記の区分を横断する出題がなされることから、領域ごとの出題割合は示されていません。
応用試験の一部は、日本語学習者の発話や教室での教師とのやりとりなどの音声を用い、より実際の教育実践に即した問題が出題され、問題解決能力や現場対応能力等が測定されます。
登録日本語教員試験の試験時間・出題数
基礎試験は全体で120分の試験時間が設定されており出題数は100問です。
各問題の配点は1点、全体で100点満点となります。
この試験では1問あたり約72秒で解答しなければなりません。
応用試験は音声による問題と文章問題の二部構成です。
聴解問題は50分間で50問、読解問題は100分間で60問となります。
文章題には途中休憩があります。
各問題の配点は1点で、全体で110点満点の試験です。
聴解問題では、1問あたり約60秒、読解問題では1問あたり約100秒で解答する必要があります。
登録日本語教員試験の出題形式
登録日本語教員試験の出題形式は、基礎試験、応用試験ともに選択式となっています。
選択肢が何択あるのかなど、詳細な情報は公表されていません。
登録日本語教員試験の配点・合格基準
基礎試験の配点は1問1点の合計100点、応用試験の配点は1問1点の合計110点となっています。
基礎試験の合格基準は「必須の教育内容で定められた5区分において、各区分で6割の得点があり、かつ総合得点で8割の得点があること」です。
一方、応用試験の合格基準は「総合得点で6割の得点があること」となっています。
登録日本語教員試験の時間割
第1回登録日本語教員試験の時間割は以下の通りです。
| 着席時刻 | 所要時間 | |
| 開場 | – | 9:00~9:40 |
| 試験① 基礎試験 |
9:40 | 10:00~12:00 (120 分) |
| 昼休憩 | – | 12:00~13:00 |
| 試験② 応用試験Ⅰ(聴解) |
13:00 | 13:20~14:10 (50 分) |
| 休憩 | – | 14:10~14:30 |
| 試験② 応用試験Ⅱ(読解) |
14:30 | 14:50~16:30 (100 分) |
※着席時刻までに自席に着席してください。試験開始時刻までの間に、注意事項の説明及び問題冊子の配布を行います。
※解答終了時刻の後、試験問題冊子とマークシートの回収及び確認作業がありますので、試験監督の指示があるまで、試験室で待機してください。試験問題冊子を持ち帰ることはできません。
※基礎試験、応用試験Ⅱ(読解)について、試験開始時刻に遅刻した場合は、20分までの遅刻に限り受験を認めます。試験を開始してから 20分以内に試験室に入室していない場合は受験することができません。遅刻が20分以内であっても遅刻した時間に係る試験時間の延長はありません。
※応用試験Ⅰ(聴解)については、遅刻は一切認めません。
登録日本語教員試験の申し込み方法
日本語教員試験の出願は電子申請のみです。
出願期間は、令和7年7月14日(月)10:00から8月22日(金)23:59までとなっています。
詳細は、日本語教員試験 試験案内をご確認ください。
出願の流れ
登録日本語教員試験の申し込みは以下の流れでおこないます。
- アカウント作成
- マイページ作成
- 受験者登録
- 受験科目申請 ・免除申請書類のアップロード
- 出願手続きの完了
- 受験料の支払い
まず、日本語教員試験サイトより願書申請サイトにアクセスし、申請用のメールアドレス登録をおこないアカウントを作成します。
登録したメールアドレスに送信されたURLよりパスワード、メールアドレス、パスワード設定を進めマイページを作成します。
アカウント登録完了後に送られてくるマイページURLよりログインし受験者情報(氏名、住所、受験希望地、資格取得ルート等と修了課程等)を入力、顔写真データのアップロードをおこない受験者登録を完了させます。合わせて、受験科目の申請、免除申請がある場合は、免除申請の書類をアップロードします。これで出願手続きは完了です。
受験料の支払い方法
出願手続きが完了後、受験料を支払います。(収入印紙での納付)
受験案内の「収入印紙提出用台紙」に、受験料分の収入印紙を貼付のうえ、以下送付先宛てに郵送します。郵便料金は出願者の負担です。
なお、「収入印紙提出用台紙」は、日本語教員試験システムで出願する際にもダウンロード可能であり、こちらでは「受験者情報」が自動的に記入されるので、日本語教員試験システムの利用が推奨されています。
■収入印紙送付先
〒151-0053
東京都渋谷区代々木 3 丁目 25 番 3 号 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 12 階
レカム BPO 株式会社内 日本語教員試験事務局
TEL:050-5433-7942
※所定の受験料より多い収入印紙を頂いても返還いたしません。また、不足があった場合、期日までに不足分を納付いただけない場合には、受験資格がなくなります。その場合も、すでに送付頂いた収入印紙は返還いたしません。
※配達の追跡ができる送付方法(簡易書留など)を利用いただくことをお勧めします。
※デジタル庁で実施するe-Gov 電子申請のガバメントクラウド移行スケジュールの遅延影響により、今回は収入印紙の郵送としていますが、今後電子納付(ネットバンキングによる振り込み)を可能とする予定です。
事前に用意するもの
登録日本語教員試験の申し込みに際し用意するものは、「顔写真データ」と「試験免除に必要な書類」となっています。
それぞれの注意点は以下となります。
・顔写真データ
※6 か月以内に撮影した、無帽、無背景の顔写真データを準備してください。(不鮮明なもの、目を閉じているもの及びサングラスを着用しているものは不可)
※受験時に眼鏡を使用する場合、眼鏡をかけて撮影したもの。
※写真はそのまま受験票に印刷されます。
※カラー・白黒は問いません。
※データ形式は「JPEG」、データサイズは「10MB以下」としてください。
・試験免除に必要な書類
※Webサイトからアップロードするため、PDFなどにデジタルデータ化してください。
■資格取得ルートごとの提出書類の一覧
| 資格取得ルート | 提出書類 |
| 養成機関ルート | ・登録日本語教員養成機関の養成課程修了証書(写し)※1 |
| 試験ルート | - |
| 経過措置 C ルート | ・必須の教育内容 50 項目に対応した日本語教員養成課程等の修了の証明 書(写し)※1 ・学士、修士又は博士の学位の証明書※2※3※4 |
| 経過措置 D-1 ルート | ・平成 12 年報告に対応した日本語教員養成課程等の修了の証明書(写し) ・学士、修士又は博士の学位の証明書(写し)※3※4 ・講習Ⅱの修了証(写し)※5 ・日本語教育機関の在職証明書(写し)※6 |
| 経過措置 D-2 ルート | ・法務省告示基準教員要件に該当する日本語教員養成課程等の修了の証 明書(写し) ・学士、修士又は博士の学位の証明書(写し)※3※4 ・講習Ⅰ及び講習Ⅱの修了証(写し)※5 ・日本語教育機関の在職証明書(写し)※6 |
| 経過措置 E-1 ルート | ・日本語教育能力検定試験合格証書(昭和62年度~平成14年度)(写し) ・講習Ⅰ及び講習Ⅱの修了証(写し)※5 ・日本語教育機関の在職証明書(写し)※6 |
| 経過措置 E-2 ルート | ・日本語教育能力検定試験合格証書(平成15年度~令和5年度)(写し) ・講習Ⅱの修了証(写し)※5 ・日本語教育機関の在職証明書(写し)※6 |
| 経過措置 F ルート※7 | ・日本語教育機関の在職証明書(写し)※6 |
※2 出願時に大学に在学中で「学位取得見込み」の場合は、出願時の学位の証明書(写し)の提出は不要ですが、受験して合格点を得ていても「仮合格」扱いとなり、試験が実施された翌年の4月末までに学位の証明書(写し)を提出する必要があります。
※3 機関等によっては学位の証明書が発行されないことがあります。その場合は学位記(写し)を提出してください。
※4 学士には学士(専門職)を、修士には修士(専門職)、法務博士(専門職)及び教職修士(専門職)をそれぞれ含みます。
※5 出願時に講習を修了していない場合、試験が実施された翌年の 4 月末までに修了証(写し)を提出する必要があります。
※6 在職証明書の様式については、以下の文部科学省ホームページ URL に掲載の様式をダウンロードし、在職の日本語教育機関に証明のための書類作成をしてもらってください。これ以外の様式は認められません。
(在職証明書様式) https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_02668.html
※7 「現職者」の要件を満たしていないため出願時は「試験ルート」で出願した者が、その後、試験合格し、経過措置期間中に「現職者」の要件を満たすこととなる場合には、登録日本語教員の登録申請の際に、「経過措置 F ルート」扱いとすることもできます。この場合、登録日本語教員登録申請時に試験の合格証書(写し)と在職証明書(写し)を提出することで、登録実践研修機関における実践研修が免除されます。ただし、経過措置の修了する令和11年3月31日(土)までに登録される必要があります。
【提出の際の注意事項】
出願時と修了証書や証明書に記載のある氏名が異なる場合は、変更や通称名の使用が分かる証明書(戸籍全部・個人事項証明書[戸籍謄抄本]等)の提出をお願いします。
受験票について
登録日本語教員試験の受験票は、オンライン出願サイトの「マイページ」より PDF 形式で発行されます。
受験票の発送はなく、自身でPDF形式の受験票をダウンロードし、A4サイズで出力印刷したものを当日会場に持参します。
受験票をスマートフォン、タブレットにダウンロードして持ち込むことは不可となっており、必ず紙に印刷する必要があります。
受験票は掲載後、登録メールアドレスに連絡がいきます。
なお、受験票を忘れた場合は身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・写真付きの学生証等)で本人確認がおこなわれますので、念のため持参することをおすすめします。
登録日本語教員資格を現職が取得するには
すでに日本語教員として働いている方であっても、認定日本語教育機関で働くためには登録日本語教員資格を取得していなければなりません。
認定日本語教育機関以外の教育機関であれば登録日本語教員資格が無くとも働くことができるものの、認定されていない教育機関で学びたいと考える留学生は今後減少していくでしょう。
したがって、現在、日本語教員として働いている方も、登録日本語教員資格の取得を検討するべきであると考えられます。
実際、多くの現職の日本語教員の方が登録日本語教員資格取得を目指しています。
もともと、登録日本語教員制度が導入されたのは、日本語に関して質の高い指導ができる教員を確保することにありました。
しかし、現職の日本語教員が今回の登録日本語教員資格を取得しなければ、制度の趣旨に反することになります。
そのため、登録日本語教員制度を管轄する文化庁は、「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」を設けて、現職の日本語教員が登録日本語教員資格を得られるルートを用意しています。
以下では、経過措置について簡単に説明していきましょう。
経過措置を利用して資格を取得する
日本語教員として働いている現職の方は、経過措置を利用して登録日本語教員資格を取得できます。
この経過措置は、一部の例外を除き、原則として法施行後5年(令和11年3月31日)までとするとされています。
経過措置には以下の表のように6つの区分があり、登録日本語教員資格取得までのプロセスが異なります。
| 区分 | 対象者 | 要件 | 必要な試験・研修 | 免除される試験・研修 |
| C | 現職者に限らず必須の50項目に対応した課程修了者 | 必須の50項目を実施していることが確認できた現行告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、学士以上の学位を有する者 | ・応用試験 | ・基礎試験 ・実践研修 |
| D-1 | 現職者のうち必須の50項目対応前の課程修了者① | 上記の養成課程等以外で、5区分の教育内容を実施していることが確認できた現行告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、学士以上の学位を有する者 | ・講習Ⅱ講習修了認定試験 ・応用試験 |
・基礎試験 ・実践研修 |
| D-2 | 現職者のうち必須の50項目対応前の課程修了者② | 上記2つに該当しないものの、現行告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、学士以上の学位を有する者 | ・講習Ⅰ講習修了認定試験 ・講習Ⅱ講習修了認定試験 ・応用試験 |
・基礎試験 ・実践研修 |
| E-1 | 現職者のうち民間試験に合格した者① | 昭和62年4月1日~平成15年3月31日の間に実施された日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)に合格した者 | ・講習Ⅰ講習修了認定試験 ・講習Ⅱ講習修了認定試験 |
・基礎試験 ・応用試験 ・実践研修 |
| E-2 | 現職者のうち民間試験に合格した者② | 平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)に合格した者 | 講習Ⅱ講習修了認定試験 | ・基礎試験 ・応用試験 ・実践研修 |
| F | 上記以外の現職者 | 上記に該当しない現職者 | ・基礎試験 ・応用試験 |
・実践研修 |
出典: 「登録日本語教員の資格取得ルート」文化庁を参考に作成
上記の表に出てくる、「講習Ⅰ講習修了認定試験」「講習Ⅱ講習修了認定試験」とは、次のような講習・試験のことを言います。
実施方法は、受講機会確保の観点から、自宅等で受講できるオンデマンドで実施される予定です。
| 講習対象範囲 | 主な学習内容 | 時間 | 講習修了試験 | |
| 講習Ⅰ | ・平成12年報告により新たに追加された【社会・文化・地域】及び【言語と心理】の2区分を中心に構成 (1)世界と日本の社会と文化 (2)日本の在留外国人施策 (3)多文化共生 (4)日本語教育史 (5)言語政策 (6)日本語の試験 (7)世界と日本の日本語教育事情 (14)談話理解 (15)言語学習 (16)習得過程 (17)学習ストラテジー (18)異文化受容・適応 (19)日本語の学習・教育の情意的側面 |
・諸外国における言語政策 ・言語教育の現状 ・諸外国における日本語教育の現状 ・日本の海外における日本語教育政策の現状 ・国内の日本語教育の現状 ・多文化共生施策 ・地域における日本語教育施策 ・在留外国人施策と日本語の試験 ・言語理解の過程 ・言語習得と発達 ・第一言語と第二言語 ・モチベーション、WTC、言語適性 |
90分×5コマ程度(各コマで単元確認(10問程度)を実施 | 50問程度 |
| 講習Ⅱ | ・平成31年報告により教育内容として新たに追加されたもの (20)日本語教師の資質・能力 (35)日本語教育とICT (36)著作権 ・入管法改正や「日本語教育の参照枠」等、近年の状況変化を踏まえた知識のアップデートが特に必要と考えられる教育内容 (2)日本の在留外国人施策 (4)日本語教育史 (5)言語政策 (13)ダイバーシティと社会的包摂 (18)異文化受容・適応 (21)日本語教育プログラムの理解と実践 (23)コースデザイン (25)教材分析・作成・開発 (26)評価法 (28)教育実習 (30)授業分析・自己点検能力 (31)目的・対象別日本語教育法 (32)異文化間教育 (33)異文化コミュニケーション (34)コミュニケーション教育 |
・目的対象別日本語学習者及び教育内容 ・6つの指導項目及び授業評価 ・授業改善方法 ・在留外国人概況(主な調査関連情報) ・入管法改正と日本語教育の関連 ・日本語教育史(令和4年現在まで) ・政府方針及び政策、文化審議会国語分科会報告等での日本語教育 ・CEFRと「日本語教育の参照枠」 ・Can doベースのカリキュラムデザイン ・Can doベースの教材分析 ・行動中心アプローチにおける評価(日本語教育プログラム評価) ・オンラインによる日本語教育のための理論 ・成果物や教育活動に伴う著作権等 |
90×10コマ程度(各コマで単元確認(10問程度)を実施) | 100問程度 |
出典: 「登録日本語教員の経験者講習について」文化庁を参考に筆者作成
なお、経過措置の詳細については、次の記事を参考にしてください。
■【現職向け】登録日本語教員の経過措置とは?6つのルートと講習内容を解説
登録日本語教員資格は取得したほうがいい?
現職で日本語教員をしている方も登録日本語教員資格を取得した方が良いでしょう。
また、日本語教育能力検定に合格している場合も、登録日本語教員資格を取得した方が良いと考えられます。
現時点では、経過措置が設けられているため、効率的に登録日本語教員資格が取得できるからです。
経過措置は時限的措置であるため、期間を過ぎた場合、通常ルートでの資格取得ルートしか取得する方法はなくなります。
登録日本語教員資格を取得するタイミングは個人の判断で決定すればよいでしょう。
しかし、認定日本語教育機関で教える日本語教師は全員、登録日本語教員の資格が必要となることから、現在認定日本語教育機関で働いている人、将来職場の選択肢を狭めたくない人は経過措置で免除のあるうちに合格したほうが良いといえます。
日本語教育能力検定試験・
日本語教員試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの日本語教育能力検定試験・
日本語教員試験講座を
無料体験してみませんか?

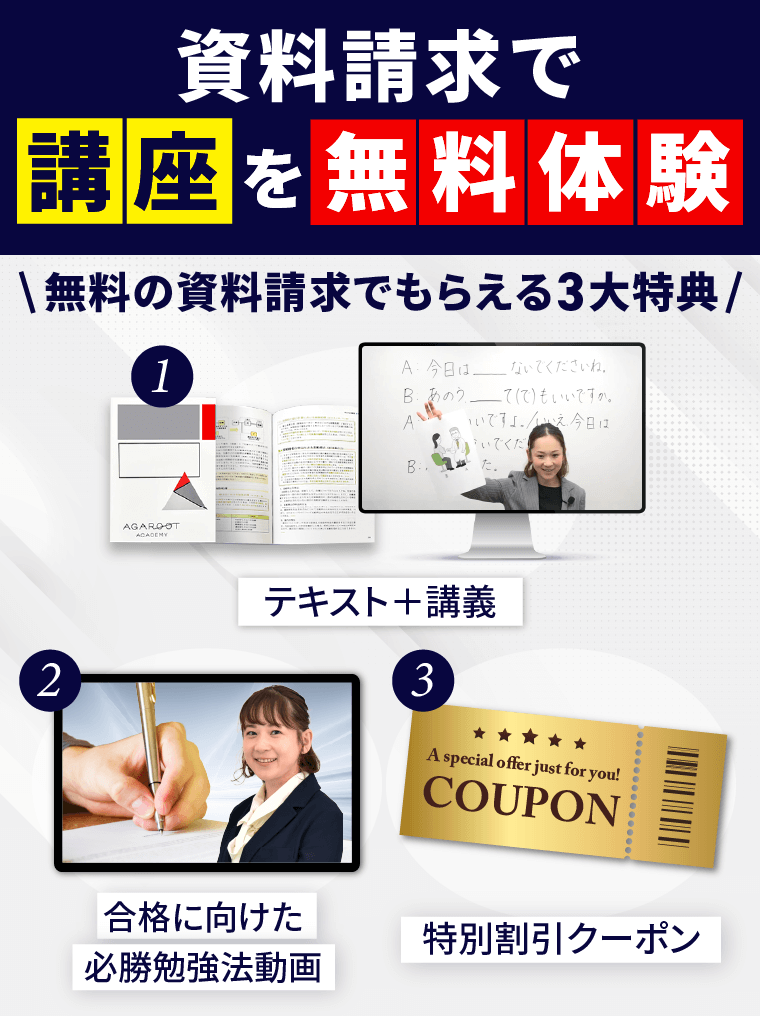
約3.5時間分の世界と日本、 異文化接触、言語教育法・実習講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!日本語教育能力検定試験・日本語教員試験対策のフルカラーテキスト
プロ講師が解説!合格に向けた必勝勉強法動画
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る


