教員の働き方改革は進んでいる?働き方改革が必要な理由と現状を解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

「教員の働き方改革って、実際どこまで進んでいるの?」と疑問をもっている方は多いのではないでしょうか。
教員の労働環境や時間外労働の実態は、かねてから社会問題とされてきました。
このコラムでは、教員の働き方改革の進捗状況を紹介し、なぜ改革が必要かを3つの理由から解説します。
さらに、各自治体で進む具体的な取り組みや改革が教育現場にもたらす変化についても触れていきます。
教員採用試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの教員採用試験講座を
無料体験してみませんか?

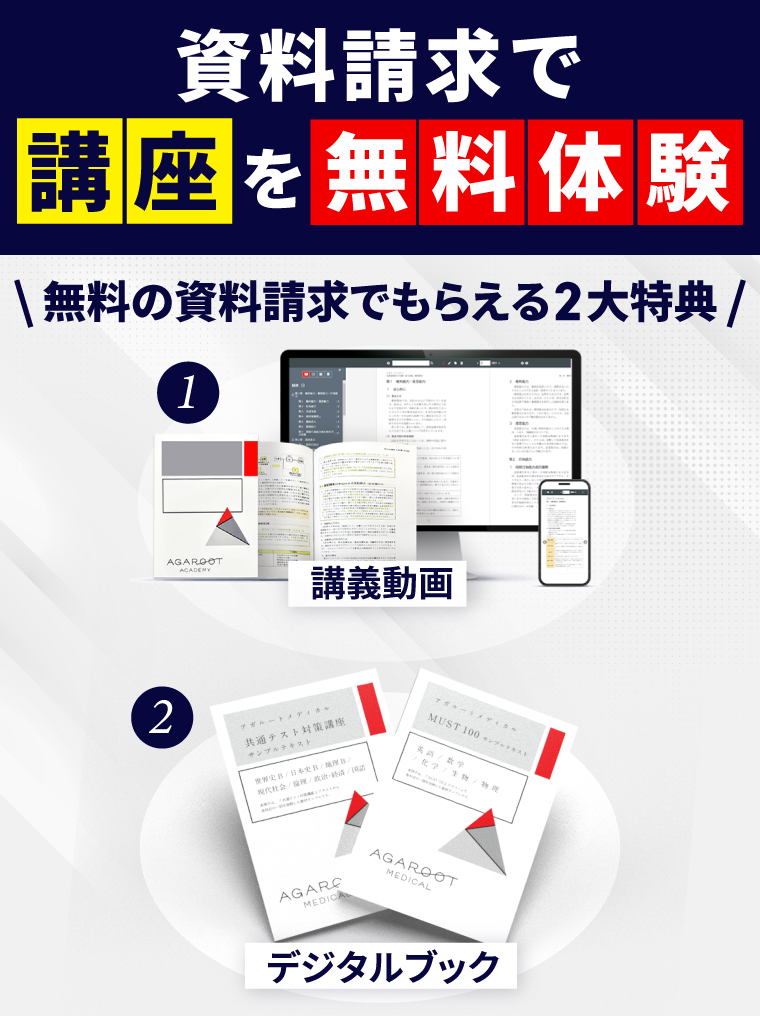
約2時間の教職教養西洋教育史講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!教員採用試験のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
教員の働き方改革は進んでいる?
結論からいえば、教員の働き方改革は進んでいるものの、依然として長時間労働等の問題は解決されていません。
以下の表は、文部科学省が公表した教員勤務実態調査(令和4年度)集計の平成28年(2016年)と令和4年(2022年)の教員の平均在校等時間をまとめたものです。
| 平成28年 | 令和4年 | 差 | ||
| 小学校 | 平日 | 11時間15分 | 10時間45分 | -30分 |
| 土日 | 1時間7分 | 36分 | -31分 | |
| 中学校 | 平日 | 11時間32分 | 11時間1分 | ‐31分 |
| 土日 | 3時間22分 | 2時間18分 | ‐1時間4分 | |
| 高校(参考値) | 平日 | – | 10時間6分 | – |
| 土日 | – | 2時間14分 | – |
データからわかるように、小学校・中学校の在校等時間は平日・休日共に減少。
しかし、小学校・中学校・高校ともに平日の在校等時間は10時間を超えており、依然として長時間労働の状態が続いています。
特に中学校・高校では休日の業務負担が2時間超のため、改善の余地があるでしょう。
ただ、改善されていることは事実といえます。
教員の働き方改革は強力に進められる
政府は「教師を取り巻く環境整備に関する合意」に基づき、働き方改革を強力に推進しています。
政府が合意した施策は以下の6つです。
- 教員調整額を令和12年までに10%に引き上げ
- 令和9年以降で、教職調整額の引き上げ方やメリハリ付け、そのほかのより有効な手段なども含めて検討・措置
- 学級担任の手当の増額、若手教員を支援等行う職の創設と処遇の実現、他学年学級担当手当の廃止など、給与体系の見直し
- 令和7年度(2025年度)に小学校の35人学級の推進や教科担任制の拡大、新人教師の支援体制強化などのため、教職員定数を5,827人増員し、令和8年度(2026年度)からは中学校の35人学級化も進める
- 教員の業務負担を削減するため「部活動の地域展開」「校務DXの推進」「長期休暇を取得しやすい環境整備」などを行い、教師の平均時間外在校等時間を月20時間程に縮減することを目指す(今後5年間で約3割削減、月30時間程とすることを目指す)
- 時間外在校時間が月20時間程になるまでに、給特法および教職調整額のあり方を幅広い観点から検討
上記のように政府は教員の給与体系の見直しや業務負担の削減を進めており、今後の改革の進展が期待されます。
合意内容をより詳しく知りたい方は、こちらのサイトを参照してください。
教員に働き方改革が必要な3つの理由
なぜ今、教員の働き方改革が求められているのでしょうか。
その背景には、次の3つの理由があります。
- 長時間労働の問題
- 部活動や指導など授業以外の負担
- 教員になりたい人が減少している
長時間労働の問題
教員の長時間労働は深刻な課題です。
授業準備や採点、会議、保護者対応など、授業以外の業務が多岐にわたることで、慢性的な時間不足に陥っています。
文部科学省「教員勤務実態調査(令和4年)」によると、月50時間以上働いている教員は、小学校で64.4%、中学校で77.2%。にのぼります。
また、過労死ラインとされる月80時間を超える教員は、小学校で0.2%、中学校で2%でした。
このように、多くの教員が長時間働いている現状は明らかです。
定時後も仕事が終わらないことがあたり前となっており、心身の健康や私生活への影響が懸念されています。
長時間労働が常態化することで、教育の質や教員自身のモチベーションの低下にも繋がりかねません。
部活動や指導など授業以外の負担
教員の業務には、授業や学級運営に加えて、部活動の指導や学校行事、校外活動の引率など、時間外の仕事が多く含まれます。
特に部活動の指導は、平日の放課後や土日にもおよび、休日出勤が常態化しているケースも珍しくありません。
これにより、教員が十分な休息を確保できないことは深刻な問題です。
近年は部活動の地域移行も進められていますが、現場の負担軽減には十分に効果が及んでいません。
授業以外の業務量が多すぎる現状では、本来注力すべき教育活動の質の低下が懸念されます。
教員になりたい人が減少している
教員採用試験の倍率は年々減少しています。
教員のなり手不足の要因のひとつとして、「教員が激務」というイメージが浸透してしまっていることがあげられます。
以下は、「教員採用試験の全国平均倍率の推移」を学校区分ごとグラフにしたものです。
「全体」
「小学校」
「中学校」
「高校」
「特別支援」
「養護教諭」
上記データのとおり、すべての学校区分で教員採用試験の倍率は年々下がっており、なり手不足が深刻化していることが明らかです。
全体の倍率で見ると、平成12年度は13.3倍あったものが、令和6年度には3.2倍にまで低下しました。
特に小学校では令和6年度の倍率は2.2倍と、最高値であった平成11年の12.9倍より大幅に低下。
また、中学校も最高値となった平成12年度は17.9倍でしたが、令和6年度には4倍となっています。
先述のとおり、「教員は激務である」というイメージが社会に定着したことが、志望者現象の一因と考えられます。
今後も教員の働き方を根本的に見直し、負担を軽減していかなければ、教育の担い手そのものが不足していくおそれがあるでしょう。
各自治体の働き方改革の取り組み
教員の長時間労働が社会問題となる中、各自治体では「働き方改革」の実現に向けたさまざまな取り組みが進行中です。
ここでは、ICT活用・教員業務支援員の導入・勤怠管理の工夫といった、具体的な事例を紹介します。
- ICTを導入して情報共有を円滑に
- 教員業務支援員の活躍で教員の負担軽減
- 勤怠管理アプリを使って在校等時間の管理
ICTを導入して情報共有を円滑に
文部科学省が公表した「全国の学校における働き方改革事例集」より、情報共有を手書きからデジタルに一新したことで、教員間のトラブルや共有が円滑になった事例を紹介しましょう。
兵庫県の篠山小学校では、ICTを活用した業務効率化が進められています。
職員室と各教室の情報共有に課題を抱えていましたが、Google Workspace for Educationの導入によって、教員同士の連携を改善。
従来は職員室で受けた保護者からの連絡をインターフォンで教室に伝えていましたが、Googleチャットの活用により、学級指導中の中断が減り、教員は自動と向き合う時間を確保できるようになりました。
また、Googleカレンダーでスケジュールや教室利用の管理もデジタル化。
手書き管理によるダブルブッキングなどのトラブルも減少し、教職員間の業務共有がスムーズになりました。
教員業務支援員の活用で教員の負担軽減
「全国の学校における働き方改革事例集」には、教員とは別に「教員業務支援員」の派遣を受け、教員の負担を軽減している事例があります。
千葉県千葉市立加曽利中学校では、「教員業務支援員(旧:スクール・サポート・スタッフ)」を受け、教員の負担軽減を実現しました。
教員業務支援員は教材印刷・資料の仕分け・データ入力・掲示物の管理・消毒作業など、幅広い業務を担うことで、教員が児童生徒への指導や教材研究に専念できる環境つくりをサポートします。
学校ごとに教員業務支援員の派遣日数は異なりますが、加曽利中学校では週4日勤務の教員業務支援員が常駐。
校長によると「気持ちよく業務 サポートをお願いできるので、本校の教職員も積極的に業務を依頼しています」とのこと。
千葉市教育委員会は、教員業務支援員への具体的な業務例を提示し、教員業務支援員の効果的な活用を各校に促しています。
勤怠管理アプリを使って在校等時間の管理
茨城県県南教育事務所が公表した「令和3年度 学校の働き方改革に関する良好事例集」では、勤怠アプリを使った在校等時間の管理の事例を紹介しています。
ある自治体では、タイムカードに加えて、勤怠管理アプリを導入することで、教職員の在校時間を「見える化」。
これにより、各教職員が自分の超過勤務時間を日々確認できるようになり、意識改革が促進されました。
月末集計だけではなく、日常的に勤務時間を意識することで、時間外勤務の平均時間も減少傾向にあります。
また、超過勤務時間が長い職員が特定できるため、40時間を超えた時点で該当職員に個別面談を実施。
早期の対策を講じることで、超過勤務時間の減少につなげています。
教員の働き方改革はいい方向へ進んでいる
教員の長時間労働や業務の多さは依然として課題ですが、各自治体では着実に働き方改革が進みつつあります。
ICTの導入による業務効率化や、教員業務支援員の活用、勤怠管理アプリによる在校時間等の見える化など、現場では具体的な改善策が実行中です。
さらに、文部科学省も制度面から改革を後押ししていることで、国・自治体・学校が一体となって取り組む姿勢が見られるようになりました。
短期間で改善することは厳しいものの「変わろうとしている動き」は確実に広がっているといえます。
今後もこうした取り組みが全国に波及していけば、教員がより安心して働ける環境が整っていくでしょう。
まとめ
教員の働き方改革は徐々に進んでいて、在校等時間は減少傾向にありますが、依然として10時間超の長時間労働が続いています。
こうした状況を受けて、政府は教員の給与体系見直しや部活動の地域移行、校務のDX推進など、制度面・運用面の両面から改革を推進中です。
また、各自治体でもICTの活用による情報共有の効率化、勤怠管理アプリの導入など、具体的な改善策が実行されています。
現場と制度の両面で教員の働き方改革は前進しており、より一層の労働環境の改善が期待できるでしょう。
教員採用試験の合格を
目指している方へ
- 教員採用試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの教員採用試験講座を
無料体験してみませんか?

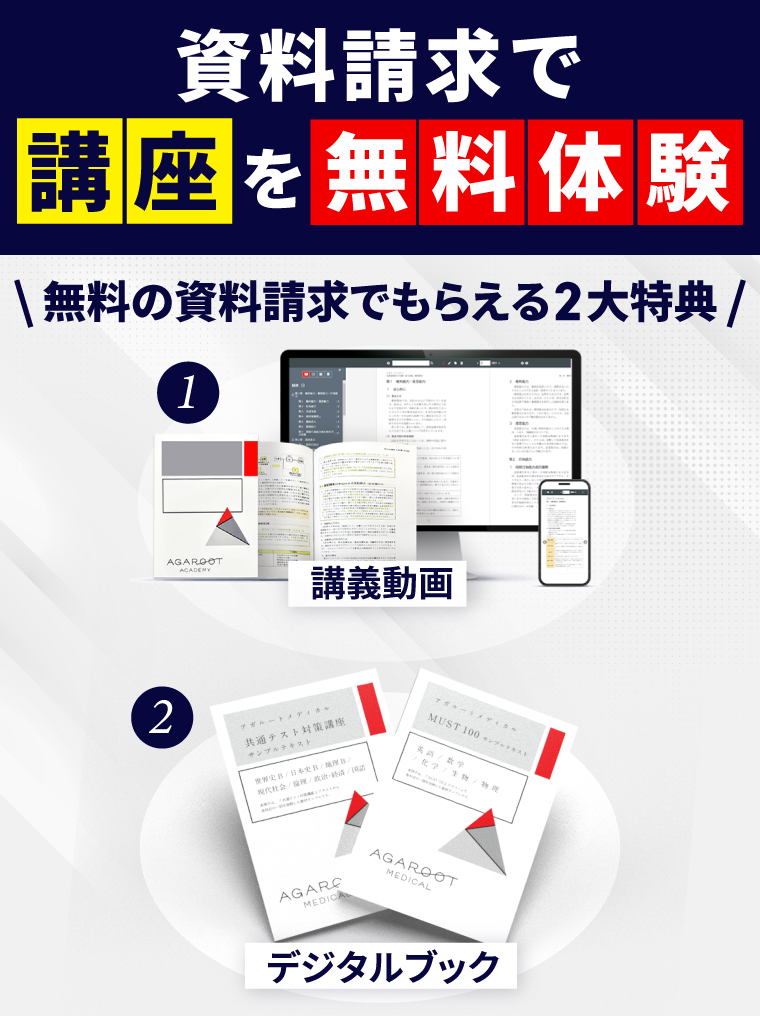
約2時間の教職教養西洋教育史講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!教員採用試験のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る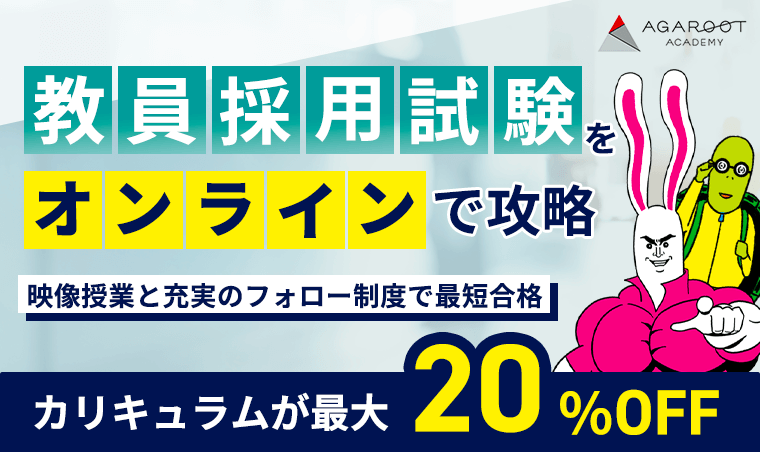
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金・全額返金など内定特典付き!
▶教員採用試験講座を見る



