教員に向いてる人とは?5つの特徴と必要な力・求められる力について解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

教員という職業に興味があるけれど「そもそも自分は教員に向いているのだろうか?」と不安を感じる方も多いでしょう。
本コラムでは、教員に向いている人の特徴5選、反対に向いていない人の特徴3選を取り上げます。
また、教員として求められる具体的な力やスキルについても詳しく解説します。
教育現場で必要とされる力を理解することで、自身の適性を見極めるヒントが得られるでしょう。
教員への道を目指す方や迷っている方にとって、進路選びの参考になる内容をお届けします。
教員採用試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの教員採用試験講座を
無料体験してみませんか?

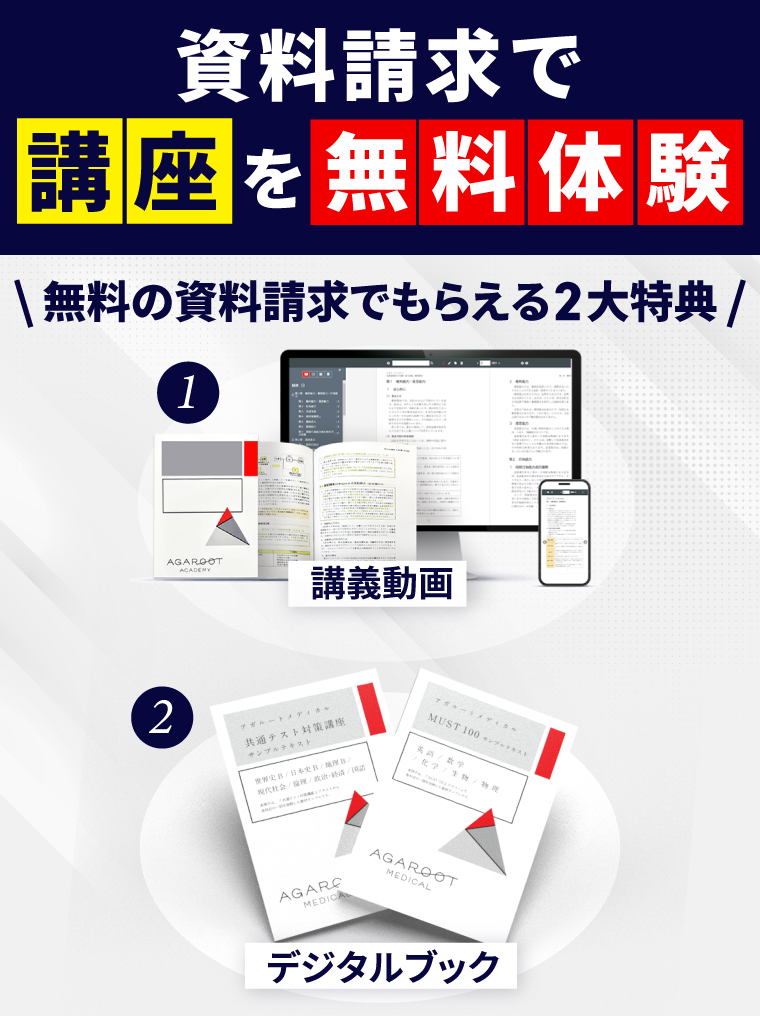
約2時間の教職教養西洋教育史講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!教員採用試験のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
教員が向いている人の特徴5選
教員が向いている人の特徴は次の5つです。
- 子どもが好き
- 人に教えるのが好き
- 臨機応変な対応ができる
- コミュニケーション能力が高い
- 話を聞くのが上手
それぞれの特徴について解説していきましょう。
子どもが好き
教員の仕事は、子どもたちと一緒に過ごす時間が多くを占めます。
授業だけではなく、休み時間や行事、さらには放課後の活動など、さまざまな場面で子どもたちと向き合う必要があります。
そのため、子どもが好きであることは教員にとって何よりも重要な資質のひとつです。
子どもたちは個性豊かで、同じ接し方がすべての子どもに当てはまるわけではありません。
時には問題行動をとる子どもや、感情を素直に表現できない子どもとも接する場面があるでしょう。
そうした中で、子どもの成長を見守り、少しずつ心を通わせていく姿勢が求められます。
子どもと過ごすことにやりがいや喜びを感じられる人は、教員としての適性が高いと言えます。
人に教えるのが好き
教員の主な仕事は「教えること」です。
しかし、教える対象は学問だけにとどまりません。
授業以外にも、人間関係の築き方や生活習慣の指導、部活動の指導など、教える場面は多岐にわたります。
そのため、「教えること」に楽しさを感じられる人は、教員に向いていると言えるでしょう。
特に、相手が理解するまで粘り強く教える姿勢は、教員にとって欠かせない資質です。
子どもたちはひとり一人異なるペースで学びます。
その違いを受け入れながら、個別にサポートしていく姿勢が必要です。
人の成長を見守り、それを支えることに喜びを感じられる人は、教員という職業に適しています。
臨機応変な対応ができる
臨機応変に対応できる人は、教育現場での問題解決能力が高く、信頼される教員になりやすいと言えます。
教育現場では、予定通りに物事が進むとは限りません。
授業中に子どもたちが突然騒ぎ出したり、思わぬトラブルが起きたりすることも日常茶飯事です。
また、子どもたちが指示通りに行動するとは限らないため、柔軟な対応力が求められます。
例えば、授業中に急に子どもたちが集中力を失った場合、予定していた内容を変更し、ゲームやディスカッション形式に切り替えるなどの工夫が求められることがあります。
また、トラブルが起きた際には、状況を冷静に把握しながら、適切な対応を迅速に取ることが重要です。
こうした対応力は、経験を積むことで身につけられる部分もありますが、元々柔軟な思考をもっている人や、変化を前向きに受け入れられる人には特に向いている職業です。
どんな場面でも落ち着いて対応できる姿勢は、子どもたちや保護者からの信頼を築く基盤となります。
コミュニケーション能力が高い
コミュニケーション能力が高い人は、教育現場で多様な人々と信頼関係を築き、スムーズな業務遂行を可能にするでしょう。
教員は子どもたちだけではなく、同僚や保護者、地域の人々など、多くの人々とかかわりながら仕事を進めます。
そのため、高いコミュニケーション能力を求められます。
例えば、子どもたちに対しては、難しい内容をわかりやすく説明する力や、子ども一人ひとりに適した声かけが必要です。
また、保護者との面談では、子どもの学習状況や生活態度を正確に伝え、相手の不安を解消することが重要になります。
同僚や管理職との連携も不可欠であり、情報共有や意見交換を円滑に行う能力が求められます。
特に、相手の気持ちを汲み取りながら話を進める力がある人は、教員として高く評価されるでしょう。
話を聞くのが上手
子どもたちや保護者からの相談に乗る機会が多い教員には「話を聞く力」も非常に重要な資質です。
特に、子どもたちは日常生活や人間関係の中で、大人が思う以上に多くの悩みを抱えています。
それらを丁寧に聞き取り、必要に応じて適切なアドバイスを行うことが、子どもたちとの信頼関係を深める鍵となります。
例えば、友人関係で悩んでいる子どもがいた場合、まずは相手の話をじっくり聞き、感情に共感することが大切です。
そのうえで、冷静に解決策を示し、前向きな行動を促す姿勢が求められます。
保護者に対しても同様に、不安や悩みに寄り添いながら信頼を築く力が必要です。
話を聞くことが得意な人は、相手が言葉にしづらい気持ちを汲み取りやすく、適切なサポートを提供できます。
このスキルは、子どもたちだけではなく、保護者や同僚とも良好な関係を築くために欠かせないものです。
教員には向いていない人の特徴3選
教員に向いていない人の特徴は次の3つです。
- 人に教えるのが苦手な人
- 柔軟性がない人
- コミュニケーションが苦手な人
それぞれに特徴について解説します。
人に教えるのが苦手な人
教員の主な仕事は、子どもたちに学問やスキルを教えることです。
そのため、人に何かを教えることが苦手な人にとっては、教員という職業は大きな負担となりかねません。
教える内容は、教科書に書かれた知識だけではありません。
授業の中で、子どもたちに理解しやすいように工夫しながら伝えることや、日常生活でのルールやマナー、部活動での技術指導など、幅広い指導が求められます。
教えるという行為には、相手の反応を見ながら適切な方法を模索する力や、根気強く繰り返し伝える忍耐力が必要です。
しかし、人に教えることに苦手意識をもつ人は、これらの対応にストレスを感じることが多いでしょう。
また、教える側が楽しめないと、その感情が子どもたちにも伝わり、学ぶ意欲を下げてしまう可能性もあります。
そのため、「人に教えることが好き」という気持ちがもてない場合、教員という職業は向いていないと言えます。
柔軟性がない人
教員の仕事は日々同じ業務を繰り返すわけではありません。
急なトラブルや予定外の出来事が発生することが日常です。
例えば、授業中に子どもが体調を崩したり、予想外の質問を投げかけられたりすることもあります。
また、学校行事や保護者対応など、計画通りに進まない場面も多々あるでしょう。
このような状況に対して、臨機応変に対応できない人は教員に向いていません。
柔軟性がない場合、突発的な問題に直面した際にストレスを感じやすくなります。
また、自分の計画が乱された時に感情的になってしまうと、子どもたちや周囲の大人との信頼関係にも影響を及ぼすかもしれません。
教育現場では、予測不能な状況を前向きにとらえ、冷静に対応する力が必要です。
そのため、固定概念にとらわれがちで変化を嫌う性格の人にとっては、教員として働くことが困難となるでしょう。
コミュニケーションが苦手な人
教員は子どもたちと接するだけではなく、保護者や同僚、地域の人々ともかかわる機会が多い職業です。
そのため、コミュニケーション能力が低い人にとっては、教員としての職務を遂行することが難しい場合があります。
例えば、子どもたちに授業内容をわかりやすく伝えることや、保護者に子どもの成績や学校生活の状況を報告することは、教員にとって重要な役割のひとつです。
また、同僚や管理職との情報共有や連携も欠かせません。
コミュニケーションが苦手な場合、これらの場面でのやりとりがぎこちなくなり、誤解を生む原因となることがあります。
特に子どもたちは教員のことばや態度に敏感に反応します。
コミュニケーションが円滑でないと、子どもたちが話しづらさを感じたり、信頼関係を築けなかったりする可能性があります。
教員として、相手の立場に立って話をする力や、共感しながらコミュニケーションをとるスキルは欠かせません。
そのため、人との交流が苦手な人には教員の職務は難しいと考えられます。
教員に必要な力と求められる力とは?
教員に必要な力と求められる力として以下の3つがあげられます。
- 教員に対する強い情熱
- 教育の専門的な知識
- 総合的な人間力
教員は、子どもたちの成長を支える重要な役割を担う職業です。
そのため、単に教科知識をもつだけではなく、さまざまな力が求められます。
教員に対する強い情熱
教員として働くうえで最も重要なことは、教育に対する強い情熱です。
教員は単なる知識の伝達者ではなく、子どもたちの未来を支える存在。
そのため、教員という職業に対する使命感や誇りをもつことが大切です。
また、子ども一人ひとりに愛情を注ぎ、彼らの成長を見守る責任感も欠かせません。
時には困難な状況に直面することもありますが、そうした場面を乗り越える原動力となるのが、この情熱です。
情熱がある教員は、子どもたちにもポジティブな影響を与え、信頼される存在となります。
教育の専門的な知識
教員には、教育に関する幅広い専門知識が求められます。
具体的には、子どもの発達段階や理解力を考慮した授業設計、生活指導や集団指導のスキルです。
これらの知識は、教科書に書かれた内容をそのまま伝えるだけでなく、子どもたちが実際に学び、成長できるように活用されます。
さらに、問題を抱える子どもやクラス全体の雰囲気を適切に把握し、その場に合った対応をとる力も必要です。
このような専門的な知識は、教員としての仕事をスムーズに進めるだけでなく、子どもたちの信頼を得るためにも欠かせません。
総合的な人間力
社会性や礼儀作法、人間性を兼ね備えた総合的な人間力が求められるでしょう。
教員は子どもたちのロールモデルとしての役割も果たします。
教員が規範となることで、子どもたちは社会で必要なマナーや倫理観を学べます。
また、保護者や同僚との円滑なコミュニケーションや信頼関係の構築にも人間力が必要です。
特に教育現場では、教科書に書かれた知識以上に、教員自身の人間性が子どもたちに影響を与える場面が多々あります。
信頼される教員であるためには、この力を磨き続ける努力が必要です。
参考:1.これからの社会と教員に求められる資質能力:文部科学省
まとめ
以上、教員に向いている人の特徴5選と向いていない人の特徴3選を解説し、教員に必要な力・求められる力を整理しました。
教員に向いている人の特徴は以下の5つ。
- 子どもが好き
- 人に教えることが好き
- 臨機応変に対応できる
- コミュニケーション能力が高い
- 話を聞くことが得意
一方、教員に向いていない人の特徴は次の3つ。
- 人に教えることが苦手
- 柔軟性がない(臨機応変な対応が苦手)
- コミュニケーションが苦手
そして、教員に必要な力と求められる力として次の3つがあげられます。
- 教育への強い情熱
- 教育の専門知識
- 総合的な人間力
教員には職業への情熱はもちろん、臨機応変に対応する力や他者との関係構築力が必要不可欠です。
この記事が、ご自身の適性を見極めるお役に立てれば幸いです。
教員採用試験の合格を
目指している方へ
- 教員採用試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの教員採用試験講座を
無料体験してみませんか?

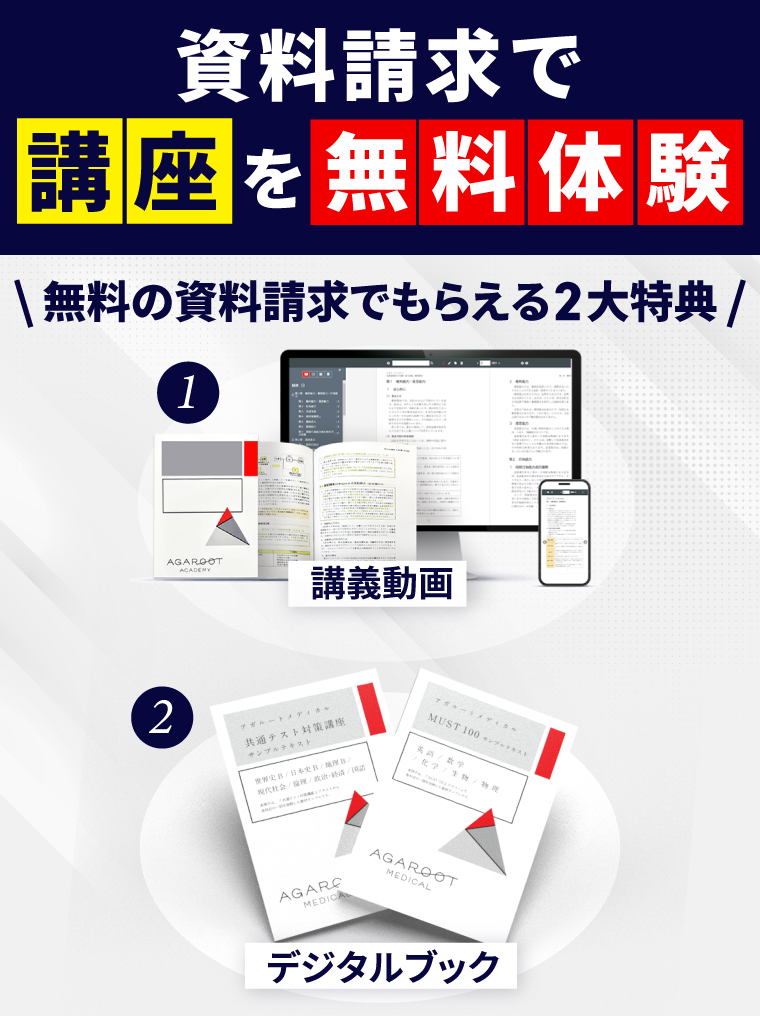
約2時間の教職教養西洋教育史講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!教員採用試験のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る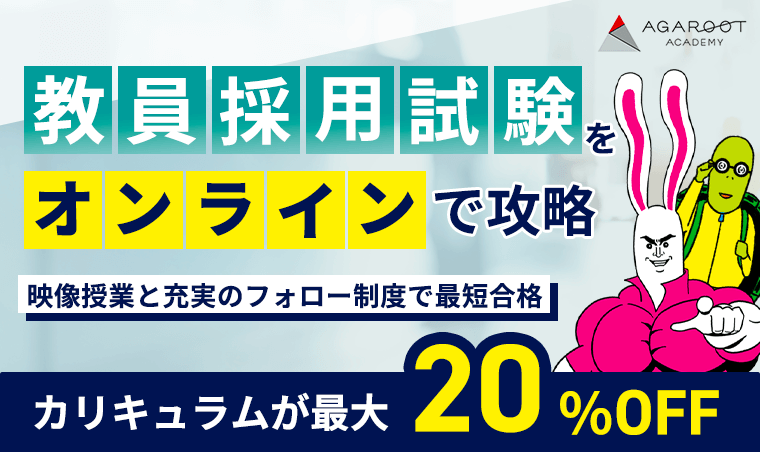
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金・全額返金など内定特典付き!
▶教員採用試験講座を見る

