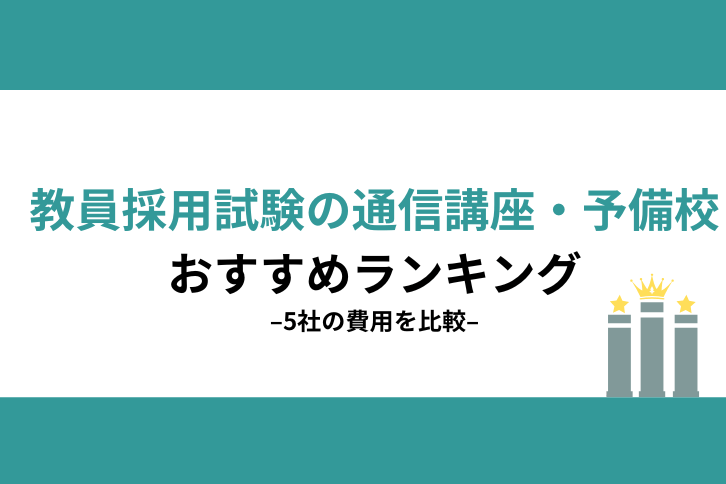英語教員の難易度は高い?必要な英語レベルと勉強法について徹底解
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

英語教員を目指す皆さんの中には、教員採用試験の英語の難易度や必要な英語レベルについて、不安や疑問がある方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、英語教員になるための難易度を教員採用試験の倍率を基に、詳しく解説します。
また、英語教員に必要な英語力や、教員採用試験で求められる英語のレベルについても具体的に説明。
さらに、試験合格を目指すための効果的な勉強方法3選と、教員採用試験の英語が効率的に学べる通信講座についても触れています。
英語教員を目指すすべての方に役立つ情報を、わかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
英語教員になるための難易度は高い?倍率から考察
結論、英語教員は他の教科と比較して、特別難しいわけではありません。
以下は、文部科学省の公立学校教員採用選考より、令和3年(2021年)〜令和5年(2023年)の教員採用選考の各教科の平均倍率をまとめた表です。
・中学校
| 教科 | 倍率 |
| 社会 | 6.1 |
| 国語 | 3.2 |
| 数学 | 4.1 |
| 理科 | 3.1 |
| 英語 | 3.5 |
・高校
| 教科 | 倍率 |
| 英語 | 3.3 |
| 公民 | 8.8 |
| 地理歴史 | 6.7 |
| 国語 | 3.8 |
| 数学 | 6.5 |
| 理科 | 6.1 |
令和3年~令和5年の英語の平均倍率を見ると、中学校は3.5倍、高校は3.3倍となっています。
これを他の教科と比較すると、中学校の英語(3.5倍)は社会(6.1倍)や数学(4.1倍)よりも低く、理科(3.1倍)や国語(3.2倍)と似たような倍率です。
また、高校の英語(3.3倍)も、公民(8.8倍)や地理歴史(6.7倍)に比べると、かなり低い倍率となっており、特別に高い競争率ではないことがわかります。
教員採用試験の英語は、他の教科と比べて過度に難易度が高いわけではなく、他の高倍率の教科に比べると挑戦しやすいと言えるでしょう。
ただし、上記はあくまで全国平均の倍率であり、自治体によって倍率は異なります。
地域によっては、英語の倍率が平均倍率よりも、かなり高くなることもあるのでご注意ください。
各自治体の英語教員の倍率一覧
教員採用試験の英語教員の倍率は、自治体によって大きく異なり、難易度に地域差があります。
ここでは、文部科学省公表の令和5年度公立学校教員採用選考試験の実施状況のデータに基づき、中学校と高等学校それぞれの「各自治体の英語教員の採用倍率」について分析します。
下表は、令和5年(2023年)の教員採用試験における、47都道府県の中学、高等学校の英語教員の採用倍率一覧です。
| 都道府県 | 中学 | 高校 |
| 北海道 | 5.4 | 1.7 |
| 青森県 | 3.9 | 10.5 |
| 岩手県 | 4.1 | 4 |
| 宮城県 | – | 3.3 |
| 秋田県 | 1.9 | 6.7 |
| 山形県 | 1.9 | 5 |
| 福島県 | 4 | 9 |
| 茨城県 | 4.3 | 3 |
| 栃木県 | 4.5 | 3.4 |
| 群馬県 | 2.9 | 4.4 |
| 埼玉県 | 2.1 | 2.3 |
| 千葉県 | 5 | – |
| 東京都 | 3.7 | – |
| 神奈川県 | 3.4 | 2.5 |
| 新潟県 | 2.2 | – |
| 富山県 | – | – |
| 石川県 | – | – |
| 福井県 | – | – |
| 山梨県 | – | 6.5 |
| 長野県 | 3 | 2.1 |
| 岐阜県 | 2.3 | 3.4 |
| 静岡県 | 3.1 | 3.8 |
| 愛知県 | 2.6 | 2.6 |
| 三重県 | 5.9 | 3 |
| 滋賀県 | 4.7 | 2.9 |
| 京都府 | 4.2 | 3.3 |
| 大阪府 | 3.8 | 5 |
| 兵庫県 | 2.5 | 3 |
| 奈良県 | 2.9 | 3.5 |
| 和歌山県 | 4.6 | 7.3 |
| 鳥取県 | – | 11 |
| 島根県 | 3.1 | 12 |
| 岡山県 | 4.6 | 5.4 |
| 広島県 | 6.2 | 4.8 |
| 山口県 | 1.6 | 3.9 |
| 徳島県 | 3.3 | 6 |
| 香川県 | 4.8 | 4.8 |
| 愛媛県 | 2.7 | 2.3 |
| 高知県 | 7.1 | 32 |
| 福岡県 | 1.3 | 6.1 |
| 佐賀県 | 0.9 | 4 |
| 長崎県 | 2.4 | 1.4 |
| 熊本県 | 2.1 | 5.1 |
| 大分県 | 1.6 | 7.8 |
| 宮崎県 | 5.5 | 3.5 |
| 鹿児島県 | 2.3 | 6.3 |
| 沖縄県 | 10.1 | 12.5 |
※福井県は「英語」を中学校と高等学校の試験区分を分けずに、中高一括で選考を行っています。
中学校・英語教員の倍率が高い上位5県は、沖縄県(10.1倍)、高知県(7.1倍)、広島県(6.2倍)、三重県(5.9倍)、宮崎県(5.5倍)です。
また、倍率の低い上位5県は、佐賀県(0.9倍)、福岡県(1.3倍)、山口県(1.6倍)、秋田県・山形県(1.9倍)となります。
高等学校・英語教員の倍率が高い上位5県は、高知県(32倍)、沖縄県(12.5倍)、鳥取県(11倍)、島根県(12倍)、青森県(10.5倍)です。
また、倍率の低い上位5県は、長崎県(1.4倍)、北海道(1.7倍)、埼玉県・愛媛県(2.3倍)、神奈川県2.5倍となっています。
中学校と比較すると、全体的に倍率が高く、難易度が高いと言える結果になりました。
高等学校・英語教員の倍率は、高知県が32倍と圧倒的に高く、競争が激しいことがうかがえます。
逆に、長崎県や北海道では倍率が2倍以下となっていて、比較的合格の可能性が高いと言えるでしょう。
英語教員の採用倍率は、地域の求人数、応募者数、人口や教育機関の数などに左右されます。
特に沖縄県と高知県は、中学校・高等学校の両方で倍率が高く、人気が集中する地域です。
倍率が高い地域では十分な準備と高い競争力が求められるでしょう。
英語教員を目指す方は、地域ごとの倍率も考慮しながら、目標とする自治体の試験に向けて計画的に学習を進めることが大切です。
英語教員になるためにはどのぐらいの英語レベルが必要?
英語教員になるためには、少なくとも英検準1級レベル、CEFR B2レベル相当以上の英語力があると安心です。
文部科学省が公表した令和5年度「英語教育実施状況調査」概要の「英語担当教師の英語力(都道府県・指定都市別)」によると、CEFR B2レベル相当以上の資格を取得している英語担当教師の割合は、中学校で平均44.8%、高等学校では80.7%でした。
CEFR B2レベル相当以上の資格を取得している英語担当教師の割合が、平均値を超える自治体も数多く報告されています。
中学校では、東京都、福井県、新潟県、富山県、石川県、静岡県、滋賀県、京都府、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、沖縄県、札幌市、埼玉市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、静岡市、名古屋市、京都市、神戸市、広島市が、令和5年度平均値(44.8%)を上回っていました。
高等学校で、令和5年度平均値(80.7%)を超えているのは、青森県、山形県、茨城県、東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県でした。
このように、英語担当教師の英語力は、中学校・高等学校ともに、自治体間の差が見られることがわかります。
さらに、英語教員には授業の発話の半分以上を英語で行えるレベルの英語力も必要です。
令和5年度「英語教育実施状況調査」概要の「英語担当教師の英語使用状況(中学校・高等学校) 」によると、中学校では、約7割の学校で英語担当教師が「発話の半分以上を英語で行っている」一方で、高等学校では約4割の学校にとどまります。
ただし、英語教育を主とする学科及び国際関係に関する学科では、約7割の学校で英語担当教師が発話の半分以上を英語で行っており、積極的な英語使用が見られます。
英語教員になるためには?
英語教員になるためには、教員免許の取得と教員採用試験に合格することが必須です。
英語教員になるための流れについて、以下の項目に分けて解説をします。
- 教員免許を取得する
- 教員採用試験に合格する
教員免許を取得する
英語の先生として教壇に立つためには、中学・高校それぞれの英語の教員免許を取得する必要があります。
一般的には、大学や短大で規定の教職課程を履修し、教育実習や介護体験などを経て免許を取得します。
外国語系の学部学科や、教育学部の英語教育専攻を選ぶと、英語教育に特化した学びができるため、効率良く免許を取得することが可能です。
特に、教育学部の英語教育専攻は、教えるための英語スキルも磨ける上、教員志望のクラスメイトと高いモチベーションで学べる点が魅力的です。
教員免許には、「専修」、「一種」、「二種」の3つの種類があります。
専修免許は大学院で修士号を取得した人が対象で、最高位の資格ですが、一般的には「一種免許」を取得するのが主流です。
一種免許は、4年制大学を卒業すれば取得可能で、高校の英語教員としても働くことができます。
一方、二種免許は短大卒業で取得できますが、高校の英語教員にはなれません。
高校の英語教員を目指すなら、必ず4年制大学を選びましょう。
教員採用試験に合格する
教員免許を取得後、実際に英語教員として働くには、教員採用試験に合格する必要があります。
この試験は、都道府県や政令指定都市の教育委員会が実施しており、公立の小学校・中学校・高等学校の教員を採用するための選考試験です。
ただし、教員採用試験合格後、すぐに教員として働けるわけではありません。
合格すると、各自治体の教員採用候補者名簿に名前が登録され、その年の採用人数に合わせて選ばれた場合に採用されます。
この名簿には成績順で記載されるため、選ばれる順番が回ってこないこともあります。
教員採用試験の受験資格は、教員免許を持っているか、または、教員免許取得予定者であることが条件です。
また、自治体によっては年齢制限が設けられており、一定年齢以上になると受験できない場合もあります。
教員採用試験の内容には、一般的に以下のような試験が含まれます。
- 筆記試験(教職教養試験、一般教養試験、専門教養試験)
- 論文試験
- 面接試験
- 実技試験(音楽、美術、体育、英語など)
英語教員を目指す場合、専門教養試験では英語に関する専門的な知識や指導方法が問われます。
論文試験では、教育に関するテーマが出題され、1時間の制限時間の間に約600〜2000字の小論文を作成。
面接試験では教育に対する姿勢や指導力が評価されるでしょう。
また、実技試験では英語のスピーキングやディスカッション能力を問われることもあります。
教員採用試験の日程は、自治体ごとに異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。
- 試験日:6~9月
- 出願:3月下旬〜4月
- 一次試験:6~7月
- 二次試験:8~9月
- 合格発表:9月下旬〜10月
試験日程は、自治体によって違うので、希望する地域の詳細な日程は事前に確認しておきましょう。
教員採用試験の難易度は高く、令和5年度教員採用試験の採用倍率は小学校が2.3倍、中学校が4.3倍、高校が4.9倍となっています。
厳しい競争を勝ち抜くためには、志望先に合わせた入念な準備が必要です。
教員採用試験の英語の勉強方法3選
効率的に英語力を向上させ、教員採用試験を突破するための勉強方法を3つ紹介します。
以下が「教員採用試験の英語の勉強方法3選」となります。
- 各自治体の出題傾向と過去問を解く
- 英検やTOEICなどの資格を取得する
- 目標やスケジュールを明確にする
それぞれの勉強方法を詳しく解説していきます。
各自治体の出題傾向と過去問を解く
教員採用試験は、自治体ごとに出題傾向が異なります。
そのため、まずは受験予定の自治体が、どのような問題を出題しているのかを把握することが重要です。
出題形式や重点を置くべきポイントを理解するには、過去問を解くことが非常に効果的。
過去問を繰り返し解くことで、実際に出題された内容に触れ、試験の傾向や形式に慣れることができます。
また、自分の弱点が洗い出されることで、どの分野に時間をかけるべきかを明確にすることができるでしょう。
文法、語彙、リスニング、ライティングなどの各分野の、自治体ごとの傾向を確認し、適切な対策を行うことが合格への近道となります。
英検やTOEICなどの資格を取得する
英語力を高めるために、英検やTOEIC等の資格を取得することも効果的です。
これらの資格を目指して勉強することで、教員採用試験で求められる語彙力や文法力、リスニング力などを総合的に鍛えることができるからです。
英検1級やTOEIC900点以上のような、上位レベルの資格を持っていることは、面接の際に強力なアピール材料になります。
確かな英語力を証明でき、面接官に対して信頼感を与えることができるでしょう。
目標やスケジュールを明確にする
英語力を高めるには、明確な目標設定とその達成のための具体的なスケジュールが不可欠です。
試験までの期間を逆算し、いつまでにどのレベルに到達するのかを明確にすることで、効率的に勉強が進められます。
例えば、英検1級レベルの英語力を身につけることを目標にする場合、まずは自分の現状の英語力を把握し、そのレベルに到達するためにどのような学習が必要かを分析しましょう。
その後、毎月、毎週、毎日の目標を設定し、具体的な勉強内容を決めます。
まずは、
「〇月までに英検1級レベルまでいく(取得する)」
「〇月には過去問で満点がとれるようにする」
などの大きな目標を立てると良いでしょう。
そして、その目標を達成するために、必要な学習内容を考えます。
長期で取り組むべき、日々の小さな目標を立てましょう。
「語彙力を強化するために、毎日30分単語帳を使った復習する」
「リスニング力を鍛えるために、起床後15分間、通信講座やアプリを使ってリスニング練習をする」
といった形で、ルーチン化する学習内容を具体的に決めます。
教員採用試験の英語の勉強は、長期間の努力が必要なため、モチベーション維持も大切です。
教員採用試験の英語を効率よく学ぶなら通信講座も検討!
教員採用試験の英語を効率よく学ぶなら、通信講座の利用も非常に有効です。
特に、アガルートの教員採用試験対策講座は、効率的に英語やその他の教科の試験範囲を学べるカリキュラムを提供しており、初学者、受験経験者問わずおすすめです。
このカリキュラムは、1次試験の教職教養や一般教養の範囲を徹底分析し、重要な項目を効果的に学習できるため、短時間で試験対策を進めたい方にも最適です。
また、模擬授業や面接など、2次試験の人物試験対策も強化しており、採点官が見るポイントと高評価を得るための言動を詳しく解説します。
なお、オフィスアワーでは、受験する自治体の試験内容に合わせて、2次試験対策を自由にカスタマイズできます。
志望先に応じたオンライン個別指導が受けられるため、確実に実力をアップさせることができます。
まとめ
以上、教員採用試験の英語の倍率を基に英語教員の難易度を考察し、各地域の倍率差や求められる英語力について解説してまいりました。
教員採用試験の英語の令和3年(2021年)〜令和5年(2023年)の平均倍率は、中学校が3.5倍、高等学校が3.3倍となっていて、他の教科と比べて特別難易度が高いわけではありません。
英語教員に必要な英語力としては、中学・高等学校共に英検準1級、CEFR B2レベル相当以上が求められます。
さらに、授業中の発話の半分以上を英語で行える指導スキルも必要です。
試験範囲が広く、長期間の勉強が必須となる教員採用試験の対策は、通信講座を利用して効率的に行うと良いでしょう。
特におすすめなのは、アガルートの教員採用試験対策講座です。
充実した教材と講師のフォロー体制が特徴で、初受験、再受験どちらの方も最短ルートで合格を目指せます。
志望自治体に合わせた模擬試験を自由にカスタマイズできるオフィスアワーで、2次試験対策も万全です。