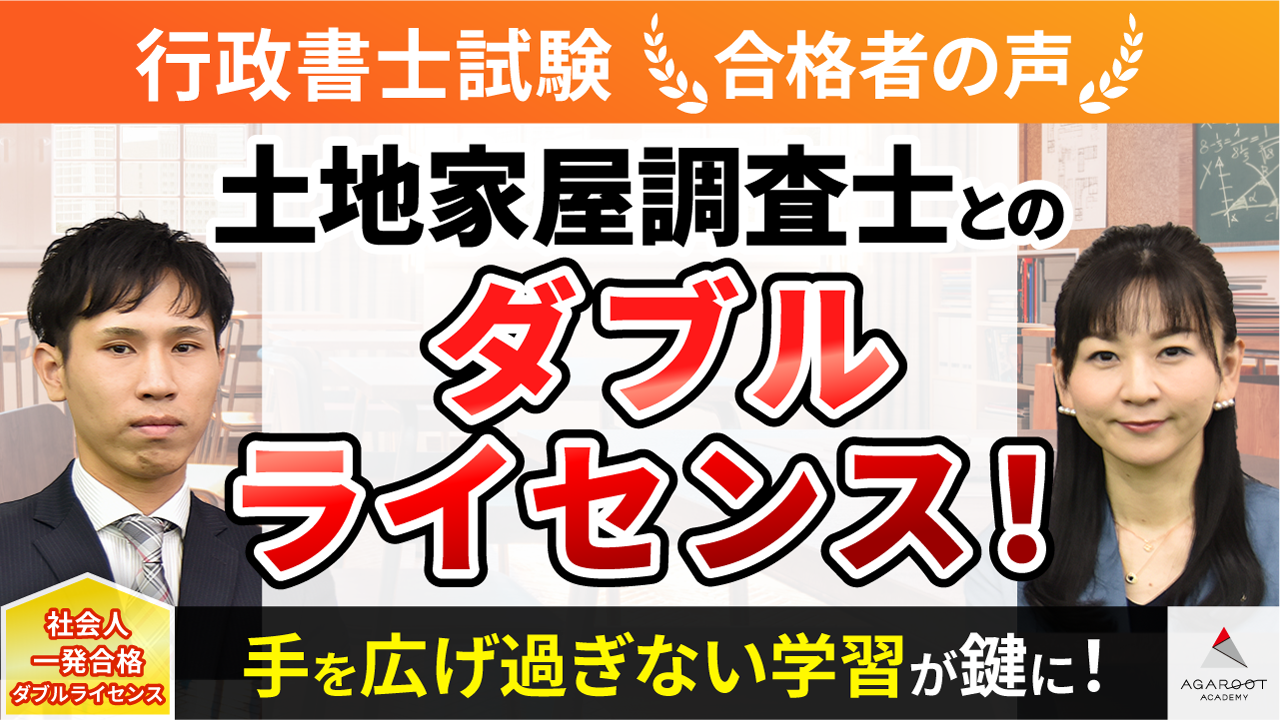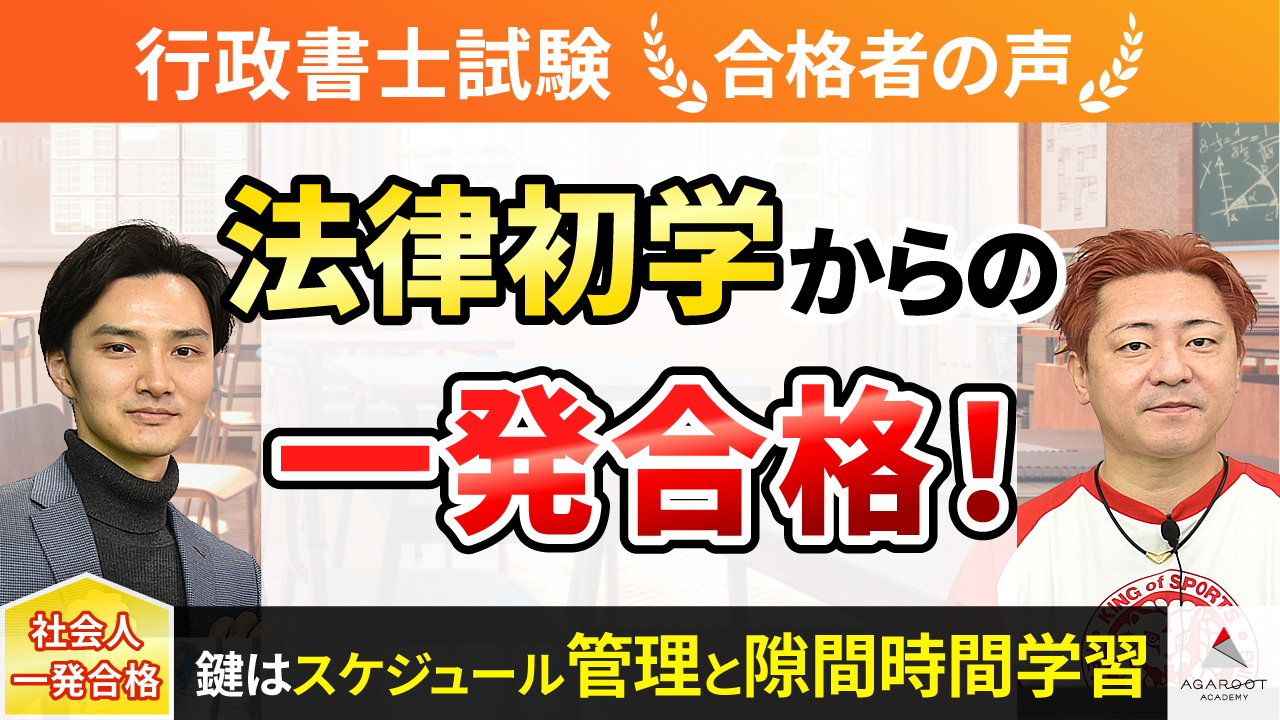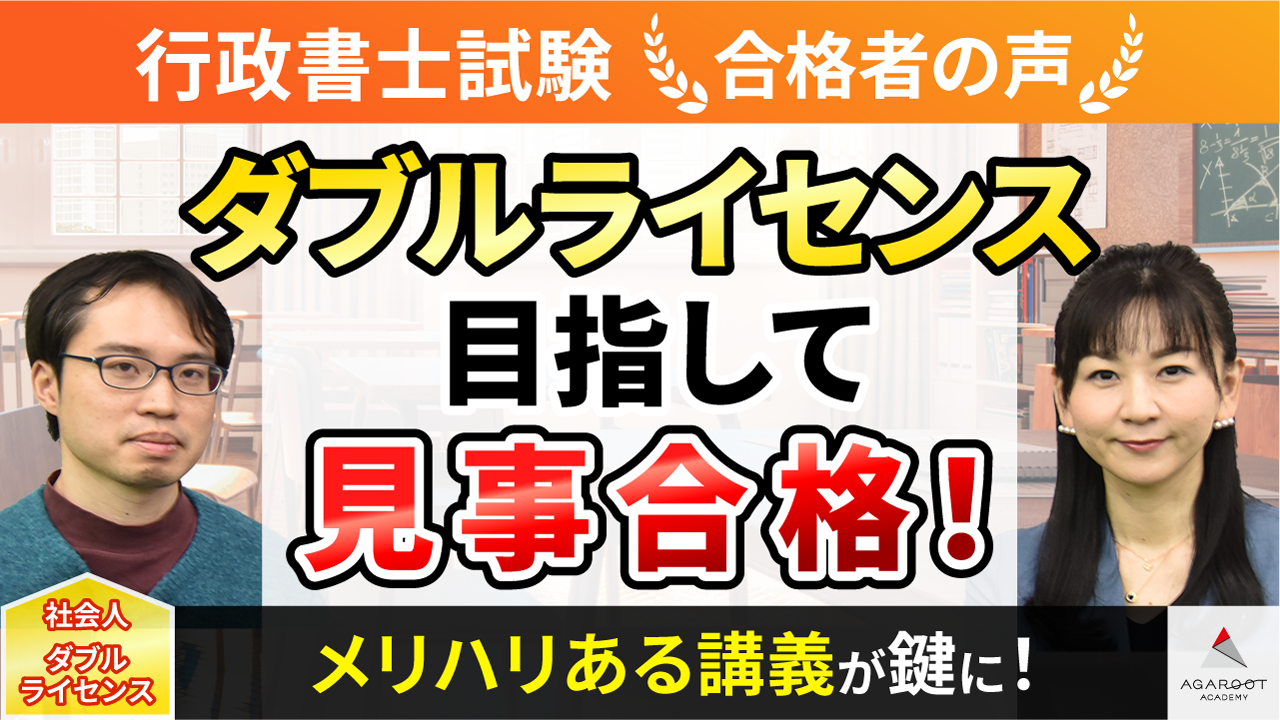合格者の声|2回目受験で似た講義を聴く必要があるのか疑問だったが、曖昧箇所のあぶりだしに効果抜群だった! 高津戸 佑一朗さん
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
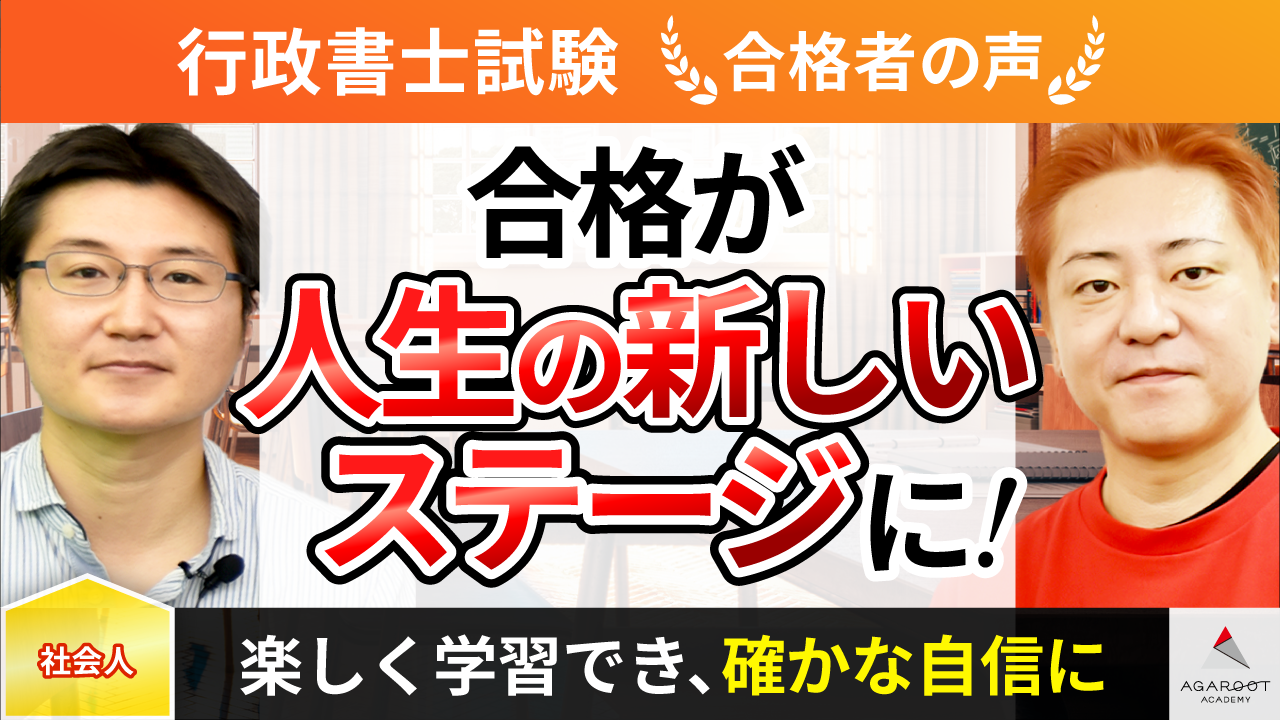
目次 [非表示]
合格者インタビュー
受講されていたカリキュラム
下記リンクは最新版となります。合格者の方の受講年度と異なります。
行政書士試験を目指した理由・契機
お恥ずかしい話ですが、会社の後輩が業務のかたわら税理士試験の勉強をしていると聞き、先輩である自分が家に帰ってダラダラしている姿を客観的に見たとき、これではいけない!と思い立ったことがきっかけです。その後、コロナの影響で外出制限がされたことをきっかけに宅建試験にチャレンジし合格。次のステップとして宅建合格後すぐに行政書士の受験を決めました。
アガルートアカデミーの講座を受講しようと思ったきっかけ
宅建を受けた時は予備校に通学していましたが、平日夜のコースであり会社で業務を終えた後に塾へ行き学習するのは想像以上に負担が重かったため、行政書士では通信講座にしようと決めていました。その中でネットの評判が良かった他校とアガルートの二択で悩みましたが、最終的には高い合格率を出していたアガルートに決めました。
またアガルートは過去問や問題演習について、全肢解説講義があるという点も非常に大きかったです。やはり文字だけ見るのと実際の解説を聴くのでは段違いだと、受講後も改めて思いました。
合格体験記・学習上の工夫
1年目・2年目共にアガルートの講義を受講いたしました。
1年目は入門総合カリキュラム(フル)を受講しました。中々ボリュームがありましたが、宅建試験の勉強をしていたため民法はある程度内容が理解できていました。しかし行政法には非常に苦戦しました。
宅建試験では過去問を周回すればある程度の高得点を取れたのですが、行政書士は過去問の周回だけでは知識が断片的にしか身につかず、何度過去問を回してもふんわりとしか理解できず、本試験でも得点源とされている行政法で大きく点数を落としてしまい、不合格という結果になってしまいました。
そこで2年目の勉強を始める前に、改めて何故行政法が解けなかったかを考えたときに、どの先生も口を酸っぱく話していた六法を使っての条文確認が殆ど出来ていなかった、という結論に至りました。先ほど書いた通り宅建試験では六法を使った勉強はしなかったため、過去問を回せば自然に理解できるようになるだろうと高を括ったのも大きな敗因の一つです。
そこで2年目は講義や問題演習の際に豊村先生がチェックを入れた条文及びその周辺条文については、週に一度見直す作業を行いました。これは行政法だけでなく全ての科目に応用しました。とは言え最初のうちはあまり効果が出ず、昨年は出来た論点の問題をポロポロ落としてしまい不安になりましたが、下手に手を広げるよりアガルートの教材と六法を突き詰めようと決心し地道に勉強を進めていると、7月~8月にかけて急に視界が開けたように理解が進んで得点が伸び始めました。
これは行政法だけに限らず、民法に関しても理解が進み、予備校の模試でも民法の択一は9問中6問以上を安定して正解できるようになりました。
行政法の強化で始めた六法の読み込みですが、結果的に民法の点数が一番伸びました。(もちろん行政法の理解も進みました)
他の科目では、憲法に関しては人権の判例を読み込むのは楽しく点も取れたのですが、点数が取れるといわれる統治の部分では苦戦しました。最後はゴロ合わせで強引に暗記しましたが、暗記したところが本試験に出題されたので、苦手でもしっかり覚えこむことが重要だと感じました。
商法・会社法に関してはアガルートの講義と問題演習を繰り返し行い、商法1問・会社法の設立or機関で1問は必ず得点する、といったように要点を絞って勉強をし、本試験でもまさにその通りに2問正解しました。
一般知識については政治・経済・社会・文章理解に関してはニュースや社会時事が好きなこともあり、この点は殆ど苦労はせずに得点できました。
また個人情報保護法に関しても割と身近な法律ということもあり、こちらもそこまで苦労せずに点数を稼ぐことが出来ました。(正直に白状すると、講義の視聴後にアガルートの問題演習を2周回しただけですが、本試験では14問中12問取れました。なのであまり参考にならないかもです)
長々と書きましたが最後に一点だけ反省点を書くとすると、やはり行政法の条文読み込みが足りなかったように感じます。
本試験では択一のみで180点と理想的な点数の取り方が出来ましたが、その内訳を見ると行政法は19問中14問・更に記述に関しては60点中18点と実は際どいラインであったことが判明しました。(特に行政法の記述は訴訟要件を間違えたため、恐らく0点であったと思います…)
これは条文を覚えることに集中してしまったため、行政不服審査法や行政事件訴訟法の準用される条文や訴訟要件について、何故準用されるのか?何故このような訴訟があるのか?といった本質的な部分をつかみきれなかったため、問題文に少しひねりを入れられると「2択までは絞れるのに…」といった状況が発生してしまいました。
なので今後皆様が学習する際は、ただ条文を覚えるのではなく「何故その条文があるのか?」を意識しながら学習すると、私のような事態を避けることが出来ると感じました。
中上級総合講義のご感想・ご利用方法
講義・問題演習共にボリューム十分で合格するために必要な知識を殆ど漏れなく提供いただけたように感じます。
1年目は入門総合カリキュラムの講義を受けていたため、「同じような講義をもう一度聴く意味はあるのかな?」と最初は思っていましたが、これが抜群に効果があります!
ある程度理解していたところに関しては「うんうん、そうだよね!」といった感じに再確認と記憶の定着が図れ、曖昧に覚えていた点に関しては「うわっ!そういえばこんなのあったぞ!」といった感じで、重点を置いて学習すべき箇所をあぶりだすのに非常に効果がありました。
また問題演習について、1年目は入門総合カリキュラムの過去問を解いていましたが、本試験では過去問と似ているけどちょっと違う論点の問題が出てきたときにそれに引っかかって点数を落としてしまいました。
中上級総合カリキュラム(ライト)の他資格セレクト問題についてはまさにそういった似ているけど少し違う論点や、重要だけど過去問にそこまで出てきていない論点といった問題を網羅していたため、最初は良く分からなかったのですが、特に直前期に模試を受けた際にその効果の大きさを改めて実感いたしました。少なくとも見たことも聞いたことも無い!といった問題は殆ど皆無と言っていいくらいになりました。
また1年目の過去問演習はテキストの参照ページが無かったため、いちいちテキストを開いて確認する作業がありましたが、こちらの問題演習にはテキストの参照ページが記載されていたため、その手間が無くなった点もよかったです。
総まくり択一1000肢攻略講座のご感想・ご利用方法
演習問題と違いB5サイズに製本されていたため、特に通勤時の電車内で重宝しました。科目も5科目全ての問題があるため、総まくり択一1000肢攻略講座が来てからは、中上級総合講義の問題演習は家で行い、電車通勤の際に総まくり択一1000肢攻略講座の問題を行うようにシフトしました。またこの講義にも1肢ごとに解説動画があるのは素晴らしいと思いました。
内容に関しても基礎から応用まであるためやりごたえ充分です。特に基礎的な問題について、問題演習の5肢択一を繰り返しやっているうちにスピードが上がっていき、段々解説も読まなくなってくるのですが、改めて一問一答形式で出たときに想像以上に正誤判断が出来ないことに驚いたので、基礎固めに非常に役立ちました。
総まくり記述80問攻略講座のご感想・ご利用方法
問題数は充分!こちらも一問毎に解説があるのは大きかったです。
特に記述に関しては結論だけでなく答えを導き出す過程も重要なため、解説動画の存在は非常に助かりました。問題に関しても2022年度試験の民法に関しては、まさにニアピンと言えるような問題が出題されたので的中精度もかなり高いと思います。
ただ個人的な意見ですが、この総まくり記述80問攻略講座は本試験直前には各問題の解答を暗記する必要がありますが、それまではこの問題に出題された条文を中心に「理解」を進めていく方が良いと思います。記述の範囲はかなり広く、採点基準も良く分からない点が多いので、この総まくり記述80問攻略講座をベースに周辺条文を広く理解していくことが重要かと思いました。
模擬試験のご感想・ご利用方法
法令問題に関しては良く出来ていると感じました。
特に行政法や民法に関しては、基本問題及び頻出問題だが受験生が間違えやすい論点を中心に出てきているので、現時点での自分の立ち位置を把握するのに非常に役立ちました。
講師へのメッセージ
2年間に及び豊村先生のお世話になりましたが、本当に楽しく勉強出来ました!
色々なサイトで豊村先生の講義は元気があって難しい法律用語をかみ砕いて教えてもらえるカリスマ講師!といった評価が書かれていますが、まさにその通りです!
自分は法律初心者で知識も殆どありませんでしたが、先生の講義で法律の知識を付け行政書士試験に合格したことで、人生における第二のスタート地点に立てたような感覚になりました。
今後はこれまで勉強してきた知識をどのように自分の人生に活用していくべきか、それを考え想像するのが楽しくて仕方ありません。自分の人生を新しいステージに引き上げていただいた先生には感謝しかございません。本当にありがとうございました!