技術士 環境部門とは?難易度や取得メリット、一次・二次試験の勉強方法
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

技術士の環境部門に興味があるけれど、どのような資格で、どんな業務を行うのかよくわからないという方もいるでしょう。
このコラムでは、技術士環境部門の概要や取得するメリット、第一次試験・第二次試験の試験内容について解説します。
また過去の合格率データをもとに第一次試験・第二次試験の難易度も分析したので、これから技術士環境部門を目指す方は参考にしてみてください。
技術士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの技術士試験講座を
無料体験してみませんか?

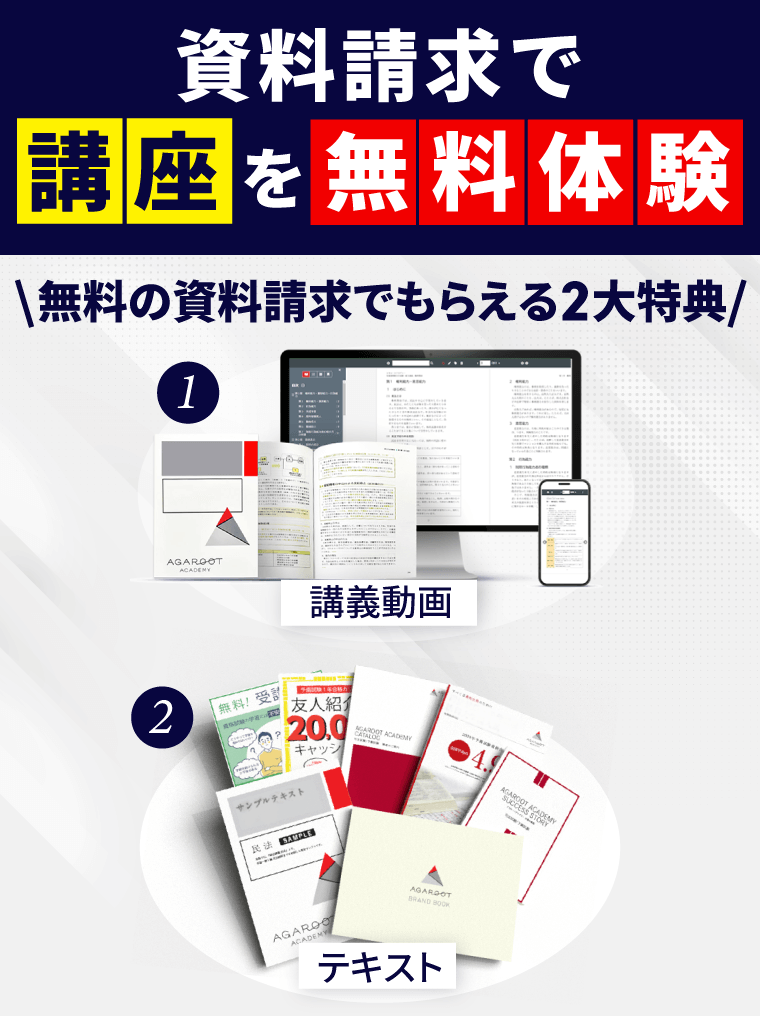
約1時間15分の20部門 筆記試験、
総合技術監理部門 択一・記述試験対策講義などが20日間見放題!
実際に勉強できる!技術士試験対策のフルカラーテキスト
技術士試験のすべてがわかるガイドブック付き!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次 [表示]
技術士環境部門とは?
技術士環境部門は、技術士資格を構成する21の技術部門のひとつで、主な仕事は自然環境や動植物の生態調査をはじめ、環境保全にかかわる技術的な支援です。
具体的には、大規模な工事による自然環境への影響を評価し、環境への悪影響を回避するために技術的なアドバイスを行います。
自然環境の復元・管理、大気や水質の汚染物質の測定・評価にも携わるため、環境保全や持続可能な社会の実現に貢献する重要な役割と言えるでしょう。
技術士環境部門を取得するメリット
技術士環境部門を取得することで得られるメリットは以下のとおりです。
- 専門性を公的に示せる
- キャリアアップにつながる
- 環境保全に貢献できる
専門性を公的に示せる
技術士環境部門の資格は国家資格なので、環境関連の法律・政策・技術的な課題に対する深い理解を持つ専門家として公的に認められます。
特に持続可能社会における環境問題が複雑化する現代においては、環境保護に貢献できる人材はますます求められ続ける人材です。
公共事業を含む様々な環境プロジェクトにおいて重要な役割を果たし、現場での判断や提言が求められる場面において頼られる存在となれるでしょう。
キャリアアップにつながる
技術士の資格を持つことは、キャリアにおいて大きなアドバンテージです。
企業や行政機関では技術士資格が重視されることが多く、特にプロジェクトリーダーやマネージャーなど責任ある上職への昇進につながる可能性が高まります。
さらに環境関連の資格やスキルを持つことは、国内外の転職市場においても強力な武器となり、求人数の多い業界での競争力を高める要素となるのです。
海外でも通用する資格なため、国際的な活躍の幅も広がるでしょう。
環境保全に貢献できる
技術士環境部門の資格を持つことで、環境保護および持続可能な社会の実現に貢献する機会が増えます。
環境問題に対する専門知識を活用し、企業や地域社会に対して適切にアドバイスすることで、環境負荷の軽減やエネルギー効率の向上、資源の持続的な利用を実現可能です。
さらに資格取得者は環境教育や意識向上の活動にも関われるため、自らの専門性を活かして次世代への環境意識の高揚に寄与できます。
持続可能な未来の実現に貢献する力を持つ人材として、社会的な責任を果たせるでしょう。
技術士環境部門の難易度は?
技術士環境部門の難易度は「高い」です。
そもそも第一次試験・第二次試験の合格率が1~3割ほどしかないのに加え、資格取得には両方の試験に合格する必要があります。
それでは、技術士環境部の第一次試験・第二次試験の合格率をそれぞれ見ていきましょう。
第一次試験の合格率
令和6年度の技術士環境部門の合格率は27.4%でした。
直近5年間の第一次試験の受験者数・合格者数・合格率は下記の通り。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 862名 | 236名 | 27.4% |
| 令和5年度 | 804名 | 276名 | 34.3% |
| 令和4年度 | 905名 | 356名 | 39.3% |
| 令和3年度 | 955名 | 108名 | 11.3% |
| 令和2年度 | 817名 | 322名 | 39.4% |
過去5年間の合格率は11.3%〜39.4%で推移しています。
最も合格率が低かった令和3年度は11.3%ですが、ほかの年度の合格率は27.3%〜39.4%と比較的安定していると言えるでしょう。
第二次試験の合格率
令和6年度の第二次試験の合格率は11.6%でした。
直近5年間の受験者数・合格者数・合格率は下記の通り。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 396名 | 46名 | 11.6% |
| 令和5年度 | 413名 | 45名 | 10.9% |
| 令和4年度 | 415名 | 53名 | 12.8% |
| 令和3年度 | 411名 | 48名 | 11.7% |
| 令和2年度 | 383名 | 52名 | 13.6% |
過去5年間の合格率は10.9%〜13.6%で推移しています。
年度により変動はあるものの、合格率はおおむね10%台で推移しており難しい試験と言えるでしょう。
技術士環境部門の難易度が高い理由
技術士環境部門の難易度が高い理由は、次の3つのポイントに集約されます。
- 専門知識の範囲が広い
- 実務経験の重要性が高い
- 第二次試験の評価が厳しい
専門知識の範囲が広い
技術士環境部門は、環境問題に関する広範な知識を要求されます。
大気、水質、土壌、廃棄物管理、リサイクルなど多岐にわたる環境課題に対処するため、関連する科学知識や対策技術の深い理解が不可欠です。
主に環境汚染のメカニズムやその影響の系統的理解、また関連法規の規制や運用基準についても深く学ばなくてはなりません。
多様なトピックを網羅的かつ系統的に学ぶ必要があり、その学習範囲の広さが受験者にとって大きな負担となっています。
実務経験の重要性が高い
技術士試験では、環境部門に関わらず実務経験が重視されます。
特に環境部門では、実際のプロジェクトへの参加や環境影響評価の実施、法律の理解等の実践的なスキルが要求されます。
理論を理解するだけでは不十分で、どのように現場で応用するかが重要です。
また受験者は、専門的な業務を通じて得た具体的経験を基に質の高い技術的レポートを作成する必要があります。
そのため専門的実務経験が不足している受験者にとって、試験のハードルは非常に高いといえるでしょう。
第二次試験の評価が厳しい
技術士試験の二次試験は、合格率が10%程度しかない難関試験です。
第二次試験では、受験者が専門的知識をもとに現場で活躍できる能力があるか試されます。
環境問題に対する技術課題を設定し、技術的解決策を論理的に提示し、それを小論文形式で実行可能な形で説明しなくてはなりません。
この評価基準の高さと記述表現の困難さが受験者に強いプレッシャーを与え、試験全体の難易度を押し上げています。
技術士環境部門の試験内容
技術士環境部門の試験内容を、第一試験と第二次試験に分けて解説します。
- 第一次試験の概要
- 第二次試験の概要
第一次試験の概要
受験資格
年齢・学歴・業務経歴等による制限はありません。
試験内容
第一次試験は、基礎科目・適性科目・専門科目の3科目で構成され、すべてマークシートの択一方式。
基礎科目と適性科目の試験問題は全部門で共通ですが、専門科目は部門別の試験問題が出題されます。
合格基準は、各科目50%以上の得点であり、1科目でも50%未満の場合、不合格となります。
技術士環境部門の試験範囲は、大気、水、土壌等の環境の保全/地球環境の保全/廃棄物等の物質循環の管理/環境の状況の測定分析及び監視/自然生態系及び風景の保全/自然環境の再生・修復及び自然とのふれあい推進です。
第二次試験の概要
受験資格
技術士第二次試験の受験資格は、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 規定の過程を修了していること
受験申込時に第一次試験に合格している(=修習技術者)か、指定された教育課程(JABEE認定課程)を修了している - 規定の業務経験を有していること
受験申込時に4年〜10年の業務経験が必要(期間は業務経験の積み方と受験する技術部門によって異なる)
規定の業務経験について、具体的な条件・期間は以下の通り。
| 総合技術監理部門以外の20部門を受験 | 総合技術監理部門を受験 | |
| 指導技術士や監督者の下で業務経験を積む場合 | 4年を超える期間 | 7年を超える期間 |
| 独自に業務経験を積む場合 | 7年を超える期間 | 10年を超える期間 |
なお、大学院での研究経歴も最大2年まで業務経験に算入可能です。
ただし、理系の大学院修士課程・専門職学位課程を修了している場合、または大学院博士課程に在籍していた場合に限ります。
試験内容
技術士第二次試験は筆記試験と口頭試験で構成され、筆記試験合格者のみが口頭試験を受験できます。
同一年度内に筆記試験と口頭試験の両方に合格することで、第二次試験合格となります。
筆記方式
科目は必須科目と選択科目。
総合技術監理部門とそのほかの部門で配点は異なりますが、合格にはすべての部門で60%以上の得点が必要です。
筆記試験の点数は、答案論文の採点者が決めるため、マークシート方式の択一式試験のような決まった正解はありません。
口頭試験
面接形式で実施され、各試問事項で60%以上の得点が必要です。
第二次試験環境部門の試験範囲は次の通り。
- 環境保全計画
環境の現状の解析及び将来変化の予測並びにこれらの評価、環境情報の収集、整理、分析及び表示その他の環境の保全及びその持続可能な利用に係る計画に関する事項(専ら一の技術部門に関するものを除く。)
- 環境測定
環境測定計画、環境測定分析、環境監視並びに測定値の解析及び評価に関する事項
- 自然環境保全
生態系及び風景並びにこれらを構成する野生動植物、地形、水その他の自然の保護、再生・修復、生物多様性保全・外来種対策に関する事項 自然教育、自然に親しむ利用及びそのための施設整備に関する事項(専ら一の技術部門に関するものを除く。)
- 環境影響評価
事業の計画及び実施が環境に及ぼす影響の調査、予測及び評価並びに環境保全の措置の検討及び評価 に関する事項(専ら一の技術部門に関するものを除く。)
技術士環境部門の勉強方法
第一次試験の勉強方法
勉強方法
環境部門の第一次試験は知識確認を目的とした試験なので、参考書で環境基礎科目や専門科目の範囲を学び、過去問で知識を定着させることが重要となります。
独学だけでなく通信講座や講習会、関連セミナーを活用し、日々進展する専門知識を深めるのもおすすめです。
また試験範囲が非常に広いため、計画を立てて効率的に勉強する必要があります。
試験の1ヶ月前までに模擬試験を受け、実際の試験形式に慣れることも重要。最新の出題傾向を把握し、トピックごとの復習も怠らずに進めましょう。
勉強すべき分野
環境部門の第一次試験の内容は、環境科学(化学分析含む)・環境技術・環境保全技術・持続可能な開発などが中心になります。
特に、日常で馴染みのない環境政策や技術評価については重点的に学びましょう。自身の職務経験に関連付けて勉強すると、試験対策のみならず、実務補修になります。
勉強時間
第一次試験の合格には最低300時間の学習が目安です。1日1.6時間勉強した場合、約半年の期間が必要となります。
思いつきや闇雲に進めるのではなく、計画的に専門書把握、関連テキスト整理、過去問解答、弱点克服を進めることが重要です。
注意点
特定の分野(自分が馴染みのある分野など)に偏りすぎないように、試験範囲の広範な科目をバランスよく学習しましょう。
特に技術士法第四章(技術士等の義務)に関する適性科目範囲を軽んじるのはNG。参考書や実務経験をもとに、問題の解き方をしっかりと整理しておきましょう。
第二次試験の勉強方法
勉強方法
技術士環境部門の二次試験対策は、過去問分析が要になります。
過去5年間程度の出題傾向を把握し、重要テーマを重点的に整理学習しましょう。
二次試験の出題形式は必須科目と選択科目ともに記述式なため、単に専門知識を習得するだけでは試験問題に対応できません。
記述式問題(小論文)を解くことを念頭に置いた環境専門知識の整理や関連法規、最新技術動向を正確に把握し、学ぶことが大切になります。
小論文記述能力を向上させるためには、問題解決能力並びに課題設定能力を高め、論理的思考力と論述力を養成することが重要です。
具体的な勉強方法として、最新の関連白書(環境白書・国土交通白書)や業界資料を活用するのがおすすめ。試験の出題傾向を反映しているため、重要な情報源になります。
また技術部門の過去問分析をして関連キーワード集を自作し、小論文の材料を確保するのも重要な対策となるでしょう。
勉強すべき分野
環境部門の第二次試験では、「環境マネジメント」「環境影響評価」「再生可能エネルギー」「分析化学知識」の分野が多く出題されます。
そのため、最新の国の環境政策動向や技術革新に注意することが重要です。
地域固有の環境問題や新たな環境基準などにも注意を払い、自身の実務経験と関連付けながら整理しておきましょう。
実務との関連性を意識することで、試験対策の理解をより深められます。
勉強時間
第二次試験の合格には、少なくとも500〜800時間の学習時間が必要です。専門知識を深め、小論文記述の対策をするうえで最低限の時間となります。
それぞれの実務経験に応じて必要な時間は変動しますが、計画的に学習時間を設定し、試験日から逆算したプランを立てる(バックワードスケジューリング)ことが成功への鍵です。
注意点
第二次試験に合格するには専門知識だけでなく、論理展開力と小論文論述力が必須です。
与えられたテーマ(試験問題文)に対して論理的に考え、自分の意見を明確に述べる力が求められます。
最新の環境政策や法律の改正に留意し、それらの改正が、試験問題にどのように影響するかを考えることが結果を左右することになります。
具体的な事例研究(ケーススタディ)やディスカッションを通じて、技術的な視点を広げることが大きな助けとなるでしょう。
まとめ
技術士環境部門は、技術士資格を構成する21の技術部門のひとつで、大規模な工事による環境への影響評価や対策提案、自然環境の復元・管理、大気や水質の測定・分析など、幅広い分野で活躍します。
試験の難易度は高く、第一次試験の合格率は約30%〜40%、第二次試験の合格率は約10%〜15%で推移。
試験範囲は広く、専門知識だけではなく、問題解決能力や論文作成能力も求められます。
特に第一次試験の対策を独学で行うことは非常に難しいため、通信講座の利用がおすすめです。
アガルートの技術士試験講座は、経験豊富な講師陣によるわかりやすい講義や、質の高い教材で、合格に必要な知識とスキルを効率的に身につけることができます。
質問対応、学習に関する悩み相談など、フォロー制度も充実しているため、ぜひ検討してみてください。
技術士試験の合格を
目指している方へ
- 技術士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの技術士試験講座を
無料体験してみませんか?

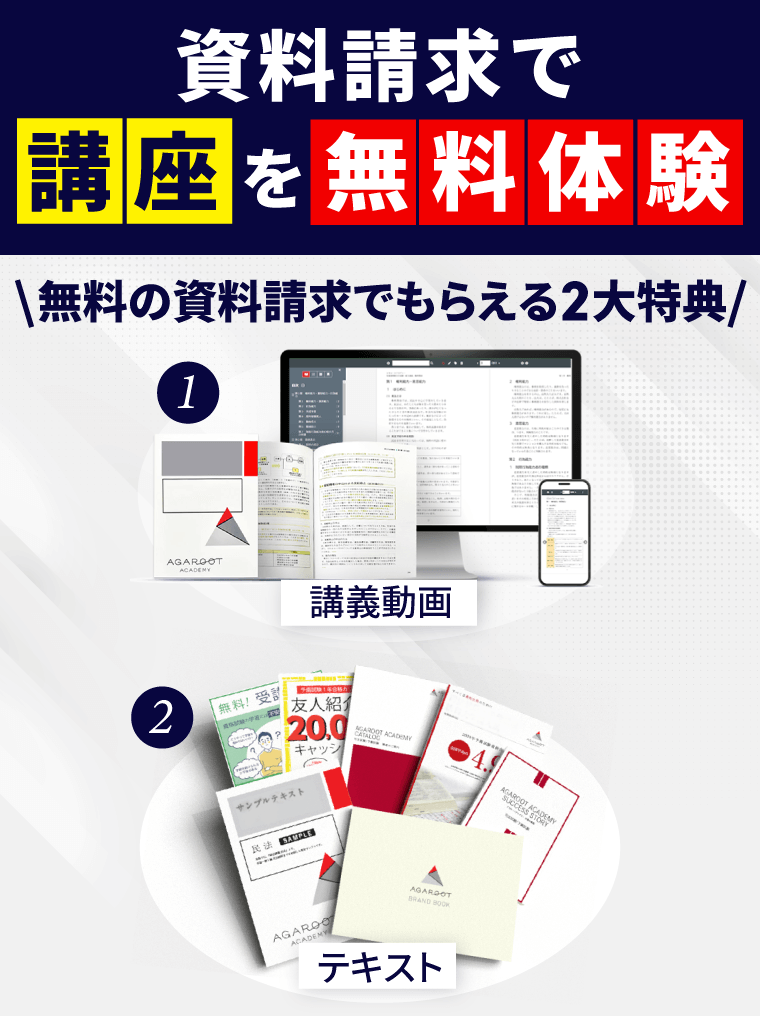
約1時間15分の20部門 筆記試験、
総合技術監理部門 択一・記述試験対策講義などが20日間見放題!
実際に勉強できる!技術士試験のフルカラーテキスト
技術士試験のすべてがわかるガイドブック付き!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
令和5年度アガルート受講生の合格率一次42.52%(全国平均1.07倍)二次45.45%(全国平均3.85倍)
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のフォロー制度で学習をサポート
7月13日までの申込で10%OFF!
▶技術士試験講座を見る※2025年 第二次試験 合格カリキュラム(フル/ライト)

この記事の監修者
北海道大学卒業後,工業用界面活性剤と食品油脂を製造する会社のプラントマネジャーを経て,大手製薬会社系列食品会社で食品素材の研究・開発ならびにテクニカルサービス業務を経験。
1994年に独立し,技術コンサルタント会社を創業,現在に至る。
平成28年,技術士(経営工学部門と総合技術監理部門を併願)試験を受験し,合格。
平成29年3月2部門同時登録。同年から技術士試験受験指導にも携わり,先達の導きもあり,4年間で数十名の受験生を支援する。
日比講師の紹介はこちら



