技術士 化学部門とは?難易度や取得メリット、勉強方法を解説!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

技術士資格の中には「化学部門」が存在します。
「化学部門の技術士になるメリットは?」「試験は難しい?」といった疑問だけでなく、「そもそもどんな資格?」と気になっている方もいるでしょう。
当コラムでは技術士化学部門について、概要や取得メリット、試験内容などを詳しく解説。
技術士の受験を検討している方はぜひ参考にしてください。
技術士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの技術士試験講座を
無料体験してみませんか?

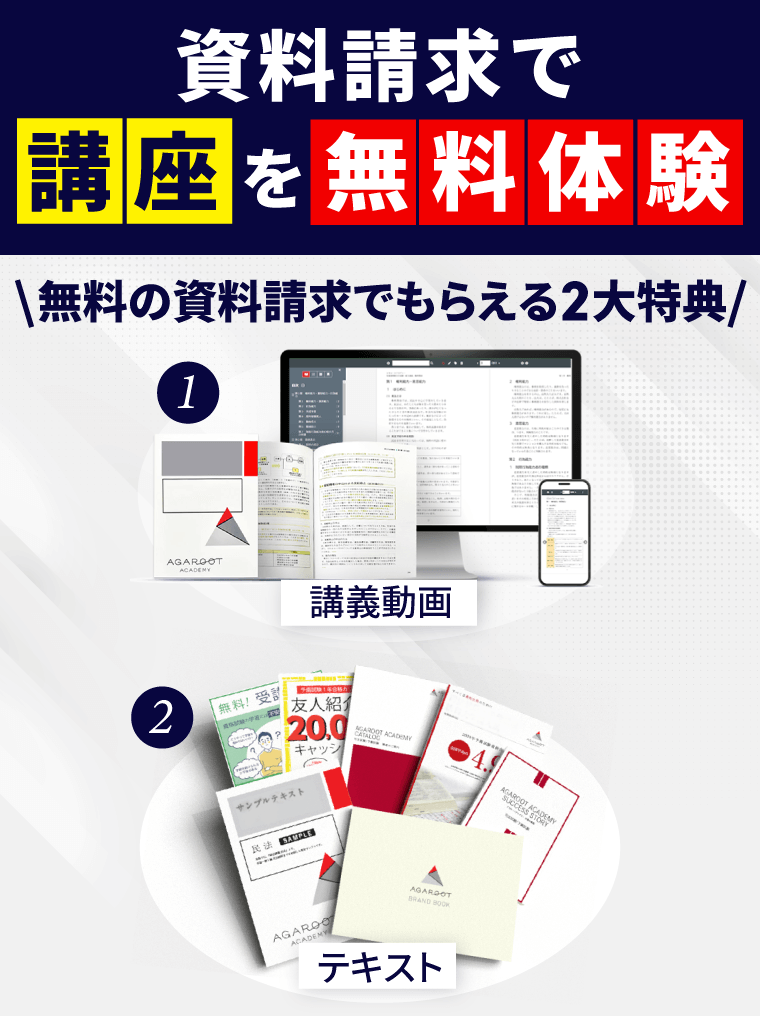
約1時間15分の20部門 筆記試験、
総合技術監理部門 択一・記述試験対策講義などが20日間見放題!
実際に勉強できる!技術士試験対策のフルカラーテキスト
技術士試験のすべてがわかるガイドブック付き!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次 [表示]
技術士化学部門とは?
技術士化学部門とは、技術士の中でも「化学」分野に精通し、化学工場における生産や新製品の開発などを担う職種のことです。
一口に「化学」といっても範囲は広く、化学部門の技術士試験の選択科目においては以下の分野が挙げられます。
- 無機化学分野:セラミックなど
- 有機化学分野:プラスチックなど
- 高分子化学分野:ポリマー、合成ゴムなど
- 燃料科学分野:石油の精製など
- 化学製品を生産するための設備
上記に関連する工場やメーカーなどの開発職や生産管理などが、化学部門の技術士の主な活躍の場となります。
化学系の製造業を目指す人には必須の資格といえるでしょう。
化学物質の研究開発を主な業務とする工学博士の学位と同時に取得されることも多いです。
技術士化学部門を取得するメリット
技術士化学部門を取得するメリットは以下のとおりです。
- 技術力と倫理観を証明できる
- キャリアアップと活躍の場が広がる
- 自己研鑽を続け専門性を向上させられる
技術力と倫理観を証明できる
技術士は、高度な専門知識と豊富な実務経験を有する技術者であることを証明する国家資格です。
化学部門では、化学物質や化学プロセスに関する深い知識、環境保全や安全に関する高い意識、そして技術者倫理に基づいた行動が要求されます。
技術士資格を取得することで、これらの能力を有していることが客観的に証明され、社会的な信頼性が高まります。
また技術士は公共の安全、環境保全、持続可能な開発に貢献することが求められており、資格を取得することでこれらの責任を果たす決意を示すことにつながります。
キャリアアップと活躍の場が広がる
技術士資格は、技術者としてのキャリアアップに大きく貢献します。
多くの企業や官公庁では技術実務、管理部門を問わず、技術士資格を保有していることが昇進・昇格の条件の一つとなっており、資格取得によってより高度なプロジェクトや研究開発に携わる機会が増えます。
また技術士はコンサルタントや独立開業など、多様な働き方を選択することが可能です。
特に化学部門では、環境問題や新エネルギー開発など、社会的なニーズの高い分野で活躍する機会が広がっています。
技術士資格は、自身の専門性を活かし、社会に貢献できる幅広いキャリアパスを切り拓くための強力な武器となります。
自己研鑽を続け専門性を向上させられる
技術士試験は高度な専門知識だけでなく、問題解決能力、コミュニケーション能力、倫理観など、幅広い能力が求められます。
試験勉強を通じてこれらの能力を体系的に習得し、総合的な技術力を向上させることが可能です。
また技術士資格を取得した後も、継続的な自己研鑽が求められます。
学会や研修会への参加、論文発表などを通じて、常に最新の技術動向や知識を習得し、専門性を磨き続ける必要があります。
技術士資格の取得は、自己研鑽の過程を通じて、技術者としての成長を促進し、生涯にわたって専門性を高め続けるため、技術者自身の自信の原動力となります。
技術士化学部門の難易度は?
技術士化学部門の難易度は、総合的に見て難しいといえます。
もっとも大きな要因としては、第一次試験・第二次試験の両方に合格する必要があることなどが挙げられるでしょう。
第一次試験の合格率
技術士化学部門の第一次試験の難易度は「やや難しい」です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 令和6年度 | 201名 | 113名 | 56.2% |
| 令和5年度 | 173名 | 112名 | 64.7% |
| 令和4年度 | 194名 | 107名 | 55.2% |
| 令和3年度 | 192名 | 93名 | 48.4% |
| 令和2年度 | 181名 | 105名 | 58.0% |
上記の表は、直近の技術士化学部門の第一次試験の合格率をまとめたものです。
直近の合格率は45〜65%ほどを推移しており、資格試験の合格率としては「高い」といえます。
ただし、母数となる受験者数はさほど多くないにもかかわらず、例年半数は不合格です。
合格率自体は高く見えますが、ある程度難易度の高い試験と考えるべきでしょう。
第二次試験の合格率
技術士化学部門の第二次試験の難易度は「難しい」です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 令和6年度 | 139名 | 25名 | 18.0% |
| 令和5年度 | 129名 | 24名 | 18.6% |
| 令和4年度 | 124名 | 23名 | 18.5% |
| 令和3年度 | 134名 | 24名 | 17.9% |
| 令和2年度 | 119名 | 29名 | 24.4% |
上記の表は、直近の技術士化学部門の第二次試験の合格率をまとめたものです。
直近の合格率は18〜24%ほどを推移しています。
10人中8人は不合格の計算となり、簡単に突破できる試験ではありません。
さらに「18〜24%」はあくまで第二次試験のみの合格率のため、第一次試験から連続して受験する場合の合格率はさらに下がります。
推定値ですが、第一次試験・第二次試験を通しての最終合格率は12%ほど。
技術士化学部門の知識範囲は非常に専門性が高く、担当業務も重い責任を伴うものです。資格取得のための試験の難易度が高いことは当然といえるでしょう。
技術士化学部門の難易度が高い理由
技術士(化学部門)試験の難易度が高い理由は、以下の3つの観点から説明できます。
- 幅広い専門知識と応用力が求められる
- 記述式問題への対応力が求められる
- 実務経験に基づく専門性が求められる
幅広い専門知識と応用力が求められる
技術士化学部門の試験範囲は、基礎化学から応用化学、化学工学、環境化学、安全工学など多岐にわたります。
高度な専門知識だけでなく、実務経験に基づいた応用力も必要です。
技術士試験は単に知識を問うだけでなく、複雑な問題に対して複数の専門分野を横断的に理解し解決課題を設定する能力、またこの課題の解決策を提案する能力が評価されます。
化学技術は、常に新しい技術や概念が生まれており、最新の技術動向を把握し、自身の専門知識をアップデートし続けなくてはなりません。
また、化学プラントの設計、建設、運転、保守管理、研究開発、品質管理、環境対策、安全対策など、化学技術者が関わる業務範囲は非常に広いです。
これらの業務において、技術士は高度な専門知識だけでなく、プロジェクトマネジメント能力、コミュニケーション能力、リーダーシップなどを要求されます。
技術士試験でも評価されるため、幅広い知識と経験に基づく応用力が不可欠です。
記述式問題への対応力が求められる
技術士化学部門の二次試験は記述式問題が中心で、論理的かつ高度な文章作成能力が必要です。
単に知識を記述するだけでなく、論理的な思考力、問題解決と課題設定能力、コミュニケーション能力などを駆使して、説得力のある文章を作成する必要があります。
試験では、与えられた問題文に対して、現状分析、問題点の抽出、課題の設定、解決策の提案、費用対効果の評価などを論理的に記述することが要求されます。
対応するためには、専門知識の整理と過去問題の分析、模擬試験の受験、専門家による添削指導などを通じて、記述力を向上させる必要があります。
また技術士試験では、技術者倫理に関する問題の対策もしなくてはなりません。
技術者倫理とは、技術者が社会に対して負うべき責任や義務に関する規範のこと。公共の安全、環境保全、持続可能な開発などに貢献することが求められます。
倫理観を身につけるためには、技術者倫理に関する書籍や論文を読むだけでなく、倫理に関する事例研究やディスカッションを通じて、倫理的思考力を養うことが必要です。
実務経験に基づく専門性が求められる
技術士試験では、単に知識を問うだけでなく、実務経験に基づいた高度な専門性と判断力が評価されます。
受験者は自身の専門分野において、高度な技術的問題を解決した経験や、プロジェクトを成功に導いた経験などをもとに、具体的な事例に基づいて説明する必要があります。
試験では、これらの経験を通じて培われた問題解決能力、課題設定能力、意思決定能力、リーダーシップなどが評価基準です。
能力を証明するためには、多年にわたる実務経験を振り返り、自身の専門性を客観的に評価しなくてはなりません。
また、技術士試験では、最新の技術動向や社会情勢を把握し、将来を見据えた技術開発や技術政策の提案能力も評価されます。
受験者は、自身の専門分野だけでなく、関連分野や社会全体の動向にも目を向け、常に最新の情報を収集し、自身の専門性をアップデートし続ける必要があります。
能力を証明するためには、学会や研修会への参加、論文発表、情報収集などを通じて、常に自己研鑽に努める必要があります。
技術士化学部門の試験内容
ここでは、技術士化学部門の試験内容について以下の内容で解説します。
- 第一次試験の概要
- 第二次試験の概要
第一次試験の概要
受験資格
技術士化学部門の第一次試験には特別な受験資格などはありません。
試験内容
技術士化学部門の第一次試験の内容は「基礎科目」「適性科目」「専門科目」の3科目で構成され、筆記形式で実施されます。
3科目それぞれに合格基準が設定されており、各科目で50%以上得点できれば合格です。
各科目ごとの具体的な試験内容については以下の通りです。
【基礎科目】
- 設計・計画に関するもの(設計理論、システム設計、品質管理等)
- 情報・論理に関するもの(アルゴリズム、情報ネットワーク等)
- 解析に関するもの(力学、電磁気学等)
- 材料・化学・バイオに関するもの(材料特性、バイオテクノロジー等)
- 環境・エネルギー・技術に関するもの(環境、エネルギー、技術史等)
【適性科目】
技術士法第四章(技術士等の義務)の規定の遵守に関する適性
【専門科目(化学)】
- セラミックス及び無機化学製品
- 有機化学製品
- 燃料及び潤滑油
- 高分子製品
- 化学装置及び設備
第二次試験の概要
受験資格
技術士化学部門の第二次試験の受験資格は以下の通りです。
- 修習技術者(もしくは技術士補)として技術士を補佐した実務経験が規定以上あること(実務経験の年数により出願経路が異なる)
- 科学技術関連の専門的応用能力を必要とする研究や分析などの従事者、または該当業務の指導者の監督下で業務に従事した経験+技術士補となる資格を得てからの業務への従事期間が規定以上あること(実務経験の年数により出願経路が異なる)
- 科学技術関連の専門的応用能力を必要とする研究や分析などの業務に従事、または該当業務の指導者としての経験が規定以上あること(実務経験の年数により出願経路が異なる)
「技術士補」は技術士の第一次試験に合格し、技術士補登録することで名乗れる資格です。
つまり、第二次試験の受験には第一次試験の合格と、数年単位の実務経験が求められます。
なお、第二次試験の受験資格を満たすために必要な実務経験は最短4年。最長7年となります。
試験内容
技術士化学部門の第二次試験の内容は「筆記試験」と「口述試験」で構成され、筆記試験に合格すると口述試験を受験できます。
筆記試験・口述試験ともに、各科目60%以上得点できれば合格となります。
試験ごとの具体的な内容は以下の通りです。
【筆記試験】
- 総合技術監理部門
- 総合技術監理部門を除く20の技術部門
【口述試験】
- 総合技術監理部門(必修)
- 総合技術監理部門(選択)
- 総合技術監理部門を除く20の技術部門
技術士化学部門の勉強方法
技術士化学部門の勉強方法について、第一次試験・第二次試験それぞれ解説します。
第一次試験の勉強方法
技術士化学部門の一次試験は、過去に出題された問題と類似した問題が出題される傾向が強いです。
そのため過去問題を収集し、問題演習、正解不正解の分析などを繰り返し、学習のサイクルを回しましょう。
過去問題を解いていく中で、出題傾向を分析することも重要です。
頻出分野や苦手分野を重点的に学習することで、効率的に合格力を高められます。
過去問題と合わせて、化学基礎の教科書や参考書を併用しましょう。
理解が曖昧だった部分や苦手分野の知識を補強するために、関連キーワードを整理したり図表(図解)でわかりやすく理解したり、さらに疎かになりがちな関連法規の学習ができたりします。
技術士一次試験の合格には、計画的な学習と継続的な努力が不可欠です。
試験日から逆算して学習期間を設定、具体的な目標を立てます。
そのとき、1週間ごとの学習目標や学習内容を具体的に計画するのがおすすめです。
ここで重要なのが、学習の成果を実感できるような工夫をしたり、リフレッシュ時間を取り入れたりしてモチベーションを維持することです。
十分な睡眠やバランスの取れた食事など、規則正しい生活習慣を心がけ、体調を整えましょう。
第二次試験の勉強方法
技術士化学部門二次試験は、専門知識だけでなく、技術者としての倫理観や課題解決能力も問われる難関試験です。
効率的な学習で合格を勝ち取るために、過去問分析とその対策、専門知識の習得、論文作成能力について、計画的な勉強が必要になります。
おすすめは過去5年分の過去問を徹底的に分析し、出題傾向を把握すること。
過去問の出題傾向から、頻出キーワードやテーマを把握したら、テキストや模範解答を参考に過去問を解き、時間配分や論文構成の論述スキルを磨きましょう。
特に技術士資格者に論文答案を見てもらいアドバイスをもらうことは、第三者からの客観的な評価を受けることによる大きな気づきになります。
さらに継続的に最新技術動向や業界課題を把握するため、専門誌や論文、業界団体が公表する資料などを確認することも重要です。
自分の専門分野だけでなく、技術者倫理、業際知識も習得することで、多角的な視点から課題を分析できるようになります。
二次試験に合格するためには、課題を正確に把握し的確な解決策を提示すること、技術者倫理を考慮し安全性を確保すること、持続可能な社会への貢献を意識することが大切です。
まとめ
当コラムでは、技術士の化学部門について以下の内容で解説しました。
- 技術士化学部門とは、「化学」分野に精通した技術士。該当分野の例としては、無機化学や有機化学、燃料科学など。
- 技術士化学部門の第一次試験はやや難しい。直近の合格率は45〜65%ほど。
- 技術士化学部門の第二次試験は難しい。直近の合格率は18〜24%ほど。最終合格率は推定で10%ほど。
- 第一次試験には受験資格はない。3科目それぞれ50%以上得点で合格。
- 第二次試験は第一次試験の合格+規定以上の実務経験が必要。筆記・口述ともにそれぞれの科目で60%以上得点で合格。
技術士化学部門の試験には非常にシビアな合格基準が設けられており、科目ごとに50〜60%以上の得点が必要です。
1科目でも基準を下回った場合は不合格となるため、例年の最終合格率も10%ほどと、難易度の高い試験といえます。
難関試験に効率よく合格したいなら、アガルートの「技術士試験講座」がおすすめ。
スマホ学習に特化したカリキュラムと教材設計で、隙間時間を有効活用しながら確実に学習を深められるでしょう。
技術士試験の合格を
目指している方へ
- 技術士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの技術士試験講座を
無料体験してみませんか?

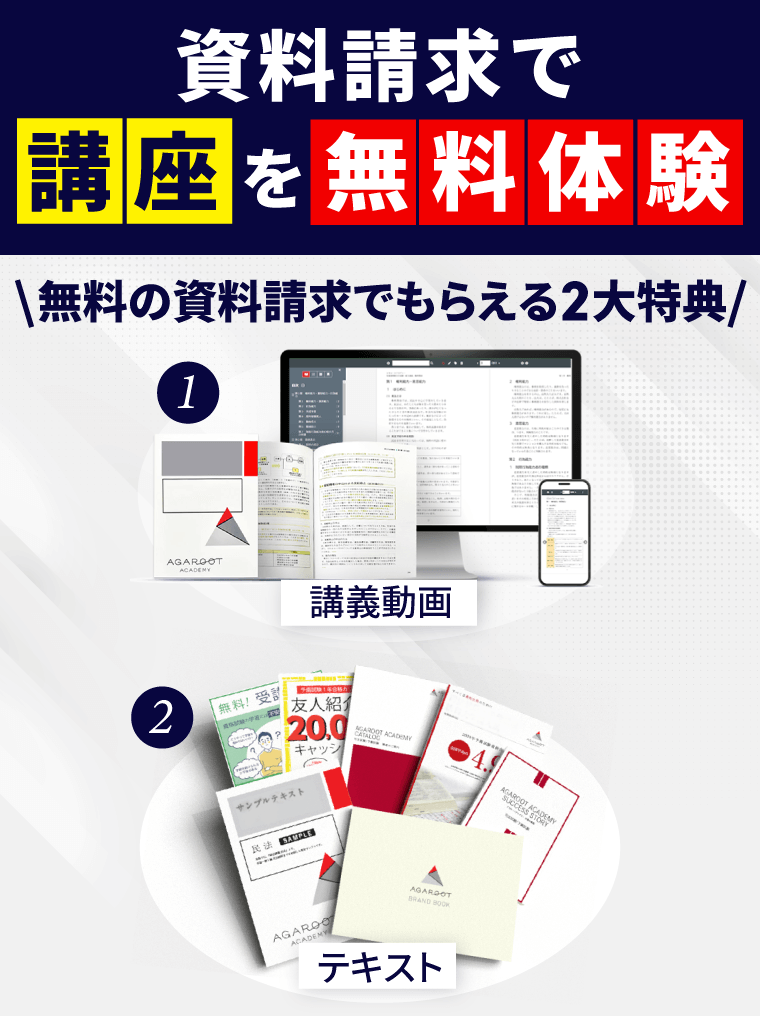
約1時間15分の20部門 筆記試験、
総合技術監理部門 択一・記述試験対策講義などが20日間見放題!
実際に勉強できる!技術士試験のフルカラーテキスト
技術士試験のすべてがわかるガイドブック付き!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
令和5年度アガルート受講生の合格率一次42.52%(全国平均1.07倍)二次45.45%(全国平均3.85倍)
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のフォロー制度で学習をサポート
7月13日までの申込で10%OFF!
▶技術士試験講座を見る※2025年 第二次試験 合格カリキュラム(フル/ライト)

この記事の監修者
北海道大学卒業後,工業用界面活性剤と食品油脂を製造する会社のプラントマネジャーを経て,大手製薬会社系列食品会社で食品素材の研究・開発ならびにテクニカルサービス業務を経験。
1994年に独立し,技術コンサルタント会社を創業,現在に至る。
平成28年,技術士(経営工学部門と総合技術監理部門を併願)試験を受験し,合格。
平成29年3月2部門同時登録。同年から技術士試験受験指導にも携わり,先達の導きもあり,4年間で数十名の受験生を支援する。
日比講師の紹介はこちら



