【飯野一講師の特別コラム9】一橋大学大学院経営管理プログラムについて|国内MBA試験
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
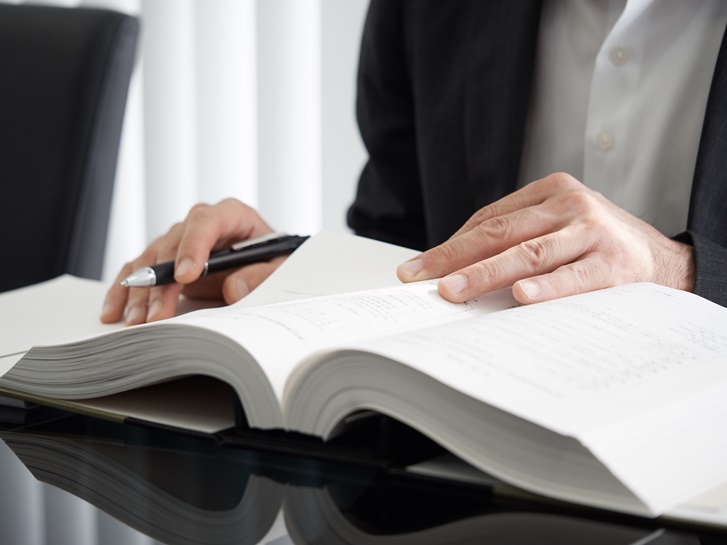
国内MBA飯野一講師に寄せられる、最も問い合わせの多い早稲田大学大学院経営管理研究科(WBS)・慶應義塾大学大学院経営管理研究科(KBS)・一橋大学大学院経営管理プログラム(SBA)について説明します。
最後は、一橋大学大学院経営管理プログラムです。
目次
特別コラム一覧
- 国内MBAの現在と過去
- 国内MBA予備校の現状と先行き
- 海外MBAとの比較&国内MBA履修形態の比較
- 国内MBAの難易度・倍率
- 国内MBAの評価と価値、活用方法
- 国内MBAの選び方
- 早稲田大学大学院経営管理研究科
- 慶應義塾大学大学院経営管理研究科
- 一橋大学大学院経営管理プログラム
- 国内MBAの未来
国内MBA試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 国内MBA試験の情報収集が大変
- 国内MBAに合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの国内MBA試験講座を
無料体験してみませんか?
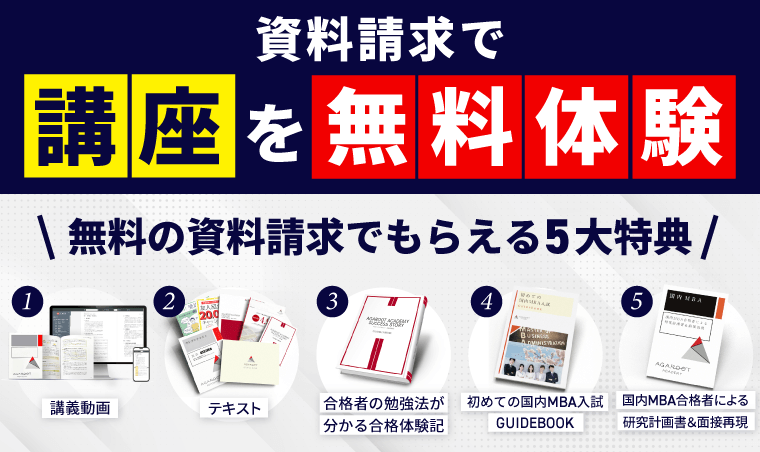
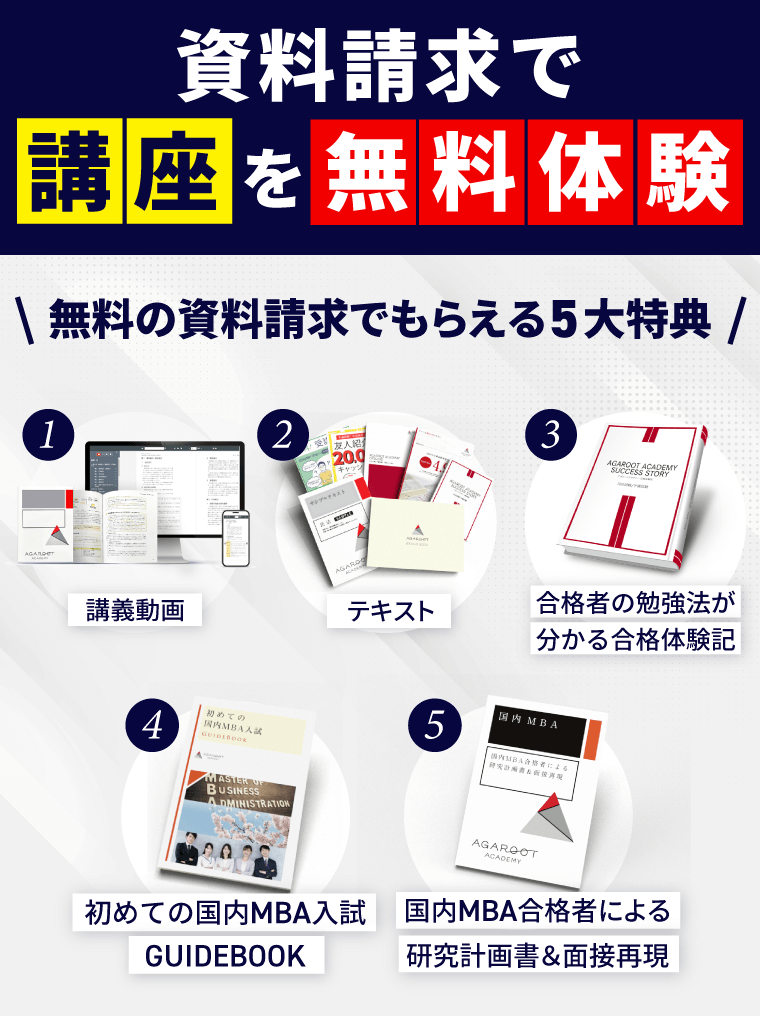
約4.5時間分の経営学の基礎講座が20日間見放題!
実際に勉強できる!国内MBA試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
国内MBA試験の全てがわかる!国内MBA試験ガイドブック
実例が満載!国内MBA合格者による研究計画書&面接再現
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る一橋大学大学院経営管理プログラムのコースについて
一橋MBAは2018年より商学研究科と国際企業戦略研究科が統合されて、経営管理研究科として生まれ変わりました。
3つのコースで成り立っておりまして、全日制の経営分析プログラム、夜間コースの経営管理プログラム、夜間でファナンスや計量分析を主に学ぶ金融・財務プログラムがその構成要素です。
ここではウインドミルに問い合わせの多い経営分析プログラムと経営管理プログラムについて説明します。
全日制の経営分析プログラムはレクチャー形式の講義がメイン
まず全日制の経営分析プログラムですが、こちらは従来の商学研究科の内容を踏襲したプログラムになっています。
慶應MBAがケースメソッドを採用しているのと対照的にケースでの授業はそれほど多くありません。レクチャー形式の講義が多くなっています。
最大の特徴は古典講読というプログラムが存在していることです。
これは他のどこの国内MBAにもない一橋MBAの大きな特徴になっています。経営学の古典と言われる書籍を読んで、その書籍の要約をしてレポートとして提出し、最後は授業でプレゼンテーションをおこなうのです。
要約だけでなく、古典を読んでそれが現在の事例に当てはまるかどうか?古典で述べられていることへの疑問点は何か?もレポートとして提出し、授業でプレゼンテーションをおこなうのです。古典として読まれている書籍は、バーナード、チャンドラー、スローンなどです。
筆者もバーナードの「経営者の役割」(ダイヤモンド社)は読んだことがあるが、非常に難解な本でした。
一度や二度読んだだけで理解できるものではないのです。一見平易な文章に見えても、大変深いレベルの含蓄のある文章が並んでいます。そのために、分厚い本を何度も読み返してやっと理解できるものなのです。
それを要約して、小論文を書いて、プレゼンテーションをするというのは非常に負荷の高い授業だと思います。
現在は社会人経験のない大学生や留学生の比率が高い
全日制の経営分析プログラムですが、以前は商学研究科として実施されていたことは先に述べました。
今から10年以上前の商学研究科は、社会人も多く在学し、大学生も多く在学する、という実務経験のない学生と社会人の割合がバランスが取れていました。
しかし、数年前から全日制に進学しても日本企業においてキャリアアップやキャリアチェンジにはそれほど有効ではないということが受験生にバレてしまってからは、社会人の学生が減少していきました。
その現象に歯止めをかけるために、一橋大学側は入試科目から英語を外し、小論文と研究計画書だけの入試に変えました。このような入試科目の変更をしても社会人学生の減少に歯止めをかけることができませんでした。そのために2018年から商学研究科と国際企業戦略研究科の統合が行われ全日制のMBAだけでなく、社会人を対象にした経営管理プログラムを開始したのです。
現在の経営分析プログラムは社会人経験のない大学生や留学生が非常に多くなっておりまして、リスクを取ってまで国内MBAに進学しようと考える方の減少を物語る結果となっています。
夜間の経営管理プログラムは情報が集まり次第お伝えします
次が夜間の経営管理プログラムに関してです。
こちらは2018年から開講されたばかりで筆者の方でもあまり情報がありませんので、今後経営管理プログラムに進学した受講生から情報を得てから加筆したいと思います。
今は書きませんがお許しください。
国内MBA試験の合格を
目指している方へ
- 国内MBA試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの国内MBA試験講座を
無料体験してみませんか?
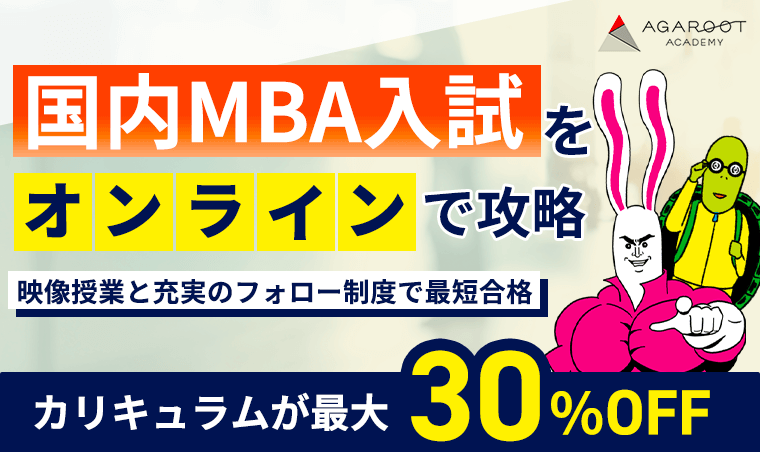
早稲田・慶應・一橋など難関MBA含む
2023年度の合格者147名!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
5月6日までの申込で10%OFF!
5月6日までの申込で10%OFF!
▶国内MBA試験講座を見る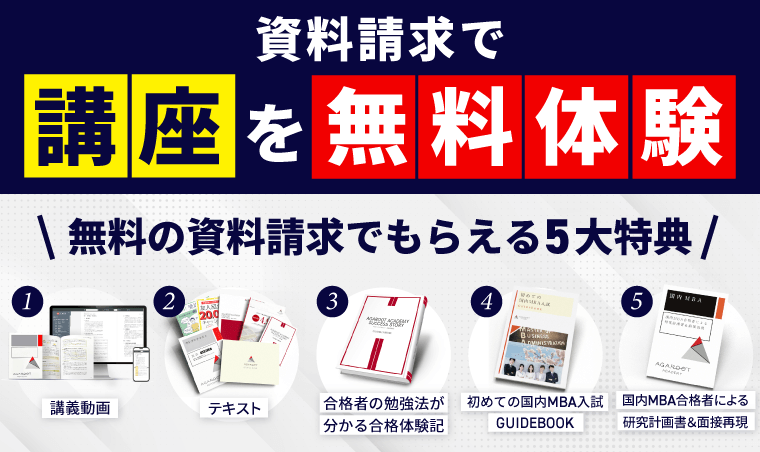
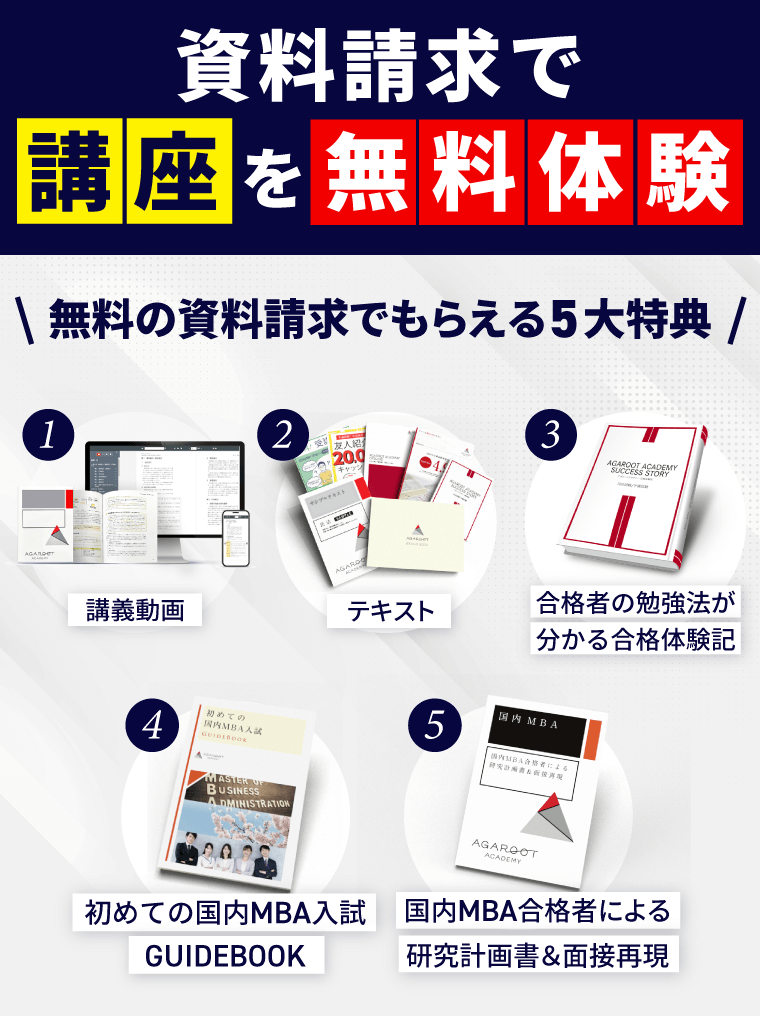
約4.5時間分の経営学の基礎講座が20日間見放題!
実際に勉強できる!国内MBA試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
国内MBA試験の全てがわかる!国内MBA試験ガイドブック
実例が満載!国内MBA合格者による研究計画書&面接再現
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
この記事の著者 飯野 一 講師
ウインドミル・エデュケイションズ株式会社で代表取締役を務めながら受験指導をおこない、約20年間にわたる指導経験を有する国内MBA受験に精通したプロフェッショナル講師。
国内MBAに関する書籍を多数出版し、ベストセラーを生み出している国内MBA受験に関する人気作家としての側面も持つ。
国内MBA修了生としては珍しい学術論文の学会発表、学会誌掲載の実績を持つ。
飯野講師の紹介はこちら



