東京都立大学MBA合格者の声|研究計画書の推敲作業はアガルートの添削による助言と合格者の研究計画書が非常に参考になった 荻原 佳祐さん
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

目次
受講されていたカリキュラム
下記リンクは最新版となります。合格者の方の受講年度と異なります。
MBAを目指したきっかけ
きっかけは、政府機関に2年間出向した際、学ぶことの面白さを改めて感じたことと、そこでの同僚や関係機関の方々の専門性や思考力に刺激を受けたことです。出向先は、同じ宇宙産業ではあったものの、分野が異なるため一から勉強する必要がありました。同僚や関係機関の方々は優秀な方ばかりで、追いつくのに苦労しましたが、学んでいくことで様々な気づきがあり面白かったです。
また、民間企業では新規事業に従事するときにフレームワークや戦略など必要に応じて調べながら取り組んでいましたが、ポイントの理解だけでなく、体系的に学んで全体感を掴みたいという考えが以前からありました。出向から元の企業に戻り、時間を確保できそうなタイミングを狙いMBAを目指すことにしました。
アガルートアカデミーを選んだ理由
アガルートアカデミーを選んだ理由の1つは、複数の予備校と比較してカリキュラムが充実しており、経営学の基礎から研究計画書の作成、面接対策までMBA受験に必要な要素をカバーできると考えたからです。合格者のインタビューでも、カリキュラムや教材に対する評価が高く、安心材料になりました。
もう一つは、MBAの合格実績です。複数の大学院に多数の合格者を輩出した実績があり、決して安くない予備校の授業料を払うのだから確実に合格したいと考えていました。
4月頃、MBA受験にあたり複数の予備校について調べ受験日までの勉強計画を逆算し、アガルートアカデミーであれば試験まで必要な対策が可能と考え選択しました。
勉強の方針とどのように勉強を進めていたか
①勉強の方針
一つ目が、計画的にコツコツと勉強することです。仕事に加えて、育児や家事をしながら限られた時間の中で勉強する必要がありました。合格体験記や合格者の研究計画書などから大学院の合格レベルをイメージし、試験までの勉強計画を立て実行しました。書籍とオンライン教材を併用し、移動時間などの隙間時間も活用しながら勉強に取組みました。
二つ目が、理解が及ばない部分があっても先に進み全体感を掴むことを重視したことです。抽象的な理論などすぐには理解が難しいなと感じることがあっても立ち止まるのではなく、何周か読んでいるうちにだんだん理解できると思いそのようにしました。
仕事やプライベートに時間を割かなくてはならない時期もあり、常に計画的に勉強できたわけではありませんが、進捗に応じて方向修正しながら取組みました。
②研究計画書のテーマ設定までの流れ
関心ある理論と自身の企業の課題とクロスする部分を研究テーマとして決定していきました。まずは、アガルートの経営学の基礎講座を受講してどういった経営理論があるのか把握しました。自身の企業で生じる経営課題を複数考え、そこから興味を持った経営理論との関連づけられないか考えました。当初は研究テーマとしては粗削りのため、研究テーマライブラリーでテーマ設定の着眼点を理解し、研究計画書の添削指導を受け、参考文献を読み込みながら研究テーマとしてふさわしい形にブラッシュアップしていきました。
③勉強のスケジュール
5月:出願書類、『研究計画書&面接再現』で合格までのイメージを整理。
6月:『経営学の基礎講座』、『出願書類・研究計画書の書き方』
7月:『経営学の基礎講座』、『出願書類・研究計画書の書き方』、『研究計画書の研究テーマライブラリ』、『小論文(基本編)』、『小論文(大学院別対策編)』
8月:『経営学の基礎講座』、『出願書類・研究計画書の書き方』、『研究計画書の研究テーマライブラリ』
9月:研究計画書の作成、添削(1回目)
10月:研究計画書の作成、添削(2回目)、『小論文(基本編)』、『小論文(大学院別対策編)』、出願書類の提出(併願校)
11月:『面接対策』、併願校が合格
12月:研究計画書の作成
1月:研究計画書の作成、出願書類の提出(都立大)、『小論文(大学院別対策編)』
2月:筆記試験(都立大)、口頭試問(都立大)
冒頭計画的に取り組むことを勉強方針と説明しましたが、実際には仕事などで忙しく時間を十分にとれず、研究計画書の作成は遅れ気味でした。研究計画書の完成度も高くない状況が続き、添削結果に落ち込むこともありました。「もっとも合否との関連が高い初稿から二稿の改善状態から、他校の併願を推奨いたします」と助言をもらったときは、相当まずいと理解しました。
改めて研究テーマを見直し、さまざまな参考文献を調査しました。過去の合格者の研究計画書や大学院の修士論文を読むなどして研究計画書を改善していきました。出願書類提出が近づくにつれ、夜寝るのが遅くなる傾向がありましたが、何度も推敲を重ねました。
ちなみに、当初は一橋大学院経営管理プログラムや法政大学経営学研究科を志望しており、秋は都立大を受験していませんでした。都立大は、研究計画書の量も多く、知識系の筆記試験もあるため受験対象からは外していました。試験勉強を進めるにつれて都立大の受験も可能そうであると判断し冬に出願しました。
受講された講座の良さ・当該講座の学習方法(使い方)
国内MBAの入試攻略講座のご感想・ご利用方法
国内MBAに受験するにあたり、どんな大学院があり、大学院ごととういう傾向があるのか、志望大学の検討や受験難易度の検討に役立ちました。内容が分かりやすいため、すらすら読めました。最初のMBA理解に役に立つと思います。
経営学の基礎講座のご感想・ご利用方法
経営学のベースの知識が不足していたので、経営学の基礎講座でどういった理論があるのかを理解しました。すんなり理解できない部分があっても、あとで理解できれば良いと思い、先に進めることを重視しました。研究計画書のテーマ検討の際には、このベースの知識をもと関心を持った理論を企業の課題と紐づけるような形でテーマ選定していきました。分かりやすい言葉遣いをしており、読みやすかったです。
出願書類・研究計画書の書き方講座のご感想・ご利用方法
テキストを読んで実際に過去合格した方がどのくらいのレベルなのか、合格レベルを理解する上で大変参考になりました。添削では時に厳しい(的確な)ご指導をいただきへこんだこともありましたが、おかげでしっかりやらねばと思えました。
研究計画書の研究テーマライブラリーのご感想・ご利用方法
研究計画書のテーマ選定にあたって、経営学の基礎講座のテキストを読むだけでは研究テーマの切り口として不十分だなと感じることがあったので、テーマライブラリーを見て、どういった切り口だと面白いのか考え方の参考にしました。
面接対策講座のご感想・ご利用方法
1度併願校の面接直前に面接を申し込みましたが、とても丁寧に良い点や改善点を指導してくださり、本番に臨む自身が付いたように思います。やはり一人では気づけない面を客観的に指摘いただける点が貴重だったと思います。MBA受験実績のある講師だったのでリアリティのある助言で参考になりました。
各種フォロー制度のご感想・ご利用方法
初回添削フィードバックは、まだ研究計画書の検討が十分ではなかったのであまり質問ができずもったいなかったなと感じています。もう少し自身の経験値があがって慣れてくると実践的な質問もできた気がしました。マンスリーゼミは、勉強の息抜きに参加出来ました。
スランプ・挫折、それを乗り越えるための工夫
納得のいく研究計画書の作成が出来ず、苦労した記憶があります。研究計画書の添削で、自身のレベルが至らないため仕方のないことですが、的確で厳しいご指摘をいただき、落ち込むこともありました。しかし、これを乗り越えないと合格はないと思い、諦めずなんども研究計画書を推敲を繰り返しました。助言のあったとおり、大学院生の研究テーマを調べたり、参考論文を数多く読んで研究分野の傾向や論文の書き方を学び、それを参考しながら少しずつ改善を繰り返すことで、何とか納得がいくレベルの研究計画になったのではないかと思っています。あの厳しいご指導がなければ、そこまで奮起できなかったかもしれません。
学習時間はどのように確保し、一日をどのように過ごしていたか
温かい時期は朝4時台に起床して、朝1~2時間程度勉強していました。電車などの移動時間も可能な時は、書籍かオンライン教材で勉強していました。
寒い時期は朝早く起床するのが苦手なので、子供を寝かしつけた後の夜の時間を利用して、勉強していました。妻も勉強していたので、休日は半分ずつ各自の自由時間として活用していました。自分が使える時間は出来るだけ有効活用できるよう前日にどんなことをするかイメージしておくことを心掛けていました。
1日中同じ場所だと集中力を切らしてしまう場合もあるので、休日は居心地の良いカフェで勉強することもありました。
直前期の過ごし方(どのような勉強をして、どのような心構えで試験を迎えたか)
出願期限直前は、研究計画書を何度もブラッシュアップしていました。合格体験記などから研究計画書に比重が置かれると分かっていたので、合格するには研究計画書を少しでも良い内容に出来るよう参考論文を読み込み、研究計画書を改善していきました。提出が近づくと、残りの日数から焦りもありますが集中力が増しました。複数校受験すると各校出願期限の度に集中期間が訪れるので、大変ではありますが、その分研究計画書の質の向上には良い機会であったように思います。
試験期間中の過ごし方
都立大は、複数回の試験形式は取らず、試験は1回のみです。出願書類、同日におこなう筆記試験と口頭試問の結果を総合して合否が決定となるため、出願後は筆記試験と口頭試問対策に集中して取り組みました。
都立大の筆記試験は複数の試験科目から1つの科目を選択して回答する形式です。私は経営組織論を選択するつもりでしたので、筆記試験対策は、都立大が公開する経営組織論のすべての過去問から出題傾向を分析するとともに、アガルートの回答例を参考に回答を作成し、何度も読み返しました。また、『はじめての経営組織論(有斐閣ストゥディア)』を読み、経営組織論に関して理解を深めました。なお、本書を選択した理由は、都立大のシラバスで経営組織の授業で利用しているテキストであり、過去の出題傾向から本書を理解しておけばおおよそ回答できると考えたためです。
受験した時の手ごたえと合格した時の気持ち
①受験した時の手ごたえ
口頭試問は、一部不十分な回答だったなと思う部分がありつつも、ある程度致命的な問題はなく回答が出来ました。
筆記試験は、過去の試験傾向から出題範囲を予測していたのですが、外してしまいました。少しやってしまったなと思いましたが、アガルートの経営学の基礎講座と『はじめての経営組織論』で学習していたので、問題ない程度には書くことができたと思います。
②合格した時の気持ち
合格結果の公開10分前ぐらいからそわそわしていました。Webサイトの合格者一覧で自分の受験番号を見つけたときは、嬉しい気持ちと、間違いではないかと自分の受験表と合格者一覧を見返してしまいました。一方で、これから勉強頑張らないとなという気持ちもわきました。
振り返ってみて合格の決め手は?また当該講座はどの程度影響したのか
①合格の決め手
決めては、他の合格体験記などでも示されていますが研究計画書であったと思います。研究計画書に評価の比重を置いているため、研究計画書が評価されこれが合格の決め手になったのではないかと予想しています。口頭試問、筆記試験はまずまずのできであったと予想しています。
②講座の影響度
研究計画書の推敲作業は、アガルートの添削による助言と過去の合格者の研究計画書が非常に参考になったと感じています。特に後者は合格ラインの目標ラインを把握や計画書の書き方について学びが大きかったです。
アガルートの面接対策の教材は、都立大とその他の大学院も含めて様々なケースを読みました。複数の面接パターンを実際に頭で想像することができ、想定問答の作成もはかどりました。
筆記試験対策は、アガルートの小論文添削講座(大学院別対策編)の回答例をもとに勉強することで、回答の書き方を学ぶことが出来ました。
この意味で、合格に対する講座の影響度はとても高かったように思います。
卒業後のキャリアについて
①MBAに期待するもの
ビジネスに関わる幅広い経営学の知識を体系的に習得でき、深い思考力を養うことが出来ると期待しています。経営に関わるには高度な分析力や戦略的な意思決定能力が必要と思いますが、MBAを通して経営学の知識や深い思考力を身に着けることで、今後のキャリアにおいて強みになると考えます。
②今後のキャリアビジョン
引き続き新規事業の開発業務に従事し、将来はイノベーションの創出につながる組織や仕組みの構築にも携わり、企業の成長に貢献したいと考えます。そのためには、大学院で経営に関する幅広い知識を体系的に習得し、基礎を身に着けたいとおみます。
受験生に対するメッセージ
アガルートの充実した教材の活用は合格の近道であると思います。MBA受験にあたり、何を勉強したらよいか分からない中で合格に向けた指針を示してくれるとともに、添削など合格までの力強いサポートがあります。仕事やプライベートでお忙しいかと思いますが、アガルートの教材を活用すればMBAの合格に近づけると思います。
もしMBAの予備校の選定で迷っている方がいれば、アガルートは間違いないと思いますので、ぜひ利用してみてください。
国内MBA試験の合格を
目指している方へ
- 国内MBA試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの国内MBA試験講座を
無料体験してみませんか?


約4.5時間分の経営学の基礎講座が20日間見放題!
実際に勉強できる!国内MBA試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
国内MBA試験の全てがわかる!国内MBA試験ガイドブック
実例が満載!国内MBA合格者による研究計画書&面接再現
合格戦略がわかる!飯野講師の著書『国内MBA入学試験パーフェクトガイド』
講師直伝!研究計画書の書き方解説動画
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る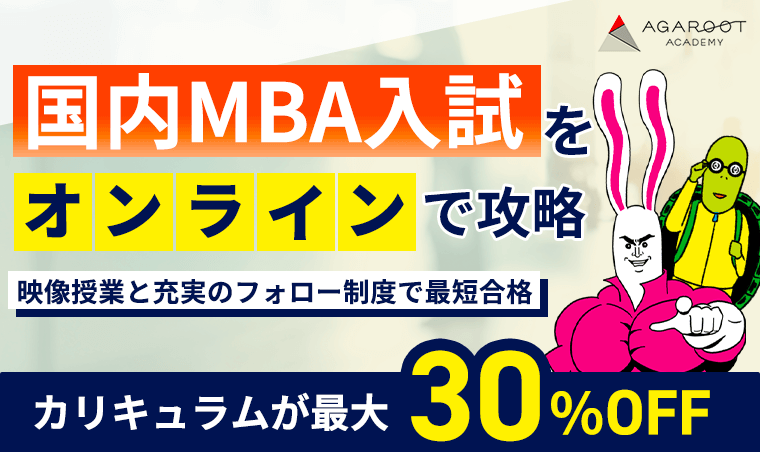
早稲田・慶應・一橋など難関MBA含む
2023年度の合格者147名!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
5月7日までの申込で5%OFF!
▶国内MBA試験講座を見る※2026年4月入学目標 秋入試対策カリキュラム
