電験三種の数学を完全攻略!必要な数学レベルや苦手でもできる勉強方法
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

「電験三種に必要な数学レベルはどのくらい?」
「数学が苦手でも合格できる?」
などの不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
本コラムでは、電験三種に必要な数学のレベルや科目ごとの出題内容、効果的な勉強法を解説します。
さらに、数学が苦手な方に向けた克服方法も紹介。
電験三種の数学に苦手意識がある方や効率的な勉強方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
第三種電気主任技術者試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの第三種電気主任技術者試験講座を
無料体験してみませんか?

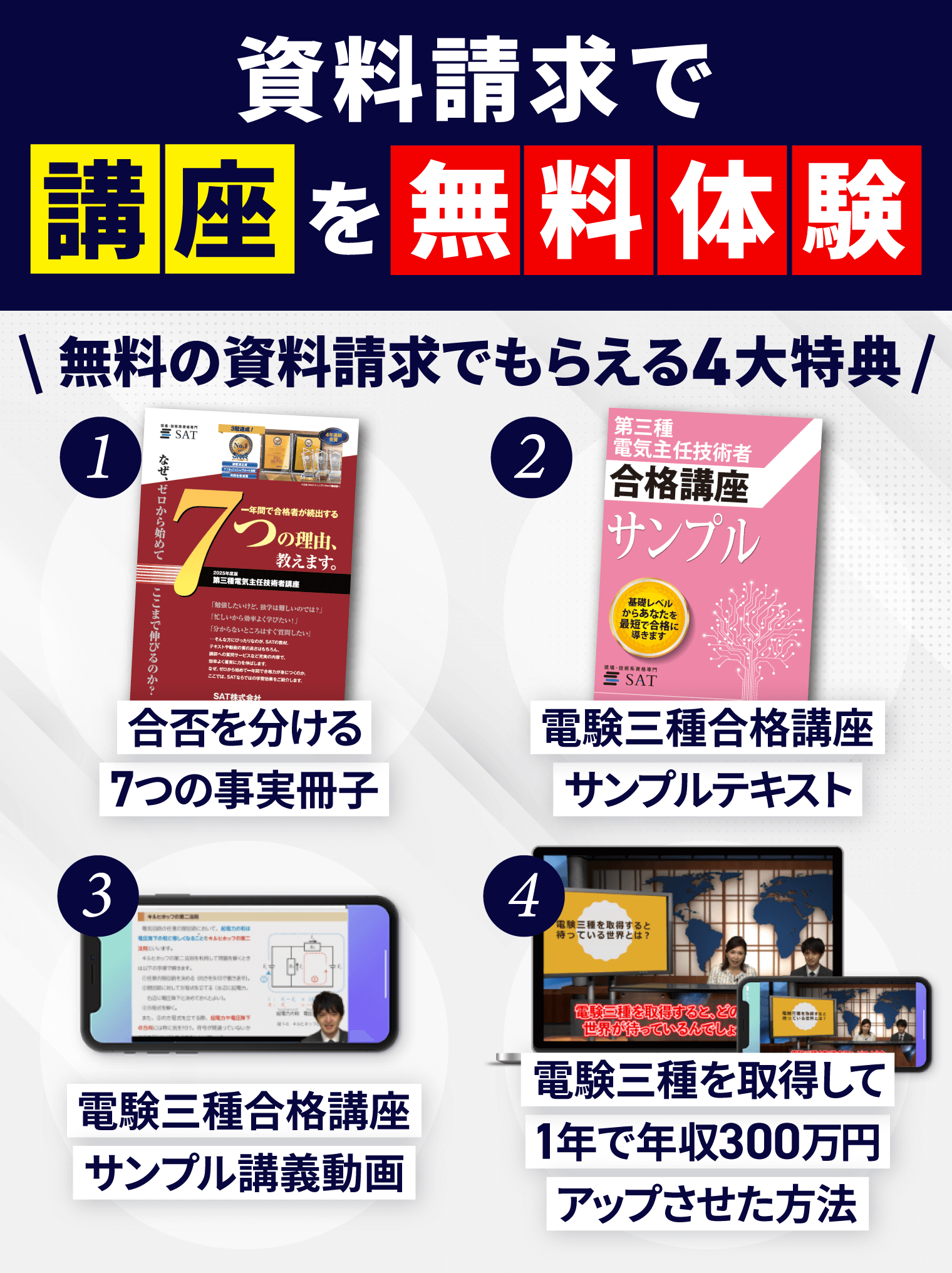
電験三種合格講座サンプル講義動画が視聴可能!
実際に勉強できる!第三種電気主任技術者試験のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
電験三種で求められる数学レベルは?
電験三種で求められる数学レベルは「高校1年生レベル」です。
電験三種の試験には、理論・電力・機械・法規の4科目があります。
電気の性質上、大きさや量を数値で表せなくてはならないため、すべての科目で計算問題が必須です。
とはいえ必要な数学レベルはあまり高くありません。
電験三種に特化した勉強をすれば、数学に苦手意識のある方でも十分に合格を目指せるでしょう。
電験三種で必要となる数学知識
電験三種で必要となる数学知識は次の6つです。
- 四則演算
- 分数
- 三角関数
- 指数
- ベクトル
- 複素数
四則演算
四則演算とは「足し算」「引き算」「掛け算」「割り算」です。
数学というより算数の分野に分類されますが、電験三種の試験では四則演算を正確にできることが必須となります。
計算ミスを防ぐために、日頃から四則演算に慣れておきましょう。
分数
電験三種の試験では、分数の計算が頻出します。
四則演算と同様、小学校で習う範囲ですが、分数の計算ルールがあやふやになっている方もいるでしょう。
数学からしばらく離れている場合、分数の基本的な計算ルールを思い出して、確実に計算できるようにすることが重要です。
特に、電気回路の合成抵抗の計算や電気の計算(繁分数)において分数の計算が必須となります。
分数の計算が正確にできないと大きく失点するため、重点的に復習しておいてください。
三角関数
三角関数は高校2年生で学ぶ範囲です。
文系に進んだ場合、三角関数を習っていないこともあります。
三角関数を理解していないと解けない問題が出題されるため、基礎からしっかりと勉強しましょう。
特に、電気の交流の計算問題で頻出するため、電験三種を受験するためには避けて通れない分野です。
指数
指数とは、数字の右上に載っている小さな数字のことで、一定の法則に従って計算を行います。
例えば「7²=7×7」「7³=7×7×7」のように、指数はかけ合わせる数字の個数を表します。
計算自体は四則演算と同じですが、指数法則を理解していないと正しく解けません。
中学の数学で学ぶ内容なため、忘れてしまった方は暗記をし直しましょう。
ベクトル
ベクトルとは、高校数学・高校物理で学ぶ「向き」と「大きさ」をもつ量のことです。
電験三種の試験では、交流回路の計算問題でベクトルが頻出します。
概念が曖昧なままでは理論や電力の計算問題が解けないため、しっかり理解し計算方法を正しく習得しましょう。
複素数
複素数とは、実数の組「a、b」を虚数単位「i」を使って「a+bi」の形で表し、ひとつの数として扱う場合の呼び方です。
電気数学で頻繁に登場する分野で、具体的には電圧(V)、電流(I)、インピーダンス(Z)を複素数を用いて表す「記号法」で頻出となります。
記号法を用いた計算では、複素数と複素数の計算方法の理解が不可欠です。
計算が複雑でも複素数を使いこなせれば、スムーズに解答を導き出せるでしょう。
電験三種の科目別で出題される数学分野
先述のとおり、電験三種の試験科目には「理論」「電力」「機械」「法規」があります。
ここでは、各科目で出題される数学分野を解説します。
理論
| 試験内容 | 電気理論、電子理論、電気計測および電子計測の3分野からの出題 |
理論では、直流回路・電磁気・静電気・交流回路・三相交流回路などが出題されます。
全体の8割以上が計算問題を占め、高校レベルの数学知識が必須です。
交流回路や三相交流回路では、三角関数や複素数を使った計算が必要になります。
理論はほかの科目の基礎となるため、最初に学びましょう。
電力
| 試験内容 | 発電所、蓄電所および変電所の設計および運転、送電線路および配電線路(屋内配線を含む)の設計および運用並びに電気材料の4分野からの出題 |
電力では、主に電力供給の流れに関連する電気系統の問題が出題されます。
理論で学んだ知識を活用すれば理解しやすいうえ、基礎的な内容が多く計算問題も4割と他科目より少なめなため、比較的合格しやすい科目です。
機械
| 試験内容 | 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送および処理に関する出題 |
機械では、発電や電気を利用する機械に関する深い知識が求められます。
最も難易度の高い科目とされ、学習範囲も広いため、時間をかけてしっかり学びましょう。
変圧器・直流機・誘導機・同期機などの分野の理解と、電動機・電気化学・自動制御などに関する専門知識の習得が必要です。
法規
| 試験内容 | 電気法規(保安に関するものに限る)および電気施設管理に関する出題 |
出題範囲には、電気設備の技術基準・電気工事士法・電気事業法・電気工事士法などの法令が含まれます。
法令の内容を理解することも求められるため、暗記をするだけでは不十分です。
穴埋め文章問題や正誤判定問題などに加えて、計算問題も出題されます。
法令に関する知識を覚えるだけではなく、内容を理解したうえでの実践力も必要です。
電験三種の数学の勉強方法
電験三種の数学の勉強は、3ステップで取り組むと効率的でしょう。
- 公式を暗記する
- アウトプットを繰り返す
- 過去問を最低10年分解く
公式を暗記する
電験三種の試験勉強で最優先すべきことは公式を覚えることです。
まずは電験三種の試験で必要となる公式を暗記しましょう。
公式は問題を解くための「道具」であり、試験では限られた時間で、いかに効率よく問題を解くかが求められます。
公式を知らずに問題を解くことは難しいため、しっかり覚えて使い方を理解しましょう。
電験三種に必要な公式は多く、すぐに覚えることは難しいかもしれません。
覚えるコツは、公式同士を関連づけて覚えること。
関係性を理解することで、記憶が定着しやすくなります。
もし忘れてしまっても、ほかの公式を使って思い出せるため安心です。
アウトプットを繰り返す
公式をある程度覚えたら、繰り返しアウトプットしましょう。
電験三種の数学を勉強するためのドリルなども発売されているため、教材を活用しながら実践的なスキルを身につけましょう。
アウトプットを繰り返すことで公式の使い方が身につき、問題を解くスピードがあがります。
学習効率の低下を感じたら、改めて公式暗記などに戻ってインプットすることも大切。
基礎知識の理解が不十分なまま進まないようにしましょう。
過去問を最低10年分解く
問題集などで勉強したら、過去問に挑戦しましょう。
過去問を解くことで、試験の出題傾向を把握し、本番の試験環境に慣れることができます。
時間を計って集中して解けば試験本番の緊張感を減らし、落ち着いて回答できるはずです。
過去問は最低でも10年分取り組むのがおすすめ。
ただ解いて終わりにせず、最低3回は同じ問題を解いて、しっかりと定着させることが大切です。
繰り返し解くことで、解法の流れや注意すべきポイントが習得できるでしょう。
数学が苦手・わからない方の克服方法
電験三種は高校レベルの数学の知識があれば合格可能です。
とはいえ、文系出身の方や数学の苦手な方は不安を感じるでしょう。
ここでは、数学が苦手・わからない方に向けて、電験三種の合格に向けた克服方法を解説します。
自分のレベルを把握しよう
まずは自分のレベルを正確に把握しましょう。
電験三種の問題集を解きながら苦手分野を探ってもOKですが、小中高の模試を活用すると自分の実力をより客観的にチェックできます。
模試の結果を確認することで、「分数の計算が苦手」「中学1年生レベルまでしか理解できていない」などといった具体的な課題が見えるでしょう。
数学は積み重ねが重要な科目なため、理解していない箇所は基礎から学び直すことで、確実に力をつけられます。
基礎の復習からスタートしよう
自分のレベルを把握したら、実力に合った基礎学習から始めましょう。
例えば、四則演算が苦手なら小学校レベル、関数の基礎が理解できていないなら中学校レベルの参考書を使い、基礎に立ち戻ってしっかりと復習します。
先述のとおり、数学は積み重ねの教科のため、基礎を着実に身につけることが苦手意識を克服する近道です。
基礎が習得できていない状態で、演習問題に挑戦しても、中々解けるようにはなりません。
焦らずに基礎から学び直し、インプットとアウトプットを繰り返すことが、電験三種に必要な数学力を養います。
通信講座を活用するのもおすすめ
独学では「どうしても無理!」という方は、通信講座を活用しましょう。
通信講座では合格に向けて最適なロードマップが組まれており、学習者が効果的にインプット・アウトプットを繰り返せるよう、手厚くサポートします。
また、学習を進める中で、わからない問題があっても自由に質問できるため、効率的に課題を解決しながら知識を定着させられます。
数学に苦手意識のある方にとって、講師の指導を受けられることや数学を基礎から学べることは、大きな安心材料となるでしょう。
まとめ
電験三種の試験に合格するためには、数学知識が不可欠です。
求められる数学レベルは高校1年生程度ですが、公式を覚えるだけではなく、繰り返しアウトプットを行うことで、確実に定着させましょう。
数学が苦手な方は、基礎から丁寧に学習し、演習を積み重ねることで克服できます。
ただし、独学では中々進まない場合もあります。
独学に不安を感じる方は、アガルートの第三種電気主任技術者講座がおすすめ。
電験三種に必要な数学を基礎から学べるカリキュラムで、効率的に学習を進められます。
第三種電気主任技術者試験の合格を
目指している方へ
- 第三種電気主任技術者試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの第三種電気主任技術者試験講座を
無料体験してみませんか?

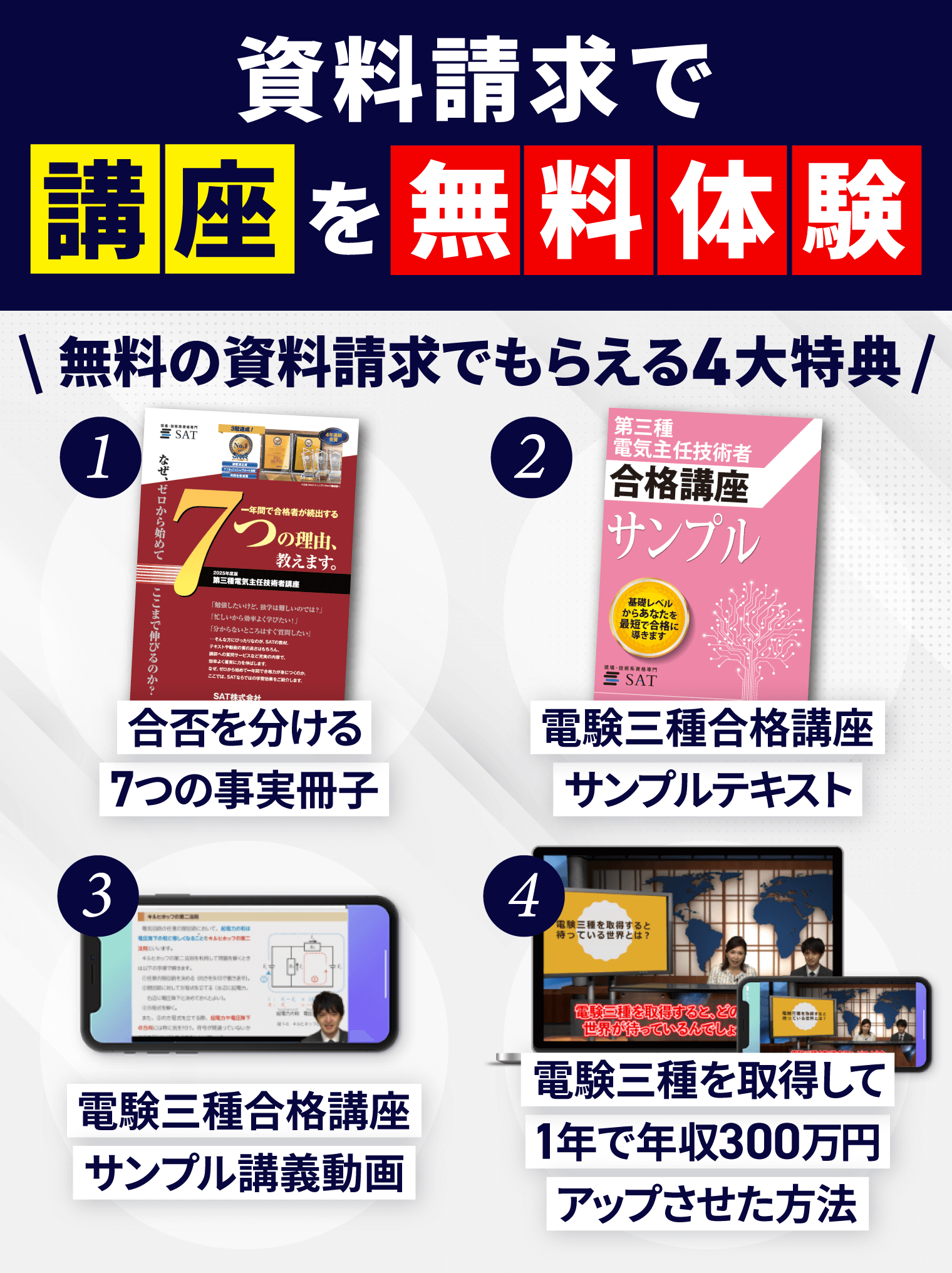
電験三種合格講座サンプル講義動画が視聴可能!
実際に勉強できる!第三種電気主任技術者試験のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る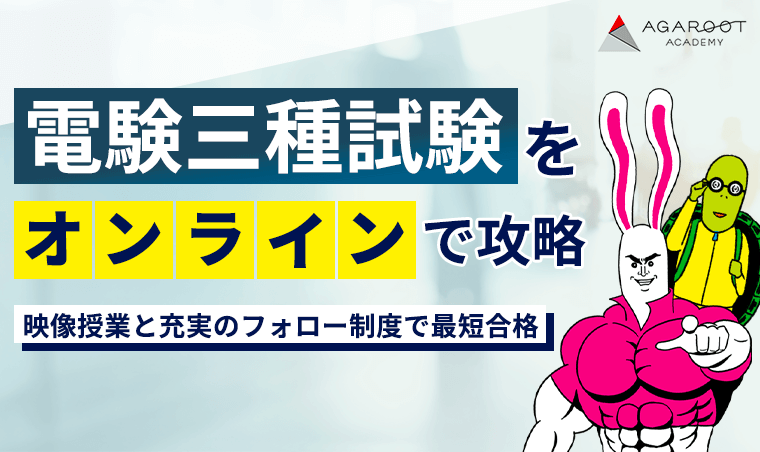
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
SATEラーニングシステムで学習状況が一目でわかる!



