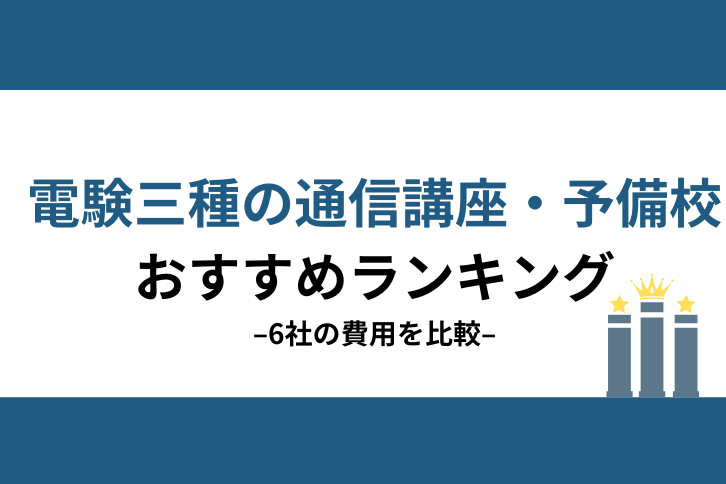電験三種試験の計算問題は捨てる?苦手を克服する4つの方法を解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

電験三種試験では、計算問題が非常に多く出題されるため、計算問題を捨てることはできません。
電験三種試験の科目は理論、電力、機械、法規の4科目。
計算問題の比率は科目によって異なるものの、少ない科目でも全体の4割、多い科目では8割以上を占めます。
特に理論科目においては、計算問題の割合が8〜9割に達します。
また、計算問題を解くために必要な学力レベルは、中学から高校の数学の理解が求められます。
したがって、電験三種試験に合格するためには、数学の基礎知識を確認し、計算練習をしっかり行うことが重要です。
第三種電気主任技術者試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの第三種電気主任技術者試験講座を
無料体験してみませんか?

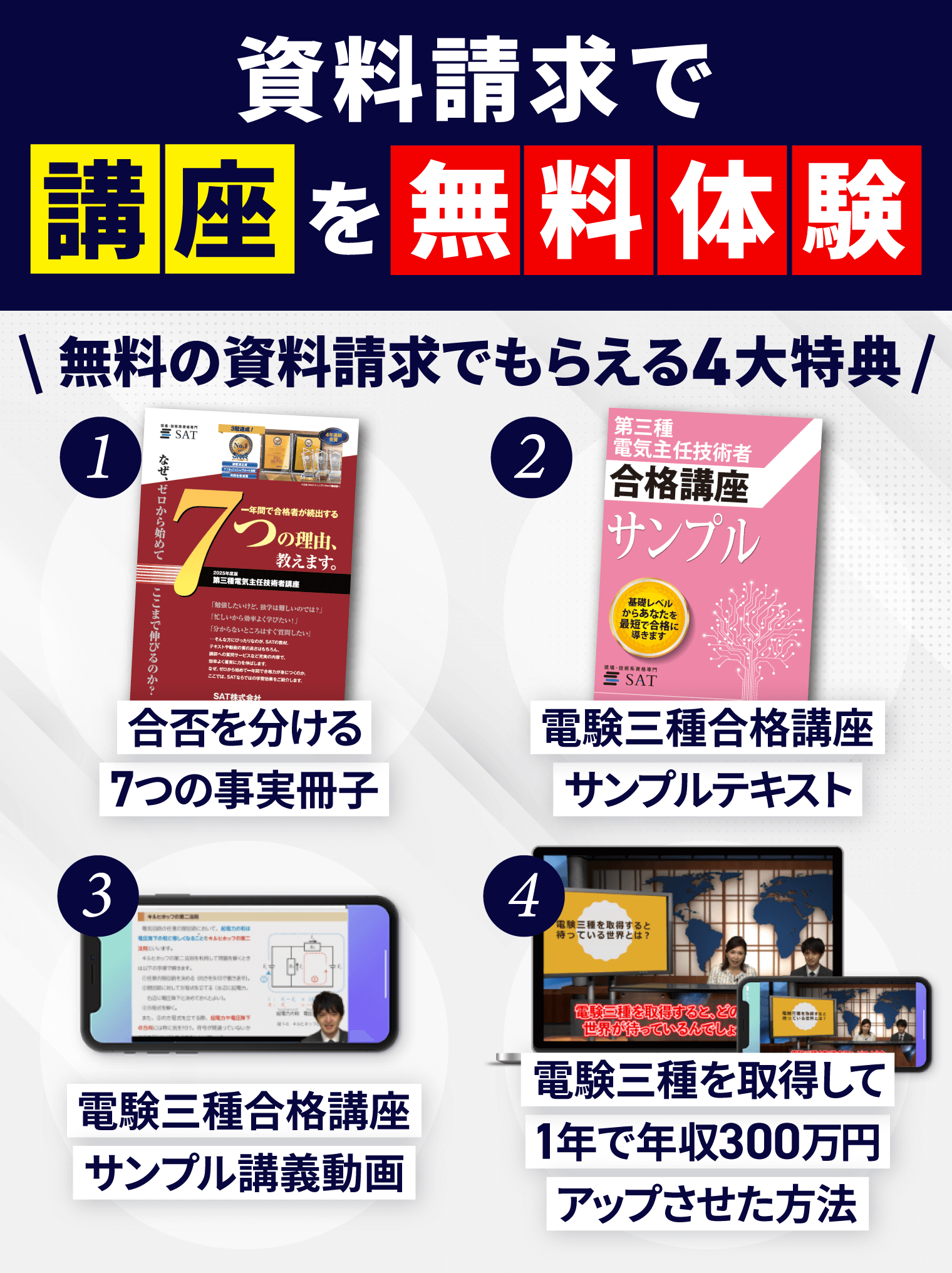
電験三種合格講座サンプル講義動画が視聴可能!
実際に勉強できる!第三種電気主任技術者試験のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
電験三種の計算問題で必要な基礎知識は?
電験三種の計算問題で求められる数学力は中学から高校レベルであり、電験三種の試験に必要な知識を習得すれば、数学が中高時代に苦手だった方でも、十分に合格が目指せるでしょう。
電験三種の計算問題で必要となる基礎知識は次の通りです。
- 四則演算
- 繁分数
- 三角関数
- ベクトル
- 指数
- 連立方程式
- 複素数
四則演算
四則演算とは、足し算・引き算・掛け算・割り算のことを指し、四則計算とも呼ばれています。
四則演算は日常生活の様々な場面で活用される算数の基礎であり、電験三種試験でも正確に行えることが求められます。
「左から順番に計算」、「掛け算や割り算を先に行う」、「カッコ内の計算を最優先する」などの基本的な計算ルールをしっかり覚えることで、電験三種の四則演算はクリアできます。
計算ミスを防ぎ、早く正確に計算できるように練習を重ねることが大切です。
繁分数
繁分数は、分母・分子のどちらか、あるいは両方が分数になっている分数のことを指します。分母だけが分数になっているものは連分数と呼ばれます。
繁分数は見た目が難しそうですが、実際には小学校で習った分数の計算を応用したものです。
具体的なやり方は、分母や分子に含まれる分数の分母がうまく相殺されるような数を分子や分母にかけることです。
要は約分。
この方法を使うことで、複雑な計算も簡略化できます。
なお、電験三種試験では、電気の計算で繁分数が頻出します。また、電気回路の合成抵抗を計算する際には分数の計算がよく出題されています。
三角関数
三角関数は、三角形の各辺や角度の間の関係を表す関数です。
電験三種試験で使うのは高校で習う、正弦(sin・サイン)、余弦(cos・コサイン)、正接(tan・タンジェント)です。
この3つの関数は、与えられた角度に対応する三角形の辺の比率を表します。文系の方ですと、三角関数を学んでいない方もいらっしゃるかもしれません。
電験三種の試験では、三角関数を理解していないと解けない問題が出題されますので、基礎からも勉強することが重要です。
ベクトル
ベクトルは、高校数学で習う向きと大きさのある量です。
有効線分で表され、矢印はベクトルの向きを意味し、長さがベクトルの大きさを表します。
電験三種試験の交流回路の計算問題で出題されます。
ベクトルを理解していないと、理論や電力の計算問題を解くことが難しくなりますので、十分に理解しておきましょう。
指数
指数とは数字の右上に書かれて、その数字を何度かけ合わせるかを示す数字や文字のことです。例えば「7²」は7を2回掛け合わせることを意味します。
指数は中学の数学で習いますが、計算自体は四則演算です。
ただし、電験三種試験の計算問題は、基本的な指数法則の習得が必須。指数法則は数学の基礎的な計算法則ですので、必ず暗記しましょう。
連立方程式
連立方程式は、複数の式を使い、複数の未知数の値を求める方程式です。連立方程式を解くための一般的な方法として、加減法と代入法が挙げられます。
電験三種試験で連立方程式を解く場合、加減法と代入法を組み合わせて解くと効率が良いでしょう。
連立方程式は、中学の数学で学びますが、過去に苦手だったり、忘れてしまったりしている方は再度復習することが必要です。
複素数
複素数は、実数と虚数の組み合わせで表される数で、一般的な形式は「a+bi」です。
aは実数部分を、bは虚数部分を表し、iは虚数単位でi²=-1です。
例えば、3+2iのような複素数では、3が実数部分、2iが虚数部分を表し、実数軸上では3の位置にあり、虚数軸上では2の位置にあります。
電験三種の電気数学では複素数を使う問題が頻出します。複素数は高校数学で習いますが、負の数やルート計算も含まれるため、苦手だった方も多いでしょう。
「2乗するとマイナスになる」という複素数の性質は、慣れるまで戸惑うかもしれませんが、段階を踏んで学んで行けば理解は難しくありません。
電験三種の計算問題のレベルは高校程度
電験三種の計算問題のレベルは、中学~高校程度です。
試験で必要な数学の知識は基礎的なものですが、数学が苦手な方にとっては難しいと感じることもあるでしょう。
しかし、実際に問題を解くことで、苦手意識を克服し、数学の基礎を身につけることが大切です。
幸いなことに電験三種の計算問題のレベルは難しいものでも高校程度ですので、時間をかけて勉強すれば必ず理解ができます。
高校までの数学の基礎を再度おさらいし、電験三種試験に必要な知識を着実に身につけましょう。
電験三種の計算問題の苦手を克服する4つの方法
ここでは、電験三種の計算問題の苦手を克服するための4つの方法を紹介し、電験三種の計算問題に対するアプローチを解説していきます。
- どのように考えて解くのか理解する
- 基礎問題と応用問題を繰り返し解く
- 毎日復習する習慣を身につける
- 通信講座を利用する
数学が苦手な方にとって、電験三種の計算問題は大きなハードル。
数学の苦手意識は、電験三種の学習進捗に大きな影響を与えます。
しかし、苦手意識を克服し、計算問題に自信を持つための方法はあります。
どのように考えて解くのか理解する
電験三種の計算問題に取り組む際は、単に答えを求めることに固執せず、どのように考えて解くかを意識することが不可欠。
これは、問題を解くプロセスを理解することが、真の理解であり、応用力も育てるからです。
さらに、なぜその計算が成り立つのかを考えて解くことで、計算の理解が一層深まるでしょう。
各公式、法則がどのような場合に使われるのか直感的にわかるようになることで、計算の根拠や背景について深く考えることができ、計算問題に対する洞察力が高まります。
基礎問題と応用問題を繰り返し解く
電験三種試験に合格するためには、まずは数学の基礎知識を確実に固めることが不可欠です。
その上で、基礎問題と応用問題を繰り返し解き、問題解決のスキルを磨きましょう。
電験三種の計算問題は、問題文から答えまでのプロセスを理解し、公式を用いて適切な式を立てる必要があります。
そして、その式をミスなく解き、正確な答えを導き出すことが求められます。繰り返し問題演習を行い、計算力・数学力を高めていきましょう。
毎日復習する習慣を身につける
重要なのは、毎日、問題演習を行い、前回学んだ内容を復習することです。
覚えるべき公式が非常に多い電験三種の計算問題。公式を丸暗記しようとすると、苦手意識が加速してしまいます。
問題を繰り返し解くことで、公式を自然と覚えられ、電験三種の計算問題に慣れていきます。
解けない問題や解説を見ないとわからなかった問題にはチェックをつけて復習し、解法プロセスを習得しましょう。
短時間でも良いので、計算問題に取り組む習慣をつけることが、合格への近道です。
通信講座を利用する
通信講座を利用することで、より効率的に計算問題を克服できます。
電験三種の試験は高難易度で、広範囲から出題されるので、独学での合格には多くの時間が必要です。
特に計算問題は高校までの数学知識が必要ですので、その復習には手間も時間もかかるでしょう。
数ある通信講座の中でおすすめはアガルートの第三種電気主任技術者講座。経験豊富なプロ講師が指導し、中学で学んだ数学の基礎から丁寧に解説します。
テキストもフルカラーで視覚的に理解しやすいので、電気や数学に苦手意識がある方も安心です。
最新のEラーニングシステムで、学習進捗管理・質問対応・テスト・暗記学習など全ての学習がスマホ一つで完結します。
講義時間が10分〜20分前後、かつ倍速再生機能付きですので、スキマ時間を利用してサクサク学ぶことが可能。
数学が苦手、計算が嫌いな方にこそ、アガルートの第三種電気主任技術者講座はおすすめです。
まとめ
電験三種試験では出題比率の高い計算問題が合否の鍵となるため、計算問題を捨てることはできません。
計算問題では数学の基礎知識が必要であり、三角関数、べクトル、複素数などの高校レベルの内容も含まれます。
そのため数学が苦手な方にとって電験三種の計算問題はかなり難しく感じるでしょう。
しかし、数学に苦手意識のある方も、数学の基礎を習得し、基礎問題と応用問題を繰り返し解けば、電験三種の合格は可能です。
反復学習による問題を解くプロセスの習得が、電験三種の計算問題の苦手を克服するでしょう。
電験三種の試験は難易度が高く、試験範囲も広いため、独学は厳しいです。
特に計算問題に関しては高校までの数学の知識が必要とされるため、独学ですと復習に時間と手間がかかってしまいます。
短期間で網羅的に学ぶなら、アガルートの第三種電気主任技術者講座がおすすめです。
現在、アガルートでは無料受講相談、資料請求でできる無料体験を実施中。
「電験三種試験に向けて、数学を中学から学び直したい」
「数学がとにかく苦手なので、講座についていけるか不安」
といった、ご要望・お悩みのある方はお気軽にご相談ください。
第三種電気主任技術者試験の合格を
目指している方へ
- 第三種電気主任技術者試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの第三種電気主任技術者試験講座を
無料体験してみませんか?

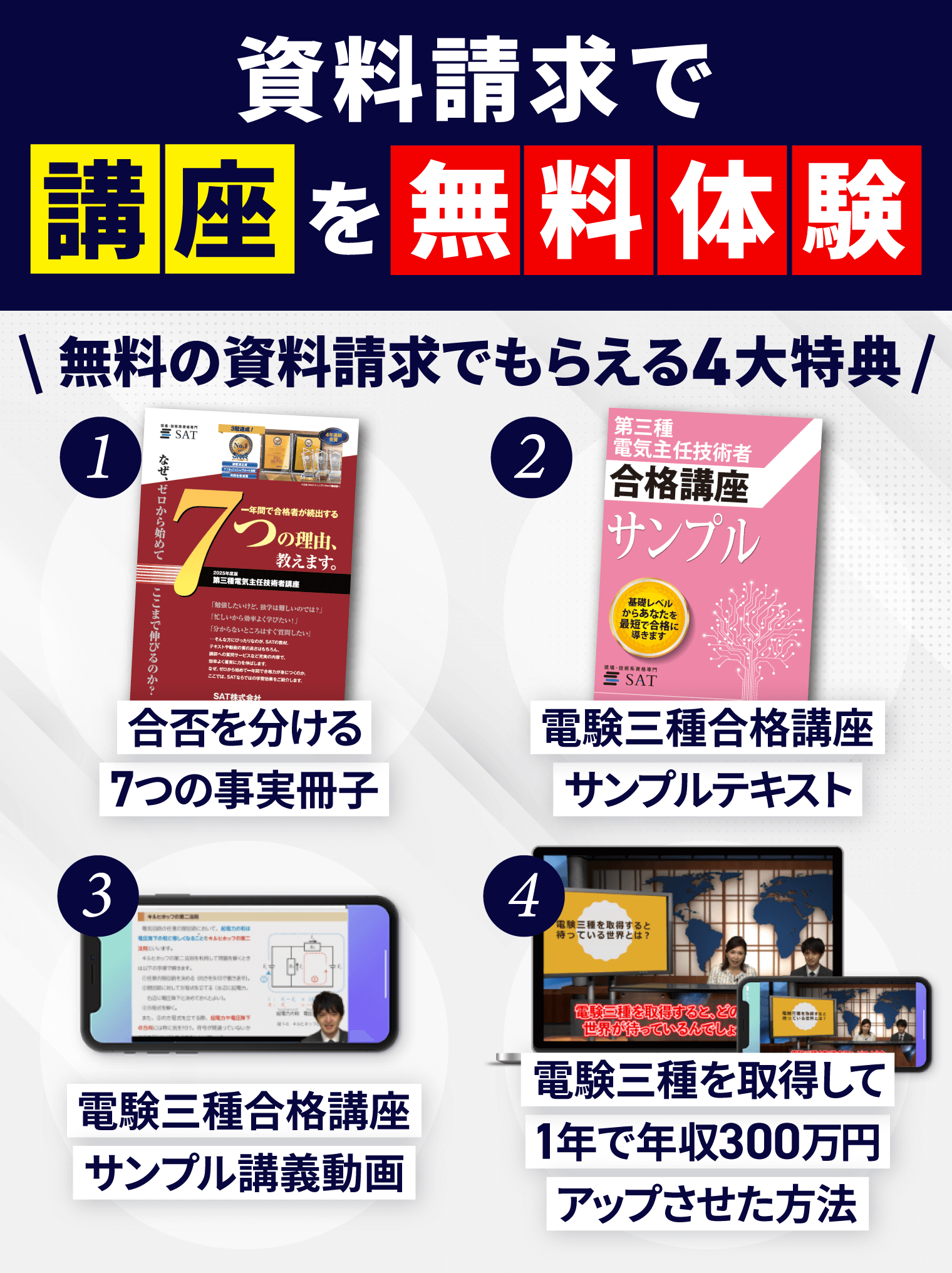
電験三種合格講座サンプル講義動画が視聴可能!
実際に勉強できる!第三種電気主任技術者試験のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る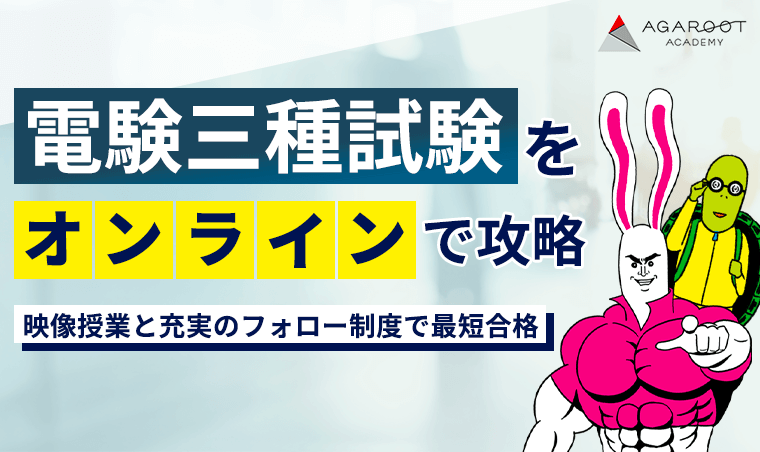
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
SATEラーニングシステムで学習状況が一目でわかる!