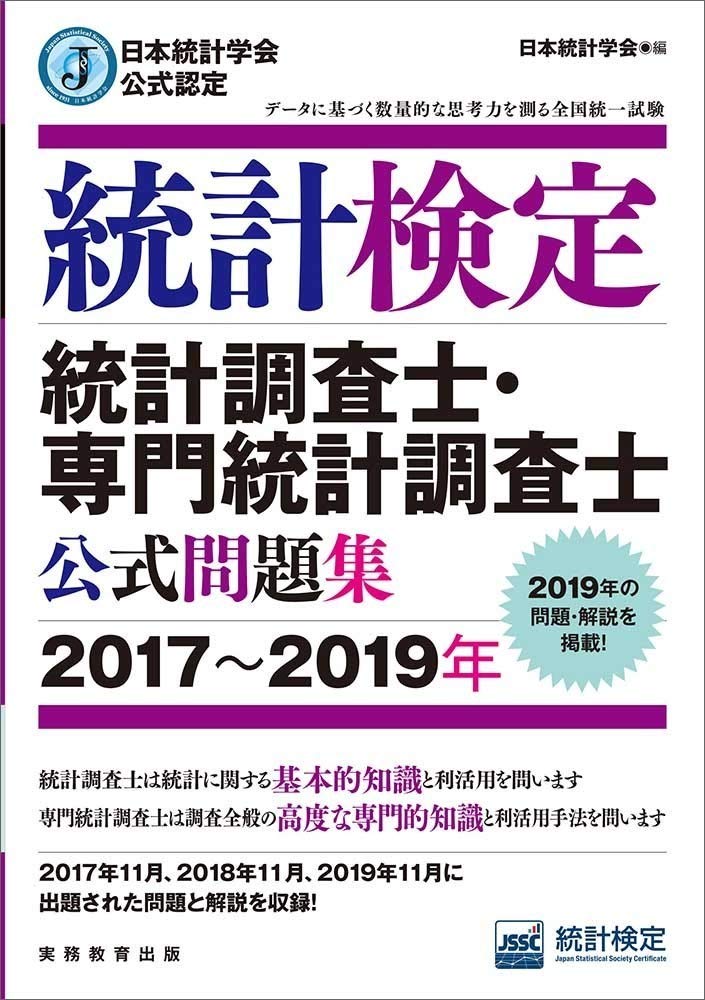統計調査士とは?基本情報、試験内容、難易度、勉強法をまるっと紹介!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

「統計調査士」は、一般財団法人である統計質保証推進協会が実施している「統計検定」の中の1つで、公的統計に関する基本的な知識を正確に認識し、適切に利用する能力を認定する資格です。
この記事では統計調査士について、試験の概要や学習方法について解説します。
目次
統計調査士とは?
統計調査士検定は、公的統計についての基礎的な知識を正しく理解し、適切に利用する能力を評価する検定試験です。
ちなみに統計調査士は、国家資格ではなく民間資格です。
統計調査士資格を取得することにより、統計検定3級合格程度の基礎知識と、社会人に求められる公的統計の理解を証明することができます。
統計調査士試験の内容は、大きく分けて「統計の基本」「公的統計調査の実務」「統計の見方と利用」の3つです。
それぞれ、統計学の基礎知識と公的統計に関連する法律、統計調査の手法とデータの取り扱いについて、統計処理についての計算やグラフなどのデータの読み取りについて問われます。
統計調査士は、マーケティングや資料における適切なデータの見せ方など、統計学を実際のビジネスに活かす視点となっているのが特徴です。
統計調査士資格は基礎的な資格であるため、それのみで仕事の幅が増えたり転職に有利になるようなことはありません。
ですが、統計調査士の勉強を通じて、アンケート調査の注意点や、資料を作る際の適切なグラフの選択方法、データの読み取り方など、ビジネスに活用できる知識を習得することができます。
統計調査士と専門統計調査士の違い
統計調査士資格の上位資格として「専門統計調査士」があり、専門統計調査士の受験資格を得るためには統計調査士資格の取得が必要です。
統計調査士と専門統計調査士の違いは、以下の通り。
専門統計調査士の方が、問題数や試験時間も多くなっています。
| 統計調査士 | 専門統計調査士 | |
|---|---|---|
| 問題数 | 30問 | 40問 |
| 試験時間 | 60分 | 90分 |
| 合格基準 | 70点以上 | 65点以上 |
| 受験料(税込) | 一般価格:7,000円 学割価格:5,000円 | 一般価格:10,000円 学割価格:8,000円 |
| 試験内容 | 統計検定3級合格程度の基礎知識に加えて、社会人に求められる公的統計の理解とその活用力の修得を評価します。 | 統計検定2級合格程度の専門知識に加えて、社会・経済で広く利用される統計や各種の調査データの作成過程、および利用上の留意点などに関する総合的な知識水準を評価します。 |
「統計調査士」は統計調査の業務で必要とされる知識と技能を認定する資格に対して、「専門統計調査士」は組織にあって統計調査を企画、運営する能力を認定する資格という違いがあります。
専門統計調査士はリサーチャーなどの業務で募集要項に挙げられることもあるため、統計調査士はその足がかりとしても重要な資格です。
求められる数学知識
統計調査士試験の内容には、統計検定3級程度の数学知識が含まれます。
これは高校数学レベルの内容であるため、数学的には難易度が高くありません。
試験内容も、高度な計算問題よりは知識を問う問題が多いため、文系出身で高度な数学に馴染みのない場合でも無理なく学習できる内容です。
統計調査士資格を取得するメリット
統計調査士は統計学をビジネスに活かすことに主眼を置いた資格です。
そのため、マーケティングのような仕事はもちろん、一般的なビジネスにおいてもグラフの作成や読み取りなど、データの取り扱いについての基本的なリテラシーを高めることができます。
世の中には、標本の数が十分ではなかったり、恣意的に数字を用いたデータも多いです。
統計調査について学び、知識を深めることによって、そのような不適切なデータを見抜けるようになったり、自身が意図せず発信してしまう事態を防ぐことができます。
また、統計調査士資格を取得することによって、上位資格である専門統計調査士の取得の足がかりになる点も大きなメリットです。
さらに、合格後に発行されるオープンバッジを名刺や履歴書に掲載することができるため、学習・スキルの証明書としてアピールすることも可能です。
専門統計調査士はビジネスでも活かせる資格であるため、キャリアアップにつながります。
統計調査士の年収は?
統計調査士の資格は、あくまで統計に関する知識や技能を証明するものなので、資格を取得した方の職種や業界、経験年数、役職などによって年収は大きく異なります。
そのため、具体的な年収を算出することは難しいですが、転職サイトでは450万円~700万円程度の求人を見つけることができました。
ダブルライセンスに相性の良い資格
統計調査士と併せて取得するメリットが大きい資格に、中小企業診断士があります。
中小企業診断士の業務では経営環境分析やアンケート調査を行うことも多く、統計の知識が必要です。
説得力の高いデータを示すためにも、その調査背景や範囲を理解し正しい解釈をする必要があります。
統計調査士資格の勉強を通じ、それらの能力を効率的に身につけることができます。
また、統計調査士は公的統計について取り扱う資格ですので、行政・自治体などで業務をおこなっている方にも相性が良い資格と言えるでしょう。
統計関連業務に直結することはもちろん、統計調査の知識を深めることによるデータへの理解度向上や、日常業務への活用などが期待できます。
統計調査士の試験内容
| 名称 | 統計調査士 |
| 受験日程 | 通年 |
| 出題形式 | CBT(5肢選択問題) |
| 受験料(税込) | 一般:7000円 学生:5000円 |
| 問題数 | 30問程度 |
| 試験時間 | 60分 |
| 合格点 | 正答率70% |
統計調査士試験は、試験会場のパソコン上で5択の中から選択肢を選ぶCBT形式の試験です。
電卓の持ち込みが認められており(関数電卓等は不可)、計算が必要な問題も出題されることがあるため、使い慣れた電卓を持参すると良いでしょう。
出題される問題数は30問程度で、試験結果は試験終了後すぐにレポートとして確認することができます。
また、統計調査士試験の試験日については、全国にある試験会場で試験が実施され、会場によって日程が異なります。
広い会場であればほぼ毎日試験を受け付けているケースもありますが、一方で地方や小規模の会場の場合、試験日が限られているので事前に試験日をチェックしておきましょう。
出題の傾向
統計調査士試験で出題される問題のうち、およそ半分程度が知識を問う問題で、のこり半分が計算問題となっています。
数学が重視される統計検定の中では比較計算が少なくなっているのが特徴的です。
出題範囲は下記の通りです。
| 統計の基本 | 統計の意義と役割 |
| 統計法規 | |
| 統計調査の実際 | 統計調査の基本的知識 |
| 統計調査員の役割・業務 | |
| 公的統計の見方と利用 | 統計の見方 |
| 統計データの利活用 |
試験時間は60分と短い印象ですが、問題数が30問程度であり、知識問題が半数を占めるため、時間が不足することはないでしょう。
計算問題ではあまり難しい計算は出題されません。
一方、知識問題に関しては詳細な内容を問う設問もあり、細かな部分も理解しておく必要があります。
統計調査士の難易度・合格率
統計調査士試験は統計検定3級程度の数学知識に加え、公的統計についての理解度が問われます。
内容は基礎的なものが多く、統計調査士試験の難易度は高くはありません。
高度な計算問題が出題されず、知識を問う問題が半数を占めることから、 文系・理系を問わず挑戦できる資格です。
で統計調査士試験の合格率を見てみましょう。
| CBT方式 | 合格率 |
|---|---|
| 2024年 | 22.9% |
| 2023年 | 64.4% |
| 2022年 | 67.1% |
| 2021年 | 67.6% |
| 2020年 | 75.8% |
| 2019年 | 82.5% |
CBT方式の試験が導入された2019年の合格率は80%以上という結果になりましたが、2021年以降65%程度の合格率を推移しています。
そして、2024年の合格率はなんと22.9%。合格率を大幅に下げています。
ちなみに統計調査士試験は、紙媒体を利用した従来の試験(PBT方式試験)が終了して全てCBT方式の受験に移行したので、PBT方式の合格率は2021年まで公開されています。
参考までにPBT方式の過去5年の合格率はこちらです。
| PBT方式 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 172 | 147 | 107 | 72.80% |
| 2020年 (試験中止) | ー | ー | ー | ー |
| 2019年 | 536 | 450 | 240 | 53.30% |
| 2018年 | 579 | 495 | 274 | 55.40% |
| 2017年 | 490 | 424 | 230 | 54.20% |
2021年の合格率は28.9%と高くはありませんが、それ以前は50%台で推移しています。
合格率のみで比較すると統計検定3級よりは難しく、2級よりは易しい、中間程度のレベルといえるでしょう。
統計調査士の勉強方法
統計調査士は、公式の学習用テキスト・過去問題集が出版されています。
特に学習用のテキストについては公式以外の書籍がほとんど出版されていないこともあり、まずはこの本の内容を一通り学習することをお勧めします。
効率のいい学習方法は以下の流れです。
- 公式テキストに一通り目を通す
- 過去問を解き、理解できていなかったところをチェックする
- 問題の解説を確認し、テキストの該当項目を読んで理解を深める
- 繰り返し過去問を解き、知識の穴を埋めていく
知識問題については応用的な内容は出題されないため、上記の流れで問題なくカバー可能です。
国が行う公的な調査結果についての理解と調査設計の仕方について多く出題される傾向にあるため、これらの範囲についてはよく確認しておきましょう。
計算問題については統計検定3級程度の内容を理解し、スムーズに計算ができる必要があります。
代表値や標準偏差、場合の数、確率といった内容については関連する語句を理解し、基本的な計算が解けるようにしておきましょう。
統計調査士の勉強時間
統計調査士の勉強時間は、初学者であれば30〜40時間程度です。
統計検定3級合格程度の基礎知識に加えて、社会人に求められる公的統計の理解とその活用力を測る試験のため、統計検定3級程度の内容をすでに学習している人であれば10〜15時間程度が目安になります。
まとめ
統計調査士は、公的統計を正しく理解しビジネスに活用する能力を評価する検定試験です。
統計調査士の資格がキャリアアップに直結するという訳ではありませんが、アンケート調査やデータの作成・読解など、直接業務に活かせる内容も多く、学習統計が注目されている昨今では有用な資格です。
上位資格である専門統計調査士はビジネスや転職にも活用できる資格ですので、本記事を参考に、まずは本資格の取得から目指してみてはいかがでしょうか。

この記事の著者 アオミ ソウ
薬学系大学院の修士課程を主席卒業後、大手製薬企業で有機合成・データサイエンス関連業務に従事(専門は生物有機化学)。
現在は研究の傍ら、ライターとして記事の執筆・イラストの制作を行っている。
主な執筆分野はサイエンス(医療、生化学、情報科学)をはじめ、ガジェット、資格など。
保有資格
2018年 危険物取扱者甲種
2021年 データサイエンス数学ストラテジスト(上級)
2021年 応用情報技術者