G検定とE資格の違いは?難易度や両方を取得するメリットを紹介
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

どちらもAI関連の検定資格として知られるG検定とE資格。
運営団体や学習分野が共通することなどから混同されることも多く、「どう違うの?」「どちらを受検すべき?」など気になっている方もいるでしょう。
当コラムではG検定とE資格の違いについて、難易度や必要な勉強時間などの各項目から詳細に分析します。
受検を検討している方はぜひ参考にしてください。
G検定の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートのG検定講座を
無料体験してみませんか?

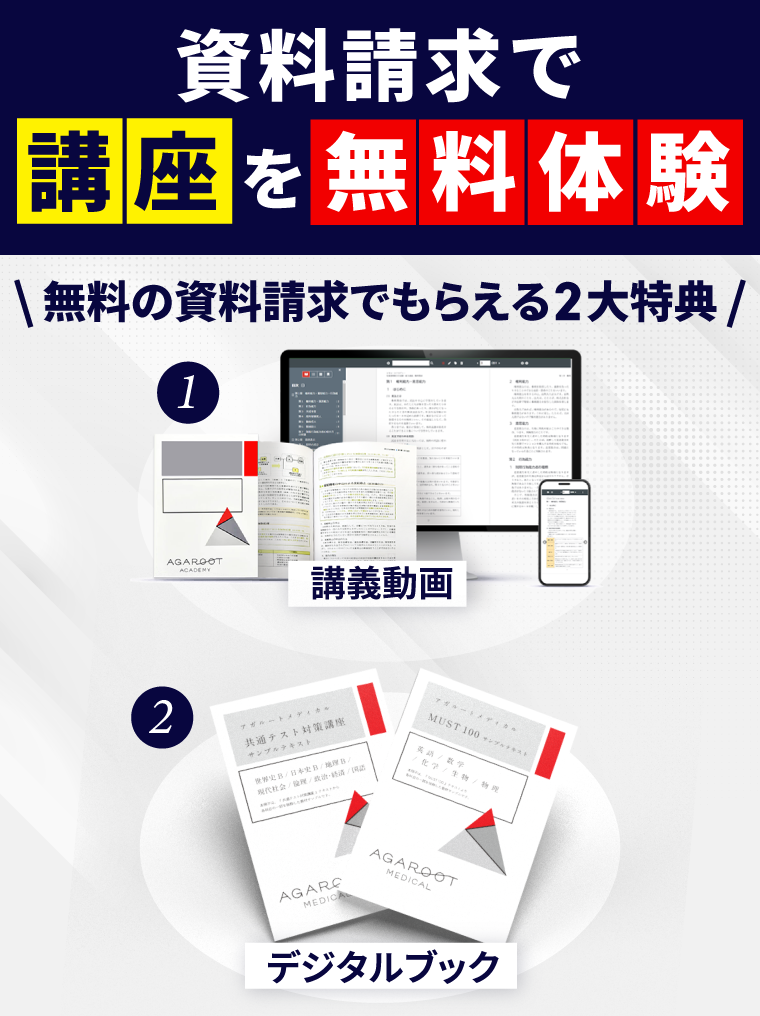
約3時間のG検定やDS検定、数学ストラテジスト資格試験対策講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!講義に対応したレジュメ(PDF)付き
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
G検定とE資格の概要
ここでは、G検定・E資格の違いについて、それぞれの概要や難易度などを取り上げながら解説します。
G検定とは
| 資格名 | G検定(ジェネラリスト検定) |
| 運営団体 | 一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA) |
| 資格種別 | 民間資格 |
| 受験料 | 一般:13,200円 学生:5,500円 ※2年以内に再受検する場合は半額 |
| 出題形式 | 多肢選択式 |
| 問題数 | 160問程度 |
| 試験時間 | 120分 |
| 試験会場 | オンライン(IBT) |
| 試験日 | 年6回・奇数月(1・3・5・7・9・11月)に実施 |
| 勉強時間 | 15〜70時間 ※独学の場合、少なくとも30〜40時間とされることが多い |
| 合格率 | 55〜75% |
| 難易度 | 普通 |
G検定はAIに関する知識を問うもので、2017年スタートの比較的新しい民間検定です。
AIやディープラーニング関連の技術や法令、ビジネス面での活用などが主な試験範囲となり、合格できれば「AIの基礎知識がある人材」であることを証明できます。
あくまで基礎知識を問う検定のため難易度は手頃で、受検資格などもないためAI関連のエントリー資格として受検する方も増えています。
オンライン受検が導入されており、年に複数回実施されるなど全体的に受検しやすい点も魅力的です。
E資格とは
| 資格名 | E資格(エンジニア資格) |
| 運営団体 | 一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA) |
| 資格種別 | 民間資格 |
| 受験料 | 一般:33,000円 学生:22,000円 協会会員:27,500円 |
| 出題形式 | 四肢選択式 |
| 問題数 | 100問程度 |
| 試験時間 | 120分 |
| 試験会場 | 各地の指定試験会場(CBT) |
| 試験日 | 年2回(2・8月) |
| 勉強時間 | 100〜200時間 |
| 合格率 | 60〜70% |
| 難易度 | 難しい |
E資格はAIエンジニア向けの民間資格です。
G検定と同じく日本ディープラーニング協会が運営しており、国内のAI関連資格の中では最高難易度の検定として知られています。
E資格では、ディープラーニングの理論に対する数式レベルで深い理解や、適切な手法で実装できるスキルがあるかが問われるのが特徴です。
もともとがプロ向けの検定であるため専門性が非常に高く、受検には指定の認定プログラムの修了が必要。
合格はG検定よりも難しいといえます。
G検定とE資格の違い
ここでは、G検定とE資格の違いについて、以下の項目で解説します。
- 難易度の違い
- 必要な勉強時間の違い
- 受験資格の違い
- 試験内容の違い
- 出題形式・問題数・試験時間の違い
- 受験方法の違い
- 試験実施頻度の違い
難易度の違い
G検定とE資格を難易度の面で比較すると、E資格の方が「難しい」です。
どちらも合格率は60〜70%ほどと高い水準で推移していますが、実態にはかなりのギャップがあります。
まず誰でも受検可能なG検定に対して、E資格は受検前にJDLAの認定プログラムを修了する必要がある点が特徴。
内容の専門性もE資格の方が高く設定されています。
そもそも試験対象者が異なるため、E資格の方は「ある程度経験を積んだエンジニアであれば60〜70%合格できる検定」といえるでしょう。
一方、G検定は問われる知識も基礎レベルであるなど、「しっかり勉強すれば初心者でも合格を目指せる」検定といえます。
G検定の方が試験範囲が「浅く広い」ため、両方を受検したい場合は最初にG検定を受ければ無理なくレベルアップできるでしょう。
必要な勉強時間の違い
合格に必要な勉強時間を比較すると、以下のようになります。
- G検定:30〜40時間
- E資格:100〜200時間
G検定・E資格ともに必要な勉強時間は個人の前提知識や経験などによっても変わりますが、一般的にはE資格の合格にかかる時間の方が長め。
E資格はそもそもエンジニアとしてある程度経験を積んでいる人を対象としているため、高度な知識を習得するために相応の時間をかける必要があります。
一方、G検定は技術面や関連法、ビジネス知識など範囲こそ広いものの、内容的には手頃。IT未経験者であっても100時間はかからずに履修できる人が多いでしょう。
もちろん、趣味でAIを利用したことがあるなど前提知識をもっている場合は、さらに短い時間で合格レベルまで到達できる可能性もあります。
受験資格の違い
G検定には特別な受験資格はありません。
一方、E資格はJDLA認定の教育プログラムを試験日の過去2年以内に修了している必要があります。
E資格には自分でプログラムを筆記してAIを「実装」する力も問われますが、本試験の出題ではスキルを判定できません。
そこで実技試験を含む特別な教育プログラムの受講を義務づけ、試験と合わせて「知識と実装力」の両方を認定する形を取っています。
教育プログラムの実技試験では、機械学習のアルゴリズムを受講生自らが実装する必要があります。
試験内容の違い
G検定・E資格のそれぞれにおける試験内容は、目的や対象者などによって以下のような違いがあります。
- G検定:AI・機械学習の基礎知識を証明。AIをビジネスに活用したい人向け
- E資格:AI・機械学習モデルの実装スキルを証明。エンジニア向け
G検定ではAIや機械学習に関連する基礎知識を、仕組みや関連法なども含めて広く扱います。
「AIをビジネスで効果的に活かすための手法」に主眼が置かれているため、IT専門職以外の職種やDX推進者も対象です。
「AIを使ってマーケティングや営業を効率化したい」「DX推進にあたって関連法も押さえたい」といった場合に受検したい検定といえるでしょう。
一方、E資格はAIシステムを実際に実装するスキルを問われるエンジニア向けの検定です。
受験前に受講が求められる学習プログラム内でも、アルゴリズムの実装試験をクリアする必要あり。
実際に現場でシステム開発などを担当している人や、エンジニア志望者などが主な対象となります。
出題形式・問題数・試験時間の違い
G検定とE資格では、どちらも多肢選択式で問題が出題されます。
試験時間も同じで、120分間の設定です。
しかし、問題数はG検定が圧倒的に多数。
E資格の出題は100問程度ですが、G検定では例年160問ほど出題されます。G検定の広い試験範囲が、問題数にも反映されているといえるでしょう。
単純計算で、1問あたりにかけられる時間はE資格では「1分12秒」・G検定では「45秒」となります。
特にG検定は時間配分がシビアなため、本番を意識した演習を繰り返しておくとよいでしょう。
受験方法の違い
受検方法については、それぞれ以下の方式で実施されます。
- G検定:IBT(Internet Based Testing)
- E資格:CBT(Computer Based Testing)
G検定で採用されている「IBT」はインターネット経由で受験する方式で、自宅のパソコンなどから受験が可能なため利便性に優れます。
通信速度などが個人の環境に依存するため公平性などに課題はありますが、試験結果がすぐわかるなどメリットも大きいです。
E資格の「CBT」は各地の試験会場に設置されているコンピュータから試験を受ける形式です。
全受検者を同一の条件で受検させることができますが、指定会場での受検のため一度に受検できる人数には限りがあります。
希望者の多い会場は早めに締め切られてしまう可能性もあるため、受検を決めたら早めに申し込むとよいでしょう。
試験実施頻度の違い
一年間の試験実施頻度で比較すると、G検定は6回・E資格は2回と、G検定の方が高頻度です。
頻度差の理由としては、以下の通り考察できるでしょう。
- G検定は自宅受検が可能なため会場の準備などが必要ない
- E資格はG検定と比較して専門性が高く、受験者数もG検定よりも少ない
G検定は例年1月から11月までの奇数月に実施されます。
一度の受検で不合格だった場合も2年以内に再受検する場合は受検料が半額になるため、年に6回のチャンスを確実に活かしましょう。
G検定とE資格の違い早見表
こちらでは、G検定とE資格の違いを比較できる早見表を作成しました。
| 資格名 | G検定 | E資格 |
| 運営団体 | 一般社団法人日本ディープラーニング協会 | 一般社団法人日本ディープラーニング協会 |
| 資格種別 | 民間資格 | 民間資格 |
| 受験料 | 一般:13,200円 学生:5,500円 ※2年以内に再受検する場合は半額 | 一般:33,000円 学生:22,000円 協会会員:27,500円 |
| 出題形式 | 多肢選択式(IBT) | 四肢選択式(CBT) |
| 問題数 | 160問程度 | 100問程度 |
| 試験時間 | 120分 | 120分 |
| 試験会場 | オンライン | 各地の指定会場 |
| 試験日 | 年6回・奇数月(1・3・5・7・9・11月)に実施 | 年2回(2・8月) |
| 勉強時間 | 約30~40時間 | 約100~200時間 |
| 合格率 | 55〜75% | 60〜70% |
| 難易度 | 普通 | 難しい |
G検定とE資格はどっちを受けるべき?
ここではG検定とE資格の特徴に基づき、「どちらの検定を受けるべきか」について解説します。
G検定がおすすめな人
以下のような人であればG検定がおすすめです。
- AIの基礎知識があることを証明したい人
- AIを用いる業務に携わりたい人
- IT業界未経験の人・学生
AIの基礎知識があることを証明したい人
G検定はAIや機械学習に関する基礎知識を証明する資格のため、AIの基礎知識があることを証明したい人におすすめです。
基礎知識のカバー範囲には、AIの仕組みのようなシステマチックなことから関連法・ビジネスへの活用方法といった内容まで含まれます。
AIには個人ユーザーも多いため、「知識がある」の内実を明確に証明することは意外に難しいもの。
G検定合格者となれば、「しっかり学習を積んで確かな知識を得た人材」であることを対外的に証明することができます。
特に、「なんとなく使ってきた」レベルの人とは明確に差別化できるでしょう。
AIを用いる業務に携わりたい人
G検定は、将来的にAIを用いる業務に携わりたい人におすすめです。
G検定はAIをビジネス活用できる人材の認定を目的としており、取得の過程で技術面から業務への活用事例まで幅広い知識を身につけられます。
営業や企画、マーケティングなどの業種でAIを取り入れたい場合、取得しておけば確かな知識のもとでDXを進められるでしょう。
最近では従来の業務にAIを導入する企業も増えているため、G検定を取得しておくことでIT専門職以外の部門でも優遇される可能性も高いです。
IT業界未経験の人・学生
G検定は受検資格がなく、試験範囲も基礎レベルの部分をメインとしているため、IT業界未経験の人におすすめです。
特に、今後IT業界での就業を検討している学生の方には最適。
G検定には学生料金が設定されているため、「就職活動を始める前に汎用性の高い資格がほしい」といった場合はとりあえずでも受検しておいて損はありません。
E資格がおすすめな人
以下のような人であればE資格がおすすめです。
- AIエンジニアを目指す人
- IT業界で通用する資格がほしい人
- ディープラーニングの実践スキルを身につけたい人
AIエンジニアを目指す人
E資格はAIや機械学習の実装スキルが身につけられるため、AIエンジニアなど、より専門的な業種を目指す人におすすめの資格です。
もちろん、すでに現職のエンジニアとして就業している方がさらなるスキルアップを目指して受検することもできます。
E資格は事前の学習プログラムで実技課題をクリアすれば受検できるため、実務経験が浅い方でも挑戦できます。
専門性の高い知識が必要でしっかりとした試験対策は必須ですが、取得できればハイレベルなエンジニアとして活躍する道が開けるはずです。
IT業界で通用する資格がほしい人
E資格はIT業界で通用する資格がほしい人におすすめです。
E資格は、AI関連の資格の中でも難易度の高いものとして広く知られています。
経歴によっては、IT関連の企業に「即戦力」として歓迎される可能性もあるでしょう。
特に、別業界からIT分野を目指したい場合は最初にE資格を取得しておけば転職時に役立てられるでしょう。
「別の業界にいたが難しい資格に合格した」という経歴を得ることで、ポテンシャルや業務への関心の高さを効果的にアピールすることもできます。
ディープラーニングの実践スキルを身につけたい人
E資格はディープラーニングの実践スキルを身につけたい人におすすめです。
特に就業を目指しているわけではなくても、AIが役立つ場面はたくさんあります。
「個人ユーザーだがもっと効果的にAIを使いたい」といった場合は、E資格に挑戦することでより高レベルな知識を得られるでしょう。
近年ではDXを積極的に推進している企業も多いため、IT業界に限らず「E資格をもっている」ことで社内評価が上げられる可能性もあります。
まとめ
当コラムでは、G検定とE資格の違いについて以下の内容で解説しました。
- G検定はAI関連の基礎知識を問う民間検定。受験資格などはなく、難易度は中程度。
- E資格はAIの実装スキルを問う民間検定で、受験には指定の学習プログラムを修了する必要あり。難易度は難しい。
- G検定は年に6回・E資格は年に2回受検できる。
- G検定がおすすめの人は、主に「AIの基礎知識があることを証明したい人」「AIを用いる業務に携わりたい人」「IT業界未経験の人・学生」。
- E資格がおすすめの人は、主に「AIエンジニアを目指す人」「IT業界で通用する資格がほしい人」「ディープラーニングの実践スキルを身につけたい人」。
G検定とE資格はどちらもAI関連の検定ですが、目的や専門性の面で大きな違いがあります。
汎用性の面ではG検定・専門性の面ではE資格がより優位。
AIを業務で広く活かしたい場合はG検定、AIエンジニアなど専門的な業種に進みたい場合はE資格を目指すとよいでしょう。
G検定の合格を
目指している方へ
- G検定に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートのG検定講座を
無料体験してみませんか?

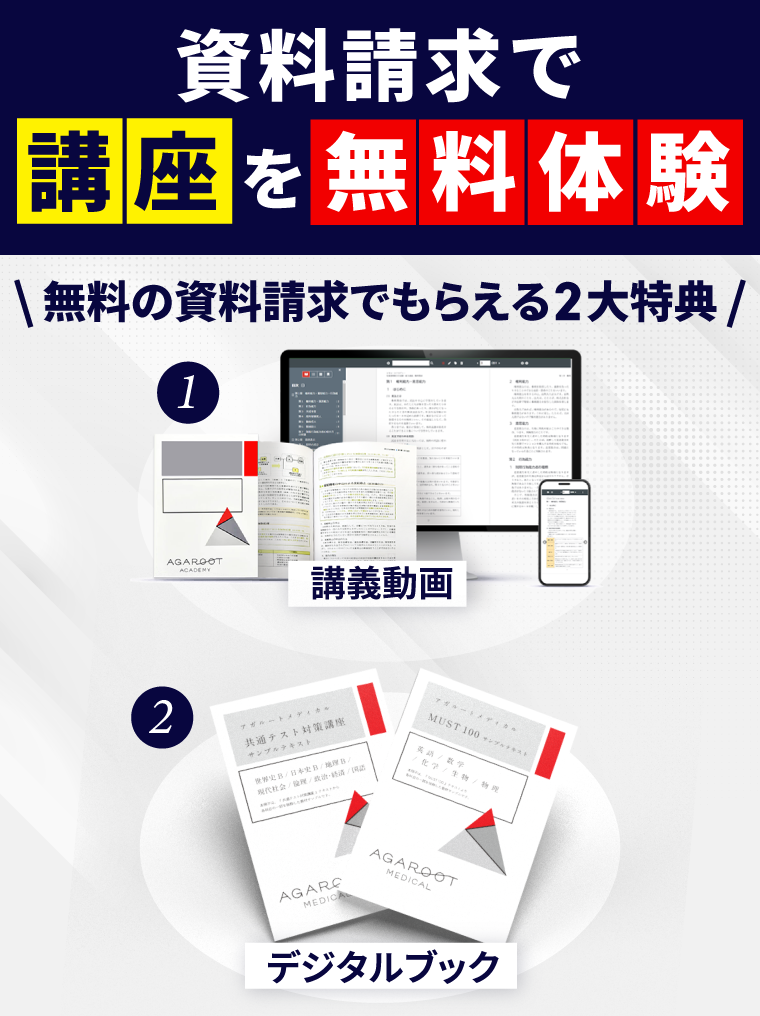
約3時間のG検定やDS検定、数学ストラテジスト資格試験対策講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!講義に対応したレジュメ(PDF)付き
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
全額返金の合格特典付き!
▶G検定講座を見る



