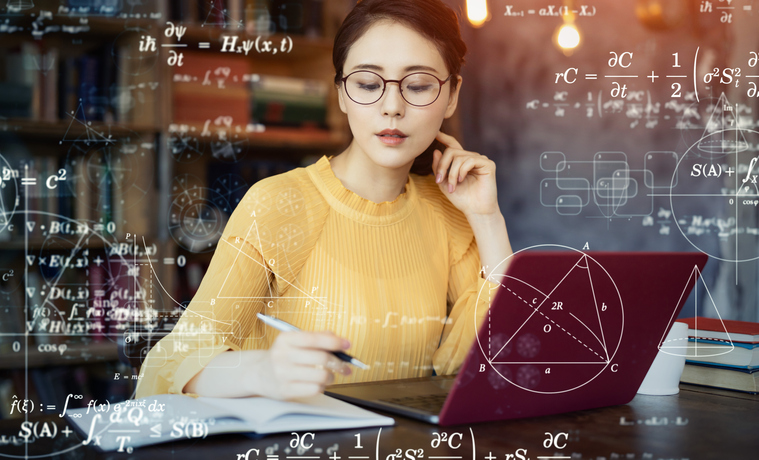統計検定準1級とは? 難易度や勉強法・勉強時間、参考書類を紹介!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

「統計検定準1級」は、一般財団法人である統計質保証推進協会が実施している「統計検定」の中の1つで、2番目に難易度の高い資格です。
一般にも認知度が高く、試験範囲に機械学習などの分野も広く取り入れられるなど、非常に実用的な資格となっています。
この記事では統計検定準1級について、試験の概要や学習方法について解説します。
目次
統計検定準1級とは?
統計検定とは、一般財団法人である統計質保証推進協会が実施している検定で、統計に関する知識や活用力を評価する検定試験です。
統計検定準1級は、その中でも実践的な資格となっており、実社会の様々な状況に対して適切な統計学の手法を応用し、問題解決に導くことができる能力を問うものとなっています。
難易度としても統計検定の中では2番目に難しくなっており、パソコンを使用して受験するCBT形式の試験の中では最上位の資格です。
内容は統計の各種手法について幅広い知識を問うものとなっており、統計学の応用分野的な立ち位置である機械学習についての内容もカバーされています。
データを解析し問題解決に導く能力を客観的に証明してくれるため、ビジネスでも高く評価される資格です。
受験者の年齢分布は20代後半から30代が多くなっており、実務経験の豊富な層が多く受験していることが読み取れます。

参考: 受験者の年齢分布(PBT方式)
求められる数学知識
統計検定準1級の内容を理解するには、大学専門課程(3-4年)レベルの数学知識が必要です。
統計検定2級で求められる数学が大学教養(1-2年)レベルであったのに対し、難易度が大幅に上がっています。
統計検定2級相当の知識は理解していることを前提に、さらに幅広い検定手法の理論と解釈方法を問われる試験となっており、統計検定2級までに含まれる範囲に関しては「本当に理解できているか」を問う内容が出題されます。
計算問題に対応するためにも、試験範囲を理解し深い知識を身に付けるためにも、微分積分や線形代数の基礎は最低限身につけておく必要があります。
統計検定準1級を取得するメリット
統計検定準1級では実務に役立つ知識を身に付けていることを示すことができるため、就職・転職活動でもアピールすることができます。
特に統計検定準1級まで取得している方は比較的少ないため、合格すれば大きなアピールポイントとなるでしょう。
面接官からも「統計検定準1級を取得しているのはすごい」と評価してもらえる可能性があります。
統計検定準1級の試験内容
| 資格 | 統計検定準1級 |
| 受験方法 | CBT |
| 試験日 | 任意 |
| 受験料(税込) | 一般:8,000円 学割:6,000円 |
| 出題形式 | 5肢選択問題、数値入力問題 |
| 問題数 | 25問~30問 |
| 試験時間 | 120分 |
| 合格点 | 100点満点で60 点以上 |
| 受験資格 | なし |
| 出題範囲 | 統計検定準1級出題範囲表 |
以前は筆記のPBT方式の試験のみで年一回の開催でしたが、2021の6月よりPBT試験が終了し、統計検定準1級は、完全にCBT方式の試験に移行となりました。
試験中に必要な計算には四則演算や百分率、平方根の計算ができる電卓を使うことができます(関数電卓は使用不可)。
計算問題も多く出題されるため、使い慣れた電卓を忘れず持参するようにしましょう。
出題される問題数は30問程度で、結果は試験終了後すぐにレポートとして確認することができます。
試験時間は120分で、1問あたり約4分程度の計算になります。
1問当たりにかけられる時間が多いように見えますが、統計検定準1級では複雑な問題も多いため、公式の導出や見直しの時間もふまえると試験時間にあまり余裕はありません。
難易度の高い設問に引っかかると時間が足りなくなってしまうこともありますので、解ける問題から確実に回答していきましょう。
統計検定準1級の特徴として、機械学習領域の出題が多いことが挙げられます。
試験の趣旨自体が「実社会の様々な問題に対し統計学を応用できる能力を問う」とされている通り、実践的でビジネスなどに役立てられる内容となっています。
統計検定準1級の試験日は?
上記でも解説しましたが、統計検定準1級は、2021の6月よりPBT方式の試験が終了し、完全にCBT方式に移行となりました。
そのため、統計検定準1級は、全国にある試験会場で試験が実施され、希望する会場で受験できます。
試験日は会場によって異なりますので注意しましょう。
例えば、首都圏や広い会場であればほぼ毎日試験を受け付けているケースもありますが、一方で地方や小規模の会場の場合、試験日が限られているので事前に試験日をチェックしておきましょう。
統計検定準1級の難易度・合格率
統計検定準1級は難易度が高い試験です。
統計学の手法や理論についての深い理解を求められるだけでなく、試験範囲が非常に広くなっていることが高い難易度の一因となっています。
ここで統計検定準1級の合格率を見てみましょう。
| CBT方式 | 合格率 |
|---|---|
| 2024年 | 35.5% |
| 2023年 | 35.3% |
| 2022年 | 35.9% |
| 2021年 | 34.8% |
直近の統計検定準1級の合格率は35%程度を推移しています。
ちなみに統計検定準1級は、紙媒体を利用した従来の試験(PBT方式試験)が終了して全てCBT方式の受験に移行したので、PBT方式の合格率は2021年まで公開されています。
参考までにPBT方式の過去4年の合格率はこちらです。
| PBT方式 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月 | 1,061 | 704 | 166 | 23.6% |
| 2020年(試験中止) | – | – | – | – |
| 2019年6月 | 1,314 | 853 | 179 | 21.0% |
| 2018年6月 | 1,001 | 643 | 130 | 20.2% |
PBT試験の合格率は例年20%ほどで、統計検定2級の半分程度の合格率でした。
基本的には試験範囲の公式テキストを学習すれば解答可能な問題ですが、全体の2割程度、相当な実力が要求される難問が出題されます。
統計検定準1級では成績優秀者の表彰をおこなっているため、受験者の点数差をつけるための措置だと予想されます。
全体の出題傾向としては浅く広い出題になっており、幅広い試験範囲から満遍なく問題が出る傾向にあります。
「易問2〜3割、難問2割」程度が含まれ、残りの半分程度はワークブックを完璧に解ければ対応できる難易度の問題が出題されています。
難問は相当な実力が要求されるため、優先的に解く問題と後に回す問題の見極めが重要です。
統計検定2級と比較すると一気に出題範囲が広がり、難易度が上がるため、いきなり統計検定準1級を受験するのは難易度が高いです。
数学・統計学が得意な方でもまずは統計検定2級あたりから力試しをしてみるのが良いでしょう。
統計検定準1級の例題
統計検定準1級では、データを読み取る読解問題のほか、母集団の推定、検定 、標本の集め方の正誤問題、確率の計算問題などが出題されます。
例題1)

2021年6月試験問題 (PBT)
統計検定準1級では、機械学習に関連した問題がほぼ毎回出題されています。
例題のようなデータを可視化した結果を選択する問題のほか、文章による用語説明を穴埋めする知識問題、計算問題との複合問題なども出題されます。
例題2)

2021年6月試験問題 (PBT)
上記のような分析手法の導出や解釈についての問題も頻出です。
統計検定準1級は範囲が広く、理解しておくべき分析手法も多岐にわたるので、それぞれ体系立てて理解しておく必要があります。
統計検定準1級の勉強時間
統計検定準1級は、2級に比べても数倍難しくなっています。
一般的に、合格に必要な勉強時間は300時間程度と言われており、統計検定2級の約5倍の時間が必要になる見積もりです。
高度な数学に馴染みがある理系出身者や、統計検定2級を取得していて統計の基礎知識がある場合でも、理解すべき範囲が幅広いため、一朝一夕で合格することは難しい試験です。
学習を進める上では
- 各種分析手法を体系立てて理解する
- 基礎となる数学を理解し使いこなす(必要な式を導出できる)
ことが重要になります。
統計検定準1級の勉強方法
統計検定準1級は出題範囲が広いので、全体をカバーするためには効率的な学習が必要です。
基礎的な数学知識があることを前提に、頻出の分野から優先して学習すると良いでしょう。
特に出題が多いのは以下の内容です。
- 「重回帰」「時系列回帰」:ほぼ毎回出題される
- 「主成分分析」「ベイズ法」
これらの分野を優先的に、ワークブックの内容を読み、説明が不十分な箇所は上記で紹介した参考書で補足します。
まずは一通りの内容を把握することを目的に、どんどん先にに進めていきましょう。
その後、練習問題や過去問を解き、解けなかった部分のワークブック・参考書を読みこみ、重要な理論の整理や式の導出などを行なってみて理解を深めます。
式については、丸暗記よりは理屈を理解し、自分で導出できることが理想です。
1度では理解できない内容でも、何度も問題を解き解説を確認することで理解度が深まってきます。
問題演習を何度も繰り返し、知識の定着をはかりましょう。
ある程度過去問の内容が理解できるようになれば、本番同様に120分の時間を計って回答にあたると試験時間の間隔を掴むことができます。
おすすめのテキスト・問題集
統計検定準1級では、ワークブックを中心に問題が出題されるため、基本的にはワークブックに沿って学習を進めていきます。
ですが、統計検定準1級は範囲が広いため、公式のワークブックやテキストでは説明が簡略化されている部分も多くなっています。
ですので、詳細な内容は分野ごとの参考書を使用し、情報を補足する必要があります。
以下に、学習に適した参考書やテキストを紹介します。
日本統計学会公式認定 統計検定準1級対応 統計学実践ワークブック

出題範囲を一通りカバーしており、出題される問題もこのテキストを踏まえた内容となっています。
本書の内容が理解できていれば確実に合格できる実力が身につく一冊です。
ですが、上記の通り解説が簡略化されている部分があり、本書だけでは理解が追いつかない場合があります。補足の参考書と合わせて学習を進めると良いでしょう。
日本統計学会公式認定 統計検定 1級 公式問題集
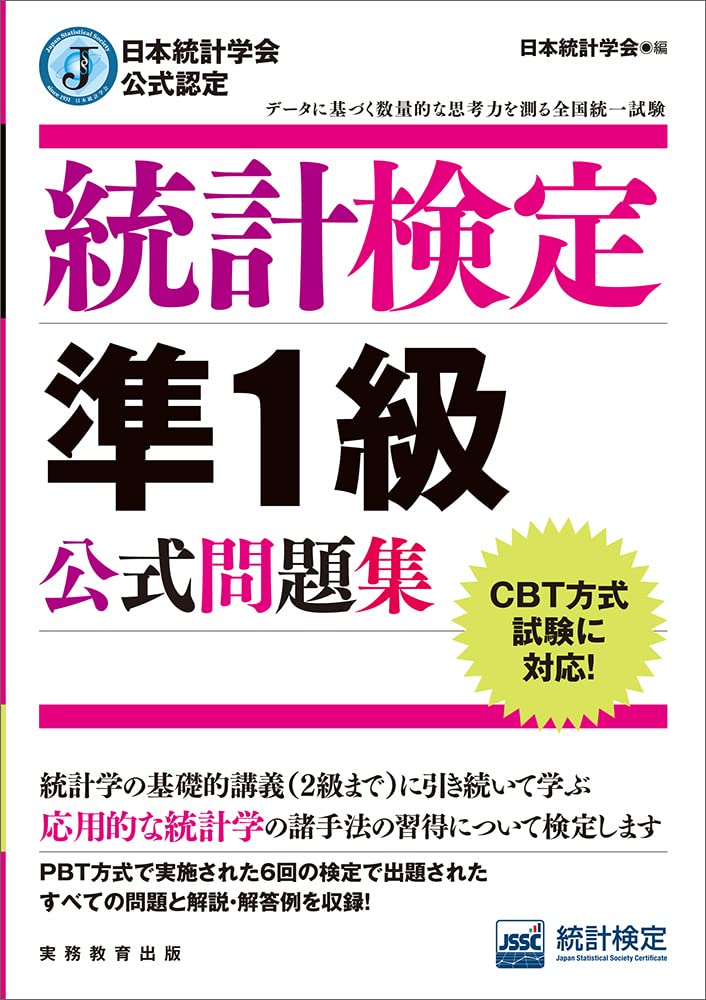
統計検定の過去問集です。1冊あたり3年分、計6回分の過去問が掲載されています。
一試験120分なので12時間あれば一周できる計算となります。
何周も繰り返し解き、自身の理解度の確認と出題の傾向を掴む用途に使用します。
注意すべきなのは、本書に収録されているのはPBT試験の過去問である点です(2021年から開始されたCBT方式の試験問題は公表されていません)。
出題範囲や難易度はCBT / PBTでほとんど変わりませんが、出題方式が異なっていることに留意しましょう。
統計学入門
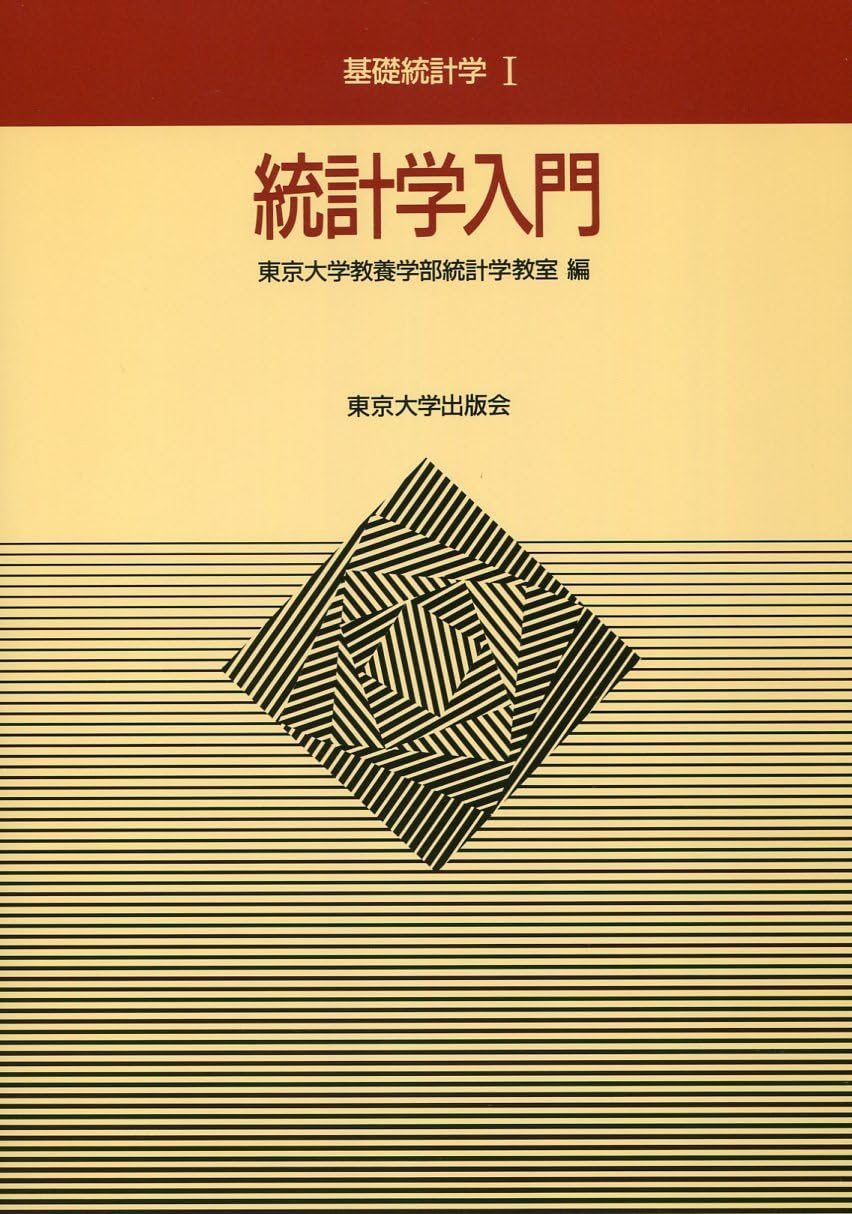
「統計学入門」は通称「赤本」とも呼ばれる統計学の良書です。
公式テキストよりも丁寧に解説されているため、「統計学実践ワークブック」の1〜13章の補足として適しています。
特に「確率」「確率分布」について手厚く解説されているため、「推定」「仮説検定」の理解度を大きく引き上げてくれます。
今後統計検定1級の受験を考えている場合、数理統計分野の基礎を固める上でも有用な一冊です。
自然科学の統計学
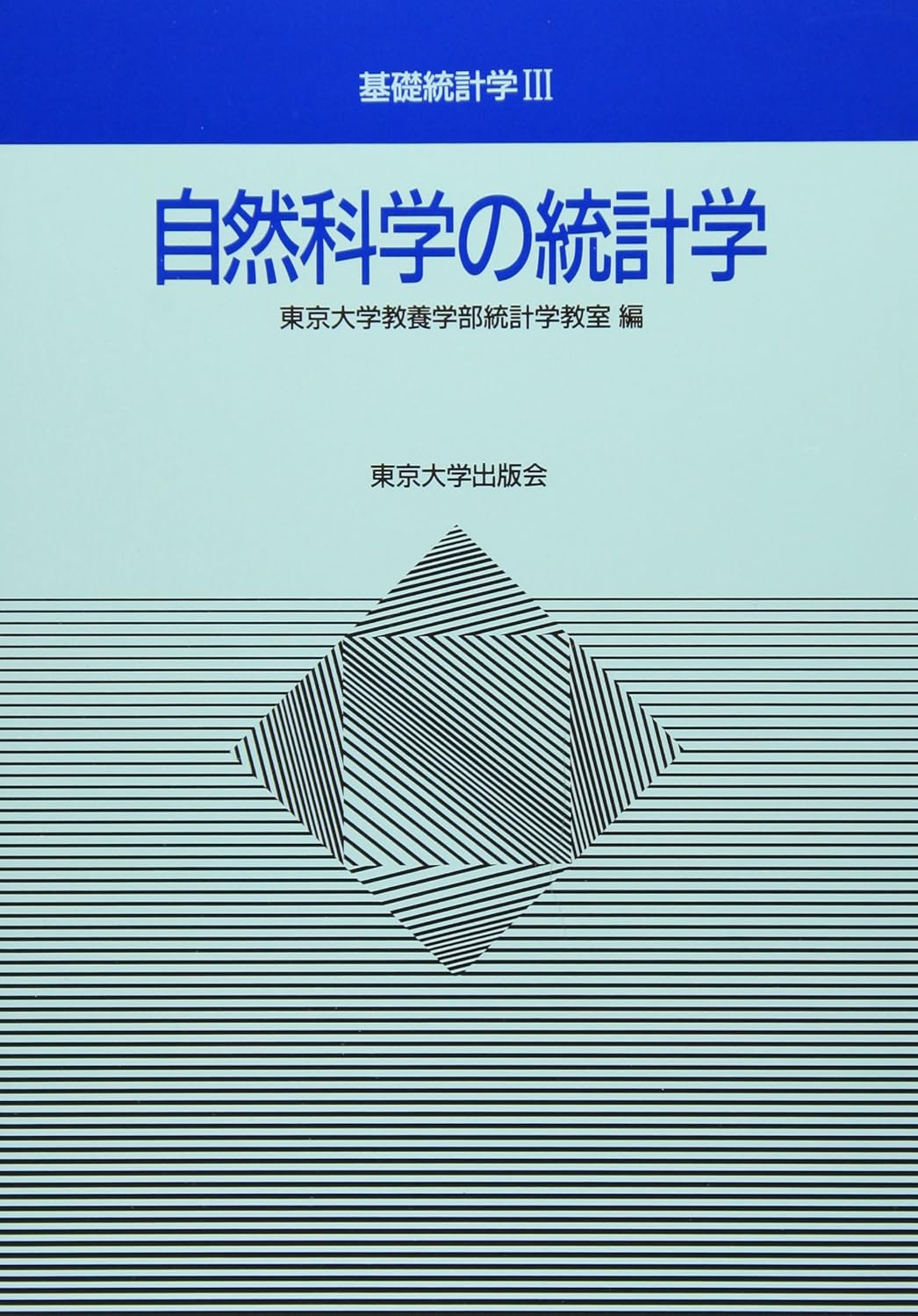
「自然科学の統計学」は、統計検定準1級の中でも、特に応用的な分野を学ぶために役立つ参考書です。
出題範囲のうち「マルコフ連鎖と確率過程の基礎」や「回帰分析」などの内容はこの参考書で詳しく学ぶことができます。
データ解析のための統計モデリング入門
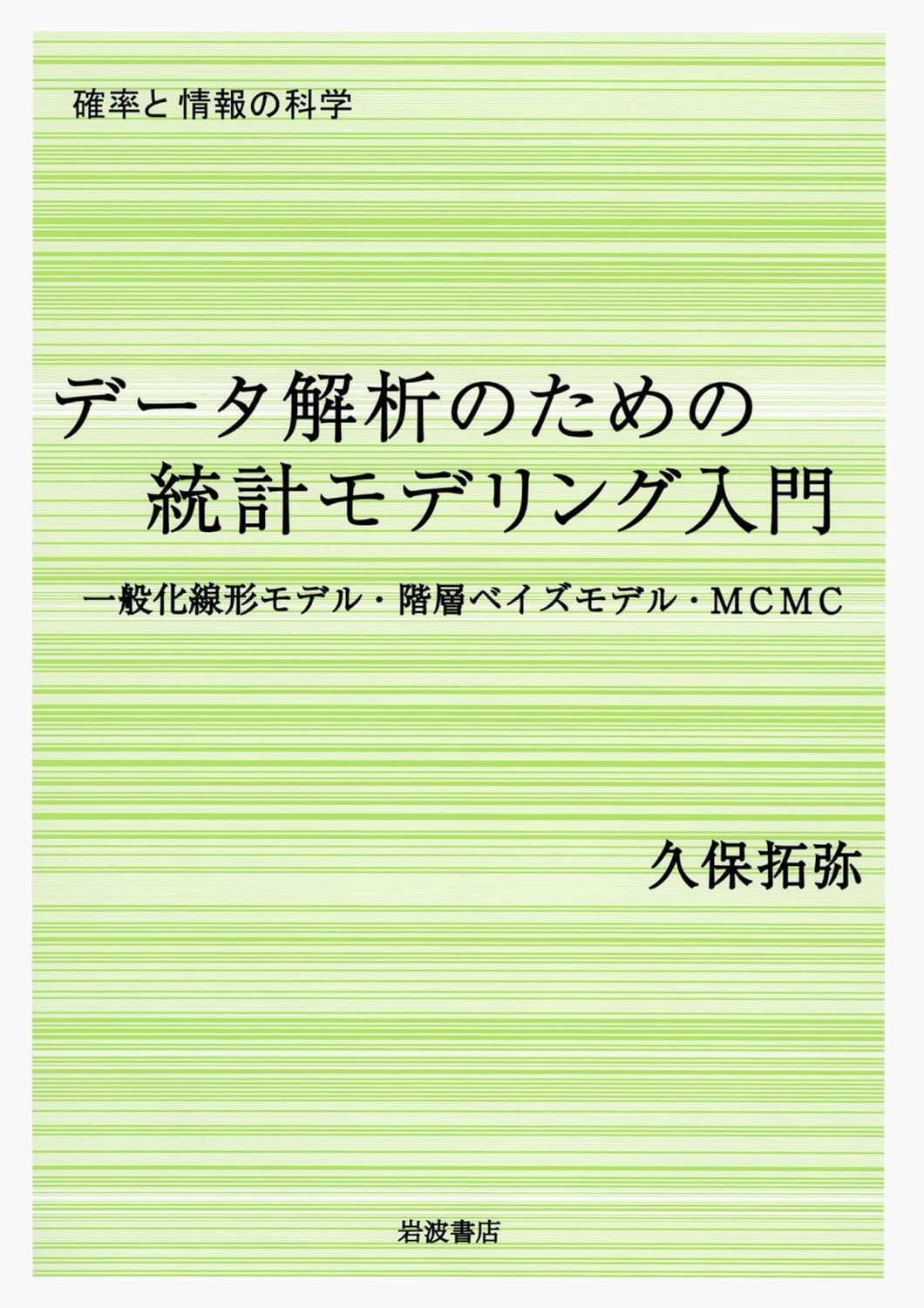
「 データ解析のための統計モデリング入門 」は、統計検定準1級の試験範囲のうち、「質的回帰」「モデル選択」「ベイズ法」の内容を学ぶことができる一冊です。
特に一般化線形モデル、MCMCについての解説が非常にわかりやすくまとまっているため、これらの範囲でワークブックの内容がわからない部分があれば、ぜひ目を通しておくことをおすすめします。
まとめ
統計検定準1級は、非常に幅広い統計学の知識と活用力認定する試験です。
統計検定2級よりも、より高度で実践的な内容となっており、ビジネスでの知名度・評価も高いため、統計学やデータ分析を活かした仕事を行う上でのアピールや自己研鑽に最適です。
ぜひ、本記事を参考に統計検定準1級資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか。

この記事の著者 アオミ ソウ
薬学系大学院の修士課程を主席卒業後、大手製薬企業で有機合成・データサイエンス関連業務に従事(専門は生物有機化学)。
現在は研究の傍ら、ライターとして記事の執筆・イラストの制作を行っている。
主な執筆分野はサイエンス(医療、生化学、情報科学)をはじめ、ガジェット、資格など。
保有資格
2018年 危険物取扱者甲種
2021年 データサイエンス数学ストラテジスト(上級)
2021年 応用情報技術者