生成AI活用の6つのメリット!デメリットと対策方法も解説!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
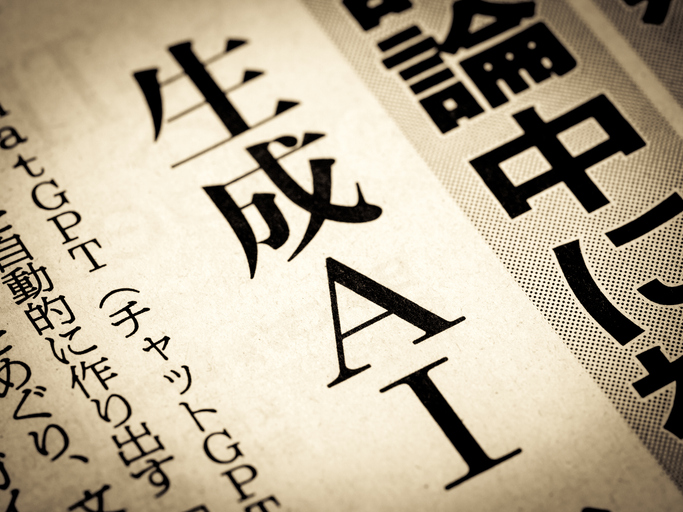
コンテンツ作成や自動応答チャットなど、活躍の場を急速に広げ続ける生成AI。
「使ってみたいが、具体的にどんなメリットがあるのか」「デメリットはないのか」など、気になっている方もいるでしょう。
当コラムでは、生成AI活用のメリット・デメリットについて解説。
デメリットを回避するための対策も併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
最短ルートで生成AIを
使いこなしたい方へ
- 生成AIを使ってみたが、思うような結果が出ない
- 生成AIの活用方法がわからない
- AIを使って業務を効率化したい
生成AIコースを
無料体験してみませんか?

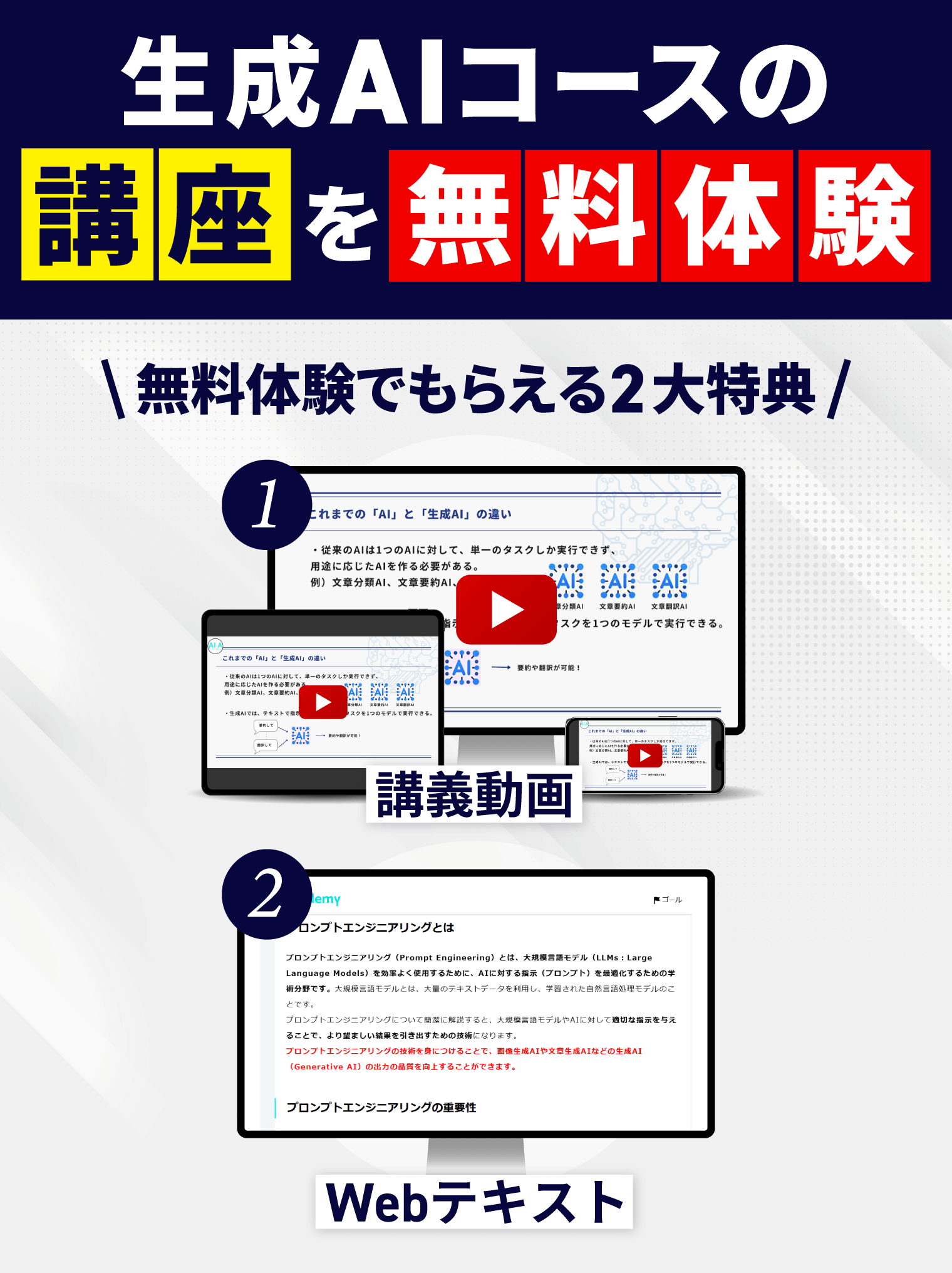
自分のスキルに合わせたカリキュラムが生成できる!
理解度を記録して進捗管理できる!
テキストの重要箇所にハイライトを残せる!
1分で簡単!無料!
▶無料体験して特典を受け取る
追加購入不要!これだけで学習できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
コース以外にも59種類のテキスト見放題!
▶生成AIコースを見る
目次
生成AIの活用で得られるメリット6選
ここでは、生成AIの活用で得られる6つのメリットについて、以下の内容で解説します。
- 作業効率・生産性が向上する
- 業務負担の軽減につながる
- コスト削減を期待できる
- 新しいアイデアを創出できる
- 一定のクオリティを担保できる
- 人為的ミスを防止・削減できる
作業効率・生産性が向上する
生成AIを活用すると、作業効率・生産性の向上が期待できます。
生成AIは文章や画像、デザインなどクリエイティブ領域の作業を得意とします。
ライターやデザイナーが手動で行っていた作業をAIにしてもらうことで、全体の作業効率と生産性は格段に上がるでしょう。
すべて手作業だった工程にAIによる自動化が加わることで、一工程あたりの負担や時間的なコストが軽減されます。その結果、よりクリエイティブな作業に時間を割けるようになるでしょう。
「一から何かを生み出す」ことは人間にしかできません。
人間が時間をかけてアイデアを出し、具体化はAIで行うといった「分業」も可能でしょう。
業務負担の軽減につながる
生成AIの活用は業務負担の軽減に繋がります。
生成AIは、反復・定型の業務を学習できるという特徴があります。
特定のルールのもとで繰り返される作業であれば簡単に自動化できるため、単純作業が原因となる業務負担や人員不足の解消が期待できるでしょう。
例えば、カスタマーサポートを設けている企業ではすでにチャットや電話対応の一部にAIの活用が始まっています。
AIが窓口になることで人的資源を割かずに24時間の顧客対応が可能となるなど、昨今の人手不足への有効な対策のひとつといえるでしょう。
また、ルールの決まった単純作業はAIに任せることで、従業員側はより高度な内容の業務に専念できるようになるといったメリットも大きいです。
コスト削減を期待できる
生成AIを上手に活用することで、コスト削減を期待できます。
生成AIの自動化によって、単純作業にかかっていた「時間」「労力」「人員」のスリム化が可能です。
さらに、業務や組織全体のコストが圧縮できるだけでなく、効率化に繋がります。
生成AI導入により、少ない人員で効率的に業務を回せるようになるだけでなく、浮いた経費や人員を重要な業務や新プロジェクトに活用できる可能性もあります。
また、生成AIの使用には複雑な操作や専門知識なども必要ないため、「生成AIのためのスタッフ」を採用・教育するコストもあまりかからないでしょう。
新しいアイデアを創出できる
生成AIの活用は、新しいアイデアの創出に繋がります。
AIには人間のような「個性」は希薄な一方、世の中の膨大なデータを蓄えています。
例えば、生成AIとのチャットを通して得た回答をヒントに、ひとりでは思いつかなかったアイデアが浮かぶといった活用方法が考えられるでしょう。
さらに、生成AIはひとまずのアイデアでも文章や画像として具体化することが得意です。
曖昧なイメージの状態からAIに具体化させたアイデアを最初の「叩き台」として、より具体的な製品や作品に繋げることもできます。
特に、アイデア勝負のクリエイターやアーティスト、プロジェクト担当者などにとっては便利なツールといえるでしょう。
一定のクオリティを担保できる
生成AIを使うことで、素人でも一定のクオリティを保ったコンテンツを制作できます。
画像や楽曲、文章などのコンテンツが必要な場合、生成AIを使えば必要な業務は言葉での指示のみ。
制作者としてのスキルや知識などが必要ないため、コンテンツ作成にかかる時間や外注費用なども削減できます。
優れたコンテンツの作成はどのような分野でも重要ですが、スキルを一から育てる・スキルのある専門家を探すとなると手間もコストもかかります。
コンテンツ作成にかかわる人材確保が難しい時、生成AIは強力な味方となるでしょう。
人為的ミスを防止・削減できる
生成AIは指示された内容に基づいて正確に作業を行うため、人為的なミスを最小限に抑えられます。
例えば、人間がデータ入力や文章作成をする際には入力ミスや誤字脱字がつきもの。
一方、生成AIであれば最初からミスのない作業が可能なため、高品質の成果物を得られます。
さらに、AIは指示内容と照らし合わせて既存の作業内容からミスを検出することにも長けています。
コンテンツ作成自体は人の手で行うとしても、作業後にAIのチェックを通せば公表前にミスを発見して修正できるでしょう。
どれほど慎重にチェックしても、目視ですべてのミスを見つけることは難しいもの。
正確で高品質な作業を行うためにも、生成AIの導入には一定の価値があるといえるでしょう。
生成AIの活用で起こり得る5つのデメリット
ここでは、生成AIの活用で起こり得る5つのデメリットについて、以下の内容で解説します。
- 期待する回答が得られないことがある
- クオリティを均一化させるのが難しい
- 真実ではない回答を行う可能性がある
- 著作権など法律の問題に触れるリスクがある
- 情報漏洩のリスクがある
期待する回答が得られないことがある
生成AIを使用している場合、期待する回答や成果が得られないことがあります。
例えば、想定とは違う内容のイラストが出力される、対象には合わない内容の文章ができるなどです。
生成AIは使用者の「文章による指示」を正確に実行しますが、逆に指示外のことは汲み取ってくれません。
指示が曖昧すぎる・指示の内容が悪いなどの場合は力を発揮できず、思い通りに動かない場合もあるでしょう。
人間なら読み取れる繊細なニュアンスやテイストなどを正確に理解させるためには、使用側にそれなりの言語能力が求められます。
対人以上にしっかりとした指示出しが必要になる点にAIならではの難しさがあるといえるでしょう。
クオリティを均一化させるのが難しい
コンテンツや回答のクオリティの均一化が難しい点は、生成AIのデメリットです。
生成AI技術はまだ発展途上な側面があります。
現行の生成AIは同じ指示を与えたとしても出力結果がランダムになるため、「安定した成果・回答」が必須の業務にはあまりおすすめできません。
例えば、別の顧客から同じ質問をされても回答内容が一致しない・同じ指示をしても成果物の内容が安定しないといった可能性があります。
さらに使用AI自体の精度が低い場合は、出力される内容に誤情報や不自然な文章が含まれる恐れも。
AI作成のコンテンツを人の手で修正する必要が生じてしまい、結果的にAI導入前より手間や時間が増える可能性もあるでしょう。
真実ではない回答を行う可能性がある
生成AIが真実ではない回答を行うリスクがあることも、念頭に置いておきましょう。
AIが虚偽の情報を生成する現象を「ハルシネーション」といいます。
AIの学習元となるネット情報には正確性を欠く内容も多く含まれるため、質問や指示への回答も不正確なものになる可能性があります。
例えば文章作成の指示を出した場合、指示内容と「関連性が高い」とAIが判断した内容からコンテンツが作成されます。
「関連性が高い」内容に誤情報が多く含まれていた場合、生成文章も事実と乖離した内容になる可能性が高いでしょう。
ハルシネーションが疑われる場合はプロや専門家によるファクトチェックの機会を設けるなどの対策が必要です。
著作権など法律の問題に触れるリスクがある
生成AIで生成する情報・コンテンツには、著作権を侵害するリスクが常にあります。
現行の法律では、著作物や作品をデータとしてAIに学習させることは禁止されていません。
しかし、学習の結果生成されるコンテンツの特徴が学習させた著作物に似ていた場合、「著作権侵害」と判定される可能性は十分にあります。
例として、学習させたイラストや小説の特徴と似た特徴がAIのコンテンツにもあれば、著作権者との間でトラブルになる可能性もゼロではありません。
社会的な信用問題に発展する恐れもあるため、たとえ違法ではなくても注意しなくてはならない点といえます。
情報漏洩のリスクがある
生成AIの使用には、情報漏洩のリスクがあります。
現在出回っている生成AIの多くは多数の使用者が入力するデータを学習して蓄積する仕様です。
迂闊に個人情報や会社の機密情報を入力してしまうと、外部ユーザーへの回答として情報漏洩する恐れがあります。
AIにとっては、機密情報も通常の情報も等しく「データ」です。
学習させてもよい情報なのかどうかは使用者側がしっかりと線引きし、重要な情報は不用意に入力しないといった規定を設ける必要があるでしょう。
特に、顧客データや開発データなどをAIを介して扱う場合は要注意。
整理や分析に便利だからと安易に入力しないよう気をつけましょう。
生成AIのデメリットへの対策5選
ここでは、生成AIのデメリットに有効な5つの対策について、以下の内容で解説します。
- 具体的で明確な指示を出す
- 期待する回答例を示す
- 人間によるチェック・検証も行う
- 生成AIに関する法律の知識を身につける
- 個人情報や機密情報を入力しない
具体的で明確な指示を出す
もっとも有効な対策は、AIに対して具体的で明確な指示(プロンプト)を出すことです。
生成AIは言葉による指示を忠実に実行しようとするため、高品質なアウトプットのためには適切な指示が何よりも重要になります。
近年ではAIに適切な指示を与える専門職として、プロンプトエンジニアと呼ばれる人も増えてきました。
生成AIの使用自体には特殊な操作などは必要ありませんが、良質なコンテンツ作成のために正確な指示出しができる人材を育てることが今後重要視されるでしょう。
期待する回答例を示す
AIに指示を与える場合、期待する回答例を最初に提示すると望む結果が得られやすくなります。
「〇〇について教えて」などと漠然と質問すると、回答内容も冗長で曖昧なものになりがちです。
回答形式について「表」「グラフ」のように指定したり、「設立年」「主要製品」「業績の推移」など具体的な項目を指示したりすることで、回答の精度を高められます。
「何をどう答えればよいか」をはっきりさせた方が答えやすい点は、相手が人間でもAIでも同じ。
求める回答内容はAIに丸投げせず、具体的に提示するとよいでしょう。
人間によるチェック・検証も行う
生成AIでコンテンツを作成した際は、人間によるチェックや検証を必ず行いましょう。
生成AIは膨大なデータを学習・蓄積するため、誤情報が含まれたり他者への権利侵害が発生する可能性も。
「人間視点から感じる不自然さ」「回答内容の正しさ」などはAIには判別できないため、人の目によるファクトチェックは欠かせない工程といえます。
特に、学習段階で既刊の著作物などを読み込んでいる場合は、学習素材とした作品の特徴が成果物に反映され、意図せず著作権侵害を犯してしまう恐れも。
生成AIは、あくまで業務効率化のためのツールです。
回答や成果物はノーチェックで採用せず、コンテンツとして適したものかをしっかり確認しましょう。
生成AIに関する法律の知識を身につける
生成AIを利用する前に、関連法の理解や判例の把握をしておくことが重要です。
生成AIが抵触する可能性のある法律としては、著作権法が代表的でしょう。
特に、コンテンツ作成の目的が私的なものかどうか・著作権者の許可が必要かどうかといった項目は要チェック。
AIの発展に対して現行法の整備はまだまだ追いついていませんが、他者の権利を守ろうとする姿勢は社会的信用を得るためにも重要です。
個人情報や機密情報を入力しない
生成AIに指示出しなどを行う際、個人情報や会社の機密情報は絶対に入力しないようにしましょう。
生成AIは取り込んだデータを蓄積し、学習する仕組みになっています。
重要情報が学習データとして使われた場合、AIサービスの提供企業に自社情報が漏れる・別のユーザーへの回答に使われるといった事態も起こり得ます。
情報整理や顧客傾向の分析、新製品の開発などに生成AIを使用する場合は特に注意しましょう。
まとめ
当コラムでは、生成AIを活用するメリット・デメリットについて、以下の内容で解説しました。
- 生成AIを活用するメリットには、「コストや手間の削減」「作業効率が上がる」「新しいアイデアを得られる」「素人でも高品質のコンテンツを得られる」などがある。
- 生成AIを活用するデメリットには、「期待する回答を得られない・回答が事実ではない可能性」「成果物が現行法に抵触する可能性」「回答がランダム」「情報漏洩リスク」などがある。
- デメリットへの有効な対策としては、「指示を明確にする・回答例を提示する」「人間によるチェック」「生成AIに関連する法律を把握」「重要情報は入力しない」などがある。
生成AI技術は日々めざましい進歩を遂げていますが、一方で現行法の整備や使用者側の意識改革はいまいち追いついていません。
「技術的に可能なこと」と「倫理的に問題があること」とのギャップで問題が生じることもあり、意図せず他者の権利を侵害してしまう恐れもあります。
生成AIは、正しく活用できればコスト削減や効率アップができる強力なツールです。
重要な情報は学習させない・成果物は必ず確認するといった対策を通して、安全に使用できるよう工夫してみましょう。
最短ルートで生成AIを
使いこなしたい方へ
- 生成AIを使ってみたが、思うような結果が出ないい
- 生成AIの活用方法がわからない
- AIを使って業務を効率化したい
生成AIコースを
無料体験してみませんか?

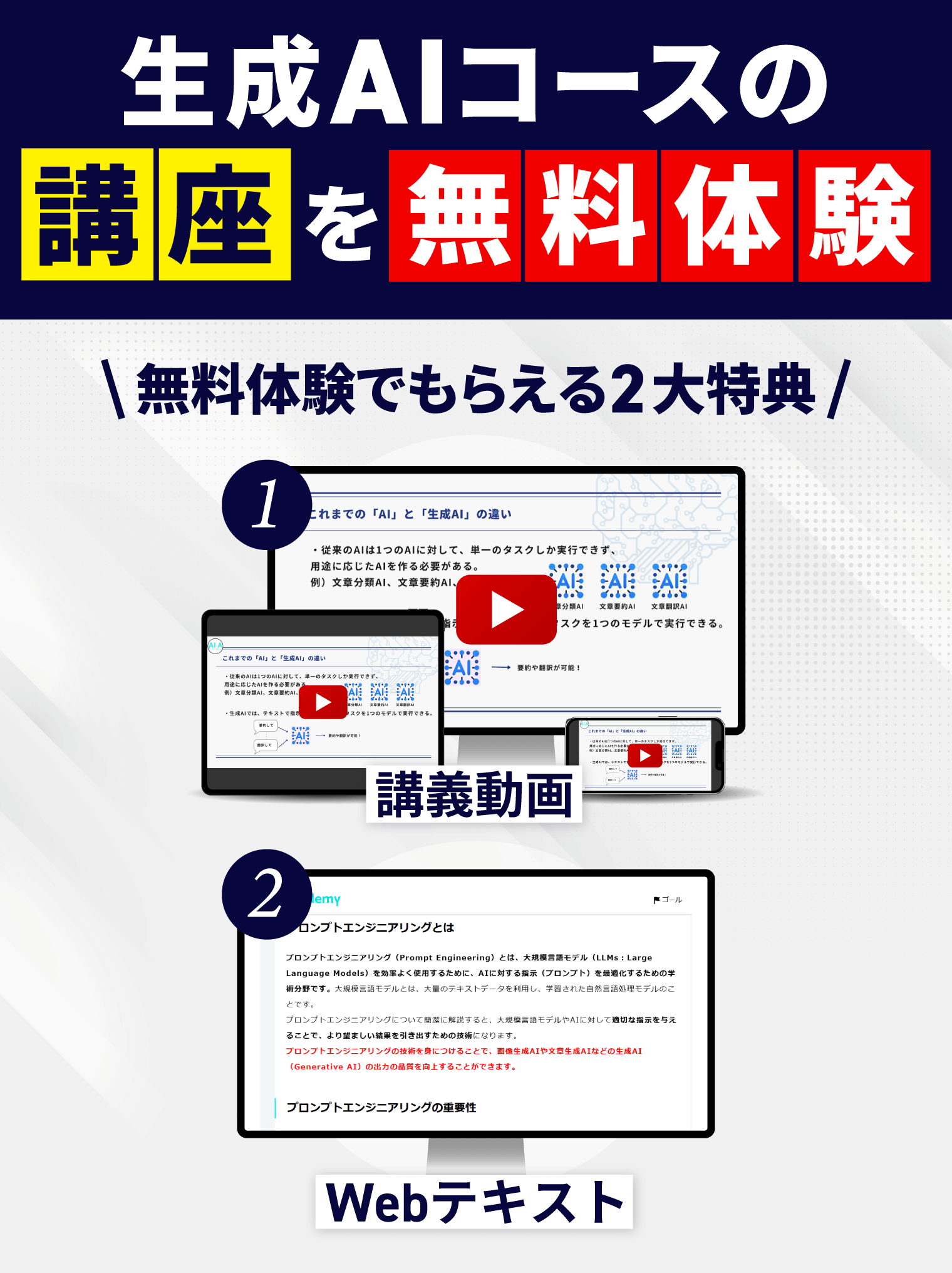
自分のスキルに合わせたカリキュラムが生成できる!
理解度を記録して進捗管理できる!
テキストの重要箇所にハイライトを残せる!
1分で簡単!無料!
▶無料体験して特典を受け取る
追加購入不要!これだけで学習できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
コース以外にも59種類のテキスト見放題!
▶生成AIコースを見る
