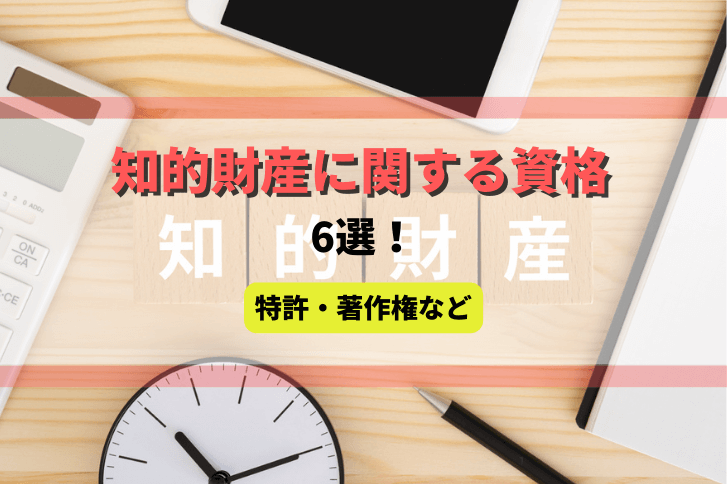女性が食いっぱぐれない資格10選!20代/30代/40代/50代の年齢別も紹介!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

ライフステージの変化によってキャリアが途絶えやすく、再就職が困難になりやすい女性の人生。
「どんな状況でも食いっぱぐれない資格はないかな?」「職に困らない資格は?」など、気になっている方も多いでしょう。
当コラムでは、「女性が食いっぱぐれない資格」について、おすすめの資格や資格選びのポイントなどを詳しく解説します。
資格取得を検討している女性はぜひ参考にしてください。
目次
女性が食いっぱぐれない資格10選
女性が食いっぱぐれない・取得すれば職に困らない資格は以下のとおりです。
保育士
保育士は児童福祉法に基づく国家資格で、子どもに対する保育・保護者に対する保育指導や援助などを担う職業です。
0〜5歳までの未就学児を保護者から預かってお世話をすることが主な業務内容で、「保育園の先生」として一般的にもよく知られています。
保育士が担当する「子ども」には乳幼児も含まれ、着替えや食事、排泄などの基本的な生活習慣を指導することも重要な業務のひとつです。
子どもの人生の最初期にかかわり、健全な育成をサポートできる点で非常にやりがいのある仕事といえるでしょう。
託児所や保育所で大勢の子どもたちを適切に世話する必要があるため、体力的にも精神的にも決して楽な仕事ではありません。
体力や健康状態に自信がある・人とかかわることが好きといった特徴があれば、最初の適性は満たしているといえるでしょう。
保育士になるためのルートは、大まかに「試験に合格」または「養成校を卒業」の2パターンで、試験を受ける場合は年に2回の受験チャンスがあります。
特別な受験資格はありませんが、最終学歴が大学以外の場合は児童福祉施設で一定以上の実務経験を積まなくてはなりません。
看護師
看護師はいわゆる「ナースさん」で、病院などの施設で傷病者の世話や診療の補助などに従事するための国家資格です。
各地の病院をはじめクリニックや介護施設、保育所など就業先の選択肢が非常に広く、「職に困らない資格」の代表格といえるでしょう。
男女比で女性の割合が圧倒的に多い資格でもあります。
具体的な業務内容は所属施設によって多少左右されますが、メインは「治療を必要とする人に対する看護」と「医師の補助」です。
毎日のバイタルチェックはもちろん、注射や採血といった専門的な医療行為や、手術の補助を行うこともあります。
社会的な需要は常に高い仕事ですが「命を預かる」行為には重い責任が伴い、夜勤が当たり前などストレスフルな働き方を余儀なくされる可能性も高いです。
看護師になるためには、文部科学省指定の学校・厚生労働省指定の養成所を卒業後に看護師試験を受ける必要があります。
思い立ってすぐなれる仕事ではありませんが、苦労が大きい分合格できた時の達成感と誇りは格別なものとなるでしょう。
薬剤師
薬剤師は医薬品に精通した「薬学の専門家」で、病院や薬局などで薬の管理や患者さんへの服薬指導などを行う仕事です。
基本業務として処方箋に基づいた「調剤」を行い、公衆衛生の向上や国民の健康の確保に務めます。
ミスがあった場合は深刻な医療事故に繋がりかねない非常に責任の重い仕事のため、薬剤師は就業までの道のりがかなり過酷です。
大学の6年制薬学部を卒業したのち、薬剤師国家試験に合格する必要があります。
さらに、実務実習の必要性やカリキュラムの密度の関係から、通信制・夜間制の「6年制の薬学部」は現在一校もありません。
社会人になってから取得を目指す場合は6年間の学業に集中しなくてはならないため、時間的・経済的にかなり余裕がある状況でなければ難しいでしょう。
しかし、薬剤師は高齢になってからでも働きやすく、病院やドラッグストアなど就職先もたくさんあります。
取得難易度は高いですが、合格できれば一生モノの資格といえます。
医療事務
医療事務は医療機関において事務作業に従事する仕事です。
窓口での対応や請求用の書類作成などが主な業務となり、実務のうえではパソコンスキルが必須。
また、患者さんや医療関係者との綿密なやり取りが業務の中心となるため、一定以上のコミュニケーションスキルが求められます。
保険証の内容などパーソナルな情報に触れる機会も多く、機密情報保持のリテラシー意識なども重要な素養となるでしょう。
医療機関という特殊な場での事務作業を担うことから一般的な事務職よりもかなり業務難易度が高く、保険制度や基本的な医療用語への理解が欠かせません。
さらに心身が弱っている方が主な対応相手となるため、繊細で適切なコミュニケーションが必要となります。
対応や処理のミスがクレームに繋がる可能性も高く、人気が高い一方難しい仕事といえるでしょう。
「医療事務」は国家資格ではないため、資格がほしい場合は「医療事務検定試験」など関連の民間資格を受験して取得する形になります。
資格や経験がなくても法律上は問題ありませんが、業務難易度からして事前にある程度知識を入れる機会はもった方がよいでしょう。
介護事務
介護事務は、介護施設や介護事業所などで事務作業を行う仕事です。
介護ヘルパーなどの現場スタッフとは異なりデスクワークが中心となりますが、窓口対応や電話対応などのシーンでは利用者や利用者家族とやり取りをする機会もあります。
介護スタッフと利用者の状況のスムーズな共有も行われるため、一定以上のコミュニケーションスキルは必須です。
所属先のスタッフの勤怠や給与の管理なども業務内容に含まれるため、過去に総務や経理の部門で働いていた場合は経験を活かせるでしょう。
また、事業所によっては清掃や利用者の送迎など「資格範囲外の雑務」を突発的に頼まれる可能性もあります。
特に小さな事業所では人手不足などの理由から「兼業」の傾向が顕著で、最初から雑務が前提とされている場合もあるでしょう。
中でも、送迎が前提とされている場合は応募時に自動車免許などが必須条件になることもあります。
介護事務への就業は資格がなくても可能ですが、「ケアクラーク技能認定試験」など関連の民間資格を取得すれば採用の可能性は上がるでしょう。
管理栄養士
管理栄養士は厚生労働省が管轄する国家資格で、対象者の状況に合わせて栄養指導や管理などに従事する仕事です。
食事内容を適切に指導するアドバイザーとして需要が非常に高く、病院や教育・介護施設以外にも保健所や自治体といった行政組織にも採用枠があります。
珍しいところでは、スポーツ選手など厳密な健康管理が求められる職業に専属の栄養士として雇われることも。
食事内容の提案や体調面の相談に乗るなど、知識を活かして専門的なサポートを行います。
また、経歴と関心によっては糖尿病など特定の病気のサポートに特化したキャリアパスの可能性もあるでしょう。
入口は同じでも多様な働き方が可能な点が管理栄養士のメリットのひとつです。
管理栄養士は、下位資格の「栄養士」からクラスアップするか、養成施設で学習を積んで取得を目指します。
どちらのルートでも最終的には管理栄養士試験に合格する必要がありますが、栄養士を経由する場合は年単位の実務経験が必要です。
登録販売者
登録販売者はドラッグストアなどで第2類・第3類医薬品を取り扱える資格で、省庁の解釈によって国家資格に分類されることもあります。
第2類・第3類医薬品には風邪薬やビタミン剤など市販の医薬品の9割以上が該当。
2009年の薬事法改正による医薬品の販売場所拡張に伴って創設された資格で、薬を置いているスーパーやコンビニなどにも採用枠があります。
ちなみに、第1類医薬品に関しては「薬剤師」の管轄です。
登録販売者は薬剤師ほど取得難易度が高くないため、医薬品関連の仕事を希望する場合は最初に目指してもよいでしょう。
ドラッグストアやコンビニ、大型のスーパーなどが主な就業場所となるため、全国どこでも活かせる点が最大のメリット。
また、登録販売者の資格をもっていればドラッグストアの店舗管理者にキャリアアップすることも可能です。
登録販売者を目指す場合は各都道府県で実施される登録販売者試験に合格後、販売従事登録を行います。
一度取得すれば生涯有効な点からも、取得価値の高い資格といえるでしょう。
宅地建物取引士
宅地建物取引士(宅建士)は不動産売買を仲介する際に必要な国家資格です。
独占業務を有する点や不動産売買を行う際は必須な点から需要が高く、不動産業界以外でも金融業界や建築業界、保険業界などにも求人があります。
主な業務内容は、不動産売買が売り手・買い手の双方にとって適切に行われるようサポートすることです。
中でも、契約書類への記名や重要事項の説明は宅建士の独占業務となっており、ほかの資格では肩代わりできません。
一度取得できれば多くの業界に就業の道が開かれ、安定した働き方が可能となるでしょう。
宅建士になるためには宅地建物取引士資格試験を突破する必要がありますが、合格の難しい試験として有名です。
独学で挑戦することは不可能ではありませんが、通信講座や予備校の利用も検討するとよいでしょう。
社会保険労務士
社会保険労務士(社労士)は社会保険や年金など、会社と雇用者の間で必要な契約などを扱う国家資格です。
行政機関への申請書類作成や帳簿書類の作成などの独占業務をもち、企業からの需要は高め。
独立開業が可能な資格のひとつでもあります。
健康保険や労働保険などの取り扱いをメイン業務としつつ、労災の治療費や休業補償の申請、労務関連のコンサルティングなど仕事内容は多種多様。
専門性が高いため取得は簡単ではありませんが、人事・労務管理の専門家として長く働ける職業といえるでしょう。
また、近年の女性の社会進出によって「女性社労士」に対するニーズも増えています。
女性ならではのライフスタイルやライフステージを共有できる相談相手として、多くの女性労働者をサポートできるやりがいが感じられるでしょう。
社労士になるためには、社会保険労務士試験に合格しなくてはなりません。
受験資格として一定以上の学歴か実務経験、または税理士や弁理士など特定の国家資格の取得が必要です。
科目合格制度がない・科目ごとに合否判定があるなど難しい試験ではありますが、挑戦の価値は高いでしょう。
ファイナンシャルプランナー(FP)
ファイナンシャルプランナーは主に個人を対象とする「お金の専門家」で、資産の観点から生活・人生設計を提案する仕事です。
保険や税制、年金などお金に関する広範な専門知識を活用し、クライアントに最適な資産運用をプランニングします。
金融業界や保険業界で企業に勤務する場合もあれば、独立して個人事務所を経営する場合もあるでしょう。
ファイナンシャルプランナーは「お金」の知識を豊富に備える必要があるため、関連制度や社会の経済情勢などに関心が高い人であれば適性があるといえます。
また、クライアント一人ひとりの状況や希望に沿って無理のない提案をするために、一定以上の洞察力や傾聴力、コミュニケーション能力も必須です。
ファイナンシャルプランナーは資格がなくても就業できますが、関連資格はいくつかあります。
特に、「FP技能検定」は国家検定の権威性が高く、おすすめです。
【年齢別】女性が食いっぱぐれない資格
ここでは、女性が「食いっぱぐれない資格」について以下の年代別に解説します。
- 20代女性が食いっぱぐれない資格
- 30代女性が食いっぱぐれない資格
- 40代女性が食いっぱぐれない資格
- 50代女性が食いっぱぐれない資格
20代女性が食いっぱぐれない資格
20代女性が食いっぱぐれない資格は下記のとおりです。
- 行政書士
- 登録販売者
- 宅地建物取引士
- キャリアコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
20代は社会人としての経験が浅い一方、人材市場での価値が高い年代です。
将来的にキャリアが広げやすい資格を取得すれば就職や転職がさらに有利になるだけでなく、キャリアの初期から安定した働き方ができるでしょう。
就転職がもっともしやすい年代のため、取得に時間がかかりやすい「行政書士」や「宅地建物取引士」は特におすすめ。
どちらも職に困らない資格なため、休職期間を挟んだとしても復職のネックになりにくいでしょう。
30代女性が食いっぱぐれない資格
30代女性が食いっぱぐれない資格は下記のとおりです。
- 看護師
- 薬剤師
- 管理栄養士
- ウェブデザイン検定
- ファイナンシャルプランナー
30代は社会人としての経験がある程度積まれるとともに、キャリアチェンジやキャリアアップを検討する方も増える年代です。
薬剤師や管理栄養士、ファイナンシャルプランナーは就業先の幅が広く、今後のキャリアの土台に繋げられる点で有利。
栄養や金融の知識は日常生活で役立つ場面も多く、「家族を守れる知識」の観点からもおすすめできます。
また、就業の自由度の観点ではウェブデザイン検定を経てウェブデザイナーを目指してもよいでしょう。
クリエイティブ関連の仕事に関心がある方はぜひ挑戦してみてください。
40代女性が食いっぱぐれない資格
40代女性が食いっぱぐれない資格は下記のとおりです。
- 医療事務
- 介護事務
- 介護福祉士
- 登録販売者
- 社会保険労務士
40代では、就転職の際に年齢的・家庭的なハンデが生じる可能性が否定できません。
年齢にかかわらず評価されやすい資格であれば、希望する勤務形態で採用される可能性を上げることができるでしょう。
医療・介護系の資格や社労士などの資格は社会的な需要が高く、子育てや社会人としての経歴を活かせる点でおすすめです。
50代女性が食いっぱぐれない資格
50代女性が食いっぱぐれない資格は下記のとおりです。
- 保育士
- 医療事務
- 介護事務
- 看護助手
- 介護福祉士
50代での就転職は40代以上に年齢的なハンデが生じやすいため、経歴を活かせる資格・即戦力になれる資格を選ぶとよいでしょう。
子育てや介護の経験をもつ方も増えてくるため、保育や介護、看護の現場であれば「実践知をもつ経験者」として採用されやすくなります。
事務職の経験がある方であれば、医療事務や介護事務などもおすすめです。
女性が食いっぱぐれない資格の選び方
女性が食いっぱぐれない資格の選び方としては、以下のポイントが挙げられます。
- 将来性はあるか
- 独占業務はあるか
- 理想の働き方をできるか
将来性はあるか
検討している資格に将来性があるかどうかは要チェックです。
将来性のある仕事、すなわち安定した需要がある仕事は「社会からなくなりにくい」ため、女性が食いっぱぐれない仕事としては最適な選択肢となるでしょう。
例えば、電気をはじめライフラインに関連する資格や、医療・介護系の資格は、「なくなると困る仕事」として常に高い需要が期待できます。
また、近年急速に需要が高まっている職種としてIT業界の資格があります。
技術の発展速度に対して人材の供給が追いついておらず、人手不足が顕在化しているからです。
IT業界以外でも「パソコンに強い人」と評価される可能性があるため、興味がある場合はITパスポートなど基礎的な資格から挑戦してみるとよいでしょう。
独占業務はあるか
独占業務のある資格かも重要なポイントです。
独占業務とは、特定の資格保有者のみが行える業務のこと。
以下に一例を挙げます。
- 行政書士:官公庁に提出する書類作成・権利義務に関する書類作成
- 宅地建物取引士:重要事項の説明・契約書類への記名など
- 薬剤師:調剤・第1類医薬品の販売・薬局の管理など
独占業務は責任の重い仕事や専門性の高い仕事が多く、必然的に業務上重要なプロセスを占めます。
担当できる人材が不在の場合は業務自体が滞る可能性すらあり、関連する企業における需要は非常に高いでしょう。
該当資格を保有していることで雇用時の優遇や好条件での採用が期待できるほか資格手当が支給されることもあり、安定的な年収アップにも効果大です。
理想の働き方をできるか
資格取得後に理想の働き方ができるかはしっかり検討すべき点です。
近年は「働き方」が多様化しており、フリーランスやリモートワーク、フレックスなどさまざまな就業形態が登場。
資格によって実現可能な就業形態は異なるため、自分の希望に沿った働き方ができる資格かどうかは必ず確認しましょう。
例えば、医療・介護系の資格は業務内容上「不定期なシフト」「夜勤」などが避けられず、安定したシフトを希望する方にはミスマッチの可能性が高めです。
逆に、宅建士や社労士は安定した企業勤めだけでなく、独立開業も可能。
登録販売者や医療事務などはパートタイムの求人も多く、ライフスタイルに合わせて柔軟な就業ができるでしょう。
最初に理想とする働き方を明確にすれば、必要な資格選びの参考になるでしょう。
女性が資格を取得するメリット
女性が資格を取得するメリットは以下の3点です。
- 専門性をアピールできる
- 安心して出産・子育てができる
- ライフスタイルに合わせて働ける
専門性をアピールできる
女性が資格を取得することで、専門性をアピールすることができます。
「資格」とは、対象分野における専門的な知識やスキルを有することの証明です。
特に、自分の能力を対外的に証明しなくてはならない就職・転職時には強力なカードとなるでしょう。
資格があれば同じような経歴の無資格人材より採用されやすくなるだけでなく、未経験の職種に挑戦する際にも効果的。
応募先の企業目線で必要な知識があることを客観的に判断できるため、「大丈夫」と思われやすくなります。
さらに難易度の高い資格であれば、資格取得までの努力など、人間性の面を評価される可能性も。
未経験の場合も資格合格に漕ぎ着けた事実を「業界への関心・ポテンシャルの高さ」としてアピールでき、経験不足を武器として活用することも可能です。
安心して出産・子育てができる
女性が資格を取ると、安心して出産・子育てができます。
出産や子育てによって一旦キャリアが途絶え、再就職が困難になりがちな点は女性共通の深刻な課題です。
しかし、資格を取得していれば特定の分野に専門性やスキルをもっていることを証明しやすく、ブランクによる「採用しぶり」が抑えられます。
企業の状況によっては、即戦力として採用される可能性もあるでしょう。
特に行政書士や社労士、宅建士のような独占業務をもつ資格であれば、企業の需要が高く再就職へのハードルがさらに下がります。
退職を機にキャリアプランを見直し、独立を目指すことも可能です。
ライフスタイルに合わせて働ける
女性が資格を取得すると、ライフスタイルに合わせて柔軟に働けるようになります。
例えば、育児のためにフルタイムからパートタイムに移行したい場合、需要の高い資格があれば短時間でも高収入を得られる可能性が上がります。
配偶者の転勤に同行すると決めた場合も、資格があれば転居先の土地で新たな仕事を見つけやすくなるでしょう。
特に、登録販売者や医療事務、管理栄養士などはドラッグストアや病院が主な就業先になり、全国どこでも職に困らない資格といえます。
「仕事中心」の人生を脱却し、自分の都合と希望に合わせて生活できるようになる点が資格取得の大きなメリットといえるでしょう。
女性が資格を取得するデメリット
女性が資格を取得することのデメリットは、「合格までに時間とお金がかかること」です。
例えば最難関レベルの税理士試験では、合格までに必要な時間は4000時間ほどとされています。
税理士ほど難易度の高い試験ではなかったとしても、100時間ほどの学習時間は覚悟する必要はあるでしょう。
さらに、薬剤師や管理栄養士のように学習方法が限られ、年単位で休職・退職を余儀なくされる資格もあります。
費用の面では、資格試験の受験料や試験会場までの移動費、テキストや参考書などの教材費などがある程度必要です。
学習期間中に仕事との両立が難しければ、生活費の工面も課題となるでしょう。
具体的な負担の程度は目指す資格や勉強方法によっても左右されますが、どの資格に挑戦する場合も数か月・数年単位で学び続ける覚悟は必要です。
「絶対に合格したい」といった覚悟こそ、挫折を回避して合格を得るためにもっとも重要な要素といえるでしょう。
まとめ
当コラムでは、女性が食いっぱぐれない資格を紹介しました。
- 保育士
- 看護師
- 薬剤師
- 医療事務
- 介護事務
- 管理栄養士
- 登録販売者
- 宅地建物取引士
- 社会保険労務士
- ファイナンシャルプランナー(FP)
女性はライフステージの変化に伴うキャリアの断絶が起こりやすく、男性と比較して再就職の難しさに直面しがちです。
資格取得は専門知識やスキルの対外的な証明にもっとも有効なカードとなり、スムーズなキャリアの再開に非常に効果的といえます。
独学では難しい資格もありますが、各予備校や通信講座などをうまく活用すれば合格は不可能ではありません。
興味や経歴の方向性や希望する就業形態などから最適な資格を選定し、ぜひ挑戦してみてください。