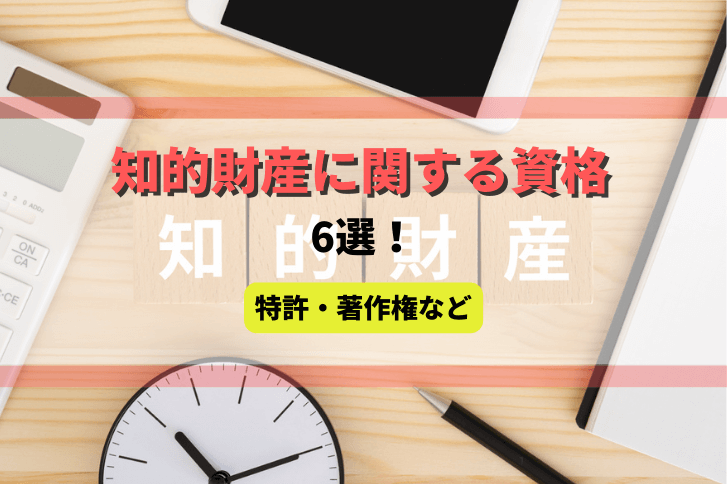資格勉強のやり方おすすめ9選!効果的な勉強方法や勉強のコツを解説!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

資格勉強におすすめのやり方には、どのようなものがあるのでしょうか。
世の中にはさまざまな勉強方法の情報が出回っており、「結局どのやり方がおすすめ?」「勉強のコツは?」など気になっている方もいるでしょう。
当コラムでは、資格勉強のやり方としておすすめの方法や効果的な勉強のコツについて詳しく解説していきます。
資格試験への挑戦を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
資格勉強のやり方おすすめ9選
資格勉強のやり方としておすすめの方法は以下の9つです。
- 試験概要を確認する
- 過去問で問題の傾向をつかむ
- テキストを繰り返し読む
- 問題集を繰り返し解く
- 動画・音声教材を活用する
- 苦手分野をノートにまとめる
- 暗記用の単語帳を自作する
- 模擬試験で本番に慣れる
- 通信講座を活用する
試験概要を確認する
最初に、試験概要を確認しましょう。
効率的に資格勉強を進めるためには挑戦予定の試験の科目や出題範囲、設問数といった「概要」をしっかり把握し、適切な受験対策を行う必要があります。
科目によって配点差が大きかったり科目ごとに合否判定があったりと、試験によって特徴はさまざま。
概要を詳しく知ることで試験に最適化された対策をできるだけでなく、確保できる勉強時間内で無理なく学習を進められるでしょう。
例えば、一部の公務員試験や司法試験などは総合点で合否が判定されるため、配点の低い科目であればある程度「捨てる」判断も可能です。
逆に、社会保険労務士や司法書士、行政書士などは科目ごとに「足切り」が行われるため、全科目をまんべんなく対策する必要があるでしょう。
過去問で問題の傾向をつかむ
過去問を活用して問題の傾向をつかむことは有効な試験対策のひとつです。
資格試験には、問題量や出題方式などにそれぞれ特徴があります。
数年分の過去問を何度も繰り返し解くことで、本試験の問題量や出題頻度の高い問題などが自然と把握できるでしょう。
場合によっては、運営公式が過去問を公開していることも。
最低でも5年分、可能であれば10年分の過去問題を用意し、積極的に取り組むとよいでしょう。
特に、最新年の過去問題は本試験の傾向と近い可能性が高く、知識の総決算・模擬試験としての利用が効果的。
学習途中に腕試しをする場合は、古い過去問から解いてみましょう。
テキストを繰り返し読む
試験種を問わず、テキストや参考書は繰り返し読み込むことが重要です。
特に、学習の初期段階でテキストに触れる際は、わからない部分があっても「通し」で最後まで目を通しましょう。
勉強を始めたばかりの時点では、理解できない箇所や知らない単語がたくさんあるはず。
1ページごとに立ち止まって調べていては時間がかかりすぎ、思うように勉強が進まないといった事態に陥る可能性があります。
最初のうちはわからない部分があっても敢えて立ち止まらず、全体を把握する意識で繰り返し読むのがおすすめ。
回数を重ねて知識が追いついてくれば、1巡目にはわからなかった部分も無理なく理解できるはずです。
問題集を繰り返し解く
問題集は繰り返し解いてみましょう。
特に、1巡目で間違えた問題は貴重な教材となります。
2巡目以降は間違えた問題だけを重点的に解くことで、効率的に苦手分野をなくせるでしょう。
問題集に取り組む際に重要なポイントは、わからない部分をきちんと認識することです。
間違えた部分・理解できていなかった部分は、あとから復習することで確実に習得できます。
問題集の段階では正解率を意識する必要はありません。
わからない問題を適当にごまかして解答してしまうと苦手克服のチャンスを逃してしまうため、「しっかり間違える」ことを心がけましょう。
動画・音声教材を活用する
文章で知識をインプットすることが苦手であれば、参考書に加えて動画や音声教材を活用してもよいでしょう。
知識が定着しやすい勉強方法は人によって違います。
動画や音声は移動中にも視聴が可能なため、ながら勉強で学べる点にもメリットがあります。
特に動画教材の場合は再生速度を変更できることも多いです。
復習時には倍速で再生するなどの工夫をすることで、より効率的に学習できるでしょう。
たとえば2倍速で視聴した場合は、単純計算で2倍のインプットが可能となります。
苦手分野をノートにまとめる
勉強を続ける中で明らかになった苦手分野は、積極的にノートにまとめましょう。
「書くこと」は脳科学的にも記憶の定着に効果的な作業です。
テキストに書かれた情報すべてを取捨選択なしにひたすら書くとなるとさすがに非効率的ですが、苦手分野に絞ってまとめることは非常におすすめといえます。
例えば、過去問に取り組む中で何度も間違えた箇所や試験における重要事項を独自にまとめれば、自身に足りない知識だけを集中的に補うことが可能。
「間違えた問題」は、当人だけの特別な教材です。
ノートにピックアップしてまとめておけば、試験直前に見直したい場合にも便利に使えます。
暗記用の単語帳を自作する
なかなか覚えられない単語に関しては、暗記用の単語帳を自作してもよいでしょう。
勉強を続けていると、「何度も間違える単語」「覚えにくい単語」が自分でもわかってくるはず。
単語カードやシート、アプリなどを利用して自分だけの「単語帳」を作れば、繰り返しの学習に大変便利です。
手軽に持ち運べる形にまとめることで、通勤中や休憩時間などのわずかな「スキマ」を活用して学習を進めることも可能になるでしょう。
ただし、単語帳の制作自体に凝って時間をかけすぎたり、作ったことに満足して終わったりしないようにだけ注意が必要です。
勉強の合間に息抜きとして少しずつ作成を進め、完成後はしっかりと学習に活かしましょう。
模擬試験で本番に慣れる
資格試験の数か月前になったら、模擬試験を受験して本番の環境に慣れておくとよいでしょう。
本番に近い難易度や問題量の模擬試験に挑戦して合格ラインに達していれば、本試験でも得点を伸ばして合格できる可能性が高いと判断できます。
逆に、模擬試験の段階では合格ラインに達していなかった場合は、学習方法の軌道修正・苦手分野克服のチャンスです。
模擬試験は本試験に似てはいますが、あくまで「模擬」。
結果に一喜一憂せず、結果を活かして本番に備えましょう。
他受験生と集まって受験・本番と同じ制限時間を体感できるなど、本番を想定した環境を併せて体感できる点も模擬試験の強みです。
何度も受ける必要はありませんが、一度は体験しておきたい教材といえます。
通信講座を活用する
独学向けの勉強方法だけでは不安がある場合は、通信講座の利用を検討してみてもよいでしょう。
特に、社会人が受験勉強をする際は本業や家事・育児との両立がネックになりがち。
各通信講座では無駄のないカリキュラムが提供されているため、忙しい方でも効率的に学習を進めることができます。
疑問点を講師に質問できる点も独学にはないメリットです。
自力ではなかなか理解に至らない部分があってもすぐ講師に確認できるため、「疑問」がモチベーションの妨げではなく学習のきっかけになります。
また、資格試験の中には記述問題や口述試験など、明確な「正解」がない出題が含まれるものもあります。
通信講座によっては添削や模擬面接で受験生をサポートしてくれることもあるため、自分が合格ラインに達しているかを客観的に判断できるでしょう。
対策が独りよがりになりにくい点で、通信講座には大きなメリットがあるといえます。
資格勉強を効果的に進めるコツ
資格勉強を効果的に進めるコツは以下の3点です。
- 完璧主義にならない
- スキマ時間を活用する
- 学習スケジュールを立てる
完璧主義にならない
勉強中は、過度に完璧主義にならないよう注意しましょう。
特に、学習の初期段階ではある程度のアバウトさをもつことが重要。
わからない箇所に突き当たったときに都度立ち止まっていると、学習効率は大きく損なわれます。
「全体を把握できないまま枝葉末節を深掘りする」ような学習方法は、先に進めないまま知識が偏ってしまう点でおすすめできません。
資格試験に挑戦する最大の目的は、「合格」です。
限られた勉強時間の中で、どうしてもわからない部分は飛ばす・優先度の低い科目は捨てるなど、柔軟な発想で臨むことが重要になるでしょう。
中には、「総合的に合格ラインを超えればOK」な試験もあります。
すべての項目を完璧に学習するよりも、「合格ラインを超えること」を目標にするとよいでしょう。
スキマ時間を活用する
スキマ時間は積極的に活用しましょう。
特に社会人の方であれば、学生時代のように「机に向かって一定時間勉強する」といったことが難しい方も少なくないでしょう。
多忙な方ほど空き時間を「探す」のではなく、意識的に「作る」意識が必要となります。
例えば、通勤時間や昼休憩、食事中といったスキマ時間は活用しやすいでしょう。
わずかなスキマ時間を最大限に活用できるよう、動画・音声教材の導入や単語帳の作成に取り組んでもよいでしょう。
特に、音声教材は車通勤の方でも聞き流し感覚で学習できるため、手軽な教材のひとつとして試してみるとよいでしょう。
学習スケジュールを立てる
本格的な受験勉強をスタートする前に、学習スケジュールを立ててください。
本試験までの期間から逆算して、当日までに学習すべき範囲を無理なく履修できるよう計画しましょう。
「◯月までに××の科目を勉強する」など大まかな目標を定められたら、1週間・1日単位などより厳密な計画も立ててみることをおすすめします。
特に時間の捻出が難しい社会人の場合、自分自身に適度なプレッシャーをかけることで日々机に向かう姿勢を維持できるでしょう。
ただし、どれほど気合をもって臨んでも不測の事態は起こり得ます。
また、あまりに過密なスケジュールはかえってモチベーションを損なう可能性も。
ある程度は勉強の遅れを想定した余裕のあるスケジュールを立てることが重要です。
資格勉強で失敗する人の勉強方法
資格勉強で失敗する人の勉強方法としては、以下の3パターンが挙げられます。
- アウトプットをしない
- ひたすら暗記しようとする
- 時間で勉強量を決める
アウトプットをしない
資格勉強に失敗する人は、インプットに集中するあまりアウトプットをおろそかにする傾向があります。
試験勉強における「インプット」はテキストなどで知識を入れること、「アウトプット」は実際に問題を解くことです。
どれほど知識を習得しても、実践しなければ定着は望めません。スポーツや音楽などでも、知識を前提に「実際に体を動かす」ことでスキルを上げていきます。
資格勉強においても、知識を一通り習得したら積極的にアウトプットを行うことが手っ取り早く合格に近づくための近道となるでしょう。
目安としては、インプットとアウトプットを1:3ほどの比率で行い、「アウトプット重視の勉強」を続けてみてください。
ひたすら暗記しようとする
ひたすら暗記しようとすると、資格勉強で失敗しやすくなります。
知識の習得にはある程度の暗記は必須ではありますが、特に情報量の多い資格試験では、出題範囲の知識を丸暗記することは現実的ではありません。
丸暗記以外で記憶に残す方法としては、例えば法律系の知識であれば条文の成立背景や意味、使い方などを一緒に把握することで覚えやすくなります。
努力してもどうしても知識がつかない場合だけ、暗記を試みる・試験直前に振り返るといった方法で学習しましょう。
時間で勉強量を決める
「今日は◯◯時間勉強する」など、時間で勉強量を決めることはおすすめしません。
資格勉強において重視すべきは「どれだけ長く勉強したか」ではなく、「どれだけの知識が身についたか」です。
時間ベースではなく、「今日はこの章をマスターする」のように成果ベースで勉強量を決めるとよいでしょう。
ただし、成果ベースに偏りすぎると疑問点でつまずいたときに学習進捗が滞る可能性があります。
「◯◯時間で××を覚える。理解しきれなくても先に進む」といった形で、時間と成果のバランスを考慮して計画を立てるとよいでしょう。
時間制限があることで自分自身にある程度プレッシャーがかかり、学習にメリハリをつけられるメリットもあります。
まとめ
当コラムで解説した資格勉強におすすめの勉強のやり方は以下の通りです。
- 試験概要を確認する
- 過去問で問題の傾向をつかむ
- テキストを繰り返し読む
- 問題集を繰り返し解く
- 動画・音声教材を活用する
- 苦手分野をノートにまとめる
- 暗記用の単語帳を自作する
- 模擬試験で本番に慣れる
- 通信講座を活用する
資格試験にはさまざまな種類のものがあるため、まずは該当の試験の概要をしっかり把握しましょう。
独学での学習に不安があるようであれば、通信講座を頼ることもおすすめです。