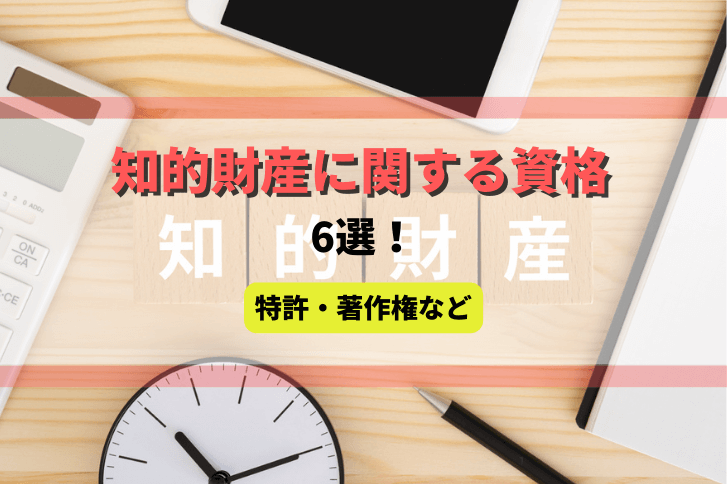受験資格なしで取れる国家資格おすすめ12選!実務経験・年齢制限なしで受験可能な資格は?
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

「国家資格を取りたいけれど、実務経験や年齢制限が心配」という不安を抱えている人は多いのではないでしょうか。
国家資格の中には、受験資格がなく誰でも挑戦できるものが意外と多いです。
このコラムでは、受験資格なしで取得できるおすすめの国家資格を紹介し、国家資格の種類や特徴、国家資格で設けられがちな受験資格についても解説します。
資格取得を目指す際の選択肢を広げるための参考にしてください。
目次
受験資格なしで取れる国家資格おすすめ12選
実務経験や年齢制限などが設けられていない、おすすめの国家資格は下表のとおりです。
| 資格名 | 特徴 |
| ファイナンシャルプランナー | 個人の資産運用やライフプランに関する相談に応じ、適切なアドバイスを行う専門家 |
| 中小企業診断士 | 中小企業の経営課題を分析し、改善策を提案する経営コンサルタントの国家資格 |
| 行政書士 | 官公署に提出する書類の作成・手続きを代行し、法律関連の相談にも対応する専門家 |
| 宅地建物取引士 | 不動産取引に関する重要事項の説明や契約書の作成・記名・押印を行うための国家資格で、不動産業界で必須の資格 |
| マンション管理士 | マンションの管理・運営に関する専門知識を活かし、管理組合や区分所有者の相談に応じ、運営改善・修繕計画の立案・トラブル解決を支援 |
| 電気工事士 | 建物や設備の電気配線や設置工事を安全に行うために必要な国家資格で、第一種と第二種に分類される |
| 電気主任技術者 | 発電所や工場、ビルなどの電気設備の保安・監督を行う国家資格で、第一種・第二種・第三種にわかれる |
| 登録日本語教員 | 日本語を学ぶ外国人に対して適切な指導を行うために設けられた日本語教師の国家資格 |
| 気象予報士 | 気象データを分析し、天気や気象現象を予測・報告する国家資格 |
| 通関士 | 輸出入手続きに関する専門知識をもち、税関への申告業務を行う国家資格 |
| 全国通訳案内士 | 外国人観光客に対し、外国語で日本の観光案内を行うための国家資格 |
| ITパスポート | ITに関する基礎知識をもっていることを証明する国家資格 |
上記の資格について、それぞれの詳細を見ていきましょう。
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー(以下、FP)は、個人の資産運用やライフプランに関する専門的なアドバイスを行う資格です。
年金・保険・税金・投資・不動産などの幅広い知識を活かし、相談者のライフステージや家計状況に応じた最適なプランを提案します。
FPは大きく分けると、企業に所属して業務を行う「企業内FP」と、独立して活動する「独立系FP」の2種類があります。
企業内FPは主に金融機関に所属し、自社の商品を活用した資産運用や保険の提案。
一方、独立系FPは特定の企業に所属せず、中立的な立場から顧客の資産設計をサポートします。
FPの具体的な業務は、顧客の収入や支出、保有資産などの情報をもとにライフプランを作成し、その実現に向けた資産運用のアドバイスを行うことです。
また、税理士や弁護士と連携し、相続対策や税務相談に対応することも。
なお、FP資格には「AFP」「CFP」「FP技能士(1〜3級)」があり、それぞれ専門性や対応可能な業務の範囲が異なります。
中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の経営に関する診断や助言を行う経営コンサルタント資格で、経済産業大臣によって認定される国家資格です。
全国の多くの中小企業が、経営戦略や財務管理、人材育成などの課題を抱えています。
中小企業診断士の役割は、こうした中小企業の問題を分析し、解決策を提案することです。
主な業務は、経営改善計画書や経営診断書の作成、経営セミナーの開催、資金調達のアドバイスなど。
資格を取得することで、経営コンサルタントとして独立する道もありますが、企業の経営企画部門や金融機関での業務にも活かせます。
特に近年の経済状況の変化により、多くの中小企業が経営危機に直面しており、診断士の役割はますます重要になったといえるでしょう。
なお中小企業診断士には専門知識だけではなく、論理的思考力や高いコミュニケーション能力が求められます。
行政書士
行政書士は、法律に関する幅広い業務を担う「法律のマルチプレイヤー」とも呼ばれる資格で、個人や企業の代理人として法的書類を作成し、申請手続きを行うことができます。
主な業務は、大きく3つに分類されます。
- 官公署に提出する書類の作成や申請手続きの代理
例:建設業許可申請・飲食店営業許可申請・古物商許可申請など - 権利業務に関する書類の作成
例:遺産分割協議書・契約書・示談書・告訴状など - 事実証明に関する書類の作成
各種議事録の作成・履歴書の作成など
行政書士は弁護士や司法書士とは異なり、法廷での代理権はもたないものの、企業の経営サポートや個人の法律相談に広く対応できるため、独立開業しやすい点が特徴です。
特に、中小企業の経営支援や外国人の在留許可申請などの分野で活躍することが多く、社会のさまざまな場面で必要とされる資格といえます。
宅地建物取引士
宅地建物取引士(以下、宅建士)は、不動産取引の公正性を確保するために宅地建物取引業法で定められた国家資格。
宅建士には「重要事項の説明」「重要事項説明書への記名」「契約書(37条書面)への記名」の3つの独占業務があり、不動産業界で働くうえで非常に重要です。
これらの独占業務は、宅建士資格をもたない者が行うと法律違反となり、罰則が科されます。
宅建士資格は不動産会社に勤務するほか、金融業界では不動産担保ローンの評価、小売業界では出店戦略のための不動産知識の提供、建築業界では施工後の不動産販売など、幅広い業界で活かすことが可能です。
不動産は高額な取引となることが多く、法律や契約に関する専門知識が求められるため、宅建士の役割は非常に重要といえます。
マンション管理士
マンション管理士は、マンション管理組合や区分所有者(分譲マンションの購入者)に対して、管理運営のコンサルティングを行う専門家です。
主な業務は4つに分けられます。
- 管理組合の運営に関する相談
会計処理の方法や運営コスト削減など、組織運営のアドバイスをする - マンションの修繕計画の立案
老朽化した建物の修繕工事の計画や、それに伴う資金計画の策定、工事会社の選定などを支援する - 管理規約や使用細則の見直し・作成
住民のルールを明確にし、円滑なマンション運営をサポートする - 住民同士のトラブル解決
騒音問題や共有スペースの使用ルール、ゴミ出しマナーなどの対立を調整し、円滑な共同生活を支える
マンション管理士は、マンションの長期的な価値を守るための重要な役割を担うため、不動産業界や管理会社での活躍が期待できるでしょう。
電気工事士
電気工事士は、電気設備の工事や取り扱いを行うために必要な国家資格で、第一種と第二種にわかれます。
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗など600V以下の電気設備の工事を行うことができ、家庭用太陽光発電設備の設置にも対応可能です。
一方、第一種電気工事士は、第二種の範囲に加えて、最大電力500kW未満の工場やビルなどの電気設備の工事も行うことができます。
電気工事士の主な業務は、建物の電気配線や照明設置を行う「建設電気工事」、鉄道の電力供給設備の保守・管理を行う「鉄道電気工事」などです。
近年では、再生可能エネルギーの普及に伴い、太陽光発電や電気自動車(EV)用の充電設備設置の需要も高まっています。
また、通信設備やエアコン設置の増加に伴い、一般家庭向けの電気工事の仕事も増加。
独立開業も可能であり、手に職をつけたい人にとって魅力的な資格のひとつといえるでしょう。
電気主任技術者
電気主任技術者は、電気設備の保安・監督を行う専門職であり、インフラを支える重要な国家資格です。
電気主任技術者には、第一種・第二種・第三種の3種類があり、それぞれ監督できる電気設備の範囲が異なります。
第一種は、すべての事業用電気工作物を、第二種は17万ボルト未満の設備を、第三種は5万ボルト未満の設備を対象とします。
主な業務は、電気設備の保安・点検、故障対応、電気工事の現場監督、設備周辺の清掃作業などです。
電気設備の維持管理は、安全確保だけではなく、効率的な運用にも直結するため、電気主任技術者の存在は不可欠といえるでしょう。
特に発電所や工場、大規模ビルなどでは、法律で電気主任技術者の選任が義務づけられているため、資格をもつことで安定した職に就きやすくなります。
また、資格取得後は電気保安法人や企業内技術者として働くほか、独立開業して企業の電気保安管理を請け負うことも可能です。
社会的評価が高く、需要のある資格のため、長期的に安定したキャリアを築けるでしょう。
登録日本語教員
登録日本語教員は、外国人に日本語を教えるための国家資格で、日本語教育の質を維持・向上させることを目的としています。
2023年に施行された「日本語教育機関の認定等に関する法律」に基づき制定されました。
日本語学校などの認定日本語教育機関で働くために必須の資格で、取得することで日本語教師としての社会的地位や認知度が向上し、ほかの日本語教師と差別化できます。
登録日本語教員の主な業務は、外国人留学生や技能実習生などを対象に、日本語の指導を行うことです。
日本語教育の現場では、単に言語を教えるだけではなく、日本の文化や生活習慣の指導も求められます。そのため、言語学や異文化コミュニケーションの知識も必要です。
今後、外国人留学生の増加に伴い、日本語教育の需要はますます高まることが予想されています。資格を取得することで、国内外の日本語教育機関での活躍の幅が広がるでしょう。
気象予報士
気象予報士は、気象データをもとに天候や気象現象を予測し、その結果を報告する専門家です。
気象庁の観測データや数値予報モデルを活用し、天気図や気象レーダーのデータを解析して、地域ごとの気象状況や長期予報を行います。
一般的に気象予報士といえば、テレビの天気キャスターを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、実際には民間企業や自治体、気象会社で活動するケースが多いです。
例えば、食品業界やエネルギー業界では、気象情報をもとに生産量や供給計画を立てるため、気象予報士のもつ専門的な知見が重宝されます。
また、地方自治体においては、災害時の防災気象情報の提供や避難指示のサポートなど、防災対策の一環としての役割も担当。
さらに、自衛隊の航空気象群などでも活躍しており、航空機運用のための気象データ収集・分析に携わります。
専門的な気象知識を多方面で活かせるため、気象予報士の職域は非常に幅広いです。
通関士
通関士は、貿易取引における通関手続きを専門的に担当する国家資格です。
具体的には、輸出入に関して必要となる税関申告書の作成や関税額の確認、納付手続き、税関検査の立ち会い、不服申し立て時の代理業務などを担います。
通関士は「通関業法」にもとづき、通関業者に勤務し、営業所ごとに設置が義務づけられているため、全国各地で活躍するチャンスがあるでしょう。
特に貿易量の多い湾岸都市や空港周辺では需要が高いです。
また、物流業界や商社などで重宝される存在でもあります。
通関士には「通関書類の審査」や「通関書類への記名」といった独占業務があり、専門性の高さが保証されていることも魅力。
貿易や物流が活発な現代社会において、通関士の存在はますます重要となっています。
全国通訳案内士
全国通訳案内士は、日本国内を訪れる外国人観光客に対し、外国語を用いて観光案内や解説を行う専門職。
語学力はもちろんのこと、日本の歴史や文化、地理に関する知識も求められるため、試験では語学力だけではなく、幅広い教養が試されます。
試験に合格後、都道府県に登録することで「全国通訳案内士」として正式に活動できます。
活動範囲は広く、観光地での案内や歴史的背景の解説、文化体験のガイド役などが主な仕事です。
働き方としては、自営業としてツアーガイドを行うほか、旅行会社や観光施設に所属して業務を担当するケースが多いです。
昨今、インバウンド需要が高まる中、訪日外国人に対して日本の魅力を的確に伝える「全国通訳案内士」の役割が重要視されています。
語学力とホスピタリティを活かして、日本文化を世界に発信する、やりがいのある職種といえるでしょう。
ITパスポート
ITパスポートは、情報処理技術者試験の初級レベルに位置づけられる資格で、ITを活用するあらゆるビジネスパーソンが対象です。
IT基礎知識だけでなく、経営やマネジメントに関する知識も網羅する試験範囲のため、ITスキルはもちろん、ビジネスリテラシーを証明する資格としても評価されています。
近年ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が増しており、業種や職種を問わず、ITリテラシーをもった人材の需要が拡大。
特に、新入社員研修やキャリアアップを目指す社会人が、基礎力強化の一環としてITパスポートを活用するケースが多いです。
また、ITパスポート取得者は、情報処理セキュリティやネットワークの基本を理解しているため、業務効率化やデジタル化推進に貢献できる人材として評価されやすくなります。
キャリア形成の基盤としておすすめの資格です。
国家資格の種類は4つ!それぞれの特徴や資格例
国家資格には以下の4つの種類があり、目的や業務範囲に応じて異なる特徴をもっています。
- 業務独占資格
- 名称独占資格
- 設置義務資格
- 技能検定
ここでは、それぞれの特徴や代表的な資格について解説します。
業務独占資格
業務独占資格とは、その資格をもつ者だけが独占的に特定の業務を行うことができる資格です。
無資格者がこれらの業務を行うことは法律で禁止されており、違反すると罰則が科せられるため、法的保護が強い資格といえます。
主に専門性が求められる職種に多く、国家試験に合格しなければ取得できません。
業務独占資格の代表的なものは以下のとおりです。
- 司法書士
- 医師
- 弁護士
- 行政書士
- 社会保険労務士(社労士)
名称独占資格
名称独占資格とは、資格をもつことで特定の名称を名乗ることが許される資格です。
資格がなくても同様の業務を行うことは可能ですが、資格名を名乗ると法律違反となります。
名称独占資格は、専門性を示すために有効です。資格保持者であることが信頼性やスキルの証明になります。
代表的な名称独占資格には以下のようなものがあります。
- マンション管理士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 技術士
- 中小企業診断士
設置義務資格
設置義務資格とは、企業や事業場で業務を遂行するために必ず設置が求められる資格です。
有資格者がいないと業務が停止してしまうため、企業からのニーズが非常に高く、就職や転職で有利になります。
多くの場合、業務独占資格や名称独占資格と重複していることが多いでしょう。
設置義務資格には以下のような資格があります。
- 宅地建物取引士
- 衛生管理者
- 管理業務主任者
- 測量士
- 通関士
- 採石業務管理者
技能検定
技能検定とは、特定の職業に必要な技能を評価する国家資格です。
合格者には「技能士」の称号が与えられ、職場での専門性を証明することが可能に。
建築業や製造業を中心に、幅広い分野で実施されており、実技試験と学科試験が組み合わされているケースが多いです。
技能検定資格には次のようなものがあります。
- ファイナンシャル・プランニング技能士
- 建築大工技能士
- 電気工事施工管理技士
- 機械保全技能士
- 塗装技能士
国家資格で設けられがちな受験資格は?
国家資格には、業務の専門性や社会的責任の大きさから、受験資格が設けられていることが多いです。
ここでは、代表的な受験資格の条件を5つ紹介し、それぞれの特徴を解説します。
- 学歴
- 年齢
- 実務経験
- 身体要件
- 講座の受講
学歴
学歴要件が設けられている国家資格は、公務員試験や専門職試験に多く見られます。
公務員試験では「高卒程度」「短大・専門卒程度」「大卒程度」などで受験レベルが異なります。
また、司法試験や社会保険労務士(社労士)なども、「原則、短大や大卒以上」が条件です。
年齢
年齢制限は主に公務員試験に設けられており、国家総合職や国家一般職、法務省専門職員などでは30歳が上限となっています。
近年は地方公務員試験で年齢制限を緩和する自治体が増加していて、35歳まで受験可能なケースもあります。
また、社会人経験者枠では59歳まで受験できる自治体も多く、年齢に関する規制は柔軟になりつつあるといえるでしょう。
実務経験
調理師や介護福祉士、技術士など、専門技術を伴う資格では、一定期間の業務従事が必須条件となることが一般的です。
例えば、建築士は学歴に応じて異なる年数の実務経験が求められ、税理士試験でも職歴や実務経験が重視されます。
さらに試験に合格しても、資格を活かして働く際に登録要件として実務経験が必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。
身体要件
身体的条件が課されている資格は、消防士・警察官・航空管制官など、公安系の職種が代表的です。
身長や体重・視力・体力などが一定基準を満たしている必要があります。
体力が求められる職務であるため、基準を満たさないと思われる場合は日頃から鍛錬しましょう。
講座の受講
専門技術が必要な資格では、指定講座の受講が受験資格となっているケースが多いです。
例えば、美容師資格は指定の美容専門学校を修了しなければ、美容師国家試験は受験できません。
資格ごとに受講期間やかかる費用が異なるため、受験を検討する際にしっかり確認しましょう。
まとめ
このコラムで紹介した、受験資格なしで取れる国家資格は次のとおりです。
- ファイナンシャルプランナー
- 中小企業診断士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
- マンション管理士
- 電気工事士
- 電気主任技術者
- 登録日本語教員
- 気象予報士
- 通関士
- 全国通訳案内士
- ITパスポート
上記の資格は「実務経験なし、年齢制限なしで誰でも受験できる」ため、受験層が幅広く、どなたでも受験可能です。
資格取得により、専門的なスキルを身につけることで、キャリアアップや新たな職種への転職が有利になります。
独立開業や専門職として活躍できる資格をもつことで、自分の強みを活かした働き方もできるでしょう。
興味のある分野から挑戦し、スキルアップを目指してみてはいかがでしょうか。