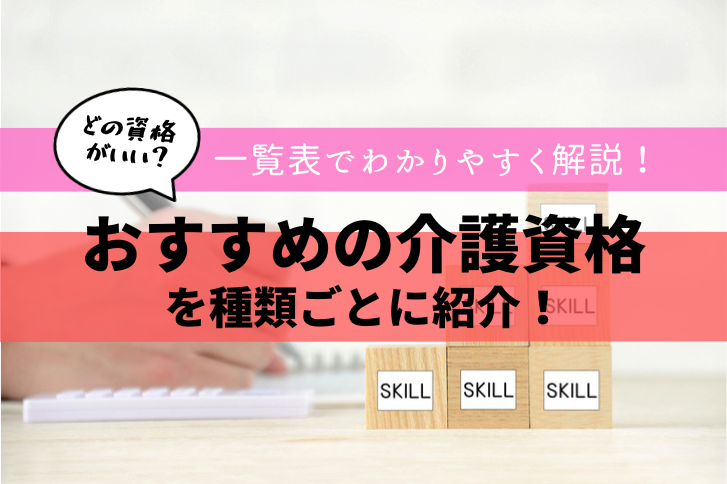電気工事の資格一覧!25種類の難易度や合格率、初心者向けのおすすめを紹介!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

電気工事に関連する資格は数多く、工事現場や発電所、大型商業施設など、資格によって活用できる就業先もさまざまです。
「どんな種類の資格があるんだろう?」「難易度はどのくらいだろう?」と取得する資格を検討している方もいるでしょう。
当コラムでは電気工事に関連する資格について、難易度や受験資格などとともに紹介します。
電気業界に興味がある方はぜひ参考にしてください。
目次
電気工事の資格おすすめ3選
電気工事に関連する資格で、特におすすめなのは以下の3つです。
| 資格名 | 合格率 | 特徴 |
| 第二種電気工事士 | 学科:50~60% 技能:65〜75% | ・住宅や小さな店舗などの住宅工事をできる・電気工事において最もポピュラーな資格・受験資格の制限ないため誰でも挑戦可能 |
| 第一種電気工事士 | 学科:55%前後 技能:65%前後 | ・第二種電気工事士の上位資格・ほぼすべての電気工事をできるようになる・3年以上の実務経験が必要なためハードルは高め |
| 第三種電気主任技術者(電験三種) | 5.5%~20% | ・受電設備や配線などの保安監督ができる・社会的な信頼度が高く就転職に有利に働く・受験資格の制限はないが難易度は高い |
特に、第二種電気工事士は業界未経験の方のエントリー資格としてもおすすめ。
電気工事関連の資格群の中では比較的難易度が低く、受験勉強を通して電気工事の基本的な知識を習得できます。
上位資格である第一種電気工事士などと違って受験資格の制限などもないため、最初に取得を目指す資格としては最適といえます。
電気工事の資格25種類一覧
ここでは、電気工事に関連する25資格を難易度とともに紹介します。
なお、それぞれの資格に掲載した表の「難易度」の項目は、合格率20%ごとに★をひとつ付ける形で判定しています。
電気工事士
電気工事士は、電気工事の従事者に与えられる経済産業省認定の国家資格です。
第一種・第二種の2階級があります。
第二種電気工事士
| 合格率 | 【学科試験】50~60% 【技能試験】65〜75% 【最終合格率】32.5〜45% |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
| 受検資格 | なし |
第二種電気工事士は、住宅や小さな店舗の電気工事などに携われる資格です。
関連資格の中では比較的合格率が高く、特別な受験資格が必要ないため、業界未経験の方が最初に挑戦する資格としておすすめできます。
第一種電気工事士
| 合格率 | 【学科試験】55%前後 【技能試験】65%前後 【最終合格率】36%前後 |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 受検資格 | なし※免状の交付に3年以上の実務経験が必要 |
第一種電気工事士を取得すると、ほぼすべての電気工事が担当できるようになります。
資格の責任が重くなる分、資格取得の難易度は第二種と比較するとやや高め。
受験資格はありませんが、合格後に免状の交付を受けるためには3年以上の実務経験が必要です。
電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、国土交通省が管轄する電気工事の関連資格です。
1級・2級の2階級があります。
2級電気工事施工管理技士
| 合格率 | 【第一次検定】45〜60% 【第二次検定】45〜70% 【最終合格率】20~42% |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 受検資格 | ・受験年度に満17歳以上であること・実務経験1年以上 |
2級電気工事施工管理技士は、建設現場で専任技術者・主任技術者として業務に従事できる資格です。
一般建設業の事業所に配置が義務付けられているなど、社会的な需要は高め。
工程の調整や図面の作成だけでなく、作業員の管理など関係者とのコミュニケーションも行います。
1級電気工事施工管理技士
| 合格率 | 【第一次検定】35~56% 【第二次検定】50〜73% 【最終合格率】17.5〜40.8% |
| 難易度 | ★★★★★ |
| 受検資格 | ・受験年度に満19歳以上であること・実務経験3年以上 |
1級電気工事施工管理技士は、工事現場の統括・監理まで行える資格です。
責任者として公共事業をはじめとする大規模なプロジェクトにも携われる分、受験資格に3年以上の実務経験が求められます。
取得できれば多くの事業所から求められる人材になれるでしょう。
電気主任技術者
電気主任技術者は、電気設備の保安・管理などを行う際に必要な国家資格です。
第一種〜第三種までの3階級に分かれています。
第三種電気主任技術者(電験三種)
| 合格率 | 5.5~20% |
| 難易度 | ★★★★★ |
| 受検資格 | なし |
第三種電気主任技術者(電験三種)を取得すると、電圧5万ボルト未満の電気工作物の保全管理に従事できます。
電気主任技術者の中では初級の位置付けで受験資格もありませんが、例年の合格率は10%を切ることもあるなど、難易度は非常に高いです。
また、電験三種試験は一次試験のみとなります。
第二種電気主任技術者(電験二種)
| 合格率 | 【一次試験】22~35% 【二次試験】12〜28% 【最終合格率】2.6〜9.8% |
| 難易度 | ★★★★★ |
| 受検資格 | なし |
第二種電気主任技術者(電験二種)を取得すると、電圧17万ボルトの電気工作物の保全管理を担当できます。
発電所や変電所といった施設にも就業の幅が広がり、将来性や社会的な需要の高い資格です。
ただし最終合格率は10%未満と、誰でも合格できる資格ではありません。
第一種電気主任技術者(電験一種)
| 合格率 | 【一次試験】19~33% 【二次試験】2〜12% 【最終合格率】0.3〜4% |
| 難易度 | ★★★★★ |
| 受検資格 | なし |
第一種電気主任技術者(電験一種)を取得すると、すべての電気工作物の保全管理に携われるようになります。
扱う電力に制限がないため、大型の電力設備を有する大手電力会社や大規模商業施設など、活躍の幅が広がるでしょう。
第二種・第三種と比較すると受験者自体が少ないため、取得できれば大きなアピールポイントになります。
一部の科目だけ合格した場合、翌年度及び翌々年度にその試験が免除される制度があるため実際の合格率はもう少し高いと予想されますが、それでも難易度が高いことに変わりはありません。
電気通信主任技術者
電気通信主任技術者は総務省が管轄する国家資格で、電気通信ネットワークの工事や維持に従事します。
伝送交換主任技術者・線路主任技術者の2資格があります。
伝送交換主任技術者
| 合格率 | 21~29% |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 受検資格 | なし |
伝送交換主任技術者は、通信データを送信先に送るための設備や機器の設置・維持を担当します。
具体的な取扱機器としては、事業所の衛生通信設備やルーター、光ファイバーなど。
快適な通信環境を維持するうえで欠かせない資格です。
線路主任技術者
| 合格率 | 30~43% |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 受検資格 | なし |
線路主任技術者は、回線やケーブルなど、データの物理的な経路となるインフラ部分の設置・維持を担当する資格です。
配線器具や電柱、配管などの監督も担当できます。
電気通信の工事担任者
工事担任者は公衆回線やケーブルテレビなどの配線接続工事に従事できる、総務省管轄の国家資格です。
担当できる通信設備の種類によって、「アナログ通信」「デジタル通信」「総合通信」の3資格があります。
また、アナログ通信とデジタル通信にはそれぞれに第一級・第二級の区別があります。
アナログ通信(旧名:AI種)
| 合格率 | 【第一級】30~38% 【第二級】40〜60% |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
| 受検資格 | なし |
アナログ通信を取得すると、アナログ電話回線やISDN回線の工事を担当できるようになります。
第一級ではPBXなど大規模な電話交換機の工事に、第二級では一般家庭や小規模な事業所における電話設備やFAXの工事などに携わることが可能です。
デジタル通信(旧名:DD種)
| 合格率 | 【第一級】25〜30% 【第二級】40〜50% |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
| 受検資格 | なし |
デジタル通信を取得すると、インターネットなどデジタル回線の工事を担当できるようになります。
第一級は、ISDNを除くすべてのデジタル通信工事が対象。
第二級には「回線速度が1ギガビット/秒以下」の制限があるため、従事可能な工事の規模がやや小さくなります。
総合通信(旧名:AI・DD総合種)
| 合格率 | 30~40% |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 受検資格 | なし |
総合通信は、デジタル通信・アナログ通信のすべての工事が対象となります。
扱える機器の種類に制限がないため、「一度の工事でアナログ回線もデジタル回線も扱いたい」といった場合には特に力を発揮します。
認定電気工事従事者
| 合格率 | -(講習のみ) |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 認定基準 | ・第一種電気工事士試験に合格 ・第二種電気工事士免状+指定の実務経験3年以上or講習の受講・電気主任技術者/電気事業主任技術者免状+指定の実務経験3年以上or講習の受講 |
認定電気工事従事者は、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の工事に必要な資格です。
個別の資格試験はなく、特定の資格保有者が実務経験を積むか、指定の講習を修了することで交付されます。
認定には電気工事士や電気主任技術者など高難易度の資格が必要なため、取得難易度はやや高めです。
特種電気工事資格者
| 合格率 | 非公開 |
| 難易度(参考値) | ★★★☆☆ |
| 認定基準 | ・電気工事士免状交付+実務検定5年以上+講習を修了 ・電気工事士免状交付+試験合格(ネオン工事) ・電気工事士免状交付+実務経験5年以上+試験合格(非常用予備発電装置工事) |
特種電気工事資格者は「ネオン工事」「非常用予備発電装置工事」の2資格を内包する呼称です。
2資格の認定基準はそれぞれ異なりますが、電気工事士の免状交付を受けていることが前提となります。
認定試験の難易度は非公開ですが、「講習参加者の例年の合格率は100%」とのデータもあり、比較的合格しやすい試験と考えられます。
消防設備士甲種4類
| 合格率 | 30%前後 |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 受検資格 | ・4類以外のいずれかの甲種消防設備士 ・乙種消防設備士+整備経験2年以上 ・消防用設備の工事補助として5年以上の実務経験 ・専門学校卒業程度検定合格 ・指定の資格保有者・教育機関で指定の学科を修了 など |
消防設備士甲種4類は、スプリンクラーや火災報知器など、電気を用いる消防設備の設置工事や整備ができる資格です。
学歴以外に指定の資格を保有することで受験できます。対象の資格には、電気工事士や電気主任技術者などがあります。
エネルギー管理士
| 合格率 | 20~35% |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 受検資格 | なし ※免状の申請に1年以上の実務経験が必要 |
エネルギー管理士は、工場などの現場で電力や熱エネルギーの管理業務に従事するための資格です。
電気供給業・ガス供給業のほか、製造業や鉱業など幅広い事業所に需要があります。
受験資格はありませんが、合格後の免状申請に1年以上の実務経験が必要です。
安全・衛生関係の資格
安全・衛生に関連する資格にも、電気工事にかかわるものがあります。
一例として、以下の9資格・講習を挙げます。
- 高所作業車運転者
- 電気取扱者(低圧、高圧・特別高圧)
- 職長・安全衛生責任者
- 車両系建設機械運転者
- 研削といし取替試運転作業者
- アーク溶接作業者
- クレーン・デリック運転者
- 玉掛作業者
- 高圧ケーブル工事技能認定
高所作業車運転者
| 合格率 | 99%※講習+修了試験 |
| 難易度 | ★☆☆☆☆ |
| 受検資格 | なし |
高所作業車運転者は、作業床の高さ10m以上の高所作業車を運転するための資格です。
高所の設備点検などに使われるため、電気工事士や電気主任技術者が取得することもあります。
取得には指定の講習+修了試験が必要ですが、難易度は低めです。
電気取扱者(低圧、高圧・特別高圧)
| 合格率 | -(講習のみ) |
| 難易度 | – |
| 受検資格 | なし |
電気取扱者は厳密には資格ではなく、電気災害防止のために作業者を対象として実施される安全衛生教育です。
法定教育のため、電気工事に関わる作業員であれば資格の種類や有無にかかわらず受講する必要があります。
職長・安全衛生責任者
| 合格率 | -(講習のみ) |
| 難易度 | – |
| 受検資格 | なし |
職長・安全衛生責任者は、特定の業務に従事する作業員を対象に実施される法定教育です。
作業現場において「監督者」や「安全衛生責任者」に選任された人に受講義務があります。
電気工事施工管理技士や電気主任技術者であれば受講を指示される可能性があるでしょう。
車両系建設機械運転者
| 合格率 | -(講習のみ) |
| 難易度 | – |
| 受検資格 | なし |
車両系建設機械運転者は、パワーショベルやブルドーザーなどの建設機械の運転者となるために必要な講習です。
工事現場で活用する機械が運転できるようになるため、電気工事施工管理技士など建設現場にかかわる資格保有者であれば受講の価値があるでしょう。
研削といし取替試運転作業者
| 合格率 | -(講習のみ) |
| 難易度 | – |
| 受検資格 | なし |
研削といし取替試運転作業者は、グラインダーや切断機といった電気工具の試運転や「研削といし」の取り替えなどに関する講習です。
工事現場などで「といし」の取り替え作業を行う場合は、受講の必要があります。
アーク溶接作業者
| 合格率 | 非公開 |
| 難易度 | ★☆☆☆☆ |
| 受検資格 | ・満18歳以上 |
アーク溶接作業者は、アーク溶接を行うための国家資格です。
所定の技能講習を受講すれば基本的に取得が可能なため、非常に「取りやすい」資格といえます。
業務の一環でアーク溶接を扱う場合は取得の必要があります。
クレーン・デリック運転者
| 合格率 | 【学科試験】57%前後 【実技試験】45〜48% 【最終合格率】26%前後 |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 受検資格 | なし |
クレーン・デリック運転者は、工場や建設現場に欠かせない重機であるクレーンやデリックを運転するために必要な資格です。
吊り上げ荷重や車種によって3種類の資格があります。建築現場の作業員を志望する場合、事前に取得しておけば業務幅が広がります。
玉掛作業者
| 合格率 | 96%〜 |
| 難易度 | ★☆☆☆☆ |
| 受検資格 | なし |
玉掛作業員は、玉掛作業(クレーンのフックに荷物を掛け外しする作業)を行うための資格です。
認定には技能試験を突破する必要がありますが、2日間の講習にまじめに取り組めば合格は難しくありません。
高圧ケーブル工事技能認定
| 合格率 | -(講習のみ) |
| 難易度 | ★★★★☆ |
| 受講条件 | ・第一種電気工事士免状取得 ・第二種電気工事士免状取得+工事経験5年以上 |
高圧ケーブル工事技能認定は、高圧ケーブルの安全な取り扱いのために電気技術者などを対象として行われる講習です。
第二種電気工事士免状+工事経験で受講する場合は少し注意が必要。
高圧ケーブルは第一種電気工事士の資格範囲のため、第二種電気工事士免状しかない場合は修了しても該当の工事は担当できません。
まとめ
当コラムでは電気工事関連の資格について、以下の資格を紹介しました。
- 電気工事士
- 電気工事施工管理技士
- 電気主任技術者
- 電気通信主任技術者
- 電気通信の工事担任者
- 認定電気工事従事者
- 特種電気工事資格者
- 消防設備士甲種4類
- エネルギー管理士
- その他安全・衛生関係の資格
一口に電気工事関連といっても、担当できる業務内容や規模、仕事の仕方などにそれぞれ違った特徴があります。
「現場で作業をしたい」「事務メインにしたい」「現場監督になりたい」など、目的に合わせて取得すべき資格を選ぶことが重要です。