測量図とは?地積測量図・確定測量図・現況測量図の必要なタイミングや入手方法を紹介
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
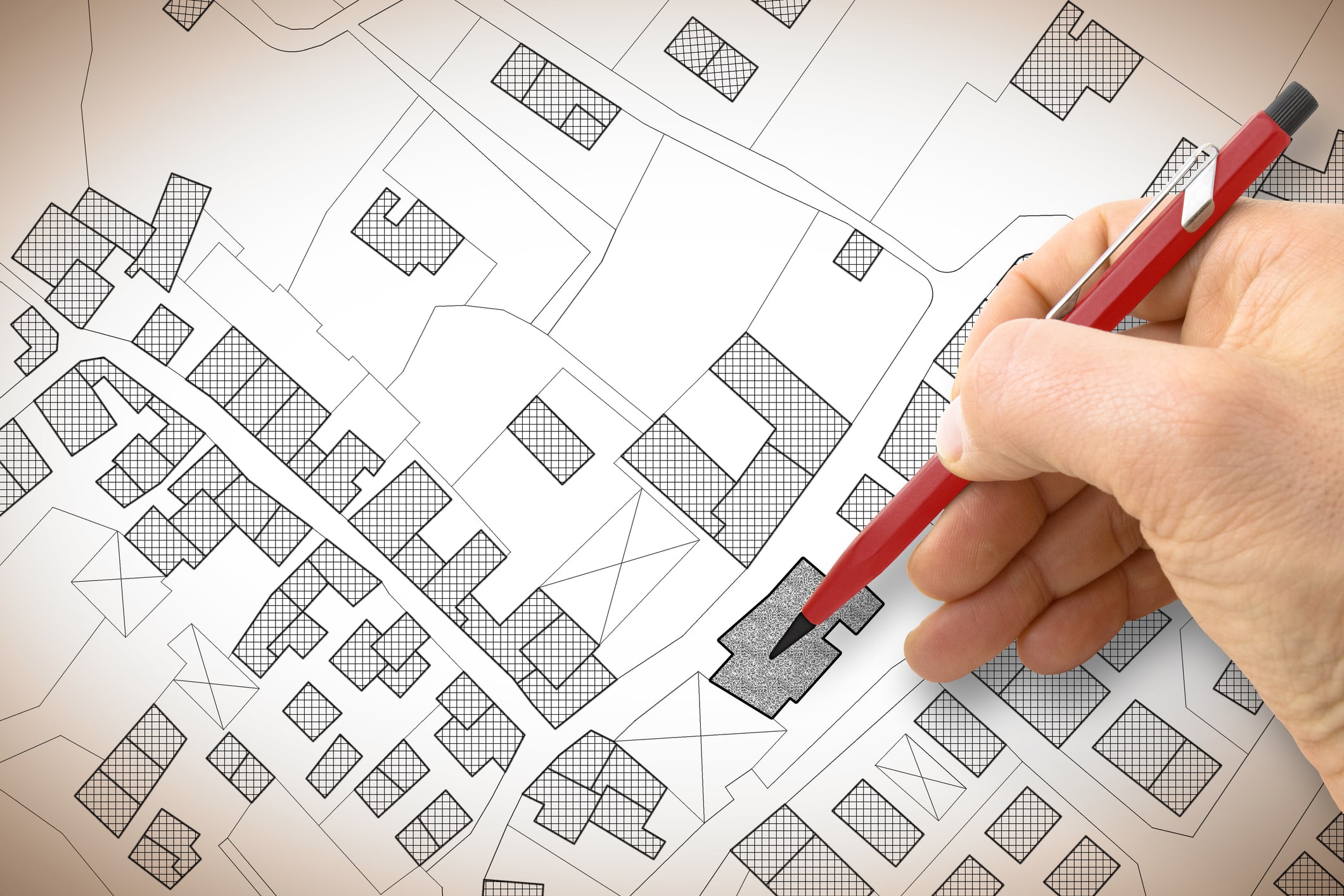
土地を売買するときは、登記記録の他に図面も必ず確認しますよね。
稀に図面がない土地もありますが、多くの場合は「測量図」があると思います。
でもそれが「どのような測量図なのか」をしっかり把握した上で確認していますでしょうか?
一口に測量図といっても、「地積測量図」「現況測量図」などの種類がありますが、それぞれの違いや意味を説明できる人は少ないのではないでしょうか。
土地は大きな財産ですから、図面の種類を間違えて思わぬトラブルなどが生じないよう、しっかりとその違いを認識しておきましょう。
目次
測量図とは?

測量図とは、その名の通り、専門家が測量した結果を示した図です。
一般的には測量は測量士が行うもの、というイメージがあると思いますが、実は民間人が所有する土地についての測量図は土地家屋調査士という国家資格者が作成します。
隣地との境界を調査・測量し、法務局へ登記できるのは土地家屋調査士だけなのです。
そして土地家屋調査士が測量した結果を図示したものが測量図となります。
どの測量図も、基本的には面積や形状が示され、境界のポイント、辺長、求積の方法などが記載されます。
また、方位や縮尺なども合わせて明示されます。
記載事項はどの測量図も似たり寄ったりですが、ものによって作成する目的や精度が異なってきます。
それでは3つの測量図についてご説明していきましょう。
測量図は地積測量図・現況測量図・確定測量図の3種類がある!

測量図には「地積測量図」「現況測量図」「確定測量図」の3つがあります。
まずはざっくりとどのようなものなのかを見ていきましょう。
地積測量図とは
地積測量図は、登記所に備え付けられる図面です。
土地の地積に関する測量図で、分筆や地積更正など、一定の登記を申請する際に提出が義務付けられています。
これらの登記を申請したことがある土地であれば登記所に備え付けてあることになります。
ただし昭和35年から始まった制度であるため、それ以前に登記申請がされた土地は地積測量図がない場合もあります。
地積測量図がない場合は、土地家屋調査士に測量と図面作成を依頼しましょう。
また地積測量図と混同されやすい言葉として「公図」があります。
公図は「地図に準ずる図面」と言われ、主に明治時代に租税徴収の目的で作成されました。
地積測量図は土地の面積や境界の距離の記載がある正確な図面、公図は土地の位置や形状が知れる大まかな図面という違いです。
現況測量図とは
その名の通り、土地の「現況」を測った図面です。
土地家屋調査士が現地にある境界標やブロック塀など、境界と思われるポイントを調査・測量し、図面にしたものです。
隣地地の所有者や、公道との境界立会いは行わずに作成されます。
確定測量図とは
確定と名が付いている通り、明確に決まった境界を示した図面です。
現況測量図を基に隣接地所有者や公道所有者(国や自治体)と立会いを行い、すべての境界が確定されたものになります。
それぞれの測量図が必要になる状況と入手方法

それぞれの図面についてまとめると、以下のような形となります。
| 地積測量図 | 登記申請で必要になるもの | (所有者)調査士に依頼して作成する(他者)登記所で入手する | 信頼度:低~高 (作成された年によって異なる) |
| 現況測量図 | 不動産取引で最初に用意するもの | (所有者)調査士に依頼して作成する | 信頼度:中 |
| 確定測量図 | 不動産取引で最終的に必要になるもの | (所有者)調査士に依頼して作成する | 信頼度:高 |
地積測量図が必要になる状況と入手方法
地積測量図は、登記申請において必要とされる図面で、土地の面積や位置・形状を公示するためのものです。
所有者が土地を分けたり、地積を正しく修正する際に添付することとされており、提出されたものは登記所に保管されます。
地積測量図は、記載事項も明確に定められている公的な図面です。
では精度も高いか、というと必ずしもそうでもありません。
先ほどもお伝えした通り、昭和35年から始まったものであるため、測量技術が今と当時でかなり差があるのです。
また、何度か記載事項が改正されており、年代によって精度が大きく変わる図面といえるでしょう。
平成17年以降のものは座標値の記載が義務付けられているため、かなり正確であるといえます。
地積測量図の取り方は、最寄りの法務局で誰でも取得することができます。また、インターネットで取得することもできます。
誰でも入手できるため、不動産取引においては不動産業者や買主側が一番先に確認する図面といえるでしょう。
現況測量図が必要になる状況と入手方法
土地の売買においては、実際に現地の広さを測量することが必要です。
稀に測量を行わずに登記記録の数値のみで売買する公簿売買もありますが、トラブルの原因となりやすいので、測量した上での実測売買が主流です。
そこでまず最初に行われるのが仮測量といわれるものです。
現地において「きっとここが境界だろう」と思われる塀やフェンス、境界杭などのポイントを測り、地積測量図や他の資料と照らし合わせて図面にするのです。
これが現況測量図です。
現況測量図があれば、その土地のおおよその面積や評価額、どれだけの建物が建てられるかを把握することができます(建築確認の申請でよく使われています)。
ただし、あくまで推測で作られたものですから、この図面をそのまま不動産取引で使うことはできません。
そこで登場するのが、これからご紹介する確定測量図です。
確定測量図が必要になる状況と入手方法
確定測量図は、現況測量図を基に、隣接地所有者や公道所有者(国や地方公共団体)と立会いを行って確定させたものとなります。
隣地所有者などからの情報で、仮測量だけでは分からなかったポイントが出てくることもあるので、精査の上で最終的な境界がここで決まります。
官民の境界も明確に決まるため、最も正確で信頼性の高いものといえるでしょう。
不動産取引においては必須の図面といえます。
測量図についてのご相談は、ぜひ信頼のおける土地家屋調査士へお寄せください。





