合格者の声|講師の方々がすごく寄り添ってくれて、こんなによくしてくれた先生のために受かろうという気持ちにすらなった 中野 由里子さん
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

目次
- 受講されていたカリキュラム
- 土地家屋調査士試験を目指した理由・契機
- アガルートアカデミーの講座を受講しようと思ったきっかけ
- 合格体験記・学習上の工夫
- 【測量士補】総合講義のご感想・ご利用方法
- 【測量士補】3時間で押さえる計算問題のご感想・ご利用方法
- 【土地家屋調査士】導入講義のご感想・ご利用方法
- 【土地家屋調査士】総合講義のご感想・ご利用方法
- 過去問解説講座(択一・記述)のご感想・ご利用方法
- 新・定規の使い方講座のご感想・ご利用方法
- [中山式]複素数計算のご感想・ご利用方法
- 書式ひな形対策講座のご感想・ご利用方法
- 実践答練のご感想・ご利用方法
- 法改正対策過去問解説講座のご感想・ご利用方法
- 直前予想模試のご感想・ご利用方法
- 合格ゼミのご感想・ご利用方法
- 講師へのメッセージ
受講されていたカリキュラム
下記リンクは最新版となります。合格者の方の受講年度と異なります。
土地家屋調査士試験を目指した理由・契機
当時、金融機関で働いておりましたが、業務内容への不満や在宅勤務ができないことから、子どもが生まれたらこの仕事は長く続けられないなぁと感じ転職を考えていました。
そんな中、測量会社を経営する義父から「土地家屋調査士を目指してみたらいいんじゃない?」と言われたのが受験のきっかけとなりました。夫の、令和6年1月から9月までの育児休業取得が決定したこと、友人が司法試験に合格したことも後押しとなり、受験を決意しました。
アガルートアカデミーの講座を受講しようと思ったきっかけ
インターネットで予備校を調べたところ最初に見つけたのが中山先生の講座でした。つまらない講義だったら続かないなぁと思っていましたが、サンプル動画を拝見したところ、「なんだこれ、おもしろそう!この先生についていけば、私でも合格に近づけるかも!」と思い、アガルートを受講することに決めました。
合格体験記・学習上の工夫
1歳と2歳の子どもを育てていたので、夜は2〜3時間おきの夜泣き対応があり、睡眠時間をしっかり取れない中での学習でした。また、夫の育休中とはいえ外に出て集中して勉強!ということもなかなかできなかったので、正直不安を抱えながら学習を進めていました。そんな中私の中でペースメーカーとなったのは合格ゼミでした。令和6年の1月下旬から学習を始め、総合講義の視聴を終えたのが3月末頃。4月から択一を始め、ゼミが始まるタイミングではまだ一通り解説動画を見ただけで記述問題を解いたことがありませんでした。ゼミは2週間に1回、課題の答練を解いた上で、その問題の論点を教えてもらったり、それについて質問するような内容でしたが、初めの何回かはついていけませんでした。どうにか他のゼミ生たちについていかないと、と必死で勉強したのを覚えています。
仕事はしていないものの、子どもの急な発熱やイヤイヤ、夜泣きなど毎日同じリズムで生活することが困難でした。今思えば本気出すのがすごく遅いのですが、7月から、この日までにこれを終わらせる、という月の目標を決めました。そして、いつなにがおこるかわからない毎日なので、毎朝その日のノルマを付箋に書き、それを終えられるよう努力していました。また、問題を解いた際にわからなかった・曖昧だったポイント(例えば敷地権など)が出てきたらそれを付箋に書き、その日のうちに総合講義テキストにもどり復習するようにしました。その時、テキストにはR7-22、答練③-22など問題集とリンクさせるようなメモ書きをするようにしました。苦手な部分にはこのメモが増えてくるので、1日のうちのどこかで苦手を克服するための時間を作り、その部分を重点的に復習しました。
そして、学習のペースが遅い私にとってかなりプラスになったのが山崎先生のヤマ当て講座でした。分野ごとに問題がまとまっていたため、知識の整理だけでなく苦手を克服することにかなり役立ちました。伸び悩んでいた択一ですが、この講座を受けて、少し自信がつきました。
質問制度KIKERUKUNも何度か活用させていただきました。初めのうちは、時期と質問内容が見合わず厳しい意見が返ってきたらこわいなぁと思い利用していませんでした。過去問をある程度解いたのちに、初質問をしたところ、その日のうちにとてもわかりやすく解説してくださいました。床面積の考え方でつまづいた時には図入りで解説してくださって、感動したのを覚えています。
不合格であと1年時間とお金を使うのなら、ケチらずに今回で絶対に決めた方がいいと、単科講座の受講を惜しみませんでした。合格ゼミ、中里先生の記述過去問解説講座、山崎先生のヤマ当て講座の3つは取ってよかったと思っています。
他校の答練や模試を受けなくてもアガルートだけで合格することができました。オンラインの予備校であるにも関わらず、講師の方々がすごく寄り添ってくれて、最終的には、こんなによくしてくれた先生のために受かろうという気持ちにすらなっていました。長時間机に向かうことができない状況でも、アガルートの講義はスマホさえあればどこでもできます。土地家屋調査士試験の受験を検討されている方はぜひアガルートの講師陣を信じて挑戦してみてください。
【測量士補】総合講義のご感想・ご利用方法
(※今回2024年ダブル合格カリキュラムを受講していますが、測量士補に関しては2021年の同講座を受講し、合格しています。)
当時私は妊娠中で悪阻と戦っていたので、長い時間集中することが困難でした。そんな中でアガルートの講義動画は1本が短く構成されているので、体調のすぐれない時でも無理なく少しずつ見進めることができました。テキストが手元になくても、テキストを写しながら講義してくださるので、ベッドの上でも十分に学習することができました。学習時間としては平日1日1〜2時間、期間は1ヶ月半程です。
中山先生は、専門用語などでつまずかないようにかみ砕いて解説してくださるので、初学者の私にとっても非常にわかりやすく、逃げ出すことなく最後まで学習できました。また、図入りのカラーのテキストが学習内容に興味を湧かせ、最後まで飽きさせないよう作られていたと思います。さらに、総合講義テキストと過去問集のリンクがついていて、学習の際に効率よく苦手分野を潰すことができました。
講義動画一周目は深入りせず、とにかく最後まで一通り見続けるようにしました。その際にチャプター番号をテキストにメモしておき、後の学習でつまずいた時にその部分の動画をすぐに見返すことができるようにしていました。テキストを自分で読んで理解するよりも、中山先生の解説を聞いた方が早く理解できるので、このチャプター番号メモはやって良かったと感じています。
中山先生の講義を聞いて、過去問を解けば間違いなく合格できます。
【測量士補】3時間で押さえる計算問題のご感想・ご利用方法
これだけやれば、合格に必要な計算問題はマスターできると感じました。体調のこともあり、集中して勉強できる期間は二週間ほどしかありませんでした。その中でこの問題集での学習は、私にとってまさに最短ルートでした。時間のない中で、何度も繰り返し問題を解きたかったので、講義動画を視聴している時間内に自分でも計算し、難しい問題には付箋を貼りました。次からは付箋のついた問題を繰り返し解くようにして解法を頭に染み込ませました。過去問でつまずいた時にも、このテキストに戻って計算方法の確認をしました。
【土地家屋調査士】導入講義のご感想・ご利用方法
「土地家屋調査士ってどんなことするんだ?試験のこともよくわからないけどやってみるか!」と勢いで講座をとった私にわくわくを与えてくれました。
土地家屋調査士試験がどんな試験なのか、科目ごとに全体像を掴むことができました。また、なんといっても先生がキラキラしていて、試験勉強だけでなく、資格取得後もわくわくが待っているような、そんな気持ちにさせてもらいました。初学者の方はまずこれを見て、気持ちを高めてから学習に入ると良いと思います。
【土地家屋調査士】総合講義のご感想・ご利用方法
この講義とテキストのおかげで合格できました。中山先生の講義は最後まで飽きさせることなく、集中して見進めることができました。
合計約76時間の講義で全範囲学習できるなんて、驚きませんか。さらに、講義を一周視聴したあとに択一過去問を解いてみると、なんとなく、「あれ、この試験、なんか受かる気がする」と思ったのです。もちろん完璧にではないですが、講義の内容と先生の話し方が頭に残るんです。時々お話しされる体験談もおもしろくてとても好きな時間でした。
はじめの1周目は講義を見ながらテキストに先生の講義内容をメモする作業をしました。私は本を何冊も活用して勉強するのが苦手なので、知識の全てをこのテキストに集約するようにして、何かわからないことがあった時にはこのテキストに戻るようにしていました。
「知識の全てをテキストに集約」をもう少し具体的に。
・講義で先生が話されていたこと
・択一で間違えた部分。これは言い回しが違うとわからなくなってしまうものや、答練など過去問とは違う角度から出題された問題の番号を記入していました。
・記述の穴埋めで問われたが知識が曖昧な部分はその問題の番号を記入。
これらをしていくと、問題の番号メモが増えていき、自分の苦手を把握することができます。
最終的に、動画で講義を見たのが2周(土地家屋調査士法除く)、過去問を解いていく間に知識が不足していると感じた部分に関しては都度該当部分の講義を見ました。テキストを読めば良いのでは?との意見があるかと思いますが、私はわからない部分は文字を読むよりも動画を見た方が早いと感じたのでそこは自分に合ったやり方をしてください。
机に向かって勉強することができない時は、「無限プレーヤー」というアプリを活用し、この総合講義と択一過去問解説講義の音声を2倍速で聞き流していました。
過去問解説講座(択一・記述)のご感想・ご利用方法
択一過去問に関しては、通しで解くというより一問一答のように一肢一肢正誤を確認するようにしていました。それにより、問いとしては正解となっても実際にはよくわかっていないところを把握し、苦手を潰すことができました。解説動画に関しては、初めのうちは自分で20問解いた後に知識の確認として視聴しました。超直前期の10/1からは机に向かって勉強できる時間がほとんどなかったので、アプリを活用し、択一過去問解説(2倍速)を片耳イヤホンで一日中聞いていました。
諸先輩方の経験談で、「時間を計ってやると、自分の弱いところを見つけられる」というものがありました。実力のない自分がそれをやってみたところ、早く解こう!と時間ばかりに重点を置き過ぎてしまい、しっかりと肢を検討できなくなってしまったので速攻やめました。ある程度実力がついてきたと感じた9月頃から、解いた時間を記録するようにしました。学習を始めてすぐは時間にとらわれず、じっくりと考えるようにしないと本末転倒になってしまうのでお気をつけください。
私が記述過去問に取り掛かったのは6月に入ってからで、学習のペースとしては非常に遅かったと思います。実力を試すなんて時間の余裕はなかったため、まずは一通り解説講義を視聴し、テキストの解説を読むことによって問題文の読み進め方や考え方を吸収しました。この時点でひな形の学習はほぼ皆無だったので、動画の視聴を終え、実際に自分で解いてみるのと合わせてひな形の学習を開始しました。私の場合は土地と建物を通しで解く時間を取ることが難しかったため、それぞれ年度ごとに解きました。そのときにわからなかった論点を付箋にメモし、問題文の最初のページに貼りました。苦手を潰す時間をとり、その際学習したい論点を付箋から探し、復習するというやり方をしました。
また、中里先生が担当されている「記述式過去問実演講座」を追加で受講することで、それぞれの先生の良いところを取り入れることができ、問題を解く上での効率化に繋がったと感じました。
新・定規の使い方講座のご感想・ご利用方法
これがなければ作図の仕方がわからず苦労するところでした。実際にどのように定規を使って作図していくのかを動画で解説してくださったので、スムーズに記述の学習を進めることができました。
この講座は記述過去問の演習に入る前、総合講義合間の息抜きとして講義の視聴をしていました。一通り見たら、あとは実践です。作図している中で不安に思った時にはもう一度講義を見返したりして、中山先生方式をしっかりと落とし込みました。
[中山式]複素数計算のご感想・ご利用方法
初めは何をやっているか全くわからない状態で、「こんな暗号のようなものを果たして覚えられるのか」と心配でした。しかし、一通り講義を聞き、実際に問題を解くことを繰り返していけば、自然と身につけることができました。最終的には、「これがなければ合格できなかった」と感じています。他校で学習したことのある私の受験生仲間も同じように言います。中山式複素数は本当に早いです。学習を始めてから慣れるまでは不安かと思いますが、ぜひ習得してほしいです。
書式ひな形対策講座のご感想・ご利用方法
これ一冊覚えたら申請書こわいものなしだと感じました。
まずは一通り講義動画と併せてテキストで申請書例を確認しました。そのあとは、書くのではなく口に出して申請書が書けるかどうかを確認しました。書くよりも喋る方が何倍も多く回数回せると思います。初めは書き方(①②③年月日種類・構造変更、増築といった順番など)がしっくりこないところもありましたが、何回も学習していくうちに理解することができました。机に向かうことができない時には、YouTubeのひな形50例聞き流しを聞いていました。「こんなの無料で配信しないでよぉ〜、みんなできるようになっちゃうじゃんねぇ」と思っていました。
実践答練のご感想・ご利用方法
択一に関しては過去問と同じ論点でもこれまでとは違う角度から出題されるので、過去問を解くだけでは理解しきれていないポイントを整理することができました。
それですが、先生や先輩方の「過去問の知識で十分」という言葉を信じて私は択一・記述共に3周程回して終了しました。これをやるよりも択一過去問を完璧にしようと思っていたからです。
試験を終えて、後悔した点が1つあります。採点の際、記述問題の配点を全く見ていなかったことです。答練を解いたあとは配点を気にせず正誤と解説だけ見ていたので、試験中「うわぁ作図って配点どれくらいなんだ?小問って配点どれくらいなんだ?わからないからどれも時間かけるしかないかぁ。」と思いながら解いていました。おおよその配点を把握していたらこんな余計なことで不安にならずに済んだと思います。答練の後はぜひきちんと採点するようにしてみてください。
法改正対策過去問解説講座のご感想・ご利用方法
試験に出る範囲での改正点を簡潔に解説してくださるので、余計な時間を使わずに理解することができました。私は試験に受かることだけ考えて、この講座で教わったこと以外は気にせず学習を進めました。
また、改正点をまとめたレジュメが元々使っていたテキストにそのまま貼れるように設計されていたのが大変便利で良かったです。総合講義テキストに情報を集約する勉強方法をとっていたので、この工夫のおかげであちこち行ったり来たりせずに学習を進めることができました。
直前予想模試のご感想・ご利用方法
他校模試を受けていなかったので、初めて択一から通しで受けたのがこの模試でした。2時間半ってこんな風にしてあっという間に過ぎるんだなぁ、と感じた9月8日。遅いですよね、初めて通しで解いたのが試験約1ヶ月前です。合格点とされる点数は越えていたものの、わかっているつもりになっていたポイントがたくさん出てきました。「やばい、あと1ヶ月しかないのにこんなにわからないことあるのか。このままだと受からないかも。」とかなり焦ったのを覚えています。ただ、やることは一つ、苦手を潰すこと。これまで把握していたのとはまた異なる苦手が炙り出されたので、その部分をしっかり復習して自分のものにすれば良い、そう思って残りの期間は択一中心に学習を進めるようにしました。(記述はそれなりに解けても択一がとても苦手でした)
合格ゼミのご感想・ご利用方法
前述の通り、勉強のペースメーカーとなりました。私は学習のスタートで出遅れていたため、とにかく他のゼミ生についていこうと必死でした。とは言え初回のゼミは旅行中のハワイから参加しました。オンライン予備校のいいところですね。
ゼミまでに与えられた課題を解き、そのあとは復習を繰り返し行いました。活用方法は答練と同じです。
ゼミには過年度の合格者の方々にも参加していただき、勉強方法を教わる機会がありました。自分の努力の足りなさを再確認できたことと、これは取り入れてみよう、というように学習方法を改善できたのもよかったと思いました。ゼミ生の一部とはリアルでも交流していて、共に戦う仲間ができたことが嬉しかったです。
講師へのメッセージ
講師の方々の講義、フォローのおかげで最短ルートで合格することができました。ありがとうございました!
土地家屋調査士・測量士補試験の合格を
目指している方へ
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る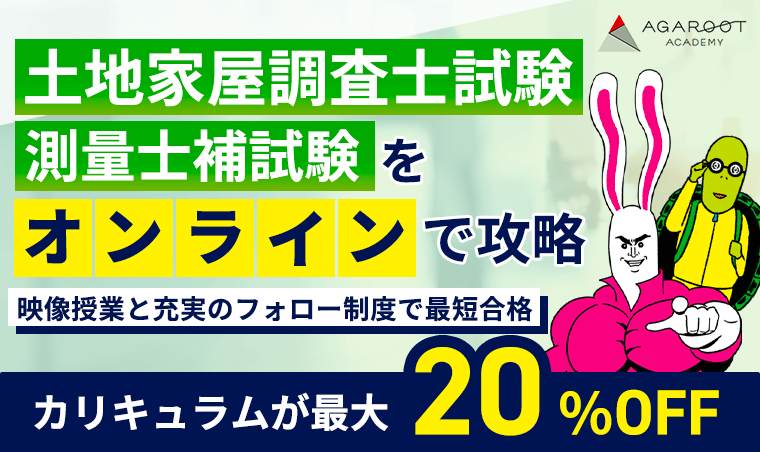
4年連続1位合格者輩出!
令和6年土地家屋調査士講座の
アガルート受講生の合格率63.64%!全国平均の約6倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
5月12日までの申込で5%OFF!
▶土地家屋調査士・測量士補試験講座を見る※2025年合格目標ダブル合格カリキュラム
