合格者の声|測量士補試験に不合格も午前試験対策に取り組み一発合格! 横山 紗梨奈さん
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

目次
- 受講されていたカリキュラム
- 土地家屋調査士試験を目指した理由・契機
- アガルートアカデミーの講座を受講しようと思ったきっかけ
- 合格体験記・学習上の工夫
- 【測量士補】総合講義のご感想・ご利用方法
- 【測量士補】3時間で押さえる計算問題のご感想・ご利用方法
- 【測量士補】3時間で押さえる文章問題のご感想・ご利用方法
- 【測量士補】実力診断模試のご感想・ご利用方法
- 【土地家屋調査士】導入講義のご感想・ご利用方法
- 【土地家屋調査士】総合講義のご感想・ご利用方法
- 過去問解説講座(択一・記述)のご感想・ご利用方法
- 新・定規の使い方講座のご感想・ご利用方法
- [中山式]複素数計算のご感想・ご利用方法
- 書式ひな形対策講座のご感想・ご利用方法
- 実践答練のご感想・ご利用方法
- 法改正対策過去問解説講座のご感想・ご利用方法
- 直前予想模試のご感想・ご利用方法
- 定期カウンセリングのご感想・ご利用方法
受講されていたカリキュラム
下記リンクは最新版となります。合格者の方の受講年度と異なります。
土地家屋調査士試験を目指した理由・契機
会社員として4年ほど勤めていましたが、今の自分の人生はこれでよいのかと思い、何か資格を取って働きたいと考えるようになりました。そのような時に土地家屋調査士という資格を知りました。この資格について調べていくうちに、デスクワークだけではなく外での仕事もあるということにこの資格ならではの魅力を感じ、受験を決めました。
アガルートアカデミーの講座を受講しようと思ったきっかけ
土地家屋調査士を受験した前年に、宅建試験を受験しました。その際、市販のテキストで合格できましたので、今回もまず本屋さんに行って情報収集をしました。そこでびっくりしたのですが、土地家屋調査士試験関連の本は、宅建試験の10分の1ほどしか取り扱いがなく、そして置いてある本も初学者の私が一から学習するにはハードルの高いものばかりでした。
ここで私は通信教育を使って学習しようと決めました。通学は私の住んでいる地域には通える所がなかったためです。パンフレットはアガルートとLECの2校を取り寄せましたが、Xを見ているとアガルートの評判が良かったのでアガルートの受講を決めました。
合格体験記・学習上の工夫
土地家屋調査士試験は全くの初学者であったため、学習の進め方がわからず、まずはアガルートの合格体験記を読み込みました。その中に、自分の学習方法と近い人を参考にするとよいとあったので、令和3年度合格の塚本優さんの学習方法が私には合っているなと感じたので、まずはその方を参考に進めていこうと思いました。
前年に宅建試験を受験していたので、その次の日から講義の視聴を開始しました。民法、不動産登記法、土地家屋調査士法と視聴したのち、択一の学習に取り掛かりました。
私が択一を最初に解く中で意識していた点が2点あります。
①テキストに戻って確認すること
問題を解いて解説を見るとどうしてもわかった気になってしまいますが、それでは頭に残らないなと思い、テキストに戻って全肢確認しました。択一は全20問、1問あたり5肢ありますので、1年分で100肢あることになります。私は該当ページに1肢ずつ付箋を貼っていきました。1年ごとに色の違う付箋を100枚ずつ貼りましたので、おかげで私のテキストはカラフルです(笑)。
最初はどこに何が書いてあるかわからず、タブレットのデジタルブックで検索して探していたので、すごく時間がかかり、心が折れそうになりました。しかし何年か進めていくとどのあたりにどんなことが書いてあるのか把握できるようになり、自分がどういったところで間違い、何がわかっていないのかがわかってくるようになりました。
②その日中、もしくは次の日に2回目を解くこと
問題を解いて、テキストに戻ることも大事ですが、私はこれでも解きっぱなしになっているような気がしました。そこで私はテキストで全肢確認したのち、その日中、もしくは次の日には同じ問題を解きなおしました。そうすることで、この肢はあそこのあの部分で確認したものだとわかるようになり、理解が進んでいきました。
1回転目を解く際に、事実的には2周したことによってこの試験に対してすごく理解が深まり、1回転目は手も足も出なかった択一の問題が2回転目では80肢はわかるようになりました。ここで知識が定着したおかげでその後の記述式もとっかかりなく解くことができました。
択一の1回転目は12月ごろに終わったので、2回転目をしつつ、複素数計算講座と定規の使い方講座の視聴も始めました。ただ私は関数電卓を触ったことがなかったので、講義を1回見ただけではさっぱり理解できず、1月中は記述の勉強に入らずに何度も講義を視聴したり、複素数計算のテキストの問題を解いたりしていました。また、これと同時にひな形を1日3問解くことを開始しました。ひな形に関しても、解く→解答を見る→また同じ問題を解く を自分の書いたものと解答が同じになるまで繰り返しました。
だいたい関数電卓の理解も深まってきたので、2月ごろ、記述式を解き始めました。土地は令和4年から、建物は平成17年から解き始めました。複素数計算とひな形を理解しながら進めていたため、土地、建物それぞれ2~3時間ほどかかりましたが、何となく解くことができました。もちろん登記の申請内容も違うし、図面もダメダメでしたが、今まで自分が学習してきたものを応用して解いていけばいいんだなという試験に対する感覚はつかめました。そしてもちろん記述式も自分で解いて、解答を見るだけでは自分の頭に残らないと思ったので、解答を確認後その日中か次の日には同じ問題を再度解きました。2回転目まではこの流れを繰り返しました。
択一も記述も2回転目までは2回ずつ解き、3回転目からは間違えたところだけを確認するようになりました。だいたいこの辺りから間違えてくる個所も減ってくるので、ルーチンとしては、例えば令和4年ならその1年分をの択一と記述をまとめて説くということをしました。最終的に択一は10回転程、記述は6回転程して、1年度分を、択一20分、土地40分、建物40分、合計1時間40分で解けるようになりました。令和6年度の本番では各階平面図を書くのに時間がかかってしまいましたが、択一17問、土地19点、建物21.5点で合格することができました。
【測量士補】総合講義のご感想・ご利用方法
測量士補試験の講座は、2月ごろから調査士試験の勉強と並行して開始しました。測量士補試験の過去問は調査士試験のものとは違い、問題の種別ごとに分かれているので、1度講義を視聴したら該当の問題を解くということをしました。ただ私は測量の経験が全くなく、語句を聞いても、イラストを見ても、全く測量についてイメージすることができませんでした。そのため、理解が深まらないまま、ある語句とある語句を何となく結びつける、計算問題は何を計算しているかわからないけど、とりあえず計算方法を覚える、わからない問題はそのまま放置するということをしていました。この状態で本試験に臨んだ結果、2問合格ラインには届かず、不合格となりました。自分で自己採点した結果、頭が真っ白になりましたが、すぐに心を切り替え、その日中に午前試験対策講座を申し込みました。私が測量士補試験においてよくなかった点は、理解を深めようとしなかったことと、わからないことはそのまま放置したことだと思ったので、午前試験対策では、なぜこの問題のプロセスはこうなるのか、そこまで理解できなければ解法だけは徹底的に覚えようとしました。そうしたことで、午前試験は択一8問、40点で合格しました。私は作図が得意ということもあったので、結果的には午前試験のほうが私には合っていたのかなと思います。
【測量士補】3時間で押さえる計算問題のご感想・ご利用方法
測量士補の過去問は問題の種類別でで2回転した後、その後は年度ごとに解いていました。私は計算問題に関しては、解き方を覚えていればある程度解けたということもあり、3時間で抑える計算問題に関しては、5月に軽く確認した程度でした。しかし本番の試験では結果的に私が苦手としていた計算問題が多く出ました。年度別で解いていて苦手としていた問題は決まっていたので、その時に理解は深められなくても、解法は徹底的に押さえておけばよかったと思います。
【測量士補】3時間で押さえる文章問題のご感想・ご利用方法
私が計算問題よりも苦手としていたのでが文章問題です。測量の経験が全くないので、水準測量やGNSS測量と聞いても、実際には何をどうするか全くイメージがわかなかったからです。3時間で押さえる文章問題は4月ごろに講義を視聴しましたが、ただ覚えるだけで語句と語句の結びつきのイメージはつかめませんでした。測量士補試験が不合格とわかってから、自分は自分のイメージができない問題は苦手なんだなと気づき、午前試験対策では特にそこを意識して問題を解くようにしました。
【測量士補】実力診断模試のご感想・ご利用方法
実力診断模試は本試験の1週間ほど前に利用しました。本番の試験は2時間ありますので、時間を計りながら実施しました。ただ測量士補試験は2時間の試験時間の中で問題数が28問しかありませんので、それほど時間に困ることはないと思います。私は講義視聴後は年度別に解いていましたので、問題の出る順番の雰囲気をつかめていたこともあり、この模試を解くにあたって特に意識したことはありません。ある程度問題の解き方がわかってきたら、年度別に解くことをおススメします。
【土地家屋調査士】導入講義のご感想・ご利用方法
私はテキスト類が届いてから、まずこの導入講義から視聴しました。学習を開始するにあたって、中山先生がおっしゃったことをメモしました。その中で印象に残っているのは、記述で問われることは、択一の知識の中からしか問われないということと、講義を視聴中にマーカーはしないということです。私はこれを聞いて、1度目の講義の視聴では中山先生がマークしたところはシャーペンで印をつけていました。そして択一でわからなかったところをテキストに戻って確認する際に、マーカーをしていました。この方法をしたことで、自分の知識がついていない重要な部分がわかりやすくなりました。
【土地家屋調査士】総合講義のご感想・ご利用方法
講義を視聴するにあたって意識したことは、テンポよく視聴を終わらせるということです。もちろんもちろん全く触れたことのない内容でしたが、私は講義視聴においては、内容をすべて理解するというよりは、この試験の全体像を把握するようなイメージで視聴しました。テキストの内容を頭に入れていくのは、講義視聴ではなく、過去問を解きながらのほうが良いと思ったからです。
中山先生の講義の特徴は、1コマ当たりの講義が10分程度ということです。例えば講義が1時間半だとしたら、1時間半まとまった時間を作らなきゃ、と少し億劫になっていたかもしれませんが、コンパクトな講義なので、まとまった時間が取れなくても飽きずに進めることができました。講義を視聴する際に、動画ナンバーをテキストに記入していくことをおススメします。こうすることで、あとからもう一度見たい部分の講義を簡単に視聴することができます。
講義を一通り視聴した後、択一の過去問に取り掛かった際に、すべての肢をテキストに戻って確認し、文字だけ見てもわからない部分は部分的に再度講義を視聴しました。前述したとおり、自分がわからないところはマーカーして、テキストに書いてないなと思った部分は、自分で書き込んだりしました。そうすることで自分だけのオリジナルテキストが出来上がっていきました。7月頃に講義を全視聴しましたが、新たな発見があまり感じられなかったので、それくらい択一を解く際にテキストを読み込みました。
過去問解説講座(択一・記述)のご感想・ご利用方法
講義を一通り視聴してから、択一の過去問に取り掛かりました。ただ、講義を最初はさらっと視聴しただけだったので、最初解く際は全然わかりませんでした。解き終わってから、アガルートの択一講座は全肢に解説動画がついているので、それを視聴してから、テキストに戻って、該当部分の確認をしました。ただ、最初は理解していない内容を、どの辺に何が書いてあるかわかっていない状態で探していたので、心が折れそうになりながら取り組んでいました。ただ平成17年から令和4年まで一通りそのように解いたら、次からは8割程度の正答率で解けるようになりました。このおかげでその後のひな形講座や記述式も特につまづくことなく進められました。
記述式は定規の使い方講座と複素数計算、そしてひな形をある程度理解できるようになってから取り組みました。ですので、問題文を読んで今まで学習してきたことを組み合わせて取り組んでいけば何となくですが流れはつかむことができました。また記述式も解説動画が充実ていたので、そちらを視聴して理解を深めることができました。私は記述の過去問は問題を見ても答えを覚えていなかったので、毎回新鮮な気持ちでできたのもよかったと思います。
新・定規の使い方講座のご感想・ご利用方法
三角定規を触るのは小学生の時以来でした。講義を視聴する前は、三角定規2つでどうやって図面を描くんだろうと思っていました。しかし実際講義を視聴してみると、描き方のコツがわかるようになりました。ただ私は左利きでしたので、講義の通りにやろうとすると、どうしてもまっすぐ線が引けず、この試験は左利きには不向きなのではと思いました。先生方に相談したところ、定規を左右鏡対象にしたらいいというアドバイスを受け、その通り実践したら、すごく描きやすくなりました。左利きの方はぜひ左右鏡対象でやってみてください!
[中山式]複素数計算のご感想・ご利用方法
複素数計算に関しても、そもそも私は関数電卓に触ったことがなかったこともあり、初めは放射計算は何をしているのか理解できませんでした。講義を1度視聴して記述式の過去問に進んだとしても手も足も出ないだろうと思い、その後4周ほど再度講義を視聴しました。視聴してから自分で理解できるまで電卓を触り続けたこともあり、4周終わったころには解説を見なくても自分で手を動かせるようになりました。ここで電卓の基礎を作っていたおかげで、記述の過去問を解いた際もそれほど座標の計算方法には困りませんでした。
書式ひな形対策講座のご感想・ご利用方法
ひな形は1月頃から取り組みました。中山先生は何度も申請書が大事!とおっしゃっていたので、一字一句間違えないことを意識しました。1日3個ずつ、正確に合うまで書きました。アガルートではインターネットからひな形用の用紙をダウンロードできたので、本番も手書きであることから、頭で覚えるのではなく、手で覚えようと思ってひたすら書きました。記述の過去問を解いた際も、これってこうだっけ?と曖昧に覚えている部分があったので、ひな形に戻って確認し、また覚えるまで書くということを繰り返して、頭の中に入れていきました。
実践答練のご感想・ご利用方法
過去問に関しては、5月ごろから年度別に1日1年度解くことをしていました。そのころから本試験は2時間半ということは意識して解いていたので、実践答練で改めて時間を意識するということはなかったと思います。実践答練は9月ごろに解きました。第1回と第2回は二日続けて解きましたが、初見の問題をあっさり解いてしまったことを少し後悔して、第3回は1週間後に解きました。ただ、実践答練は重箱の隅をつつくような問題で、難易度も高く、点数的にはあまりよくありませんでした。ですので、実力を計ったというよりかは、自分の知識の復習という意味合いで取り組みました。その後過去問と同じような感じで解く方もいるようですが、私は1回解いて復習してからは、本試験とは少し傾向が違うかなと思って、解かなかったです。
法改正対策過去問解説講座のご感想・ご利用方法
法改正対策過去問解説講座は、実は視聴していません。ホームルームで今年の法改正の案内があり、定期カウンセリングでも確認しましたが、今年の改正は案内があった会社法人等番号をかっこをつけて書かなくなったくらいと言われましたので、わざわざ時間をとってみる必要はないなと思いました。過去問を解く際はかっこなしで書くよう軌道修正しましたが、定期カウンセリングではかっこを書いてしまっても特に点数には響かないだろうといわれたので、特に今年は法改正で大幅に変わることはなかったと思います。
直前予想模試のご感想・ご利用方法
実力診断模試は、本試験の1週間前に取り組みました。答練とは違って、本試験と同レベルの難易度で、この模試の点数は本試験で取れる点数とだいたい同じと言われていたので、解く際は手が震えました。本試験よりも手が震えていたと思います。この模試では自己採点で一応合格点は取れていました。1週間前に自宅で緊張感をもって取り組めたこと、そして合格ラインを突破できていたことが、私にとってはすごく自信となり、本試験には不安なく臨むことができました。
定期カウンセリングのご感想・ご利用方法
定期カウンセリングは中山先生、中里先生、高野先生にお世話になりました。毎月楽しくお話させていただきました。また講義の内容だけではなく、試験前日や当日の過ごし方もアドバイスをいただき、参考になりました。
土地家屋調査士・測量士補試験の合格を
目指している方へ
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る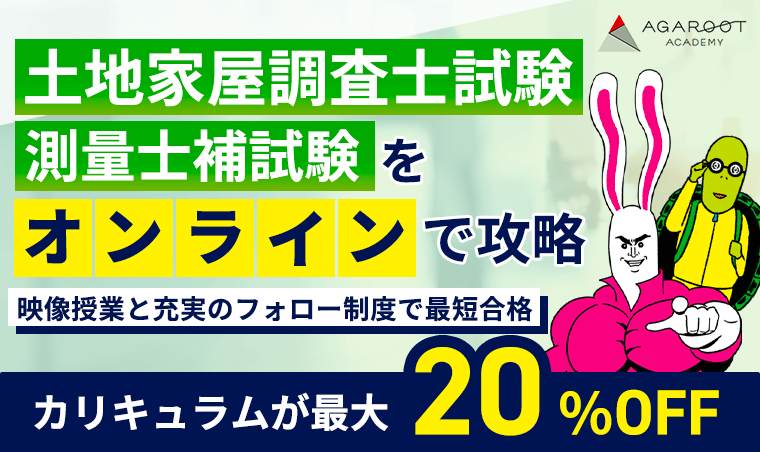
4年連続1位合格者輩出!
令和6年土地家屋調査士講座の
アガルート受講生の合格率63.64%!全国平均の約6倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
5月12日までの申込で5%OFF!
▶土地家屋調査士・測量士補試験講座を見る※2025年合格目標ダブル合格カリキュラム
