第二種電気工事士試験の勉強時間は?勉強法・学習期間の目安も紹介
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

第二種電気工事士の資格取得を目指している方、勉強時間や効果的な勉強法について悩んでいませんか?
「独学で進めているけど、この方法で本当に合格できるのだろうか?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
仕事や家庭の忙しさの中で、勉強の進め方や時間の確保に苦労している方も少なくありませんよね。
そこでこのコラムでは、第二種電気工事士試験に合格するために必要な勉強時間や、効率的な学習方法、さらには学習期間の目安について解説します。
短期間で効率よく学習を進めるためのコツや、独学と講座利用のメリット・デメリットも含めてお伝えしますので、試験合格に向けた学習プラン作りに役立てていただければと思います。
本コラムを読むことで、自分に合った勉強法とペースを見つけ、合格するための指針が得られるはずです。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
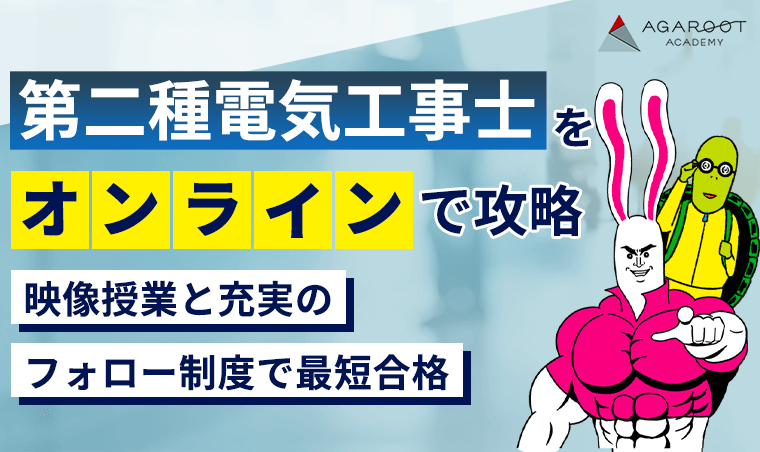
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
▶第二種電気工事士試験講座を見る
第二種電気工事士合格に必要な勉強時間・勉強期間の目安
これまでまったく電気に関する知識がなかった人が、独学で第二種電気工事士に合格するためには、どの程度の勉強時間と期間が必要なのか気になるところです。
この資格は、電気工事を行う際に必要な基礎知識を問われるものであり、試験内容も比較的難易度が高くないとされています。
しかし、しっかりとした準備がなければ合格は難しいため、計画的な勉強が重要です。
第二種電気工事士合格に必要な勉強時間は100~200時間程度
電気工事に関する知識がまったくない人が、独学で第二種電気工事士に合格するために必要とされる勉強時間は、おおよそ100~200時間程度といわれています。
この時間は、基本的な理論を学び、実際の問題に慣れるために必要な時間の目安です。
第二種電気工事士の試験は、国家資格の中でも比較的難易度が高くない試験であり、しっかりとした対策を行えば、多くの人が合格を目指せる内容です。
しかし、難易度が低いからといって油断せず、十分な準備が必要です。
第二種電気工事士合格に必要な勉強期間の目安
勉強時間は確保できる時間や個々の進捗状況に応じて異なりますが、いくつかのケースに分けて目安となる勉強期間を紹介します。
自分のライフスタイルに合わせて、無理のないペースで進めることが大切です。
以下では、勉強時間について場合分けをしながら、合格に必要となる勉強時間の目安を示していきます。
毎日60分勉強する場合は3~7ヶ月
もし、毎日60分の勉強時間を確保できる場合、週に約7時間、1ヶ月で約28時間の学習が可能です。
このペースで勉強を続けると、大体3~7ヶ月で必要な勉強時間である100~200時間を満たすことができます。
特に仕事や他の用事で忙しい人には、少しずつでも毎日続けることで、確実に知識を積み重ねることができるので、この方法がおすすめです。
毎日90分勉強する場合は2~5ヶ月
毎日90分勉強する場合、週に約10.5時間、1ヶ月で約42時間の学習が可能です。
このペースで進めると、2~5ヶ月で100~200時間の勉強時間を満たすことができます。
この勉強ペースは、やや早めに試験合格を目指したい人に向いており、集中して取り組むことで効率的に学習を進めることができます。
平日60分+休日120分勉強する場合は3~6ヶ月
平日は60分、休日はそれぞれ120分の勉強時間を確保する場合、1週間で約9時間、1ヶ月で約36時間の学習が可能です。
このペースであれば、大体3~6ヶ月で必要な勉強時間を満たすことができます。
平日には短時間の学習で基礎を固め、休日にまとまった時間を使って理解を深めるといったメリハリのある勉強スタイルが効果的です。
平日120分+休日240分勉強する場合は1.5~3ヶ月
短期間で集中的に合格を目指す場合、平日120分、休日240分の勉強時間を確保すると、1週間で約18時間、1ヶ月で約72時間の学習が可能です。
このペースで進めると、1.5~3ヶ月で必要な勉強時間を満たすことができます。
仕事や生活に余裕があり、短期集中で試験に臨みたいという人には、この方法が最適です。
しっかりと計画を立て、集中力を保ちながら勉強することで、効率よく試験対策を進めることができます。
働きながらの勉強はスキマ時間の活用が重要
仕事をしながら資格試験の勉強を進めるのは、多くの人にとって難しいことかもしれません。
しかし、忙しい生活の中でも、スキマ時間を有効に活用することで、勉強時間を確保し、試験合格への道を確実にすることができます。
ここでは、働きながらコンスタントに勉強を続けるための具体的な時間の使い方をいくつか紹介します。
通勤時間の活用
多くの社会人にとって、通勤時間は1日の中で比較的自由に使える貴重な時間です。
往復の通勤時間を合わせれば、40分から1時間程度は確保できる場合もあります。この時間を有効に使うことで、毎日確実に勉強を進めることができます。
例えば、電車やバスの中では、スマートフォンのアプリを使って問題を解いたり、過去問をチェックしたりすることができます。
また、参考書やノートを持ち歩いて、短い時間でも繰り返し目を通すことが習慣化すれば、着実に知識が身につきます。
昼休憩の活用
昼休憩の15分から20分も、学習に充てることで効率的に勉強を進めることができます。
例えば、昼食後にコーヒーを飲みながら、覚えたいポイントを再確認したり、暗記カードを使って簡単なクイズ形式で知識をチェックすることができます。
このような軽い学習でも、毎日続けることで大きな成果につながります。
自宅でのスキマ時間の活用
自宅でのスキマ時間も、勉強に活かすことが可能です。
例えば、風呂に入っている間や掃除をしている最中に、音声教材を使って耳から学習する「耳勉」を取り入れることができます。
耳勉は、リスニング形式で勉強内容を復習できるので、手が離せない状況でも学習を進めることができます。
また、料理中や洗濯をしている間にも音声教材を流しておくことで、生活の一部に勉強を組み込むことができ、より効率的に時間を使うことができます。
夜のリラックスタイムの活用
夜のリラックスタイムに、軽い復習を取り入れるのも有効です。
例えば、寝る前の10分間を使って、その日の学習内容を復習することで、記憶の定着が促進されます。
短時間でも毎日続けることで、徐々に知識が積み重なり、試験対策として非常に効果的です。
また、この時間は新しいことを学ぶよりも、既に学んだことを振り返ることに集中すると、無理なく勉強を続けることができます。
週末の集中学習
週末には、まとまった時間を確保して集中して学習することも重要です。
平日はスキマ時間を中心に学習し、週末にはより難易度の高い問題や、理解が深まっていない分野の学習に時間を割くことで、全体のバランスを保つことができます。
週末の集中学習は、スキマ時間ではカバーしきれない部分を補完する良い機会です。
働きながら勉強を続けるためには、これらのスキマ時間を最大限に活用することがカギとなります。
毎日の生活の中で無理なく勉強を続けることができれば、試験合格への道は確実に近づいていくでしょう。
大切なのは、一度に長時間勉強するのではなく、少しずつでもコンスタントに勉強を続けることです。
この積み重ねが、試験本番での自信と実力につながります。
第二種電気工事士試験の勉強法
第二種電気工事士試験に合格するためには、学科試験と技能試験の両方にしっかりと対策を立てる必要があります。
それぞれの試験には異なるアプローチが求められるため、効率的に学習を進めることが重要です。
ここでは、学科試験と技能試験の具体的な勉強法を紹介していきます。
学科試験の勉強法
学科試験は、第二種電気工事士試験の第一関門であり、電気に関する基礎的な知識を問われます。
この試験に合格するためには、理論の理解と問題に慣れることが求められます。以下に、学科試験の効率的な勉強法を紹介します。
テキストや講義動画をまず1周させる
学科試験対策の第一歩として、まずはテキストや講義動画を一通り目を通すことから始めましょう。
初めての内容や専門用語が多く出てくるため、最初は理解しきれない部分もあるかもしれませんが、ここでは全体像を掴むことが目的です。
わからないところに時間をかけすぎず、まずは全体の流れを把握することが大切です。
このステップで試験内容をおおまかに理解し、どのような範囲が出題されるのかを把握します。
過去問題を繰り返し解いていく
テキストを一通り読んだら、次に過去問題に取り組みましょう。過去問を解くことで、出題傾向を掴むことができ、実際の試験での対応力が養われます。
過去問を解く際にわからない箇所があれば、その都度テキストや動画に戻って確認し、理解を深めていきます。
このプロセスを繰り返すことで、知識の定着が進みます。
また、過去問を解くことで、自分の弱点や理解が不十分な部分を洗い出し、それを重点的に復習することが効果的です。
暗記学習も平行して進める
学科試験には暗記が必要な分野も多く含まれています。特に、配線図記号や基本的な電気理論などは確実に覚えておく必要があります。
暗記の際には、まずは得意な分野や簡単だと思うところから進めると良いでしょう。
得意な分野から取り組むことで、成功体験が積み重なり、モチベーションが維持しやすくなります。
また、暗記は一度に大量の情報を詰め込むのではなく、少しずつ、何度も繰り返し確認することで確実に覚えていきます。
技能試験の勉強法
一方、技能試験は、実際に電気工事の作業を行う試験であり、学科試験とは異なるスキルが求められます。
ここでは、効率よく技能試験に合格するための具体的な勉強法を紹介します。
工具・実技キットを揃える
技能試験に向けた準備として、まずは指定工具と実技キットを揃えましょう。
指定された工具以外にも、自分が使いやすい便利な工具を追加で用意しておくと、作業効率が上がります。
例えば、作業をスムーズに進めるための高品質なドライバーやニッパーなどを用意すると良いでしょう。
実技キットは、試験に出題される候補問題に対応したものを選び、実際に手を動かして練習することで、試験当日に自信を持って臨むことができるでしょう。
複線図の書き方をマスターする
複線図の書き方は技能試験の合否を左右する重要なポイントです。
複線図を正確に描くことができるようになると、作業の手順が明確になり、ミスを減らすことができます。
まずは基本的な複線図の書き方を理解し、何度も練習してマスターしましょう。
複線図の理解は、技能試験だけでなく、実際の電気工事においても非常に役立つスキルです。
候補問題で2回以上練習する
技能試験の合格には、実際に手を動かして練習することが不可欠です。
試験センターから公表されている候補問題を使い、少なくとも2回以上練習しましょう。
最初の練習では時間を気にせず、解説動画を参考にしながら、しっかりと手順を確認します。
2回目の練習では、試験本番を意識して時間を測りながら進めると良いでしょう。
作業中にうまくいかない部分や苦手な作業があれば、重点的に動画を確認したり、繰り返し練習することで克服できます。
欠陥条件をしっかり覚える
技能試験には、いくつかの欠陥条件が設定されており、これに該当すると不合格になる可能性があります。
例えば、接続不良や配線ミスなど、試験でよく見られるミスをしっかり把握しておきましょう。
欠陥条件を理解し、それを避けるための手順を身につけることが重要です。
正確な作業を心がけ、ミスを防ぐために、常に冷静に手順を確認しながら進めるようにしましょう。
短期間で合格したいなら講座利用がおすすめ
独学で第二種電気工事士試験に挑戦することには、費用がかからないという大きなメリットがあります。
自分のペースで学習を進められるため、働きながらでも試験勉強を続けやすいという利点もあります。しかし、独学にはいくつかのデメリットも存在します。
まず、独学で使用する教材や情報の正確性を、自分自身で判断しなければならないという課題があります。
特に初めて学ぶ内容の場合、その情報が正しいかどうかを証明するのは難しいことがあります。
また、解説が理解できない場合、その箇所に時間がかかり、結局理解が浅いまま進んでしまうことも少なくありません。
さらに、自分が知りたい部分や苦手な部分に対する詳しい解説が見つからないと、必要以上に時間を費やしてしまうこともあります。
このような状況では、効率的な学習が難しく、結果として試験対策に多くの時間がかかってしまう可能性があります。
特に短期間で合格を目指している場合、独学のデメリットが大きく影響することも考えられます。
そこで、短期間で確実に合格したいと考えている方には、講座の利用をおすすめします。
講座では、正確な知識を持つ講師が指導を行い、わからない点があればすぐに質問して解決することができます。
これにより、間違った知識に惑わされることなく、効率的に学習を進めることが可能です。
また、講座では、試験に特化した教材や過去問を使用して学習を進めるため、出題傾向をしっかりと把握することができ、実践的な試験対策が可能となります。
さらに、講座では、モチベーションを維持するためのサポートが充実していることも多く、独学では得られない学習環境が整っています。
これにより、試験に向けた準備を効率的かつ確実に進めることができ、結果として短期間での合格が目指せるのです。
講座を利用することで、独学のデメリットを解消し、正確な知識をサクサクと身につけることができます。
試験合格に向けて確実な準備をしたい方には、ぜひ講座の利用を検討してみてください。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
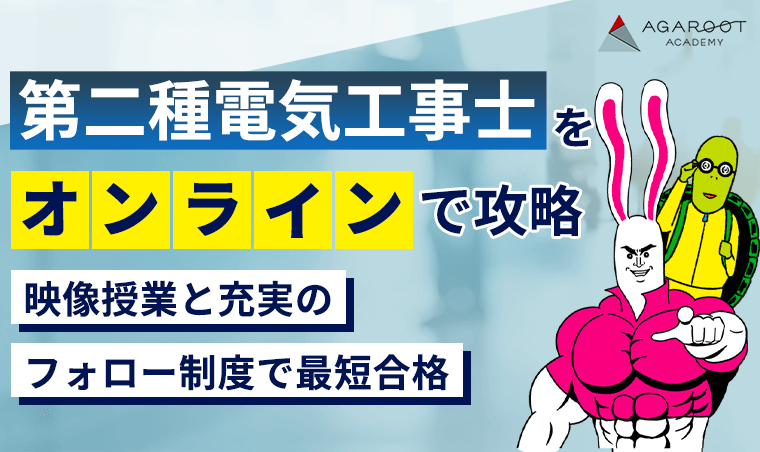
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
▶第二種電気工事士試験講座を見る


