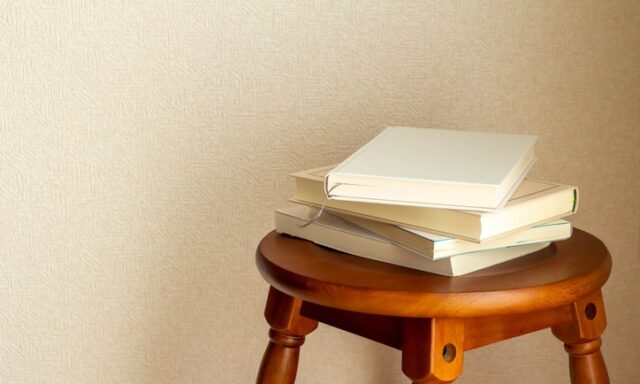第二種電気工事士は受験資格なし! 試験情報と資格のメリットを解説!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

電気工事のキャリアを考えている方、資格取得を目指している方の中には、「受験資格が必要なのでは?」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
特に、これまで電気工事の経験がない方にとって、資格試験に挑戦するハードルが高く感じられることは少なくありません。
また、「資格を取得したところで、本当に役立つのだろうか?」といった疑問を抱えている方も多いかもしれません。
実は、第二種電気工事士の資格は、誰でも受験できる国家資格であり、学歴や実務経験は一切問いません。
さらに、この資格を取得することで、転職やキャリアアップがしやすくなり、日常生活でも大いに役立つスキルを身につけることができます。
この記事では、第二種電気工事士試験の受験資格がないことをはじめ、試験の詳細や勉強法、さらに資格を取得するメリットについて詳しく解説します。
このコラムを読むことで、資格取得への一歩を踏み出すための具体的な方法がわかり、不安を解消して自信を持って試験に臨むことができるようになるでしょう。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
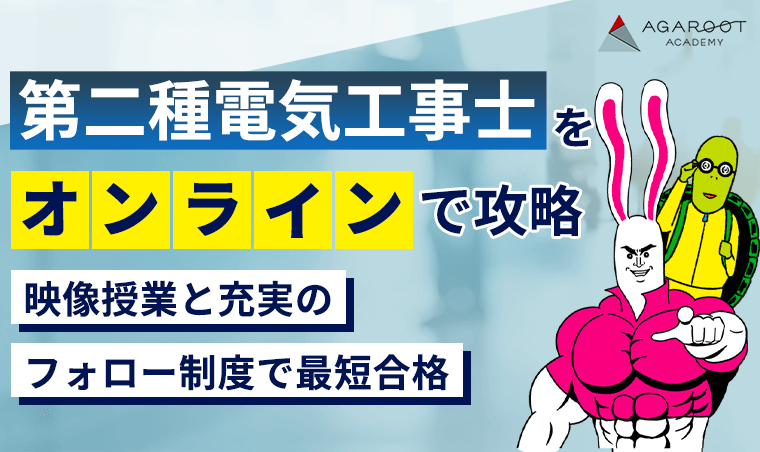
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
▶第二種電気工事士試験講座を見る
第二種電気工事士に受験資格はない
第二種電気工事士の試験は、受験資格が特に設定されていないため、誰でも受験することが可能です。
この試験は、学歴や年齢、さらには実務経験に関係なく、電気工事に興味を持つすべての人に開かれています。
そのため、初心者や学生、あるいはキャリアチェンジを考えている方にとっても、挑戦しやすい国家資格となっています。
第二種電気工事士試験に合格すると、電気工事士としての免状を得ることができます。
この免状を取得すれば、住宅や小規模な店舗などの電気工事を行うことが可能となり、電気設備に関する仕事の幅が広がります。
特に、将来独立して電気工事業を営みたいと考えている方にとっては、この資格は大きな一歩となるでしょう。
また、上位資格である第一種電気工事士についても、受験資格がありません。
そのため、第二種電気工事士に合格していなくても、誰でも第一種電気工事士の試験を受けることができます。
しかし、第一種電気工事士の免状を取得するためには、試験に合格した後、実務経験が3年以上必要です。
この実務経験は、第二種電気工事士として働いた経験や、それに準ずる電気工事の実務経験が該当します。
第二種電気工事士ができること
第二種電気工事士の資格は、電気工事を行うための基本的な国家資格であり、特に600V以下で受電する電気工作物に関する工事を行うために必要な資格です。
この資格を取得すると、家庭や小規模な商業施設、工場などでの電気工事が可能になります。
第二種電気工事士の資格を持つことは、電気工事の現場で働く上で大きな強みとなり、多くの場面で活躍できるようになります。
一般住宅や小規模店舗等での電気工事
第二種電気工事士資格を持っていると、一般住宅や小規模な店舗、事務所などで幅広い電気工事を行うことができます。
具体的には、以下のような作業が可能です。
- コンセントやスイッチの設置・交換
新たにコンセントやスイッチを設置する、あるいは古くなったものを交換する作業を行うことができます。
家庭や店舗での電気設備の維持・改善に重要な役割を果たします。
- 照明器具の設置
天井照明や壁付けの照明器具の取り付け、交換を行うことができます。
特にLED照明の普及に伴い、古い照明器具から新しい省エネ型の照明器具への交換工事の需要が高まっています。
- 電気配線工事
新築やリフォーム時における電気配線の敷設工事も行えます。住宅や店舗の内装工事に伴う配線の引き直しや、新規配線の施工を担当することが可能です。
- ブレーカーや分電盤の設置・交換
分電盤やブレーカーの設置、交換も行えます。特に、電力使用量の増加に対応するための増設や、安全性を高めるためのブレーカーの交換は重要な業務です。
- アース工事
安全性を確保するための接地工事(アース工事)も第二種電気工事士が担当できる作業です。
これにより、漏電時に人や機器を守るための安全対策を施すことができます。
これらの作業は、電気の安全を確保するために欠かせないものであり、家庭や小規模な施設での快適な生活や営業活動を支える重要な役割を果たします。
資格を持つことで、これらの作業を合法的かつ安全に行うことができるため、電気工事業界において非常に価値のある資格といえます。
現場代理人としての業務
第二種電気工事士の資格を持つことで、電気工事現場において現場代理人としての業務を行うことも可能です。
現場代理人とは、工事現場の責任者として、工事の進行を管理し、品質、安全、工程の全体を監督する役割を担います。
具体的には、工事の計画、進捗の確認、作業員の指導、安全対策の実施、工事の品質管理など、多岐にわたる業務を担当します。
ただし、現場代理人としての業務は、単に資格を持っているだけでは難しく、通常は一定の実務経験が必要とされます。
電気工事の現場での経験が豊富であれば、工事の進行をスムーズに進めるための適切な判断が求められます。
例えば、工事中に予期せぬ問題が発生した際にも、迅速に対応し、工事を無事に完了させるためのリーダーシップが求められます。
現場代理人としての経験を積むことで、さらなるキャリアアップの道が開かれ、将来的には第一種電気工事士の取得や、電気工事会社の経営など、幅広い可能性が広がります。
第二種電気工事士資格を取得するメリット
第二種電気工事士資格を取得することには、多くのメリットがあります。
これは、電気工事に関する専門知識と技術を持つことを証明する国家資格であり、取得することで幅広いキャリアオプションが広がります。
資格取得後には、転職やキャリアアップに直結するチャンスが増え、日常生活でも役立つスキルが得られます。
転職に活かすことができる
第二種電気工事士の資格は、転職市場で非常に有利に働きます。現在、日本では電気工事士の人材が不足しており、その需要は非常に高いです。
特に、建設業界や設備管理業界では、電気工事士の資格を持つ人材が求められています。
資格を取得することで、これらの業界での転職がスムーズに進む可能性が高まり、企業からのニーズが高い分、年収アップも見込めます。
また、多くの企業では、電気工事士資格を持っている社員に対して資格手当を支給しています。
資格手当が支給されることで、基本給に加えて収入が増えるため、家計のサポートにもなります。
さらに、資格を活かしてキャリアアップを目指すことで、より責任のあるポジションに就くことができ、将来的には管理職や経営者としての道も開けるでしょう。
第二種電気工事士資格は、特に中途採用や未経験からの転職を考えている方にとって大きな武器となります。
資格取得により、未経験でも電気工事の現場で即戦力として評価されることが増え、他の候補者と差別化を図ることができます。
これにより、採用の確率が高まり、安定した職業に就くことが可能になります。
DIYや物件の修繕をおこなうことができる
第二種電気工事士資格を取得すると、趣味として行うDIYの幅が広がります。
例えば、自宅の電気設備を自分で修理したり、新しい照明器具を取り付けたりすることが可能になります。
通常、電気工事は資格がないと行うことができませんが、第二種電気工事士の資格を持っていると、自宅での簡単な電気工事を合法的に行うことができ、これにより、外部の業者に依頼する手間やコストを削減することができます。
さらに、賃貸物件を所有している大家にとっても、この資格は非常に有用です。
賃貸物件のオーナーが資格を持っていれば、ちょっとした修繕やリフォームを自分で行うことができ、大幅に出費を抑えることが可能です。
例えば、テナントが退去した後の物件の点検や修繕作業を自分で行うことで、リフォーム業者に依頼する必要がなくなり、経費を節約できます。
また、電気設備に関する知識があると、DIYの範囲が広がり、家や物件の価値を向上させることができます。
資格を取得することで、ただの趣味を超えて、実用的なスキルを持つことで日常生活の質を向上させることができます。
第二種電気工事士試験の概要
第二種電気工事士は、電気設備の工事において重要な役割を担う資格であり、この資格を取得するためには国家試験に合格する必要があります。
国家資格である第二種電気工事士試験は、毎年上期と下期の年2回実施されており、受験者は学科試験と技能試験の両方をクリアする必要があります。
この試験の特徴の一つは、特に受験資格が必要ない点です。
つまり、年齢や学歴、実務経験を問わず、誰でも挑戦できる資格試験です。そのため、幅広い層の受験者が毎年試験に挑戦しています。
学科試験では、電気工事に関する基礎知識や法律、規則に関する問題が出題され、受験者はこれに合格した後、技能試験に進みます。
技能試験では、実際に工具を使用して電気設備を配線・組み立てる作業を行い、その正確さとスピードが評価されます。
技能試験の合格には、作業において「欠陥」がないことが求められます。
第二種電気工事士試験の日程
第二種電気工事士試験は、毎年上期と下期の2回に分けて実施されます。2025年度の試験日程は以下の通りです。
上期試験
- 学科試験(筆記方式):2025年5月25日(日)
- 学科試験(CBT方式):2025年4月21日(月)~5月8日(木)
- 技能試験:2025年7月19日(土)または7月20日(日)
下期試験
- 学科試験(筆記方式):2025年10月26日(日)
- 学科試験(CBT方式):2025年9月19日(金)~10月6日(月)
- 技能試験:2025年12月13日(土)または12月14日(日)
例年、上期の学科試験は5月下旬、技能試験は7月中旬から下旬にかけて行われます。
一方、下期の学科試験は10月下旬、技能試験は12月中旬に実施されるのが一般的です。
試験日程は毎年調整されることがありますが、おおよその時期は固定されています。
なお、学科試験は、筆記方式とCBT(Computer Based Testing)方式があり、筆記方式では、指定された日程で会場に実際に出向き試験を受けるのに対して、CBT方式では、特定の期間内に指定された会場に出向いて試験を受けることになります。
第二種電気工事士試験の科目・範囲
第二種電気工事士試験は、学科試験と技能試験の二部構成で実施されます。それぞれの科目と試験範囲は以下の通りです。
| 試験種別 | 科目 | 試験範囲 |
|---|---|---|
| 学科試験 | 電気に関する基礎理論 | 電気回路、電気機器、電力工学など |
| 電気機器の性能及び使用法 | 照明器具、電動機、コンデンサなど | |
| 電気設備の構造及び工事方法 | 配線工事、接地工事、電線の種類と使用法など | |
| 法令 | 電気設備に関する法律、技術基準、安全基準など | |
| 技能試験 | 電気工事の基本作業 | 電線の接続、配線工事、器具の取り付けなど |
学科試験は、電気工事に関する基礎理論、電気機器の性能、電気設備の構造と工事方法、関連法令の知識が問われます。
学科試験に合格するか、前年度に学科試験に合格した場合は免除されます。技能試験では、実際に工具を使用して作業を行い、正確さが重視されます。
なお、学科試験については、以下のような特定の要件を満たした場合免除となります。
| 免除項目1 | 令和6年度 第二種電気工事士 上期学科試験の合格者 |
| 免除項目2 | 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による実業学校又はこれらと同等以上の学校において、電気工事士法で定める電気工学の課程を修めて卒業した方 |
| 免除項目3 | 1) 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の取得者2) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者 |
| 免除項目4 | 改正前の鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した方 |
| 免除項目5 | 旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された方 |
第二種電気工事士試験の実施形式
第二種電気工事士試験は、学科試験と技能試験の2つの形式で実施されます。
学科試験は、筆記試験として行われるほか、コンピュータを利用したCBT(Computer-Based Testing)方式でも実施されます。
CBT方式は、指定された試験期間内であれば、受験者が自分の都合に合わせて試験日を選べる形式です。
試験会場に設置されたコンピュータを使って解答し、従来の筆記試験よりも柔軟な受験が可能です。
技能試験は、受験者があらかじめ公表されている候補問題に基づいて実際の作業を行う実技試験です。
指定された工具を使用し、与えられた配線図に従って作業を進めます。
この試験では、作業の正確さや安全性が重視され、ミスがないかが厳しく評価されます。
第二種電気工事士試験の試験時間
第二種電気工事士試験の試験時間は以下の通りです。
- 学科試験:120分
- 技能試験:40分
学科試験では、全体で120分間の試験時間が与えられます。受験者はその時間内に、出題される問題にすべて解答する必要があります。
一方、技能試験では40分の試験時間内に、与えられた配線作業をすべて完了しなければなりません。
第二種電気工事士試験の合格基準
第二種電気工事士試験の合格基準は、学科試験と技能試験で異なります。
学科試験では、100点満点中60点以上を取得することが合格基準となっています。全体の6割以上の得点を取ることで、次の技能試験に進むことができます。
技能試験の合格基準は、作成した作品に「欠陥」がないことです。
技能試験では、細かな作業ミスや指定通りに作業が完了していない場合、欠陥とみなされ、不合格となります。
欠陥が一つでもあれば不合格となるため、すべての作業を正確に行うことが求められます。
第二種電気工事士試験の合格率・難易度
第二種電気工事士試験は、電気工事士としての基本的な資格であり、多くの人が受験しています。
合格率や難易度については、受験者にとって非常に気になるポイントです。
ここでは、過去数年間の合格率とその推移、そして試験の難易度について紹介します。
第二種電気工事士試験の合格率
第二種電気工事士試験の合格率は、年度や期によって変動がありますが、比較的安定しています。以下は、過去数年間の合格率をまとめた表です。
| 年度 | 期 | 学科試験 | 技能試験 | ||
| 合格率 | 受験者数 | 合格率 | 受験者数 | ||
| 2024年度 | 下期 | 55.9% | 62,323 | 69.5% | 43,570 |
| 上期 | 60.2% | 70,139 | 71.0% | 50,668 | |
| 2023年度 | 下期 | 58.9% | 63,611 | 68.8% | 45,790 |
| 上期 | 59.9% | 70,414 | 73.2% | 49,547 | |
| 2022年度 | 下期 | 53.3% | 66,454 | 70.6% | 44,101 |
| 上期 | 58.2% | 78,634 | 74.3% | 53,558 | |
| 2021年度 | 下期 | 57.7% | 70,135 | 71.1% | 51,833 |
| 上期 | 60.4% | 86,418 | 74.2% | 64,443 | |
| 2020年度 | 下期 | 62.1% | 104,883 | 72.9% | 66,113 |
| 上期 | ー | ー | 67.8% | 6,884 | |
最新回である2024年度下期の試験では、学科試験の合格率が55.9%、技能試験の合格率が69.5%となっています。
ここ数年の合格率は、学科試験で50%台後半から60%台前半、技能試験では70%前後で推移しており、比較的安定しています。
これらのデータからもわかるように、第二種電気工事士試験は比較的合格しやすい試験であると言えるでしょう。
第二種電気工事士試験の難易度
第二種電気工事士試験は、受験資格が特に設けられていないため、誰でも挑戦できる国家資格です。そのため、多くの人がこの資格取得を目指して受験しています。
合格率が高めであることからもわかるように、この試験は国家資格の中でも比較的取得しやすいとされています。
学科試験は、電気に関する基礎知識を問われる内容であり、しっかりと勉強すれば合格が可能です。
また、技能試験では実技が重視されるため、練習を積んでおくことが合格の鍵となります。
特に、候補問題に基づいて練習を重ねることで、実技試験への対策を十分に行うことができます。
全体的に見て、第二種電気工事士試験は「難易度が低めの国家資格」として広く認識されています。
そのため、初めて資格を取得する方や、電気工事の業界に興味を持っている方にとっては、非常に挑戦しやすい試験となっています。
ただし、油断は禁物であり、確実に合格するためには、しっかりとした勉強と実技の練習が必要です。
第二種電気工事士試験の勉強法
第二種電気工事士試験は、学科試験と技能試験の2つの試験で構成されており、それぞれに異なる勉強方法が求められます。
試験対策を効率的に行うことで、合格の可能性を大幅に高めることができます。以下では、学科試験と技能試験に向けた具体的な勉強法を紹介します。
学科試験の勉強法
まずは、学科試験の勉強法から解説していきましょう。
まずはわからなくてもテキストを1周させる
学科試験の勉強を始めるにあたり、最初のステップとしてテキストを一通り読むことが重要です。
この段階では、全体の試験内容を掴むことが目的です。もちろん、初めて触れる内容や専門的な用語が多く、わからない部分も出てくるでしょう。
しかし、わからないことがあっても気にせずに読み進めることが大切です。
テキストを1周させることで、試験範囲全体の概要を理解でき、自分の得意分野や苦手分野が見えてきます。
この基礎理解が、後の勉強をスムーズに進めるための土台となります。
何度も過去問を解く
テキストを一通り読み終えたら、次に取り組むべきは過去問の演習です。過去問を解くことで、実際の試験の形式や出題傾向を把握することができます。
また、過去問を解く際には、正解・不正解にかかわらず、関連するテキストの部分を再度確認し、理解を深めることが大切です。
特に、何度も間違えてしまう問題や理解が不十分な箇所に関しては、重点的に学習することで、確実に克服していきましょう。
過去問を繰り返し解くことで、自然と試験で問われる知識が身につき、得点力を高めることができます。
技能試験の勉強法
次に、技能試験の勉強方法について解説していきます。
工具・練習キットを揃える
技能試験に向けて、まず取り組むべきは必要な工具と練習キットの準備です。
試験に使用する工具は受験者自身が用意しなければならず、指定された工具を揃えることが求められます。
また、練習用のキットを購入することで、実際の試験に近い環境での練習が可能になります。
指定された工具以外にも、作業を効率よく進めるための便利な工具を揃えることをお勧めします。
これにより、作業スピードが向上し、試験での時間管理がしやすくなります。
複線図の書き方をマスターする
技能試験の重要なポイントの一つが、複線図の書き方を正確にマスターすることです。
複線図は、配線作業を行う際の指針となるもので、これを正しく描けることが試験合格のカギとなります。
複線図の書き方を習得するためには、何度も練習を重ね、正確に描けるようになるまで繰り返し取り組むことが必要です。
複線図をスムーズに書けるようになることで、試験当日の作業効率が格段に向上します。
実際に候補問題で練習する
技能試験では、事前に公表されている候補問題を使って実際に練習を行うことが非常に効果的です。
候補問題は試験で出題される可能性のある問題であり、これをしっかりと対策することで、本番の試験でも自信を持って作業に臨むことができます。
練習の際には、作業の進め方や時間配分を確認しながら、効率的に進めることを心がけましょう。
また、動画サイトなどにアップされている作業手順を解説した動画を参考にすると、実際の作業の流れが理解しやすくなります。
これにより、自分が苦手とする部分を補強し、全体の作業を効率的に進めるためのヒントを得ることができます。
欠陥条件を覚える
技能試験では、作成した作品に「欠陥」があると不合格になります。
そのため、欠陥とみなされる条件をしっかりと理解し、作業の際に注意を払うことが重要です。
欠陥条件には、配線の誤りや接続の不備、寸法の不正確さなどが含まれます。これらを覚えておくことで、作業中に細心の注意を払い、ミスを防ぐことができます。
また、練習の段階でこれらの条件を意識しながら作業を行うことで、本番でも冷静に対応することができるでしょう。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
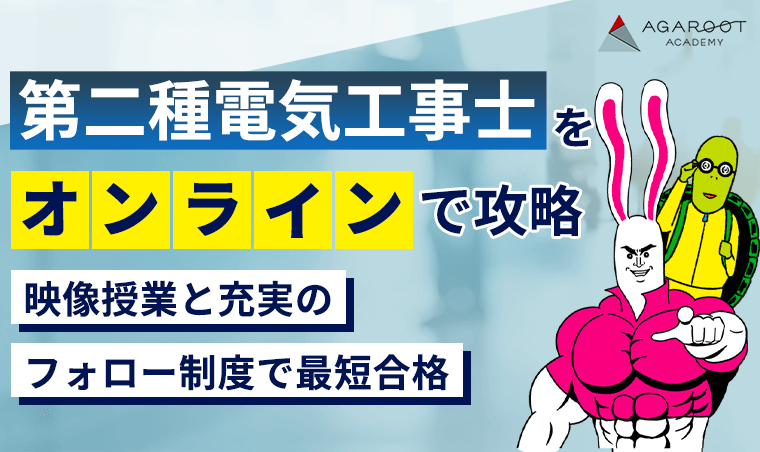
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
▶第二種電気工事士試験講座を見る