第二種電気工事士の合格率・難易度・合格ライン・欠陥の判断基準を解説!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

第二種電気工事士試験の合格率や難易度、そして合格ラインや欠陥の判断基準について、疑問を抱えていませんか?
「試験の難易度はどのくらいなのか」「どのくらい勉強すれば合格できるのか」「技能試験で注意すべきポイントは?」といった悩みを抱えている方は少なくないでしょう。
特に、初めて受験する方にとっては、これらの情報を正しく理解し、適切な対策を立てることが合格への大きな一歩となります。
実際、第二種電気工事士試験は国家資格の中では比較的合格しやすいと言われていますが、だからといって油断は禁物です。
学科試験では確実に60点を取り、技能試験では欠陥を出さないようにする必要があります。
合格ラインや欠陥の判断基準を正確に理解し、効率的に勉強を進めることで、合格の可能性を大幅に引き上げることができます。
このコラムでは、第二種電気工事士試験に関する合格率や難易度、具体的な合格ライン、そして技能試験での欠陥の判断基準について詳しく解説します。
この記事を読むことで、試験に向けた効果的な対策を立てるための具体的な方法がわかり、合格に向けて一歩前進できるでしょう。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
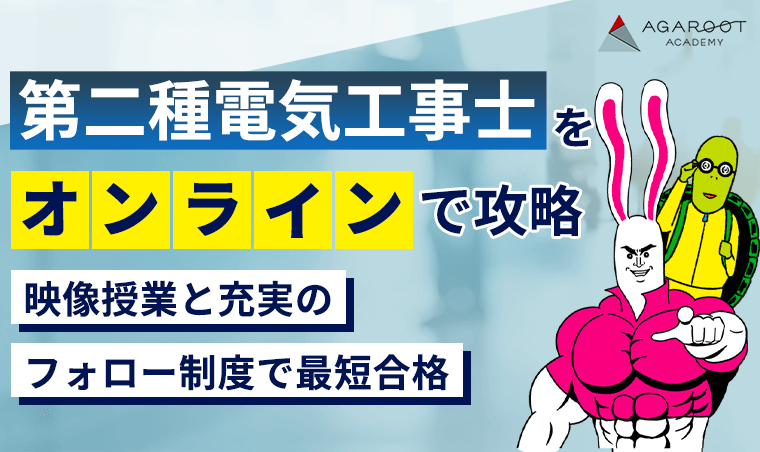
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
▶第二種電気工事士試験講座を見る
目次
第二種電気工事士試験の合格率
第二種電気工事士試験の合格率は、年度や期によって変動が見られますが、概ね60%〜70%程度です。
以下では、過去数年の合格率と受験者数のデータを紹介します。
| 年度 | 期 | 学科試験 | 技能試験 | ||
| 合格率 | 受験者数 | 合格率 | 受験者数 | ||
| 2024年度 | 下期 | 55.9% | 62,323 | 69.5% | 43,570 |
| 上期 | 60.2% | 70,139 | 70.1% | 50,668 | |
| 2023年度 | 下期 | 58.9% | 63,611 | 68.8% | 45,790 |
| 上期 | 59.9% | 70,414 | 73.2% | 49,547 | |
| 2022年度 | 下期 | 53.3% | 66,454 | 70.6% | 44,101 |
| 上期 | 58.2% | 78,634 | 74.3% | 53,558 | |
| 2021年度 | 下期 | 57.7% | 70,135 | 71.1% | 51,833 |
| 上期 | 60.4% | 86,418 | 74.2% | 64,443 | |
| 2020年度 | 下期 | 62.1% | 104,883 | 72.9% | 66,113 |
| 上期 | ー | ー | 67.8% | 6,884 | |
このデータから分かるように、合格率は一定の範囲内で変動しています。
第二種電気工事士試験の最新回(2024年度下期)の合格率は、学科試験が55.9%、技能試験合格率が69.5%です。
近年の試験では、学科試験と技能試験の合格率が比較的安定しており、技能試験ではおおよそ7割が合格しています。
例年であれば、学科試験の合格率は50%台後半から60%台前半、技能試験の合格率は70%前後が一般的です。
受験者数は年々増減があり、特に2020年度は下期の受験者数が非常に多かったことが特徴です。
これは、新型コロナウイルスの世界的な流行に伴い、試験の実施が中止となったのが理由となっています。
第二種電気工事士試験全体の合格率
第二種電気工事士試験における一発合格の合格率については、受験者の受験回数が公開されていないため、正確な一発合格者の割合は不明です。
試験の合格率は毎年公開されていますが、個別の受験回数に関するデータはないため、各自が一発で合格するかどうかは、個々の努力や試験対策によるところが大きいと言えます。
第二種電気工事士試験の高校生の合格率
高校生の第二種電気工事士試験の合格率については、電気書院のデータを参照すると、2022年度の高校生合格率は約81.4%とされています。
このデータは、特定の高校における受験者数と合格者数に基づいて算出されたものであり、全国的な合格率を示すものではありません。
注意すべき点として、データの参照元である電気書院が対象としたのは、合格者が出た133校のみであり、その中には工業高校とそれ以外の高校が混在しています。
したがって、この合格率はあくまで参考値であり、高校生全体の合格率を正確に反映しているわけではありません。
工業高校では専門的な教育が行われているため合格率が高い一方で、一般高校ではその準備が不足している場合もあり、学校ごとの合格率にはばらつきがあります。
第二種電気工事士試験の難易度
第二種電気工事士試験の難易度は、比較的低いと言えます。これは、まず受験資格が特に設けられておらず、誰でも挑戦できることが大きな要因です。
また、合格率を見ると、学科試験では60%前後、技能試験では70%前後と、国家資格の中でも合格率が高い部類に入ります。
このような点から、試験全体の難易度はそれほど高くないと考えられます。
しかしながら、学科試験と技能試験にはそれぞれ異なる難易度の特徴があります。
学科試験は、電気工事に関する基礎知識が問われるため、しっかりと勉強すれば比較的合格しやすいです。
しかし、技能試験に関しては、合格率は高いものの、実技の練習が不可欠です。
特に、技能試験では実際に電線を扱い、器具の取り付けや配線作業を行うため、練習なしでは合格基準を超えるのは難しいでしょう。
技能試験では、時間内に正確に作業を完了することが求められます。
この点で、合格率が高く見えても、試験の準備にしっかりと取り組まなければ、合格は難しいと言えます。
また、技能試験では、工具の正しい使い方や、安全に作業を進めるための知識も必要です。
これらの実技スキルは、日常的に電気工事の作業を行っていない受験者にとってはハードルが高いかもしれません。
さらに、合格率の高い試験ではありますが、初めて受験する方や、実技に不安を抱える方にとっては、しっかりとした対策が不可欠です。
試験対策としては、実技の練習を十分に行い、過去問題を解くことで、試験の出題傾向を把握することが重要です。
第二種電気工事士試験の合格ライン(合格基準点)と欠陥の判断基準
第二種電気工事士試験における合格基準点は、学科試験と技能試験で異なります。
学科試験においては、合格基準点は60点と定められており、全100点満点の試験で60点以上を得点することで合格となります。
このため、学科試験では、約6割の得点を目指して試験対策を進めることが重要です。
一方、技能試験における合格基準は、試験で作成する作品に「欠陥」がないことが合格の条件となります。
技能試験では、正確な作業と仕上がりが求められ、作成した作品に欠陥があると不合格となります。
電気工事士技能試験の欠陥の判断基準
1.未完成のもの
2.配置,寸法,接続方法等の相違
2-1.配線,器具の配置が配線図と相違したもの
2-2.寸法(器具にあっては中心からの寸法)が,配線図に示された寸法の 50%以下のもの
2-3.電線の種類が配線図と相違したもの
2-4.接続方法が施工条件に相違したもの
3.誤接続,誤結線のもの
4.電線の色別,配線器具の極性が施工条件に相違したもの
5.電線の損傷
5-1.ケーブル外装を損傷したもの
イ.ケーブルを折り曲げたときに絶縁被覆が露出するもの
ロ.外装縦われが 20mm 以上のもの
ハ.VVR,CVV の介在物が抜けたもの
5-2.絶縁被覆の損傷で,電線を折り曲げたときに心線が露出するもの
ただし,リングスリーブの下端から 10mm 以内の絶縁被覆の傷は欠陥としない
5-3.心線を折り曲げたときに心線が折れる程度の傷があるもの
5-4.より線を減線したもの
6.リングスリーブ(E形)による圧着接続部分
6-1.リングスリーブ用圧着工具の使用方法等が適切でないもの
イ.リングスリーブの選択を誤ったもの(JIS C 2806 準拠)
ロ.圧着マークが不適正のもの(JIS C 2806 準拠)
ハ.リングスリーブを破損したもの
ニ.リングスリーブの先端または末端で,圧着マークの一部が欠けたもの
ホ.1つのリングスリーブに2つ以上の圧着マークがあるもの
ヘ.1箇所の接続に2個以上のリングスリーブを使用したもの
6-2.心線の端末処理が適切でないもの
イ.リングスリーブを上から目視して,接続する心線の先端が一本でも見えないもの
ロ.リングスリーブの上端から心線が 5mm 以上露出したもの
ハ.絶縁被覆のむき過ぎで,リングスリーブの下端から心線が 10mm 以上露出したもの
ニ.ケーブル外装のはぎ取り不足で,絶縁被覆が 20mm 以下のもの
ホ.絶縁被覆の上から圧着したもの
ヘ.より線の素線の一部がリングスリーブに挿入されていないもの
7.差込形コネクタによる差込接続部分
7-1.コネクタの先端部分を真横から目視して心線が見えないもの
7-2.コネクタの下端部分を真横から目視して心線が見えるもの
8.器具への結線部分
(1)ねじ締め端子の器具への結線部分
(端子台,配線用遮断器,ランプレセプタクル,露出形コンセント等)
8-1.心線をねじで締め付けていないもの
イ.単線での結線にあっては,電線を引っ張って外れるもの
ロ.より線での結線にあっては,作品を持ち上げる程度で外れるもの
ハ.巻き付けによる結線にあっては,心線をねじで締め付けていないもの
8-2.より線の素線の一部が端子に挿入されていないもの
8-3.結線部分の絶縁被覆をむき過ぎたもの
イ.端子台の高圧側の結線にあっては,端子台の端から心線が 20mm 以上露出したもの
ロ.端子台の低圧側の結線にあっては,端子台の端から心線が 5mm 以上露出したもの
ハ.配線用遮断器又は押しボタンスイッチ等の結線にあっては,器具の端から心線が 5mm 以上露出したもの
ニ.ランプレセプタクル又は露出形コンセントの結線にあっては,ねじの端から心線が5mm 以上露出したもの
8-4.絶縁被覆を締め付けたもの
8-5.ランプレセプタクル又は露出形コンセントへの結線で,ケーブルを台座のケーブル引込口を通さずに結線したもの
8-6.ランプレセプタクル又は露出形コンセントへの結線で,ケーブル外装が台座の中に入っていないもの
8-7.ランプレセプタクル又は露出形コンセント等の巻き付けによる結線部分の処理が適切でないもの
イ.心線の巻き付けが不足( ),又は重ね巻きしたもの
ロ.心線を左巻きにしたもの
ハ.心線がねじの端から 5mm 以上はみ出したもの
ニ.カバーが締まらないもの
(2)ねじなし端子の器具への結線部分
{埋込連用タンブラスイッチ(片切,両切,3路,4路),埋込連用コンセント,パイロットランプ,引掛シーリングローゼット等}
8-8.電線を引っ張って外れるもの
8-9.心線が差込口から 2mm 以上露出したもの
ただし,引掛シーリングローゼットにあっては,1mm 以上露出したもの
8-10.引掛シーリングローゼットへの結線で,絶縁被覆が台座の下端から5mm 以上露出したもの
9.金属管工事部分
9-1.構成部品(「金属管」,「ねじなしボックスコネクタ」,「ボックス」,「ロックナット」,「絶縁ブッシング」,「ねじなし絶縁ブッシング」)が正しい位置に使用されていないもの
9-2.構成部品間の接続が適切でないもの
イ.「管」を引っ張って外れるもの
ロ.「絶縁ブッシング」が外れているもの
ハ.「管」と「ボックス」との接続部分を目視して隙間があるもの
9-3.「ねじなし絶縁ブッシング」又は「ねじなしボックスコネクタ」の止めねじをねじ切っていないもの
9-4.ボンド工事を行っていない又は施工条件に相違してボンド線以外の電線で結線したもの
9-5.ボンド線のボックスへの取り付けが適切でないもの
イ.ボンド線を引っ張って外れるもの
ロ.巻き付けによる結線部分で,ボンド線をねじで締め付けていないもの
ハ.接地用取付ねじ穴以外に取り付けたもの
9-6.ボンド線のねじなしボックスコネクタの接地用端子への取り付けが適切でないもの
イ.ボンド線をねじで締め付けていないもの
ロ.ボンド線が他端から出ていないもの
ハ.ボンド線を正しい位置以外に取り付けたもの
10.合成樹脂製可とう電線管工事部分
10-1.構成部品(「合成樹脂製可とう電線管」,「コネクタ」,「ボックス」,「ロックナット」)が正しい位置に使用されていないもの
10-2.構成部品間の接続が適切でないもの
イ.「管」を引っ張って外れるもの
ロ.「管」と「ボックス」との接続部分を目視して隙間があるもの
11.取付枠部分
11-1.取付枠を指定した箇所以外で使用したもの
11-2.取付枠を裏返しにして,配線器具を取り付けたもの
11-3.取付けがゆるく,配線器具を引っ張って外れるもの
11-4.取付枠に配線器具の位置を誤って取り付けたもの
イ.配線器具が1個の場合に,中央以外に取り付けたもの
ロ.配線器具が2個の場合に,中央に取り付けたもの
ハ.配線器具が3個の場合に,中央に指定した器具以外を取り付けたもの
12.その他
12-1.支給品以外の材料を使用したもの
12-2.不要な工事,余分な工事又は用途外の工事を行ったもの
12-3.支給品(押しボタンスイッチ等)の既設配線を変更又は取り除いたもの
12-4.ゴムブッシングの使用が適切でないもの
イ.ゴムブッシングを使用していないもの
ロ.ボックスの穴の径とゴムブッシングの大きさが相違しているもの
12-5.器具を破損させたもの
ただし,ランプレセプタクル,引掛シーリングローゼット又は露出形コンセントの台座の欠けについては欠陥としない
第二種電気工事士試験の勉強法
第二種電気工事士試験は、学科試験と技能試験の二つに分かれており、それぞれに異なる勉強法が求められます。
学科試験では、電気に関する基礎知識が問われ、技能試験では実際の配線作業や器具の取り付けなど、実技能力が評価されます。
以下に、効果的な勉強法を紹介します。
学科試験の基本の勉強法
学科試験対策としては、以下のポイントをしっかりと押さえておきましょう。
テキストを1周させる
学科試験に向けた最初のステップは、テキストを一通り読むことです。試験範囲を把握し、全体の内容を掴むために、まずはテキストに目を通しましょう。
この段階では、わからない部分があっても気にせずに進めて構いません。重要なのは、試験全体の概要を理解し、出題されるテーマに慣れることです。
テキストを1周することで、自分が得意な分野や苦手な分野が見えてきます。
初めて学ぶ内容が多い場合でも、この段階でしっかりと基礎を押さえることで、後の学習がスムーズに進みます。
過去問を何度も解く
テキストを一通り読んだ後は、過去問に取り組みます。過去問を解くことで、実際の試験形式や出題傾向を理解することができます。
テキストの内容を覚えるだけでなく、過去問を解くことによって実際に試験に出る問題に対応できる力を養います。
わからない問題や間違えた問題があった場合は、再度テキストに戻り、関連する部分を確認しましょう。
何度も同じ問題で間違える部分は、特に重点的に学習することが重要です。過去問を繰り返し解くことで、得点力が着実に向上します。
技能試験の基本の勉強法
他方で、技能試験は次のポイントに注意してください。
工具・実技キットを揃える
技能試験の勉強においては、まず試験に使う指定工具を揃えることから始めます。
試験では自分で工具を準備する必要があるため、指定された工具と、練習用の実技キットを購入しましょう。
工具には指定以外のものも使用可能ですので、便利な道具を揃えることで作業効率が向上します。
工具の選定は重要で、手に馴染むものや使いやすいものを選ぶことで、作業の正確さとスピードが向上します。
また、練習用キットは本番に近い状態での練習を可能にするため、しっかりと準備を整えることが成功の鍵となります。
複線図の書き方をマスターする
技能試験では、複線図を正確に書くことが求められます。
複線図とは、電気配線を示す図面であり、これを正しく描けることが試験合格の重要なポイントとなります。
複線図を書く練習を繰り返し行い、正確かつ迅速に描けるようにしておきましょう。
複線図をマスターすることは、実際の配線作業をスムーズに進めるための基本です。
複線図の理解が深まると、作業手順の理解も進み、ミスを減らすことができます。
候補問題で実際に練習する
技能試験では、あらかじめ提示される候補問題を使って実際に練習を行います。これにより、実際の試験で何が出題されても対応できるようになります。
候補問題を一通り練習し、それぞれの問題に対してどのように対応するかをしっかりと身につけておきましょう。
実際に手を動かして練習することで、作業の流れや手順を体で覚えることができます。
特に、最初は時間がかかる作業でも、繰り返し練習することで効率的に進められるようになります。
効率的な進め方、時間配分を確認していく
技能試験では、作業の効率と時間配分も重要です。限られた時間内で正確に作業を完了するためには、効率的な進め方を身につける必要があります。
動画サイトなどには、作業手順や効率的な進め方がわかる教材がアップされているため、これを活用して自分の弱点を補強しましょう。
また、試験で重要なのは、欠陥条件をしっかりと覚えることです。
欠陥の判断基準を理解し、それに基づいて作業を進めることで、試験本番でもミスなく作業を完了することができます。
技能試験は、学科試験と異なり、実際の作業能力が問われます。
そのため、しっかりとした準備と十分な練習が不可欠です。効率的な勉強法を取り入れ、試験に向けた万全の準備を進めましょう。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
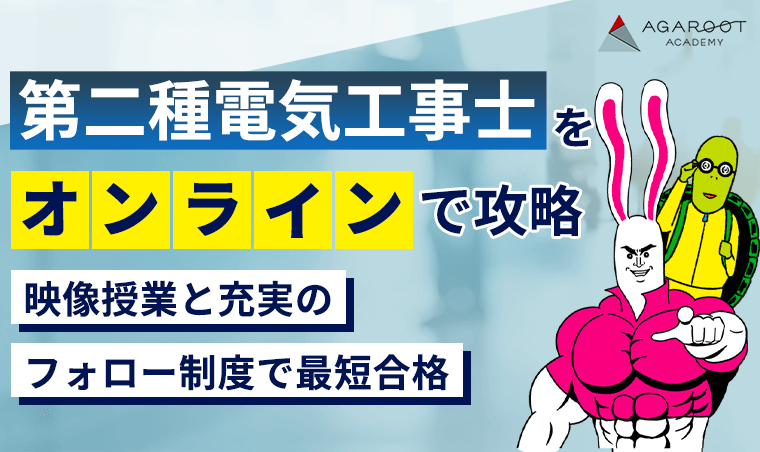
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
▶第二種電気工事士試験講座を見る



