第二種電気工事士学科試験の概要・日程・合格率・過去問・勉強法を解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

第二種電気工事士の資格を取得するためには、始めに学科試験に合格しなければなりません。
学科試験は範囲が広く、合格するためにはコツがあるため、無計画に勉強を始めてしまうと合格に時間がかかってしまいます。
まずは、第二種電気工事士の学科試験の内容を把握し、短期間で合格するための計画を立てましょう。
本コラムでは、第二種電気工事士の学科試験の概要についてくわしく解説します。
過去問や例題、基本の勉強法にも触れるため、受験する予定の方は参考にぜひご覧ください。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
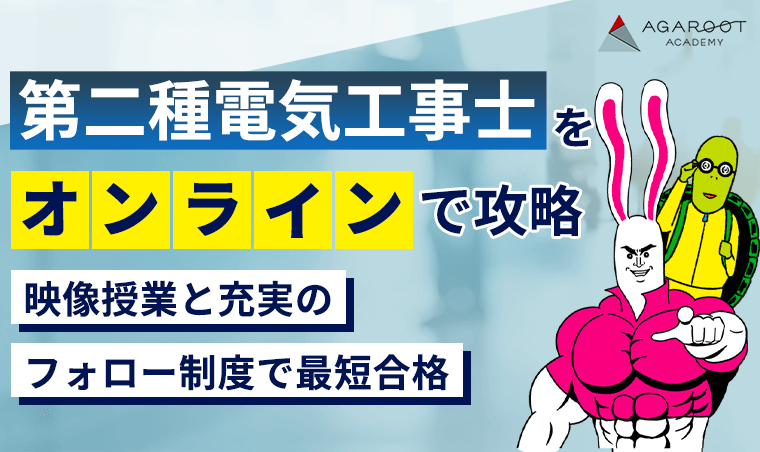
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
▶第二種電気工事士試験講座を見る
目次
第二種電気工事士試験学科試験の概要
第二種電気工事士試験学科試験の概要は、以下のとおりです。
| 試験方法 | ・四肢択一式 ・筆記方式もしくはCBT方式 | |
| 試験時間 | 120分 | |
| 出題数 | 一般問題 | 約30問 |
| 配線図問題 | 約20問 | |
| 配点 | 1問2点 | |
| 科目 | ・電気に関する基礎理論 ・配電理論及び配線設計 ・電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 ・電気工事の施工方法 ・一般用電気工作物等の検査方法 ・配線図 ・一般用電気工作物等の保安に関する法令 | |
| 合格基準 | 60点以上 | |
第二種電気工事士試験学科試験の試験方法
学科試験の出題形式は、四肢択一です。
正しいと思う答えを、イ、ロ、ハ、ニからひとつ選びます。
また、試験方式は筆記方式とCBT方式があり、どちらかを選択して受験します。
筆記方式の解答は記述式ではなく、マークシート式です。
鉛筆などを使用して、解答欄のマークを塗りつぶします。
対して、CBT方式は問題用紙やマークシートの代わりに、指定会場に準備されているパソコンの画面上で試験を行う方式です。
なお、一般財団法人電気技術者試験センターのホームページでは、CBT方式の体験談を無料で利用可能です。
CBT方式がどのような試験なのかくわしく知りたい方は、体験版を操作してみましょう。
第二種電気工事士試験学科試験の試験時間
学科試験の試験時間は、120分です。
ただし、試験時間は変更される場合があります。
最新の情報は、一般財団法人電気技術者試験センターのホームページで確認しておきましょう。
第二種電気工事士試験学科試験の出題数
学科試験の出題数は合計50問です。
一般問題が約30問、配線図問題は約20問という割合で出題されます。
しかし、問題の割合や出題数は変更されることがあるため、出題数についても一般財団法人電気技術者試験センターのホームページでチェックしておきましょう。
第二種電気工事士試験学科試験の配点
学科試験の配点は、1問2点です。
出題数は50問のため、満点は50問×2点=100点となります。
第二種電気工事士試験学科試験の科目・範囲
学科試験の試験科目は、7科目です。
以下、試験科目とその概要一覧です。
| 科目 | 概要 | |
| 1 | 電気に関する基礎理論 | 電気に関する基礎的な法則を利用して解く問題 |
| 2 | 配電理論及び配線設計 | 電気の配線に関する理論や、配線の設計に関する問題 |
| 3 | 電気機器、配電器具並びに電気工事用の材料及び工具 | 電気工事に関する資材や工具の使用方法に関する問題 |
| 4 | 電気工事の施工方法 | 工事を行う場所の制限や事故の予防方法などに関する問題 |
| 5 | 一般用電気工作物等の検査方法 | 工事現場での検査や測定に関する問題(法令や安全基準を満たしているかどうか) |
| 6 | 配線図 | 写真を組み合わせるなど配線図に関する問題配線図から複線図を描く応用問題が出題されるケースもある |
| 7 | 一般電気工作物等の保安に関する法令 | 電気工事士が可能な工事内容などを含む法令に関する問題 |
また、各科目の出題範囲も公表されているため、範囲をしっかり把握してから勉強を始めましょう。
学科試験の科目と科目の範囲は、以下のとおりです。
| 科目 | 範囲 | |
| 1 | 電気に関する基礎理論 | ①電流、電圧、電力及び電気抵抗 ②導体及び絶縁体 ③交流電気の基礎概念 ④電気回路の計算 |
| 2 | 配電理論及び配線設計 | ①配電方式 ②引込線 ③配線 |
| 3 | 電気機器、配電器具並びに電気工事用の材料及び工具 | ①電気機器及び配線器具の構造及び性能 ②電気工事用の材料の材質及び用途 ③電気工事用の工具の用途 |
| 4 | 電気工事の施工方法 | ①配線工事の方法 ②電気機器及び配線器具の設置工事の方法 ③コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法 ④接地工事の方法 |
| 5 | 一般用電気工作物等の検査方法 | ①点検の方法 ②導通試験の方法 ③絶緑抵抗測定の方法 ④接地抵抗測定の方法 ⑤試験用器具の性能及び使用方法 |
| 6 | 配線図 | 配線図の表示事項及び表示方法 |
| 7 | 一般電気工作物等の保安に関する法令 | ①電気工事士法、同法施行令、同法施行規則 ②電気設備に関する技術基準を定める省令(注1、2参照) ③電気用品安全法、同法施行令、同法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令 |
第二種電気工事士試験学科試験の合格基準
学科試験の合格基準は、約60点です。
正確な合格基準の情報は公表されていませんが、例年60点取れれば合格しています。
配点が1問2点の出題数合計50問の試験であるため、30問以上正解できれば合格できる基準です。
また、四肢択一式のため、正解肢を選択できる知識があれば合格は難しくないでしょう。
2025年度第二種電気工事士の試験日、日程
2025年度第二種電気工事士の試験日と詳しい日程を紹介します。
なお、第二種電気工事士試験は上期と下期で、年2回実施されています。
- 2025年度第二種電気工事士試験上期試験の日程
- 2025年度第二種電気工事士試験下期試験の日程
2025年度第二種電気工事士試験上期試験の日程
| 上期試験 | ||
| 受験申込受付期間 | 令和7年3月17日(月)~4月7日(金) | |
| 学科試験日 | CBT方式 | 令和7年4月21日(月)~5月8日(木) |
| 筆記方式 | 令和7年5月25日(日) | |
| 学科試験合格発表(WEB公表) | CBT方式のみ | 受験日から2週間後の正午より |
| 筆記方式・CBT方式 | 令和7年6月9日(月) | |
| 技能試験日 | 令和7年7月19日(土)または7月20日(日) | |
| 技能試験合格発表(WEB公表) | 令和7年8月15日(金) | |
2025年度第二種電気工事士試験上期試験の申込期間は、令和7年4月21日(月)の10時から4月7日17時までです。
学科試験免除者の方も同様の期間となり、すべてインターネット申込となります。
学科試験日は、筆記方式だと令和7年5月25日(日)のみです。
CBT方式を選択すれば、令和7年4月21日(月)〜5月8日(木)の期間中に好きな日にちが選べます。
なお、CBT方式希望者は、受験申込み完了後、受験日程と指定会場をホームページ上で選択する手続きがあるため注意が必要です。
令和7年度の上期の学科試験の合格発表日は令和7年6月9日(月)です。
ただし、CBT方式で受験した方は、受験日から2週間後の正午よりマイページで確認することもできます。
また、技能試験の試験日は令和7年7月19日、7月20日のどちらかです。
令和7年度の上期の技能試験の合格発表日は令和7年8月15日(金)です。
2025年度第二種電気工事士試験下期試験の日程
| 下期試験 | ||
| 受験申込受付期間 | 令和7年8月18日(月)~9月4日(木) | |
| 学科試験日 | CBT方式 | 令和7年9月19日(金)~10月6日(月) |
| 筆記方式 | 令和7年10月26日(日) | |
| 学科試験合格発表(WEB公表) | CBT方式 | 受験日から2週間後の正午より |
| 筆記方式・CBT方式 | 未発表 | |
| 技能試験日 | 令和7年12月13日(土)または12月14日(日) | |
| 技能試験合格発表(WEB公表) | 未発表 | |
2025年度第二種電気工事士試験下期試験の申込期間は、令和6年8月18日(月)の10時から9月4日(木)の17時までです。
下期試験も同様に、インターネット申込のみです。
また、学科試験免除者の方も同様の期間となります。
学科試験日は、筆記方式だと令和7年10月26日(日)です。
CBT方式を選択すると、令和7年99月19日(金)~10月6日(月)の中で好きな日にちを選べます。
なお、CBT方式希望者は、受験申込み完了後に受験日程と指定会場をホームページ上で選択しなければなりません。
令和7年度の下期の学科試験の合格発表日はまだ公開されていません。参考までに、2024年度の下期の学科試験の合格発表は、筆記方式とCBT方式ともに、令和7年11月11日〜12月15日に一般財団法人電気技術者試験センターのホームページで発表されました。
さらにCBT方式を受験した方は、受験日から2週間後の正午よりマイページでの確認が可能です。
また、技能試験の試験日は令和7年12月13日(土)または12月14日(日)です。
令和7年度の下期の技能試験の合格発表日はまだ公開されていません。参考までに、2024年度の下期の結果は、一般財団法人電気技術者試験センターのホームページ上で、令和7年1月17日〜2月17日に行われます。
第二種電気工事士試験学科試験の合格率
第二種電気工事士試験学科試験の合格率について、過去数年分を以下にまとめました。
| 期 | 合格率 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年度(令和6年度) | 下期 | 55.9% | 62,323名 |
| 上期 | 60.2% | 70,139名 | |
| 2023年度(令和5年度) | 下期 | 58.9% | 63,611名 |
| 上期 | 59.9% | 70,414名 | |
| 2022年度(令和4年度) | 下期 | 53.3% | 66,454名 |
| 上期 | 58.2% | 78,634名 | |
| 2021年度(令和3年度) | 下期 | 57.7% | 70,135名 |
| 上期 | 60.4% | 86,418名 | |
| 2020年度(令和2年度) | 下期 | 62.1% | 104,883名 |
| 上期 | ‐ | ‐ |
※2020年度の上期試験は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
最新の2024年度下期学科試験の合格率は、55.9%でした。
また、ここ数年の学科試験の合格率は55~60%程度です。
例年、受験した半数以上の方が合格しているため、試験難易度は比較的高くないと予想できます。
直近でもっとも低い合格率だったのは、2022年度(令和4年度)の下期学科試験で、53.3%でした。
対して、もっとも高い合格率だった試験は、2020年度(令和2年度)の下期学科試験の62.1%です。
しかし、2020年度(令和2年度)の上期学科試験が新型コロナウイルス感染症の影響のために中止となっており、下期試験に受験者が集中したことにより合格者が多くなった可能性があります。
影響はあるかもしれませんが、例年の合格率の傾向から、第二種電気工事士試験の学科試験の合格率は60%ぐらいだと把握していて問題ないでしょう。
第二種電気工事士試験学科試験の免除対象者
第二種電気工事士試験では、定められた条件に該当する方は学科試験の免除対象者となります。
しかし、学科試験免除の対象者となっても、自動的に免除にはなりません。
学科試験免除の権利をもち、免除を希望する方は、試験免除の申請を必ず行いましょう。
対象となる方は、以下のとおりです。
- 前回の第二種電気工事士試験学科試験に合格した方
- 高等学校、高等専門学校及び大学等において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方
- 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の取得者
- 鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した方
- 旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された方
- 旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者
前回の第二種電気工事士学科試験に合格した方
直近で実施された学科試験の合格者が対象です。
また、学科試験免除の権利は、権利を取得した試験の次に実施される試験のみに有効となります。
つまり、下期学科試験に合格した場合、次年度の上期試験のみ免除対象になります。
免除申請には、合格した年度の学科試験受験番号の入力が必須です。
受験番号は、一般社団法人電気技術者試験センターホームページ内の免除情報の検索から検索できます。
高等学校、高等専門学校及び大学等において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方
高等学校や専門学校、大学などで経済産業省令および電気工事法で定める電気工学の課程を修めて卒業した方は、学科試験の免除対象者です。
なお、経済産業省令で定める電気工学の課程とは、電気理論・電気計測・電気機器・電気材料・送配電・製図(配線図を含むものに限る)および電気法規です。
全課程の電気工学に関する所定の単位をすべて修得する必要があります。
また、免除申請時に必要な書類は、学科試験免除証明書です。
学科試験免除証明書には学校長からの証明が必要になります。
自分が学科試験免除の条件を満たしているかどうかわからない場合は、卒業した学校へ確認しましょう。
第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の取得者
第一種・第二種・第三種電気主任技術者資格を一つ以上取得している方は、学科試験が免除になります。
免除申請時に必要な証明書類は、電気主任技術者免状の複写(コピー)です。
鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した方
改正前の鉱山保安法第18条の規定による試験の中で、電気保安に関する事項を受けもつ係員の試験に合格した方は、学科試験の免除対象者です。
免除申請時に必要な証明書類は、合格証明書もしくは国家試験合格証の複写(コピー)になります。
旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された方
旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関して相当の知識経験を有すると認定された方は、学科試験が免除になります。
免除申請時には、自家用電気工作物主任技術者技能認定証明書もしくは自家用電気工作物主任技術者技能認定書の複写の提出が必要です。
旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者
旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者も、学科試験免除の対象者です。
免除申請に必要な書類は、資格の取得方法により異なります。
旧電気事業主任技術者資格検定規則に基づく検定試験の合格者の場合は、合格証明書もしくは合格証書の複写が必要です。
旧電気事業主任技術者資格検定規則による認定学校(旧制の大学・工業専門学校・工業学校などの電気科)の卒業者の場合は、卒業証明書または卒業証書の複写を提出します。
第二種電気工事士試験学科試験の過去問・例題
第二種電気工事士試験学科試験の過去問と例題を、それぞれ紹介します。
過去問演習や例題練習は、実力が身に付くほかに試験の傾向がわかるメリットがあります。
受験対策にぜひ活用してください。
- 第二種電気工事士試験学科試験の過去問
- 第二種電気工事士試験学科試験の例題
第二種電気工事士試験学科試験の過去問
第二種電気工事士試験学科試験の過去問は、試験を実施する一般財団法人電気技術者試験センターのホームページで公開されています。
なお、学科試験は2022年度までは学科試験ではなく筆記試験という名称で実施されていました。
以下、学科試験の過去問へのリンクです。
2024年10月27日(日)実施
2024年5月26日(日)実施
2023年10月29日(日)実施
2023年5月28日(日)実施
第二種電気工事士試験学科試験の例題
第二種電気工事士試験学科試験の例題は、一般財団法人電気技術者試験センターのホームページで科目別で公開されています。
電気に関する基礎理論の例題
【例題】
直径2.6mm、長さ20mの銅導線と抵抗値が最も近い同材質の銅導線は。
イ.直径1.6mm、長さ40m
ロ.断面積8mm2、長さ20m
ハ.直径3.2mm、長さ10m
ニ.断面積5.5mm2、長さ20m
【解答】
ニ.断面積5.5mm2、長さ20m
配電理論及び配線設計の例題
【例題】
図のような単相3線式回路において、消費電力125W、500Wの2つの負荷はともに抵抗負荷である。
図中の×印点で断線した場合、a-b間の電圧[V]は。
ただし、断線によって負荷の抵抗値は変化しないものとする。

イ.40
ロ.100
ハ.160
ニ.200
【解答】
ハ.160
電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の例題
【例題】
写真に示す器具の用途は。

イ.白熱電灯の明るさを調節するのに用いる。
ロ.人の接近による自動点滅に用いる。
ハ.蛍光灯の力率改善に用いる。
ニ.周囲の明るさに応じて街路灯などの自動点滅させるのに用いる。
【解答】
ニ.周囲の明るさに応じて街路灯などの自動点滅させるのに用いる。
電気工事の施工方法の例題
【例題】
単相100Vの屋内配線工事における絶縁電線相互の接続で、不適切なものは。
イ.絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆した。
ロ.電線の引張強さが15%減少した。
ハ. 差込形コネクタによる終端接続で、ビニルテープによる絶縁は行わなかった。
ニ.電線の電気抵抗が5%増加した。
一般用電気工作物等の検査方法の例題
【例題】
一般に使用される回路計(テスタ)によって測定できないものは。
イ.交流電圧
ロ.回路抵抗
ハ.漏れ電流
ニ.直流電圧
【解答】
ハ.漏れ電流
配線図の例題
【例題】
図には配線図が示されている。
図の指示に従い、配線図問題をよく読んで、選択肢の中から答えを一つ選びなさい。
【注意事項】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。

②で示す部分の接地工事における接地抵抗の許容される最大値[Ω]は。
イ.10
ロ.100
ハ.300
ニ.500
【解答】
ニ.500
一般用電気工作物等の保安に関する法令の例題
【例題】
「電気工事士法」の主な目的は。
イ.電気工事に従事する主任電気工事士の資格を定める。
ロ.電気工作物の保安調査の義務を明らかにする。
ハ.電気工事士の身分を明らかにする。
ニ.電気工事の欠陥による災害発生の防止に寄与する。
【解答】
ニ.電気工事の欠陥による災害発生の防止に寄与する。
第二種電気工事士試験学科試験基本の勉強法
第二種電気工事士試験学科試験の基本的な勉強法を4つ紹介します。
- テキストをわからないところがあっても1週させる
- 過去問題を繰り返し解く
- 暗記学習も並行して進める
- 効率的に学びたいなら講座利用がおすすめ
テキストをわからないところがあっても1周させる
学科試験の勉強を始める際には、学科試験の試験内容を掴むため、まずはテキストにひと通り目を通しましょう。
テキストを読む際には、わからないところがあっても気にせずに最後まで読むようにしてください。
わからないところの理解を優先してしまうと、時間がかかって効率性が下がってしまいます。
過去問題を繰り返し解く
テキストで各科目の範囲を把握し、知識がある程度身に付いたあとは過去問題を解きましょう。
過去問題は、何度も繰り返し解くのが重要です。
過去問演習をし、間違えた問題を復習することを繰り返せば実力が身に付き、苦手な科目の克服にも繋がります。
過去10年〜15年分の過去問を集めて解くとさまざまな問題に触れられ、試験の傾向なども把握できます。
また、学科試験の合格ラインは60点以上といわれていますが、過去問で平均80点取れるようになれば、合格できる可能性は高くなるでしょう。
暗記学習も平行して進める
学科試験で出題される問題の多くは知識問題となるため、問題演習と並行して暗記学習を進めるようにしましょう。
知識を暗記するためには、どれだけ繰り返して学習したかが重要です。
まずは得意な分野、簡単と感じる分野から進めて、徐々に難しい分野を覚えていくと効率的です。
なお、知識問題には、電気工事に関する単語や法令、配線図、配線図記号、鑑別などが出題されます。
工事方法や法令は似たようなものや種類が多いものもあるため、違いをしっかりして暗記する必要があるでしょう。
また、学科試験において暗記すべき知識量は多いため、自分が1日にどれくらい勉強時間を取れるかを考え、必要な期間を計算しておくことも大切です。
学習スケジュールをしっかり立てて、コツコツ勉強するようにしましょう。
効率的に学びたいなら講座利用がおすすめ
短期間で合格できる実力を身に付けたい、確実に一発合格したいという方は、独学ではなく通信講座の利用がおすすめです。
通信講座であれば、学科試験を熟知した講師の講義動画などを繰り返し見ることができ、さらに要点をまとめられたテキストで無駄なく勉強することが可能です。
さらにアガルートの講座であれば、講義やテキストなどをスマホひとつで利用できるため、スキマ学習もできます。
通勤時間や就寝前のちょっとした時間を活用すれば、仕事などで忙しい方でも短期間で合格が目指せるでしょう。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
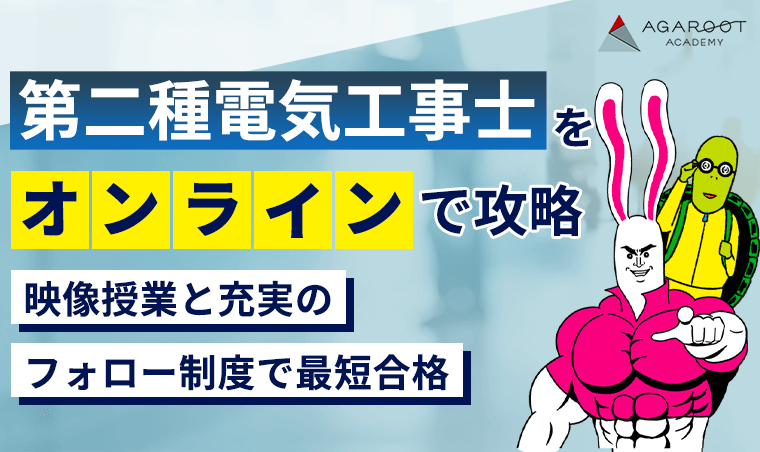
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
▶第二種電気工事士試験講座を見る



