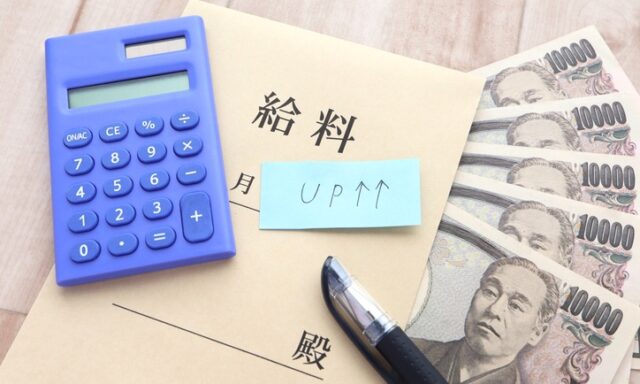第二種電気工事士とは?仕事内容、試験情報、合格率・難易度を紹介!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

「電気工事士に挑戦したいけど、何から始めればいいのか分からない…」「第二種電気工事士って何ができるの?試験はどれくらい難しいの?」そんな疑問や不安を抱えていませんか?
電気工事士の資格は、特にこれから電気業界に飛び込もうとしている方にとって、大きな一歩となる資格です。
しかし、その第一歩を踏み出す前に、仕事内容や試験の難易度、合格率などについて正確な情報を知っておくことはとても重要です。
「いざ試験に挑戦してみたけれど、思ったより難しかった…」とならないために、この記事では、第二種電気工事士の仕事内容や試験の詳細、さらには合格率や難易度について詳しく解説します。
この記事を読むことで、第二種電気工事士の全体像が明確になり、資格取得に向けた計画を立てる際の大きな助けになるはずです。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
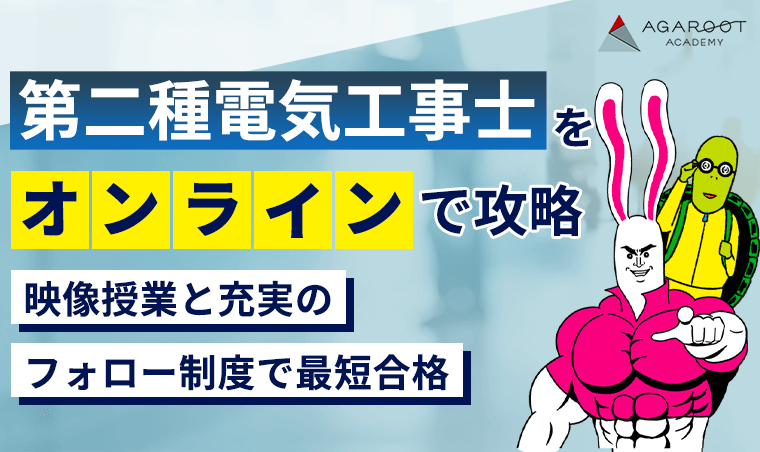
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
会員20万人突破記念!
全商品5%OFF!
第二種電気工事士とは?
電気工事士は、日本において電気工事を安全かつ確実に行うために必要とされる国家資格です。
電気設備の設置や保守、修理を行うためには、この資格を持っていることが法律で義務付けられています。
電気工事士には第一種と第二種の2種類があり、それぞれ対応できる工事の範囲や難易度が異なります。
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な商業施設などで使用される電気設備の工事を担当するための資格です。
具体的には、600V以下の低圧電気設備の工事を行うことができ、配線や照明、コンセントの設置、エアコンの取り付けなどが含まれます。
第二種電気工事士資格は、学歴や職歴、実務経験が不要で、誰でも受験することができるため、電気工事士としてのキャリアをスタートさせるのに最適な資格です。
一方で、第一種電気工事士は、第二種で行える工事に加え、500キロワット未満の大規模な電気設備の工事も担当できます。
そのため、第一種電気工事士の試験は難易度が高く、また、免状を取得するためには3年以上の実務経験が必要です。
多くの人はまず第二種電気工事士の資格を取得し、実務経験を積んだ後に第一種電気工事士を目指すというステップを踏みます。
次に、第二種電気工事士が実際にどのような仕事をするのか、そしてこの資格を取得することで得られるメリットについて詳しく見ていきましょう。
第二種電気工事士の仕事内容
第二種電気工事士の仕事は多岐にわたりますが、代表的な仕事内容は以下のとおりです。
配線工事
第二種電気工事士の主な仕事内容の一つは、一般住宅や小規模店舗における配線工事です。
これには、照明器具やコンセントの設置が含まれ、正確な配線と安全性を確保することが求められます。
電気の流れや負荷を正確に理解し、適切に設計された配線を行うことで、電気設備が安全に使用できるようにします。
エアコンの設置工事
第二種電気工事士は、家庭やオフィスでのエアコン設置工事も担当します。
エアコンの設置には電力の供給が不可欠であり、電気工事士が電源の配線や設置場所の確認、適切な取り付けを行います。
特に夏場や冬場の需要が高く、エアコン設置工事は重要な業務の一つです。
現場代理人としての役割
さらに、第二種電気工事士は、現場代理人として工事現場の監督や進行管理を行うこともあります。
現場代理人は、工事が計画通り進むように指揮をとり、他の工事業者との連携を図るなど、現場の中心的な役割を担います。
この経験を積むことで、第一種電気工事士へのステップアップや、さらなるキャリアの発展が可能になります。
第二種電気工事士を取得するメリット
第二種電気工事士の資格を取得することには、以下のようなメリットがあります。
就職や転職で有利
第二種電気工事士の資格を持つことで、電気工事業界での就職や転職が非常に有利になります。
資格を有していることは、即戦力として企業に評価されるため、求人に応募する際の大きな強みとなります。
また、多くの企業では資格手当が支給されるため、収入面でもプラスとなることが多いです。
収入の増加
資格を取得することで、資格手当が支給される企業が多く、月々の給与が増える可能性があります。
また、資格を持っていることで昇進の機会が増え、さらなる収入増加が見込めます。
第二種電気工事士は、経験を積むことで将来的に第一種電気工事士や他の上位資格を取得する道も開かれており、長期的なキャリアアップにつながります。
自宅のリフォームやDIYに役立つ
第二種電気工事士の資格があれば、自宅での電気工事を自分で行うことができ、リフォームやDIYに役立てることができます。
これにより、工事費用を削減できるだけでなく、家族や友人の依頼にも応えられるため、生活の幅が広がります。
将来の安定性
一度取得すれば更新の必要がない第二種電気工事士の資格は、長期にわたり使えるスキルとして非常に安定しています。
電気工事の需要は今後も増加すると予測されており、この資格を持つことで長期的に安定した職業人生を築くことが可能です。
また、第一種電気工事士などへのキャリアアップを目指すことで、さらなる収入増加やキャリアの発展が期待できます。
第二種電気工事士試験の概要
第二種電気工事士になるためには、国家資格である第二種電気工事士試験に合格する必要があります。
この試験は、電気工事を行うために必要な知識と技能を確認するもので、年に2回、上期と下期に実施されています。
第二種電気工事士試験は、学科試験と技能試験の2つのセクションから構成されており、どちらもクリアすることが合格の条件です。
受験資格に関しては特に制限がなく、年齢や学歴、実務経験に関係なく誰でも受験が可能です。
学科試験と技能試験の両方に合格すると、各都道府県知事から免状が交付され、正式に第二種電気工事士として活動することが可能になります。
第二種電気工事士試験の試験日・日程
2024年度の第二種電気工事士試験の試験日程は次の通りです。第二種電気工事士試験は上期と下期に分かれて実施されます。
上期試験
- 申込み期間:2024年3月18日(月)~4月12日(金)
- 学科試験:CBT方式2024年4月22日(月)~5月9日(木)
筆記方式2024年5月26日(日) - 学科試験合格発表:2024年6月10日(月)
- 技能試験:2024年7月20日(土)または7月21日(日)
- 技能試験合格発表:2024年8月16日(金)
下期試験
- 申込み期間:2024年8月19日(月)~9月5日(木)
- 学科試験:CBT方式2024年9月20日(金)~10月7日(月)
筆記方式2024年10月27日(日) - 学科試験合格発表:2024年11月11日(金)
- 技能試験:2024年12月14日(土)または12月15日(日)
- 技能試験合格発表:2025年1月17日(金)
2025年度の第二種電気工事士試験の試験日程は次の通りです。
上期試験
- 申込み期間:2025年3月17日(月)~4月7日(金)
- 学科試験:CBT方式2025年4月21日(月)~5月8日(木)
筆記方式2025年5月25日(日) - 学科試験合格発表:2025年6月9日(月)
- 技能試験:2025年7月19日(土)または7月20日(日)
- 技能試験合格発表:2025年8月15日(金)
下期試験
- 申込み期間:2025年8月18日(月)~9月4日(木)
- 学科試験:CBT方式2025年9月19日(金)~10月6日(月)
筆記方式2025年10月26日(日) - 技能試験:2025年12月13日(土)または12月14日(日)
例年、上期試験は3月中旬から4月上旬にかけて申込みが行われ、4月下旬から7月下旬にかけて試験が実施されます。
下期試験は8月中旬から9月上旬に申込みを行い、9月下旬から12月下旬にかけて試験が行われます。
学科試験合格発表は上期試験では6月、下期試験では11月で、技能試験合格発表は、上期試験では11月、下期試験では翌1月です。
第二種電気工事士試験の試験の申し込み方法
第二種電気工事士試験の申込み方法は、インターネットを利用したオンライン申し込みが原則となっています。
令和6年度より、受験申込方法は、原則としてインターネットによる申し込みです。
受験者は、一般財団法人電気技術者試験センターの公式ウェブサイトにアクセスし、マイページを作成します。
そこから必要事項を入力し、顔写真をアップロードします。
その後、受験手数料9,300円をクレジットカード、銀行振込、またはコンビニ決済などで支払います。振込手数料は受験者の負担となります。
第二種電気工事士試験の受験料
第二種電気工事士試験の受験料は9,300円で、試験の申込み手続き時に支払う必要があります。振込手数料も受験者の負担となります。
申込みが完了して受験料が支払われると、受験票が発行され、試験当日に持参することになります。
第二種電気工事士試験の科目、範囲
第二種電気工事士試験は、学科試験と技能試験の2つのセクションで構成されており、それぞれ異なる科目と範囲が設定されています。
学科試験の科目と範囲
| 科目 | 範囲 |
|---|---|
| 電気に関する基礎理論 | 電流、電圧、電力、電気抵抗、導体・絶縁体、交流電気の基礎、電気回路の計算 |
| 配電理論及び配線設計 | 配電方式、引込線、配線 |
| 電気機器・配線器具・材料・工具 | 電気機器と配線器具の構造と性能、材料の材質と用途、工具の用途 |
| 電気工事の施工方法 | 配線工事、機器・配線器具の設置、コードとキャブタイヤケーブルの取り付け、接地工事 |
| 一般用電気工作物の検査方法 | 点検、導通試験、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、試験用器具の使用方法 |
| 配線図 | 配線図の表示方法と表示事項 |
| 保安に関する法令 | 電気工事士法、技術基準、省令など |
技能試験の科目と範囲
電線の接続、配線工事、電気機器及び配線器具の設置、材料及び工具の使用方法、コード及びキャブタイヤケーブルの取付け、接地工事、電流・電圧・電力・電気抵抗の測定、一般用電気工作物等の検査、故障箇所の修理
なお、学科試験免除については、特定の条件を満たす受験者に適用されます。
例えば、前回の学科試験に合格している場合や、電気工学の特定課程を修了している場合などが該当します。
第二種電気工事士試験の実施形式
第二種電気工事士試験は、学科試験と技能試験で異なる形式が採用されています。
学科試験
学科試験は、従来の筆記方式と、近年導入されたCBT(Computer Based Testing)方式のいずれかを選択して受験できます。
筆記方式では問題用紙とマークシートを使用して回答し、CBT方式ではパソコンの画面上で問題に回答します。
CBT方式は、試験期間中に自分の都合の良い日程と場所を選んで受験できる利便性があります。
技能試験
技能試験は、指定された材料と工具を使って実際の電気工事を模した作業を行い、その正確さとスピードが評価されます。
技能試験では、制限時間内にすべての作業を終えることが求められます。
第二種電気工事士試験の試験時間
学科試験
- 試験時間:120分
- 出題数:50問(一般問題30問程度、配線図問題20問程度)
技能試験
- 試験時間:40分
- 試験内容:電気回路の配線、電気機器の設置、測定および検査など
学科試験は120分で50問を解答する形式で、時間配分が重要です。
技能試験は40分の制限時間内で、指定された作業を完成させる必要があり、正確さと速さが求められます。
第二種電気工事士試験の合格基準
学科試験
合格ラインは、全体の正答率が約60%以上とされています。50問中30問以上の正解が必要です。
技能試験
合格基準は「欠陥がないこと」です。試験で指示された作業を正確に行い、作業に欠陥がないことが求められます。技能試験では、正確さが特に重視されます。
第二種電気工事士試験の合格率・難易度
第二種電気工事士試験は、電気工事に必要な国家資格の一つであり、受験者数も多く、幅広い層に人気のある試験です。
この試験は、合格率や難易度が比較的安定しており、国家資格の中では取得しやすい資格とされています。
ここでは、第二種電気工事士試験の合格率とその難易度について説明します。
第二種電気工事士試験の合格率
以下は、第二種電気工事士試験の過去数年の受験者数と合格率のデータです。
| 年度 | 上期・下期 | 学科試験 | 技能試験 | ||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 令和6年度 | 上期 | 70,139 | 42,194 | 60.2% | 50,668 | 35,949 | 71.0% |
| 下期 | 62,323 | 34,851 | 55.9% | 43,570 | 30,266 | 69.5% | |
| 令和5年度 | 上期 | 70,414 | 42,187 | 59.9% | 49,547 | 36,250 | 73.2% |
| 下期 | 63,611 | 37,468 | 58.9% | 45,790 | 31,499 | 68.8% | |
| 令和4年度 | 上期 | 78,634 | 45,734 | 58.2% | 53,558 | 39,771 | 74.3% |
| 下期 | 66,454 | 35,445 | 53.3% | 44,101 | 31,117 | 70.6% | |
| 令和3年度 | 上期 | 86,418 | 52,176 | 60.4% | 64,443 | 47,841 | 74.2% |
| 下期 | 70,135 | 40,464 | 57.7% | 51,833 | 36,843 | 71.1% | |
| 令和2年度 | 上期 | – | – | – | 6,884 | 4,666 | 67.8% |
| 下期 | 104,883 | 65,114 | 62.1% | 66,113 | 48,202 | 72.9% | |
| 令和元年度 | 上期 | 75,066 | 53,026 | 70.6% | 58,699 | 39,585 | 67.4% |
| 下期 | 47,200 | 27,599 | 58.5% | 41,680 | 25,935 | 62.2% | |
なお、令和2年度については、学科試験が中止となっています(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)。
令和6年度下期試験の最新データでは、学科試験の合格率が55.9%、技能試験の合格率が69.5%となっており、学科試験と技能試験の合格率は比較的安定して高い水準を維持しています。
ここ数年、学科試験の合格率は概ね55%から60%の間で推移しており、技能試験の合格率も70%前後で推移しています。
このデータからも、第二種電気工事士試験は、一定の努力をすれば比較的合格しやすい試験であることがわかります。
第二種電気工事士試験の難易度
第二種電気工事士試験は、受験資格が設けられておらず、年齢や学歴、実務経験に関係なく、誰でも受験することができます。
このため、初学者やキャリアチェンジを考えている人にも非常に受けやすい試験となっています。
さらに、過去のデータからもわかるように、合格率が比較的高く国家資格の中では難易度が低めであると言えるでしょう。
また、試験は学科と技能の2つに分かれており、学科試験では基本的な理論や法規に関する問題が出題され、技能試験では実際の電気工事の作業が評価されます。
しっかりとした準備と学習を行うことで、初めて受験する人でも十分に合格を狙うことができます。
第二種電気工事士試験の勉強法
第二種電気工事士試験は、学科試験と技能試験の2つのパートで構成されています。
特に学科試験は、電気工事に関する基礎的な知識が問われるため、しっかりとした準備が求められます。
ここでは、学科試験の効果的な勉強法を紹介します。試験に合格するためには、計画的に学習を進め、効率よく知識を習得することが重要です。
テキスト・過去問演習を繰り返す
第二種電気工事士試験の学科試験対策の基本は、テキストと過去問演習の繰り返しです。
まず、信頼できるテキストを選び、各章の内容をしっかりと理解することが重要です。
電気理論や法令に関する部分など、暗記が必要な箇所は確実に覚えておく必要があります。
テキストで基礎知識を習得したら、過去問演習に取り組みましょう。
過去問を解くことで、出題傾向や問題の形式に慣れることができます。また、過去問を繰り返し解くことで、理解が深まり、記憶が定着します。
間違えた問題は、なぜ間違えたのかをしっかりと分析し、テキストに戻って復習することで、同じミスを繰り返さないようにしましょう。
学習サイト・無料アプリを活用する
学習サイトや無料のアプリを活用するのも、第二種電気工事士試験の学習には効果的です。
インターネット上には、試験対策に特化した学習サイトや動画チュートリアルが豊富にあります。これらのリソースを利用することで、テキストだけでは理解しにくい部分も視覚的に学ぶことができます。
また、無料の学習アプリをスマートフォンにダウンロードしておけば、通勤・通学の合間や空いた時間に気軽に勉強できます。
アプリには、クイズ形式で問題を解けるものや、過去問を分野ごとに練習できるものがあり、隙間時間を有効に活用できます。
動画サイトでは、プロの講師が難しい概念を分かりやすく解説している動画もあり、これらを活用することで、理解を深めることができます。
効率的に学習するなら講座利用がおすすめ
効率的に学習を進めたい、または特定の分野でつまずいている場合は、講座の利用を検討することをおすすめします。
独学での学習は、自分のペースで進められる反面、理解が不十分なまま進んでしまうこともあります。
特に電気工事に関する法律や技術的な部分では、専門的な解説が必要となることが多いため、プロの講師から直接指導を受けることが有益です。
講座では、試験に特化したカリキュラムが組まれており、効率的に必要な知識を習得することができます。
また、講座によってはオンラインでの受講が可能なため、忙しい方でもスケジュールに合わせて学習を進められます。
さらに、講座では模擬試験や個別指導なども行われるため、自分の弱点を把握し、試験対策を強化することができます。
全体として、第二種電気工事士試験の学科試験に合格するためには、テキストと過去問を繰り返し学習し、学習サイトやアプリを活用しながら、効率的に知識を定着させることが大切です。
必要に応じて講座を利用し、確実に合格を目指しましょう。
第二種電気工事士試験の合格を
目指している方へ
- 第二種電気工事士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの
第二種電気工事士試験講座がおすすめ!
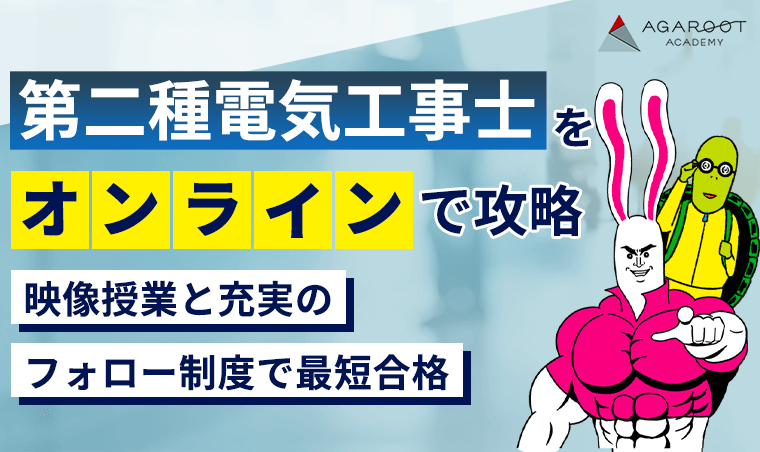
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
会員20万人突破記念!
全商品5%OFF!